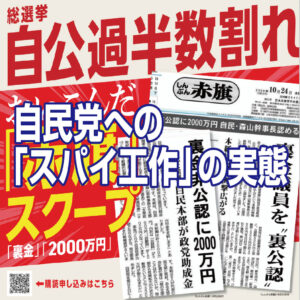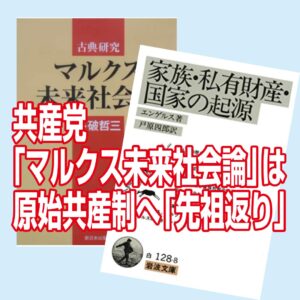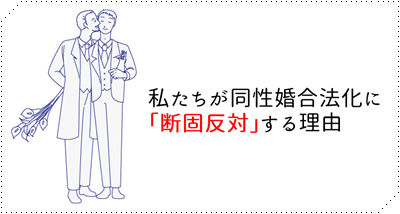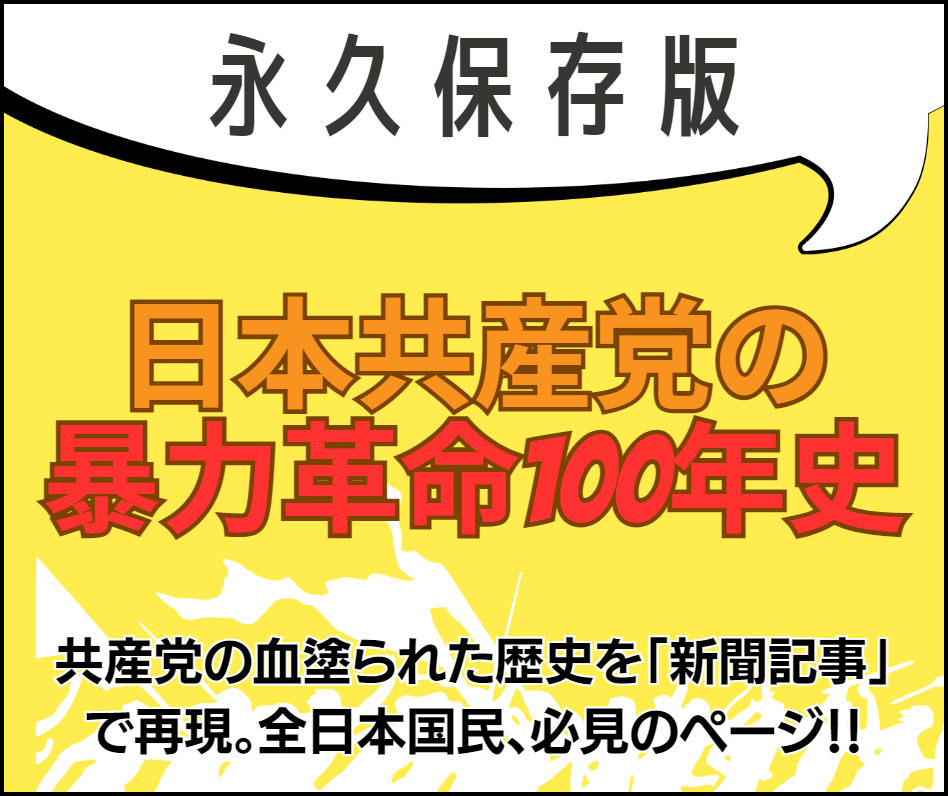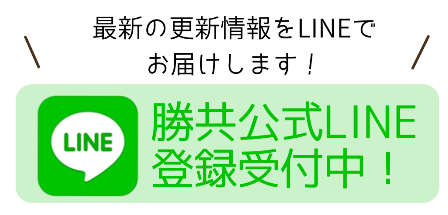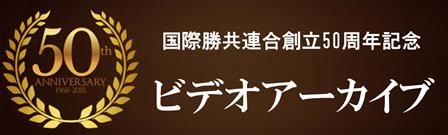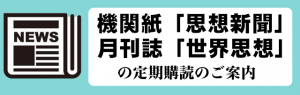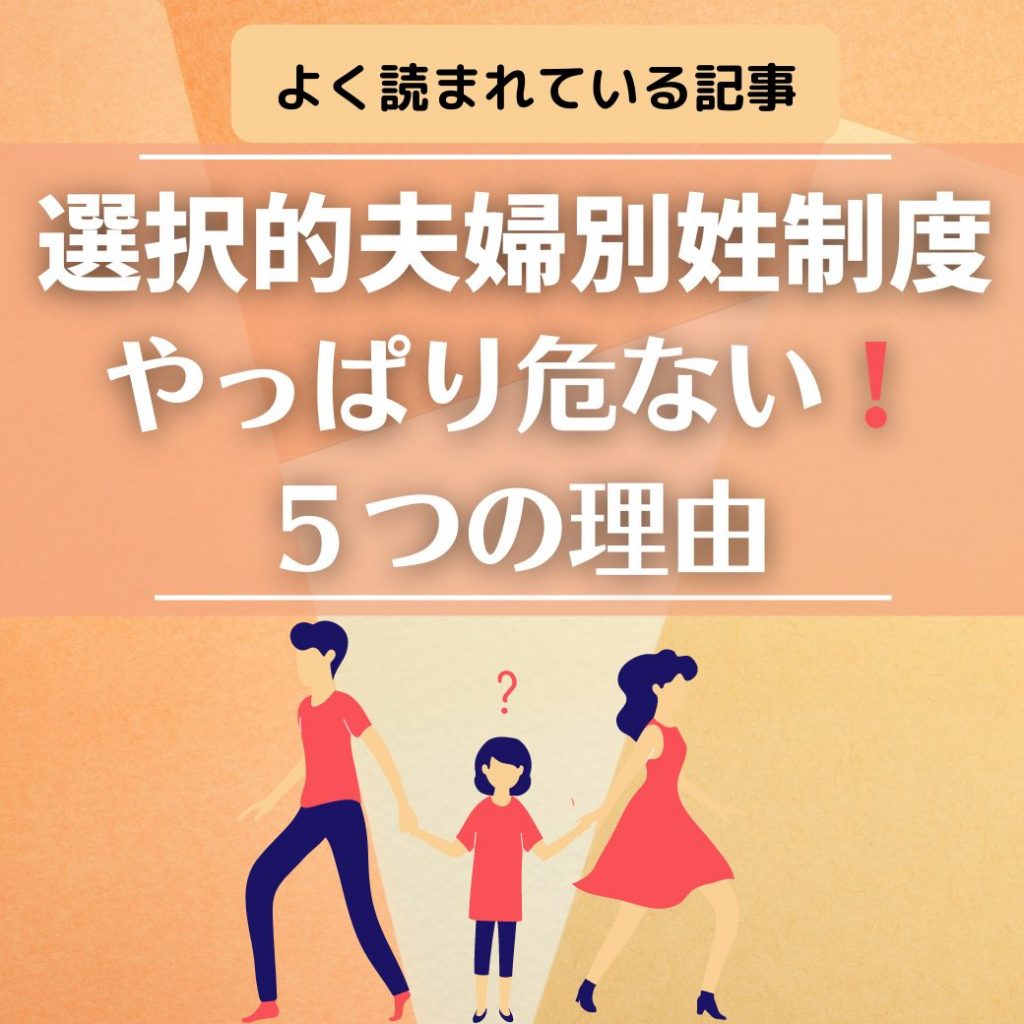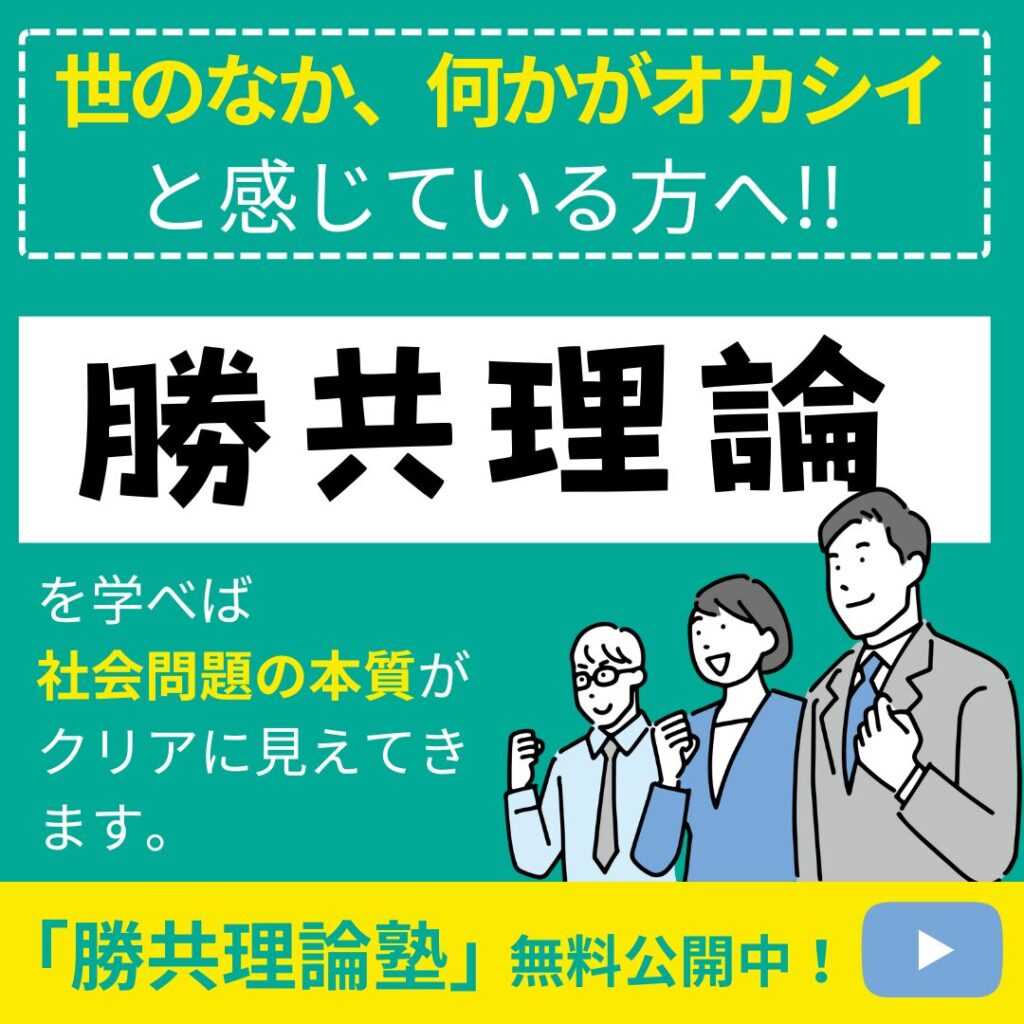「思想新聞」7月15日号から【特別寄稿】の記事を紹介します。
「集団的自衛権」とは自国への攻撃がなくても、同盟国など自国と密接な関係にある国への攻撃を自国への攻撃と見なし、共同で反撃できる国際法上の権利で国連憲章51条で認められている。欧米32カ国加盟の北大西洋条約機構(NATO)では、条約中に集団的自衛権を明記する。第2次安倍政権が2014年に同盟国である米国との集団的自衛権の行使容認の閣議決定し10年が経過。同閣議決定による15年の「安保法制」に基づき岸田政権は「安保3文書」を策定、「敵基地攻撃能力」(反撃能力)の保有を宣言。米国製長射程巡航ミサイルの導入や、スタンドオフミサイルなどの開発を進める。これら「反撃能力」は日米同盟の抑止力を強化するものである。
厳しい安全保障環境を完全に無視する「反対論」
14年当時、「安保法制」に対し、共産党、民主党、社民党は、「戦争法」「徴兵制になる」などと激しく反対したが、10年経ってもそんな事態にならず、日本の平和は保たれている。にもかかわらず、今も共産党や立憲民主党、社民党などは集団的自衛権に反対し閣議決定の撤回を要求している。
ただし立民は今は「違憲部分」のみに反対すると主張を変更するもその内容は明確ではない。これら野党の反対理由は、自国が攻撃されずに米国が攻撃された場合に米国と共同で反撃すれば憲法9条の平和主義・専守防衛の理念に反し、日本は「米国の戦争に巻き込まれる」というものだ。
だが安保法制上、日本の集団的自衛権行使は、無条件ではなく、米国への攻撃が「日本の存立を脅かす事態」に限られる。このような存立を危機事態における集団的自衛権の行使は、安全保障上憲法9条も許容する権利で違憲ではない。
反対勢力はこの点を無視している。集団的自衛権に反対する宮崎礼壱元内閣法制局長官は、他国に加えられた武力攻撃を阻止する集団的自衛権の行使は憲法上許されないとの1972年10月14日の政府答弁書を根拠に閣議決定による憲法解釈変更は違憲と主張(「しんぶん赤旗」7月3日)。
しかし、50年以上も前の政府答弁書を根拠に違憲論を主張すること自体、法解釈上も相当ではない。なぜなら法解釈は時代と共に変化するのであり、憲法解釈も例外ではないからだ。50年前には現在のように、南シナ海、東シナ海、台湾有事、尖閣有事など「力による現状変更」を躊躇しない核を含む軍事大国化した覇権主義の中国や、核保有国として核ミサイル開発や発射実験に邁進する北朝鮮による北東アジアの軍事的脅威は存在しなかったのである。元長官の上記主張は50年後の現在の極めて厳しい安全保障環境を完全に無視するものであり、憲法解釈上も安全保障上も相当ではない。
2015年、安全保障関連法をめぐり荒れる参院本会議場
侵略へのハードルを極限まで引き上げる
このように、「集団的自衛権反対論」は日本を取り巻く厳しい安全保障環境を完全に無視することに共通点がある。上記の政党や論者は日本の存立と日本国民の安全より「憲法9条」を優先し、これを絶対視し金科玉条とする、まさに「本末転倒」と言えよう。
NATOの集団的自衛権の実態を見ても、その核を含む抑止力は絶大で、1949年のNATO発足以来、これまでに加盟国が侵略された事例は皆無だ。とりわけ核を含む対露抑止力は盤石であり、だからこそ長年中立政策をとってきたフィンランドやスウェーデンさえもNATO加盟へと雪崩れ打ったのであり、ロシアから侵略されたウクライナもNATO加盟を切望しているゆえんである。
日本の米国との集団的自衛権についても、対中、対露、対北朝鮮への核を含む抑止力は絶大である。なぜなら核を含む世界最大最強の軍事力を有する米国との集団的自衛権に基づく「日米共同防衛体制」の構築は、上記国からの日本に対する侵略へのハードルを極限まで引き上げるからだ。
自国を単独で防衛するよりも、集団で防衛する方が遥かに合理的であり効果的であることは自明である。とりわけ、日本のように自国のみで十分な防衛体制を講じることが困難な国にとっての国益は計り知れない。「集団的自衛権」に反対する上記野党や論者は、このような米国との「集団的自衛権」が有する絶大な抑止力を完全に無視しており、日本の国益を著しく損ねるものである。
(外交評論家 加藤成一)