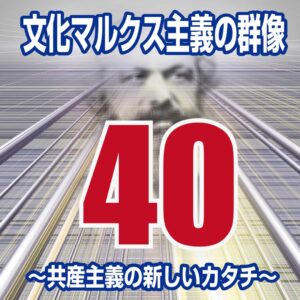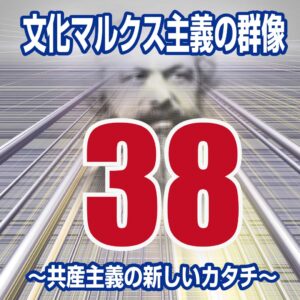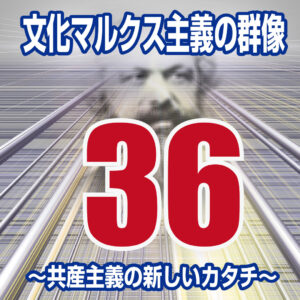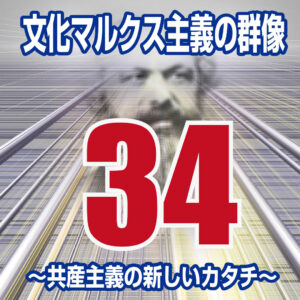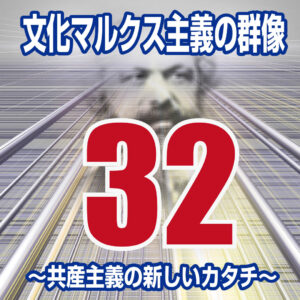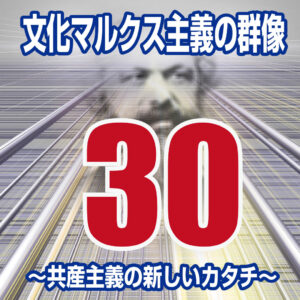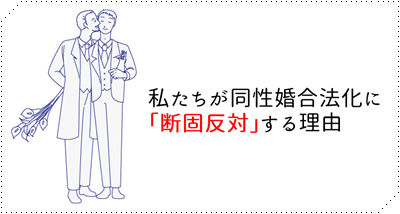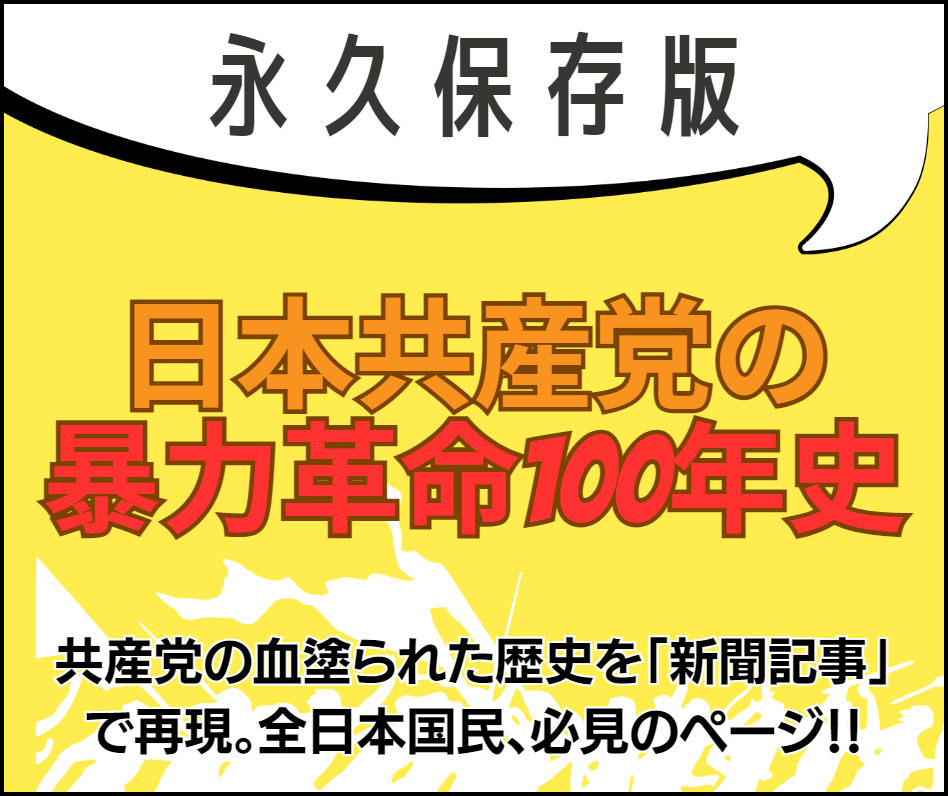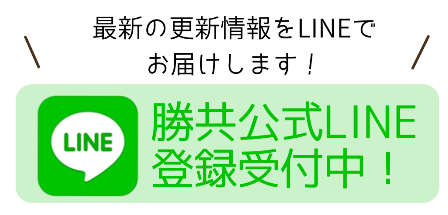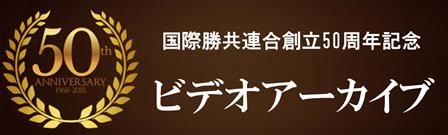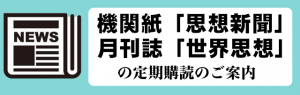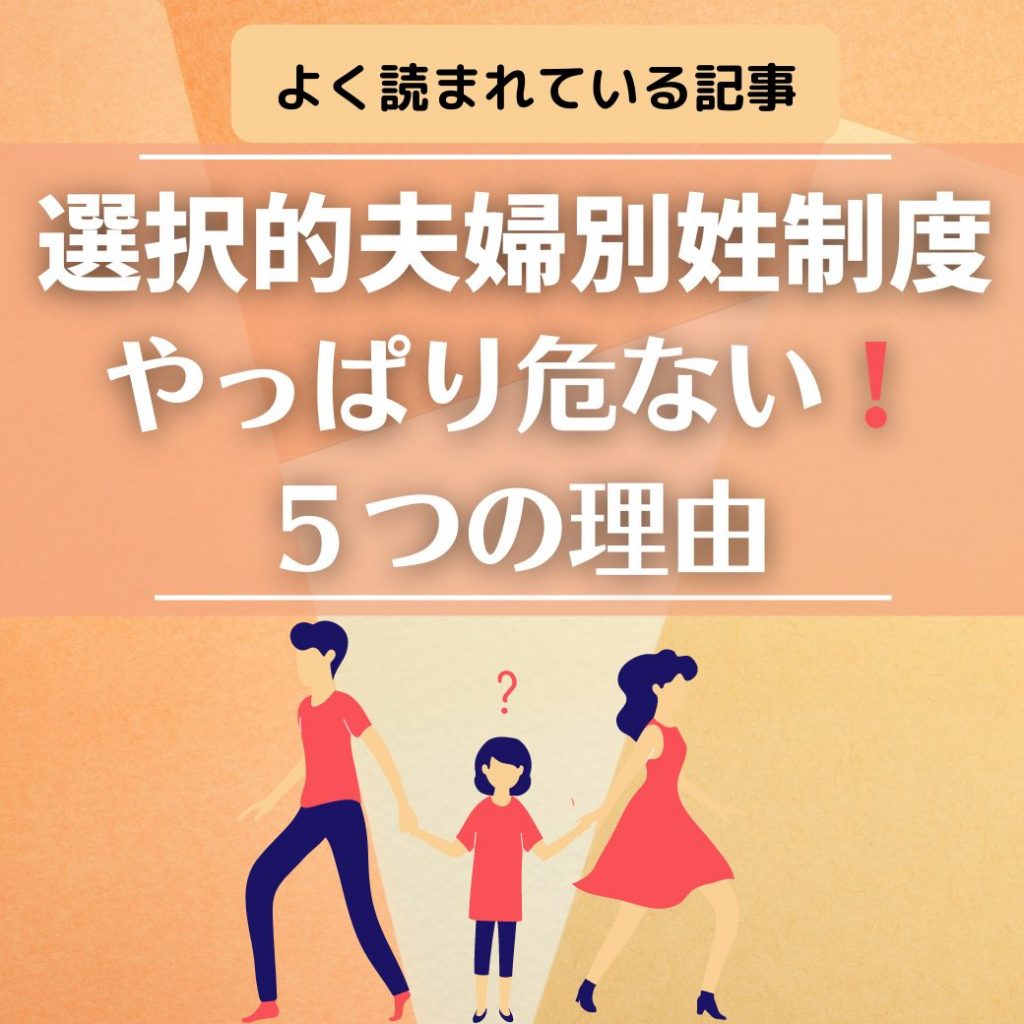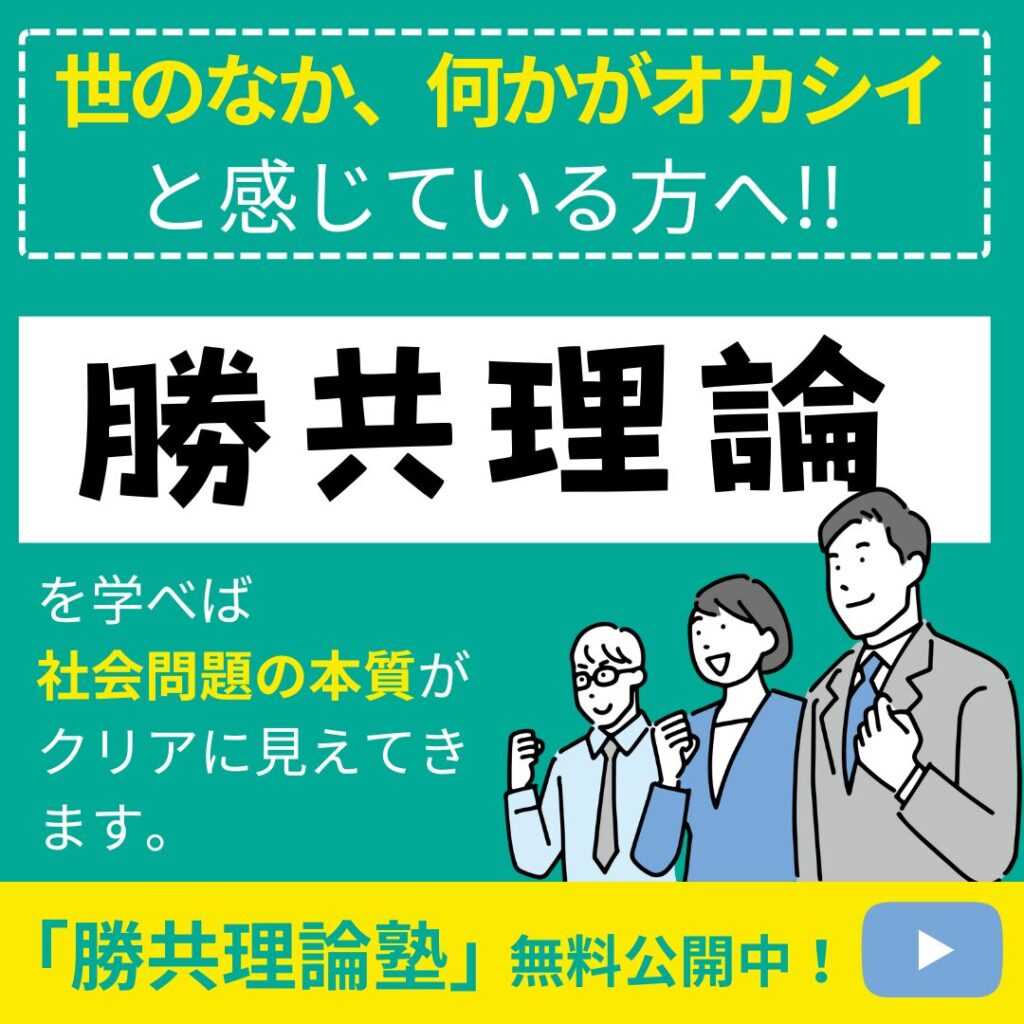日本人と天皇の意味を分析
ルース・ベネディクト
ルース・ベネディクト(1887〜1948)
日本文化論の『菊と刀』を書いた米国の人類学者ルース・ベネディクトは、ミードとは同じボアズ学派に属する「姉弟子」でした。彼女は元来、日本文化を専門とする文化人類学者ではありませんでした。ポストモダン思想は「反西欧」から知日へ向かう傾向がありますが、今回はベネディクトと米国が日本の「天皇制」について考えた問題について若干触れてみましょう。
前回とりあげたミードに対して、師のボアズ教授と共に「先輩」のルース・ベネディクトの影響が極めて大きいとD・フリーマンは述べています。
ベネディクトと言えば、日本人にとって『菊と刀』で知られるように、ミード以上に日本になじみ深い文化人類学者と言えるかもしれません。
とはいうものの、『菊と刀』は今日、外国人による画期的日本文化論という歴史的評価にもかかわらず、「文化の型」というカテゴリーを武器にして、日本を「外的な恥の文化」と断じ、「国策による対日戦争と占領政策を正当化した書」という側面を否定することはできません。
米軍戦時情報局の海外戦意分析課で働く
さて、ルース・ベネディクトが、国策に基づき「日本文化の型」を分析・研究した『菊と刀』の原型となった報告書では、特に文化間の優劣を斟酌するような研究ではなく、むしろ極東軍事裁判で昭和天皇の「戦争責任」を訴追する勢力に対し否定的なアドバイスを行ったようです。この点、ポーリン・ケント龍谷大学助教授が「『菊と刀』 のうら話」と題する論文で、対日戦争の最中、米軍の戦時情報局の海外戦意分析課で働いたベネディクトを次のように述べています。
◇
一九四四年に入ると、戦争の中心がだんだんヨーロッパから太平洋の方へ移ります。そこで日本という敵国に ついて情報を集める必要性が生じ、夏から海外戦意分析課が設立されます。ここでは日本の軍隊と市民はいつまで戦う気かを予想することが仕事の中心で、文化人類学以外にも、政治学、社会学、心理学、日本のことをよく知っている日系人などの専門家三十人ぐらいが集まって課が構成されました。ですから、ベネディクトが一人で日本のことを調べていたのではなく、大きな研究チームで行いましたので、早いペースでたくさんの情報を処理することができました。
『菊と刀』
海外戦意分析課では、主に海外で捕虜となった日本の兵士の面接データを分析して日本人の考えていることを想定しました。例えば、日本人は天皇についてどう考えているかということも大きな課題でした。何千人のデータのうちの三千人ぐらいが天皇について何かをコメントし、そのうちたったの七人しか悪口を言っていません。ここから日本人にとって天皇が大変重要な存在であることが判明しました。連合軍にとって天皇はヒトラーのような存在で、当然死刑にすべきだと信じていました。しかし海外戦意分析課では、天皇を死刑にすれば日本の社会的秩序が一気になくなるだろうと予測しました。ちょうど終戦前、天皇の問題をどう扱うかを決める会議が行われ、情報局の代表として出席したのがレナード・ドゥーブという人だったのですが、彼女はベネディクトのことをよく知りその判断力を尊敬していましたので、ベネディクトに相談しています。ベネディクトは、天皇を死刑にすれば日本人は絶望的になる、ヒトラーと同じように扱うことは事実の単純化にすぎない、などとアドバイスしました。結局、会議ではプロパガンダで天皇の悪口を言ってはならない、天皇の死刑は占領に悪影響をもたらすだろうという方向づけがなされ、天皇を特別扱いにする結論となりました。
『タイム』見出し「彼女が天皇を救った」
戦後『タイム』誌にベネディクトの記事が載せられた時、見出しは「彼女が天皇を救った」(She saved the Emperor)となっていました。ベネディクトがどこまで決定に影響を与えたのかはっきりしませんが、そのアドバイスが何らかの形で高いレベルに届いたに違いありません。海外戦意分析課には捕虜の面接以外にも、日本の新聞やラジオ放送、兵士から没収した日記や手紙、あるいは時々入ってくる軍事機密などの情報が、連合軍の最新情報とともに入ってきました。
課では「日本人はどこまで戦う気か」を分析しながら、日本の兵士に「早く降参しよう」というパンフレットやチラシをまきました。日本人に最も説得力のあるメッセージとはどんなものかを探るのも海外戦意分析課の仕事でした。
そこでベネディクトは主に新聞報道やラジオ放送を担当していました。アメリカでは日本人は訳の分からない人たちで、天皇のために自分の命がなくなるまで戦う恐ろしい敵だ、というイメージが非常に強かったのです。この「訳のわからない日本人」を説明するために、他の研究者は日本人の性格が強迫的なので攻撃的になる とか、アメリカの十代の青年と同じぐらいの精神年齢なので、十代の青年として調べたらわかるだろうとか、暴力団の心理に似ているからギャングと比較できるだろう(ミード) とか、まさに「訳の分からない研究方法」を用いて日本人の性格を解明しようとしました。つまり、西洋社会で発達した理論や方法を、西洋社会で適用する心理学的な方法と同じように、日本社会に適用しようとすれば、当然、結果的に日本人は「アブノーマル」に見えてきます。しかし、ベネディクトは自分のそれまでやってきた文化人類学の研究から、日本人には安定した文化的なパターンがあるとわかっていたので、日本人の行動をアブノーマルなものとして受け取るのではなく、日本人にとってその行動にどのような意味があるのかということを探ろうとしました。
◇
こう見ると、日本人の精神をヤクザ的と解したミードに比べれば、ベネディクトは非常に冷静でした。
ただ天皇不起訴の背景には、日米双方に通じた人脈も一役買っていました。もちろん、マッカーサーとの会見で「私はどうなってもよいから国民を助けてほしい」という昭和天皇の人格に深い感銘を受けたこともあったでしょうが、マッカーサーの補佐官だったボナー・フェラーズ准将が知日派であり、新渡戸稲造の弟子・河井道らキリスト教人脈も不起訴に働いたと言われます。
戦後、「共産主義者」の嫌疑がベネディクトにかかります。師のボアズはユダヤ人で、1933年にドイツでヒトラー政権が成立すると、反ナチの旗幟を鮮明にユダヤ人支援活動を精力的に行います。アーリア人種優越を説きユダヤ人抹殺を政策とするナチスに対し、ボアズはイデオロギー的にも対極にありました。信条的には反共だったと言われますが、「反ナチ」という点で、多くの亡命ユダヤ人を庇護する中、共同歩調を取ったと言えるでしょう。
考えてみれば、米国の国策としても、「反ナチス」からすれば、人種主義よりむしろ文化決定論に与したと言えます。ファシズムとの戦いこそが至上命題だったのです。その意味では、ベネディクトが保守的よりは進歩的、リベラルな思想に傾斜していったとしても不思議ではありません。
ミードとベネディクトは同性愛だった?
彼女はもともとミセス・ベネディクトとして、子に恵まれず社会活動など「脱主婦業」の一環で文化人類学を聴講し始め、コロンビア大大学院の博士課程をわずか一年半で修了するほどの才能を見出されます。
ヒラリー・ラブスリーの『マーガレット・ミードとルース・ベネディクト』(伊藤悟・訳)やケント龍谷大助教授も指摘するように、ベネディクトとミードとが単に同僚や親友の関係以上に恋人、つまり同性愛関係(レズビアン)にあったようです。かくて文化相対主義とは、国際理解には有効ではあれ、文化破壊にもつながる「両刃の剣」なのかもしれません。
(「思想新聞」2025年3月1日号より)