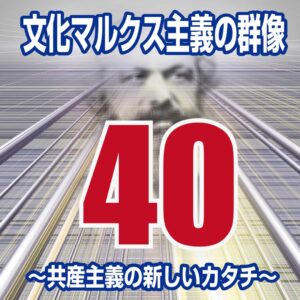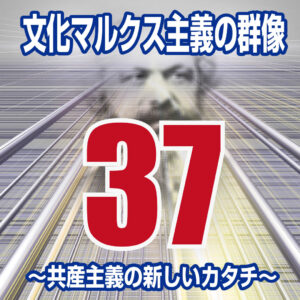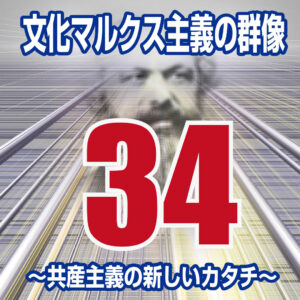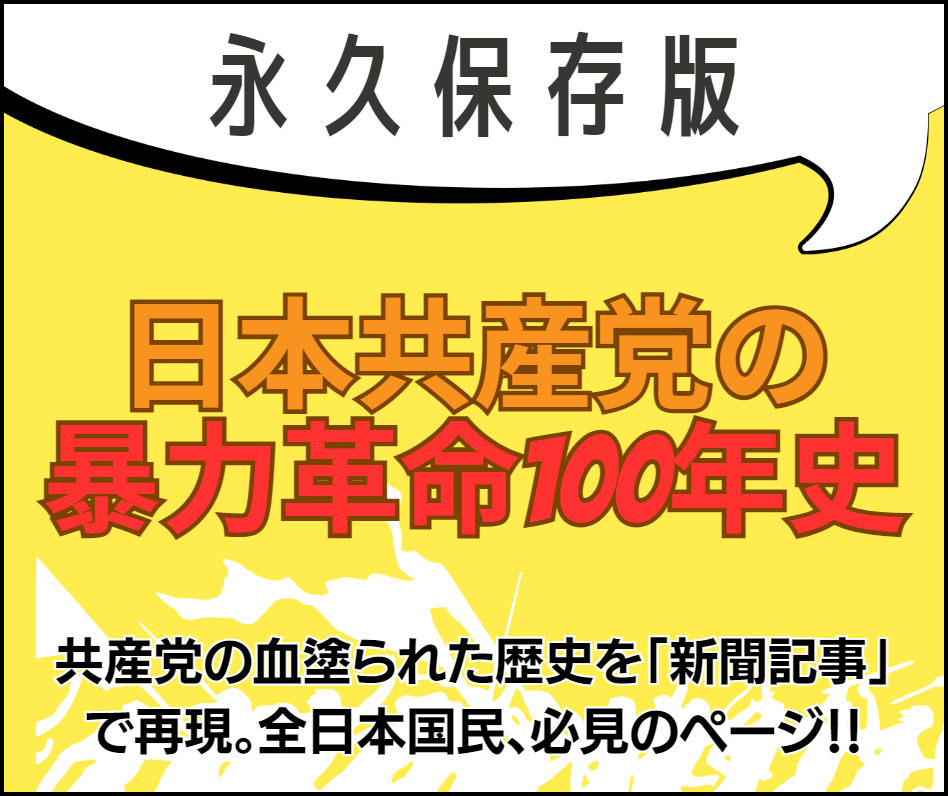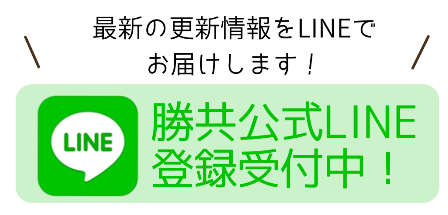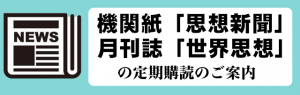反権力としての「ラングの専制」
ロラン・バルト(上)
構造主義・ポスト構造主義・ポストモダンと称される思想群には、総じて「反西欧」「反コギト中心主義」などといった共通するトーンを帯びていることがわかります。そしてそれは「個人的原子論」とも言うべきものに彫琢されて姿を現します。ロラン・バルトの「構造主義的記号論」も、その典型例と言えます。。
無ポストモダン思想に共通するトーン
この「共通のトーン」とは、「反西欧(=「反キリスト教」)」「反コギト(思惟する自我)=反形而上学」「反理性主義」で、これはどんな構造主義関係の入門書・参考書にも共通して強調される特徴です。
確かに、この「共通のトーン」にあるのは、人間個人の「決断」と「主体性」が特筆大書された「実存主義思想」の対極にあるものであることが窺えます。
ここで考えたいのは、前回も触れた宗教をめぐる「二つの民主主義の流れ」の模式図で表わされた「差異」が現代にまで洋の東西を問わず、国家・社会に影響を及ぼす可能性です。
レヴィ=ストロースが否定したのは、あくまでサルトルのマルクス主義的実存主義であり、マルクスの考え自体の全否定ではなかったのです。このため、東洋的なマルクス主義(例えば毛沢東主義)が、ソ連主導マルクス主義(スターリニズム)に対し不満を抱く勢力の受け皿となりました。
その毛沢東流のマルクス主義(マオイズム)を信奉したのが、構造主義的マルクス主義者でフランス共産党員であったアルチュセールです。彼らにとってマルクス主義は「西欧」よりも、アジアやアフリカなどの「第三世界」で輝きを増す「真理」と映ったのです。
ところがその一方、マルクスの思想こそ実は「過った民主主義」つまり「全体主義」(ファシズムと共産主義)へと帰結するイデオロギーと考えたのが、先に紹介し「二つの民主主義の流れ」を説く政治学者A・リンゼイでした。この考えに近いのが、実は宗教哲学者マルティン・ブーバーの「我と汝」の考え方です。
ポストモダンと個人的原子論の彫琢
バルトが主張する「ラング(母国語)の専制からの解放」というものは、コミュニケーションから形成される人間の絆を断ち切り、個々人に切り離してしまうことになりかねません。ましてや権力論を唱えるミシェル・フーコーの立場を援用するならば、「母国語」(ラング)は「権力によって恣意的に定められた。従ってそんな権力のルールに従う必要などない」と考えてしまいます。
かくして個々人が家族や社会から切り離されたいわば一種の「個人的原子論」というべきものが彫琢され正当化されて、それが個人主義的政策に反映していくことになります。
この「ラングの専制」に対してバルトの唱える「異論」とは、わかりやすい例として挙げれば、「日教組」教師らが唱える「日の丸・君が代の強制は憲法違反」という主張であったり、「入学式・卒業式は国家によるエリート意識植え付けの場であるからこれを粉砕しなければならない」という「入学式・卒業式粉砕闘争」の論理などです。
この「極左」の論理では、「国家機関という装置から自治を勝ち取って大学が存在している」という神話を根拠もなく一方的に信じているにすぎないのです。だからそこには、自分の親が払った税金によって大学が運営されている、という視点が全くありません。
源流としてのマルクス・フロイト・ニーチェ
もっとも、西欧哲 レヴィ=ストロースの打ち立てた構造主義は、やがて彼自身の思惑と離れ、構造主義からポスト構造主義へと向かうことになります。アラン・ブルームが米アカデミズムに吹き荒れた性解放運動を告発した『アメリカン・マインドの終焉』で強調したのは、マルクス主義、フロイト主義、左翼化したニーチェ主義です。ブルームに加え、内田樹・神戸女学院大名誉教授は「構造主義というのは、…私たちは自分では判断や行動の『自律的な主体』であると信じているけれども、実は、その自由や自律性はかなり限定的なものである、という事実を徹底的に掘り下げたことが構造主義という方法の功績なのです。……これが前-構造主義期において、マルクスとフロイトが告知したことです」(『寝ながら学べる構造主義』)と述べ、さらに「人間の思考が自由ではない」と主張したニーチェを加え、構造主義に連なる3つの源流と指摘します。
この内田氏の構造主義解釈は、マルクス主義への評価と共に非常に肯定的です。しかしレヴィ=ストロースに限れば、内田氏の評価は極めて正当なものです。「近親相姦の禁忌」など人類共通に見られる規範習俗、伝統文化の独自性についてレヴィ=ストロースは尊重しているからです。
コギト神話解体叫ぶ「お一人様」思想
こうした難点というものは、いやしくも「科学」あるいは「学問」というものを標榜した時から、厳しい批判の目にさらされます。それはマルクス主義であれ、現象学であれ、○○思想であれ変わりません。
「コギト神話解体の系譜」とはニーチェ哲学に起因し、ポストモダンに連なると言われます。
この「コギト」とは、何度も言うようですが、近世哲学(大陸合理論)の祖とされるデカルト哲学における「われ思う、ゆえにわれ在り」(コギト・エルゴ・スム)の「われ思う(コギト)」からきたものであり、「思惟するこの私」が「私という存在」を保証していたものでした。この「思惟する私」以外のいっさいのものは疑う、というのがデカルトの「方法的懐疑」の立場でした。
ところがここで問題提起したいのは、「コギト神話の解体」と言いながら実は、コギト中心主義に陥っているのが、ポストモダン思潮ではなかったでしょうか。なぜなら、人と人の「つながり」「関係性」というものを切り離し、捨象したところに残ってゆくものは、つまるところ「独我論」でしかないからです。
「我-汝」vs「我-それ」のブーバー流世界観
さて、宗教哲学者マルティン・ブーバーはこうした状態を、「われ—それ」の世界観と述べました。現代風に言えば、「おひとり様の世界観」ということになるでしょう。これに対し、自分が呼べば応え反応してくれる、関係性を重視した人間観・世界観を、ブーバーは「われ—なんじ」の世界観と呼びました。「おひとり様」とは反対に、「同伴者のいる思想」ということになるでしょう。
ホッブズ〜ベンサム〜マルクスという「過てる民主主義の系譜」からは、全体主義と独裁が出現しても、「利他性」「自発的善」というものは決して導き出されることはありません。
自発的善と利他性保障する正統民主主義
その一方で、ピューリタニズム〜カント〜ウェーバーという「正統的民主主義の系譜」からは人間の利他性への信頼というものが明確に存在しています。
現代は宗教不信の時代と言われます。オウム真理教やイスラム原理主義勢力によるテロ、直近では旧統一教会問題でますます拍車が掛かっています。
しかしながら宗教は、この利他性と自発的善のゆえにピューリタニズムによる近代民主主義の源流となったと言えます。逆に洋の東西を問わず、こうした利他性と自発的善が保障されなければどんな宗教であっても結局、人々の間に受け容れられないのではないでしょうか。つまるところ人間の信ずる信仰・信条・信念は、「内なる精神の自由」によってしか動かないからとは言えないでしょうか。
日本の因果応報思想的な「贈与の円環」
![]() レヴィ=ストロースにとってサルトルのマルクス主義実存哲学こそ真っ向から対立した「天敵」です。しかしソシュール記号学を構造主義的立場で引き継いだロラン・バルトは、サルトルの「アンガージュマン」思想を文学領域におけるマルクス主義として展開しようとしたのです。
レヴィ=ストロースにとってサルトルのマルクス主義実存哲学こそ真っ向から対立した「天敵」です。しかしソシュール記号学を構造主義的立場で引き継いだロラン・バルトは、サルトルの「アンガージュマン」思想を文学領域におけるマルクス主義として展開しようとしたのです。
ポストモダンと称される構造主義・ポスト構造主義思潮における柱の一つ、「反(または脱)コギト中心主義」「コギト神話の解体」という考え方が実は、「コギト」(思惟する私が存在を規定し、保障する)の枠組みから抜け出ることができていない、それはなべて「われ-なんじ」の世界観ではなく、「われ-それ」の独我論(お一人様)的世界観を体現していると指摘できます。
そうした構造主義思潮のうち、例外として注目に値するのが、「贈与の円環」という一種の「利他的世界観」です。これはたとえて言えば、「情けは人の為ならず 身に廻る」(世話尽)と因果応報的思想にも通じる世界があると言えます。
そしてレヴィ=ストロースによる新しい切り口(「贈与の円環」という行動様式)は、ロラン・バルトにおいて充分に活かされているとは到底言えず、むしろサルトルが依拠したところの、マルクス主義的実存哲学の方向へと「退化」したと言えるかも知れない、と述べました。
戦後の若者の桎梏となったサルトル
実際、バルトのマルクス主義とサルトル思想からの影響はどのようなものだったか。「戦後民主主義」が、日本のみならず世界的なマルクス主義と実存主義思潮の伸張によって肥大化されていった渦中に、サルトルのアンガージュマン(社会参加=企投)が鎮座し、左翼労働・学生運動を扇動していきました。しかもそれはさながら日教組が「国旗・国歌の強制」だと騒擾する以上に、社会に生きる若者にとって「傍観」「日和見」を許さぬまさに苛酷な「強制」(あるいは桎梏)となったのが、このサルトルの詭弁だと言えます。
トロツキストにマルクス主義を指南
バルトは、スイスのサナトリウム(療養所)で同室になったジョルジュ・フルニエ(義勇兵としてスペイン内戦に参加後、抗独レジスタンス運動に参加したトロツキスト)が、「バルトにマルクスやトロツキーの思想を手ほどきしたというのです。サルトルがスターリンを批判し毛沢東主義になったように、バルトも、スターリンと袂を分かちスターリンに追放・暗殺されたトロツキーの思想的影響を受けたことが窺えます。
【資料】ソシュールからバルトへ受け継がれた「ラングの専制」
「ラング(母国語)の専制。この問題が終生ソシュールを苦しめた。『言語学でなし得ることの大きな空しさがわかった』という言葉は切実だ。この問題が容易に解決の道が見出せないことは、次のロラン・バルトの文章からも理解できるだろう。バルトは、ソシュールの困難を同様に自覚した一人である。『権力が……持続し遍在するのは、権力が、社会の枠を越えたある組織体に寄生しているからである。その組織体が、単に政治の歴史や有史以後の歴史だけでなく、人間の来歴全体と密接に結びついているからである。人間が存在して初めて以来ずっと権力が刻み込まれているこの対象こそ、言語活動(ランガージュ)である–あるいはもっと正確には、言語活動の強制的表現としての言語(ラング)である』(『文学の記号学』)」(別冊宝島『現代思想・入門』より)
(「思想新聞」2025年9月15日号より)