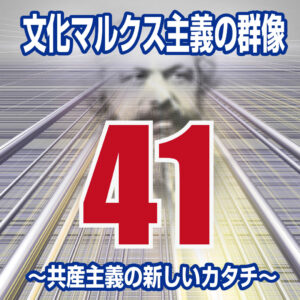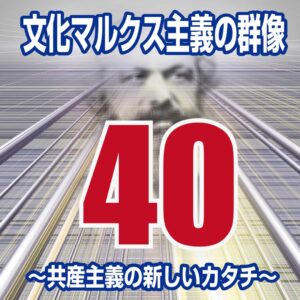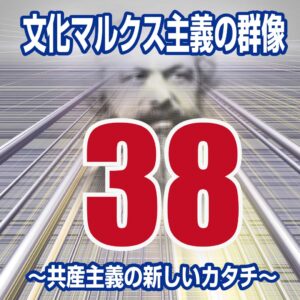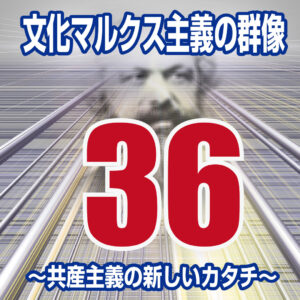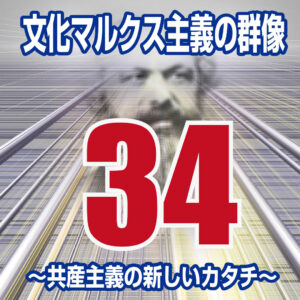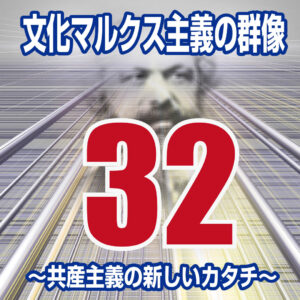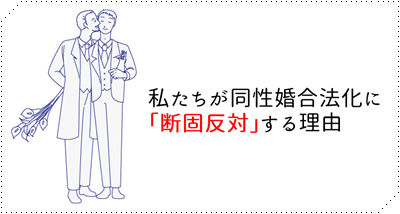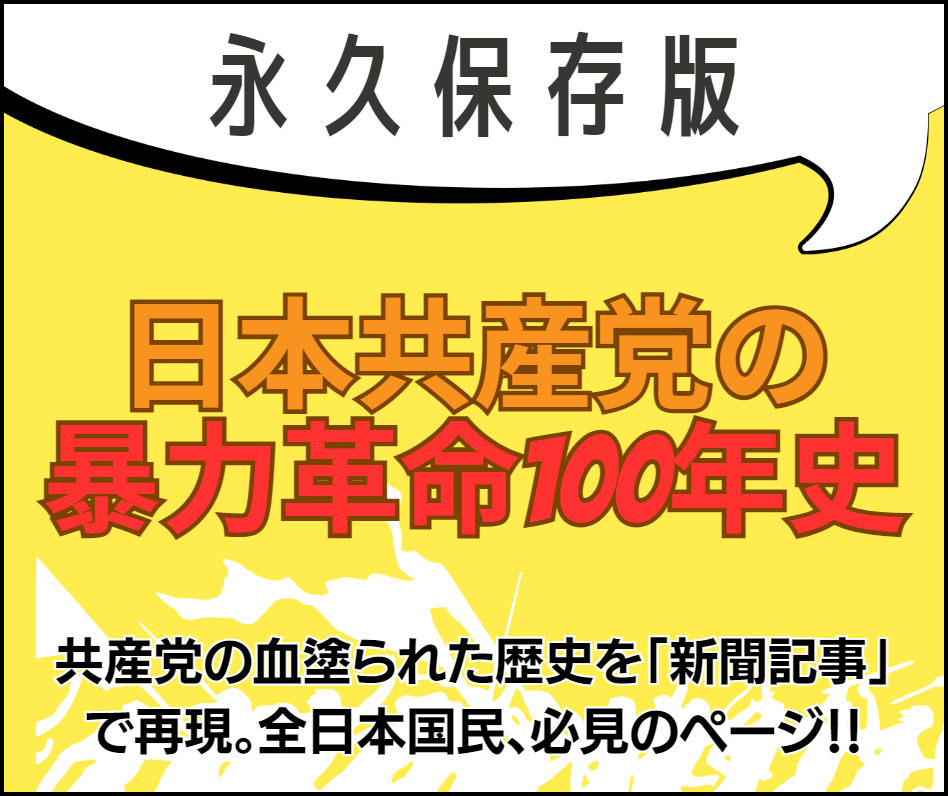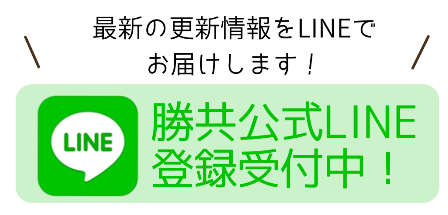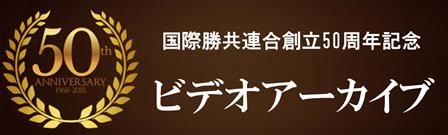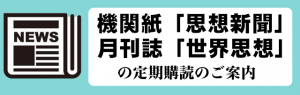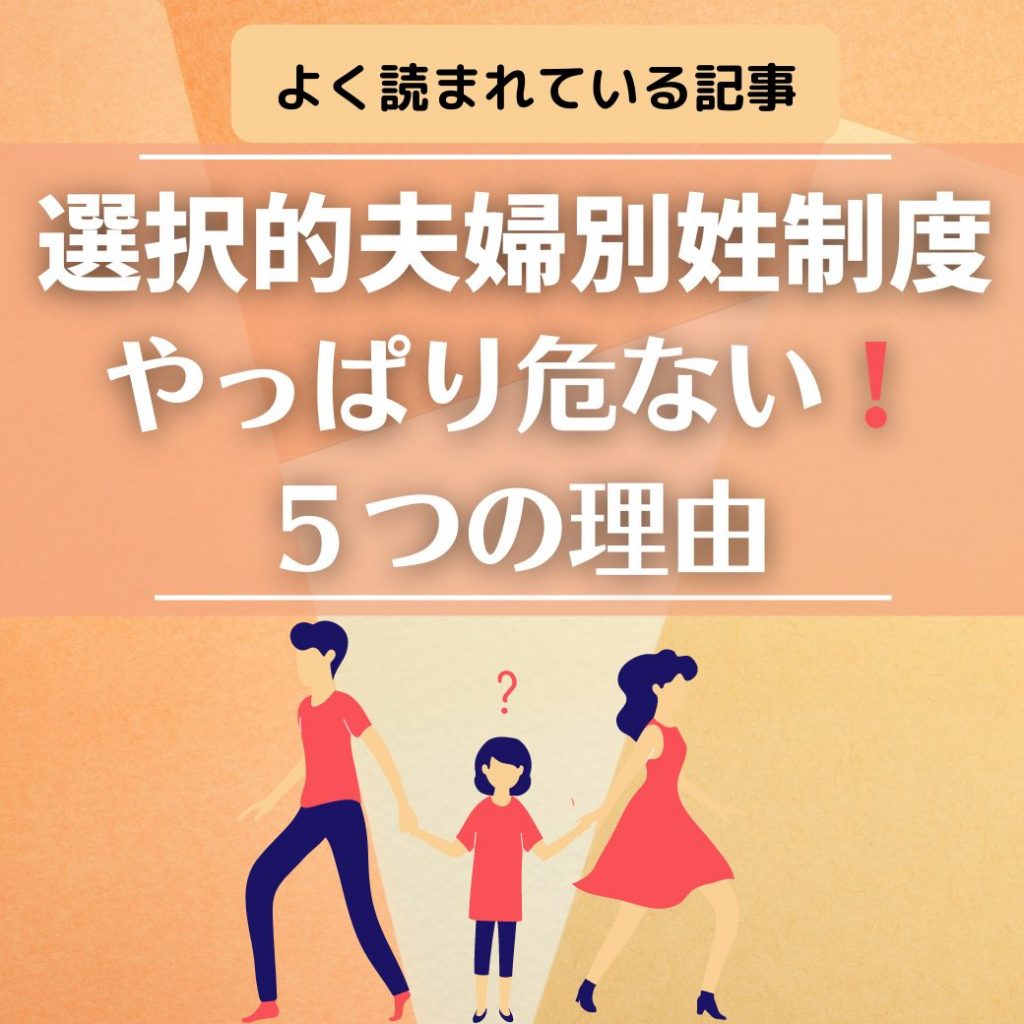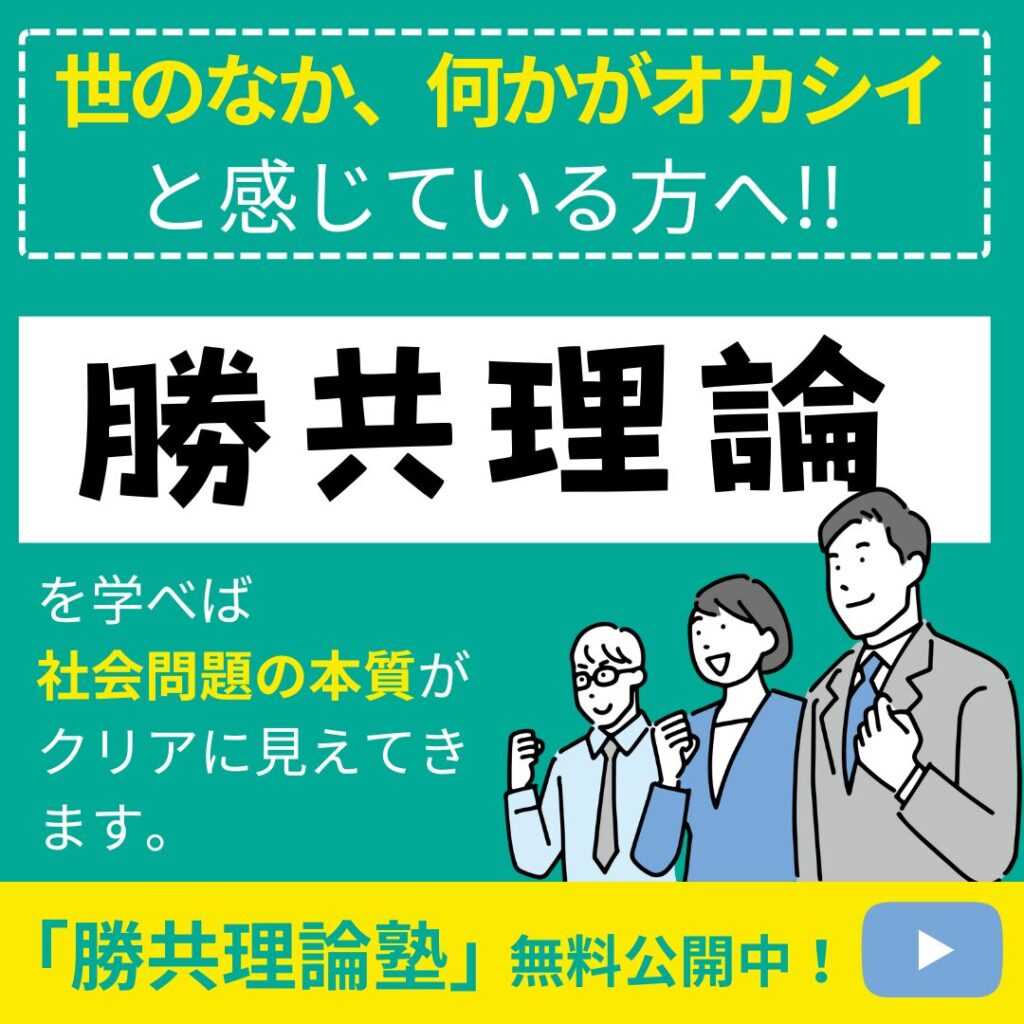スターリン戦争の欺瞞冷笑するバルトーク
ロラン・バルト(中)
ロラン・バルトはソシュールの記号学(論)を敷衍・駆使した構造主義哲学者ですが、当初は文芸批評家として知られました。ここで記号論での「術語」を確認すると、「ラング」は母国語のこと、「スティル」とは「スタイル」、「エクリチュール」とは「言葉遣い」ですが、内田樹氏は「エクリチュールとスティルは違います。スティルはあくまで個人的な好みですが、エクリチュールは、集団的に選択され、実践される《好み》」と解説(『寝ながら学べる構造主義』)。
バルトはマルクス主義における文化・芸術上の理念である「社会主義リアリズム」とは異なる形での「革命的なアンガージュマン(社会参加)のエクリチュール」を模索するのですが、その一方「作者(著作権)の死」をも主張することになります。つまり文学作品などは作者の手を離れれば、生成する「テクスト(織物)」という考え方です。そこで引用などの概念も改めることになります。
バルトークのオケコンとショスタコーヴィチ
ここで想起したいのが、ハンガリーの作曲家ベラ・バルトークのエピソードです。バルトークはブダペスト音楽院教授からナチス台頭後、米国に亡命します。
米国で貧窮に喘いでいたバルトークを助けたいと、指揮者S・クーセヴィツキーは、手兵ボストン交響楽団のために委嘱した作品が、今日「オケコン」として広く知られる「管弦楽のための協奏曲」です。
しかし白血病に冒されたバルトークは曲の完成・初演しほどなく他界(1945)。このバルトークの傑作で諧謔的に引用されるのが、ソ連の「体制派作曲家」、D・ショスタコーヴィチの交響曲第7番です。
ソ連と親和性が高かったF・ルーズベルト米政権では、レニングラードをナチスの手から守った《大祖国戦争》を描いたとされるこの曲は、トスカニーニやストコフスキーら名指揮者により、70分強の大作ながら頻繁に演奏。第5交響曲でソ連政府に「社会主義リアリズム」を体現した作品とされ、「ソ連を代表する作曲家」を確立したショスタコーヴィチでした。
しかし、米国内の「ソ連=正義」という空気一色にもかかわらず、バルトークは冷やかに見ていました。なぜならナチスの侵略から祖国を守ったはずのソ連は、バルト三国やポーランド、ルーマニア、フィンランドなどをドイツと分割しようとしたのです。
つまり「祖国を侵略から守る戦争」とは全くソ連のプロパガンダに過ぎませんでした。ハンガリーも元々、ロシアやトルコといった大国の脅威にさらされてきたのです。「祖国防衛戦」を謳ったともてはやす米国を、バルトークは壮大な茶番に映り、自作品の中で「小国の悲哀(エレジー)」と並べて配置しシニカルに批判したと言えましょう。
バルトークは戦後のヤルタ体制の下で辛酸を嘗めた祖国の運命をもはからずも「予言」したことになるかもしれません(戦後東欧圏に組み込まれ、民主化を求めたもののソ連軍によって武力鎮圧されます〔「ハンガリー動乱」〕)。
ショスタコーヴィチと「ジダーノフ批判」
今日では、ショスタコーヴィチが最も忠実に「社会主義リアリズム」という芸術上のイデオロギーに基づいて作曲した作品としてはオラトリオ「森の歌」がよく知られています。
この「森の歌」が創作された背景は、1948年に「ソ連の芸術家らが西欧モダニズムに毒されている」という共産党中央委員だったジダーノフによる批判により一種の「文化革命」が起こったことにありました。この「第9事件」によってショスタコーヴィチは再び「ブルジョワ(走資派)」のレッテルを貼られて冷遇されることになります。それを打開したいとの意図の下で創作されたのが「森の歌」で、歌詞がスターリン賛美となったのはやむをえなかったと言えるかもしれません。ソ連という共産主義体制の下で生き残ろうとしたショスタコーヴィチのような芸術家は、ある意味苛酷なものでした。しかしこうした「社会主義リアリズム」賛美は、冷戦時代にあって日本をはじめ多くの西側諸国における左翼人士らによって片棒を担がれてきたのです。
さて、ロラン・バルトは「政治的なエクリチュールについては、より真実である。そこでは、言語のアリバイは、同時に、威嚇であり、称賛なのだ。現に、権力なり戦闘なりこそが、エクリチュールの最も純粋な範型を生み出しているのである」と『零度のエクリチュール』に記したように、「政治的」「マルクス主義的」「革命的」と各々のエクリチュールを述べています。
さらに「このようなプチ・ブルジョワ的なエクリチュールは、共産主義的な著作家たちによって、再び取り入れられた。それというのも、指し当たっては、プロレタリアートの芸術的な規範は、プチ・ブルジョワジーのものと異なっていることはできない(これは、教説に合致する事象でもあるが)からであり、また、社会主義リアリズムの教条そのものが、宿命的に、慣例的なエクリチュールへと強制するからである。…そんなわけで、フランスの社会主義リアリズムは、芸術のあらゆる意図的な標章を無節度に機械化しつつ、ブルジョワ的な写実主義(リアリズム)のエクリチュールを、再び取り入れたのだ」と社会主義体制の中の「社会主義リアリズム」を批判し、むしろ西側の左翼ヒューマニズム的な「プチブル的エクリチュール」の方がむしろ、かえってマルクス主義的に言えば「唯物弁証法」に適っているという論旨を展開しているのです。
社会主義リアリズムと「作者の死」
ロラン・バルトは作品が作者の手を離れた瞬間、「《作者》は死ぬ(消滅)」と述べます(「作者の死」)。しかしこれは、作者が物理的・身体的に死を迎えるという意味ではありません。
ある作品Aがあり、作品Aを部分的に引用して別の作者による作品Bが出来上がった場合、著作権の問題はどう扱われるのかというものが問われてくるでしょう。ロラン・バルトと「社会主義リアリズム」の問題について言及します。
「模倣と創造」という考え方があります。「オケコン」にはショスタコーヴィチの第7交響曲の主題が諧謔的に引用されるも、これはいわゆるショスタコーヴィチの著作権を侵害する「盗作」にあたりません。このバルトークの場合は引用が主題の一部であり、作品引用の意図が明確で、バルトークの作品としてのオリジナリティは保たれています。
ところが、現代イタリアの作曲家ルチアーノ・ベリオの「シンフォニア」の場合、問題はもっと深刻で露骨です。この作品の第3楽章は実はG・マーラーの交響曲第2番《復活》第3楽章がそのまま引用され、さらにストラヴィンスキー、シェーンベルク、ベートーヴェン、ドビュッシーなどの作品を細切れにして繋げた「コラージュ」で、現代音楽では特に知られた作品です(ニューヨーク・フィルの委嘱作品として作曲された)。しかし、そうしたコラージュ作品というものが果たして「作曲行為」と呼べるのかという根源的な問いを振りまきある種のスキャンダルを呼びました。
ところでショスタコーヴィチの名誉のため言えば、第9番の後の「第10番」は、スターリンの死後発表され、反スターリン的な「最高傑作」という評価の高い作品となっています。
さて、ベリオの「シンフォニア」のようなコラージュ作品には果たして「著作権」を主張する「資格」があるのでしょうか。もちろんベートーヴェンやモーツァルトなど、死後1世紀以上も経っている作曲家の作品に1次的な「著作権」は存在しないでしょう。
明確に「原曲」があるにもかかわらず、それには著作権が存在しないため、歌の著作権がその歌手ないしグループにあるとなると、「そもそも著作権っていったい何なの?」という釈然としない疑問に戸惑うことも出るかもしれません。
テクストの生成と作者の死の意味
このような「著作権をめぐる問い」に対して一つの解釈を与えるのが、バルトの「テクストの生成」と「作者の死」の考え方です。そこでは、書物や文書、芸術作品など「作者によって書かれたもの」とは、「読み手(ないしは鑑賞者)によって編み上げられるテクスチャ(織り物)にほかならない」と見なす立場で、一種の「存在=生成論」と見なしてよいと思われます。こうした立場は、例えばハイデガーやフッサールの現象学、西田幾多郎といった思想にも通じる世界があると指摘できましょう。
これを、内田樹氏が「オープンソース」としてのリナックス登場の背景を説明しています(『寝ながら学べる構造主義』)。
◇
インターネット上でのテクストや音楽や図像の著作権についていろいろな議論が展開していますが、バルトは今から40年前に、既に「コピーライト」というものを原理的に否定する立場を明らかにしています。
作品の起源に「作者」がいて、その人には何か「言いたいこと」があって、それが物語や映像やタブローや音楽を「媒介」にして、読者や鑑賞者に「伝達」される、という単線的な図式そのものをバルトは否定しました。…「コピーライト」あるいは「オーサシップ」という概念は、その文化的生産物が「単一の産出者」を持つ、という前提がないと成り立ちません。「作者」とは、何かを「ゼロ」から創造した人です。聖書的な伝統に涵養されたヨーロッパ文化において、それは「造物主」を模した概念です。誰かが「無からの創造」を成し遂げた。そうであるなら、創造されたものはまるごと造物主の「所有物」である。そう考えるのはごく自然なことです。
近代までの批評はこのような神学的信憑の上に成立していました。つまり、作者は作品を「無から創造」した造物主である、と。
(「思想新聞」2025年10月1日号より)