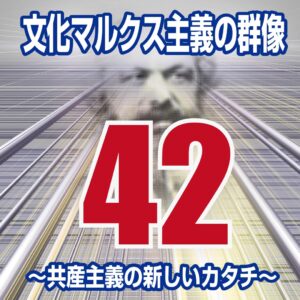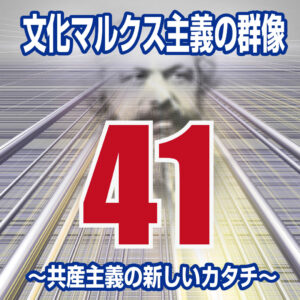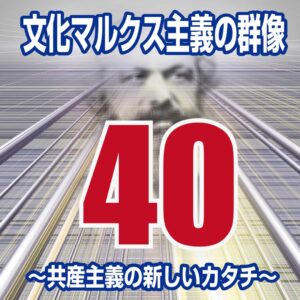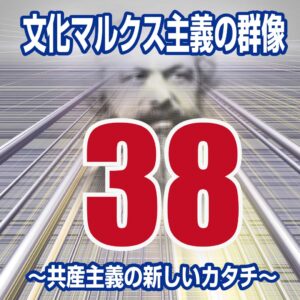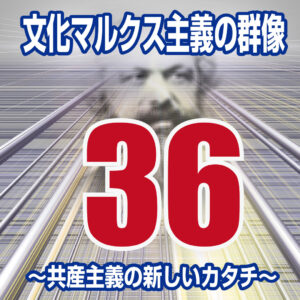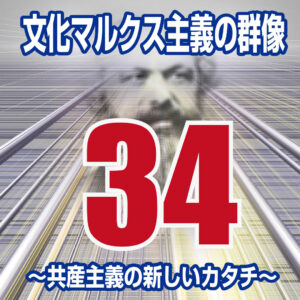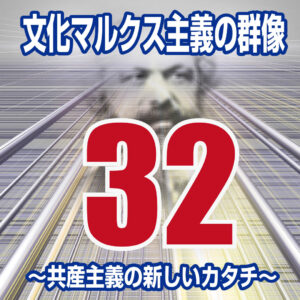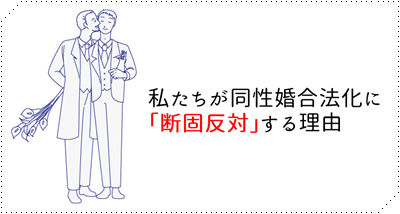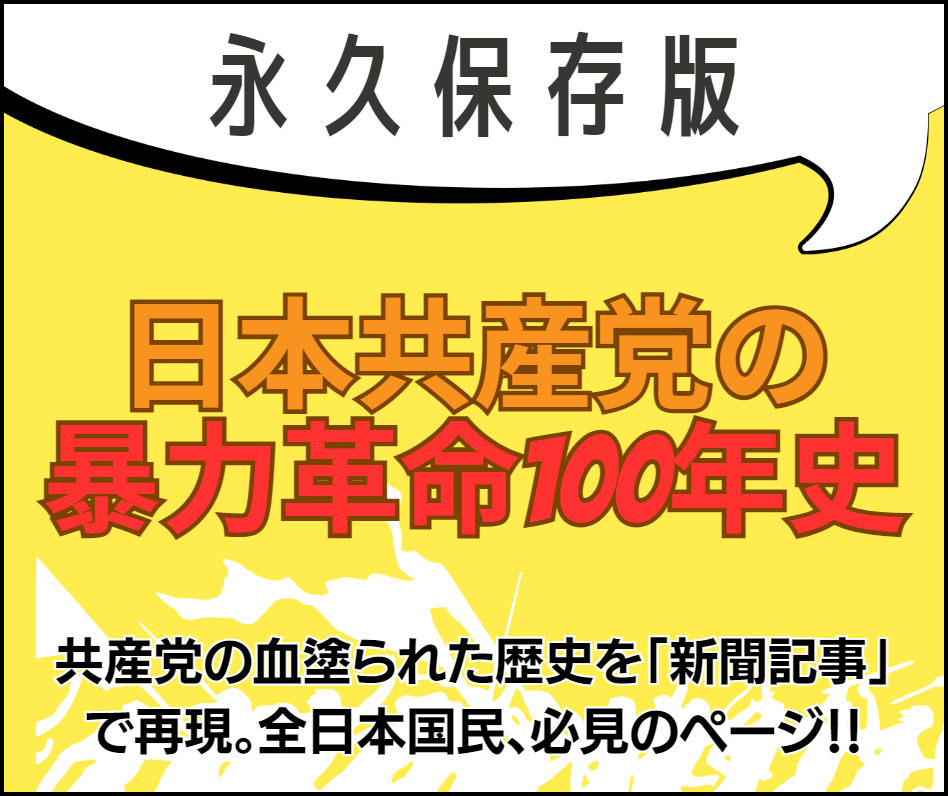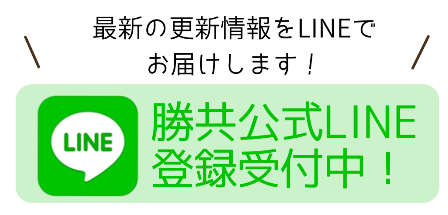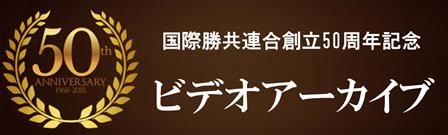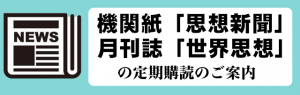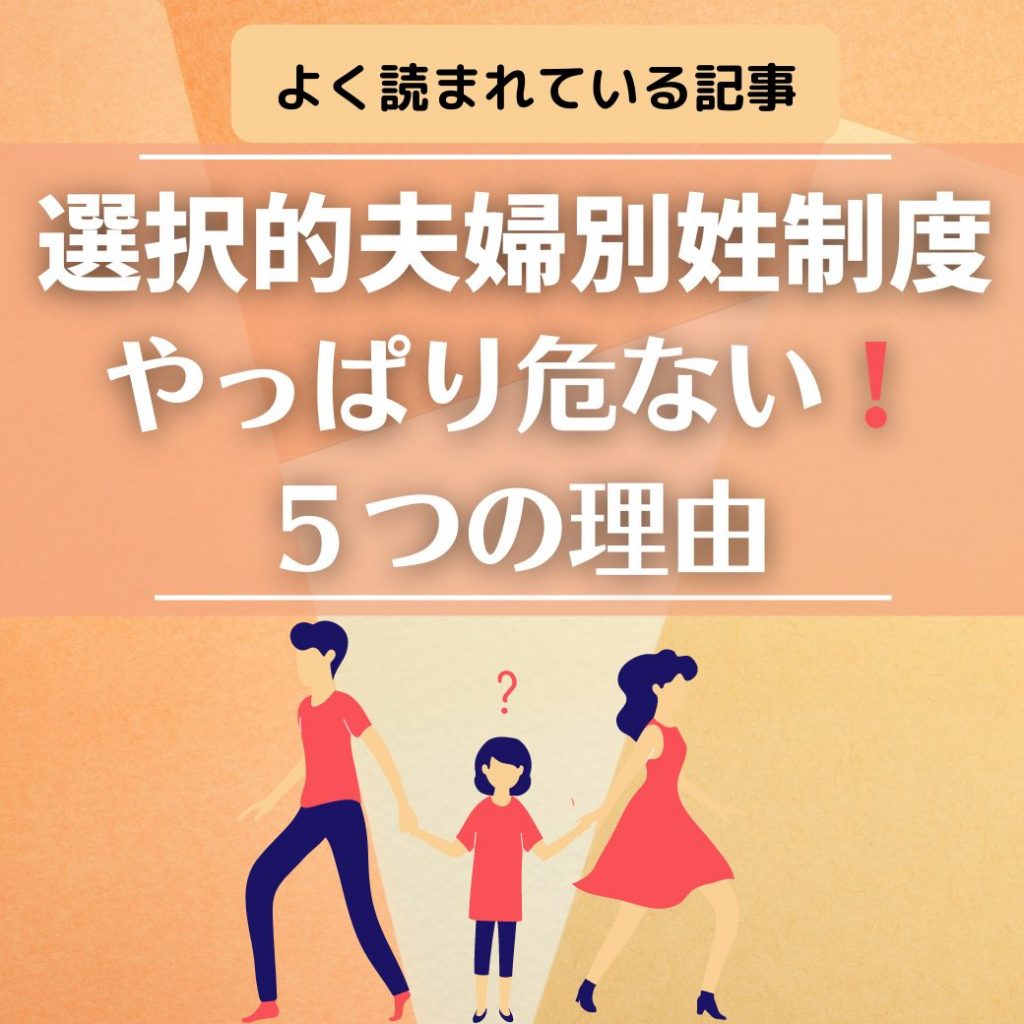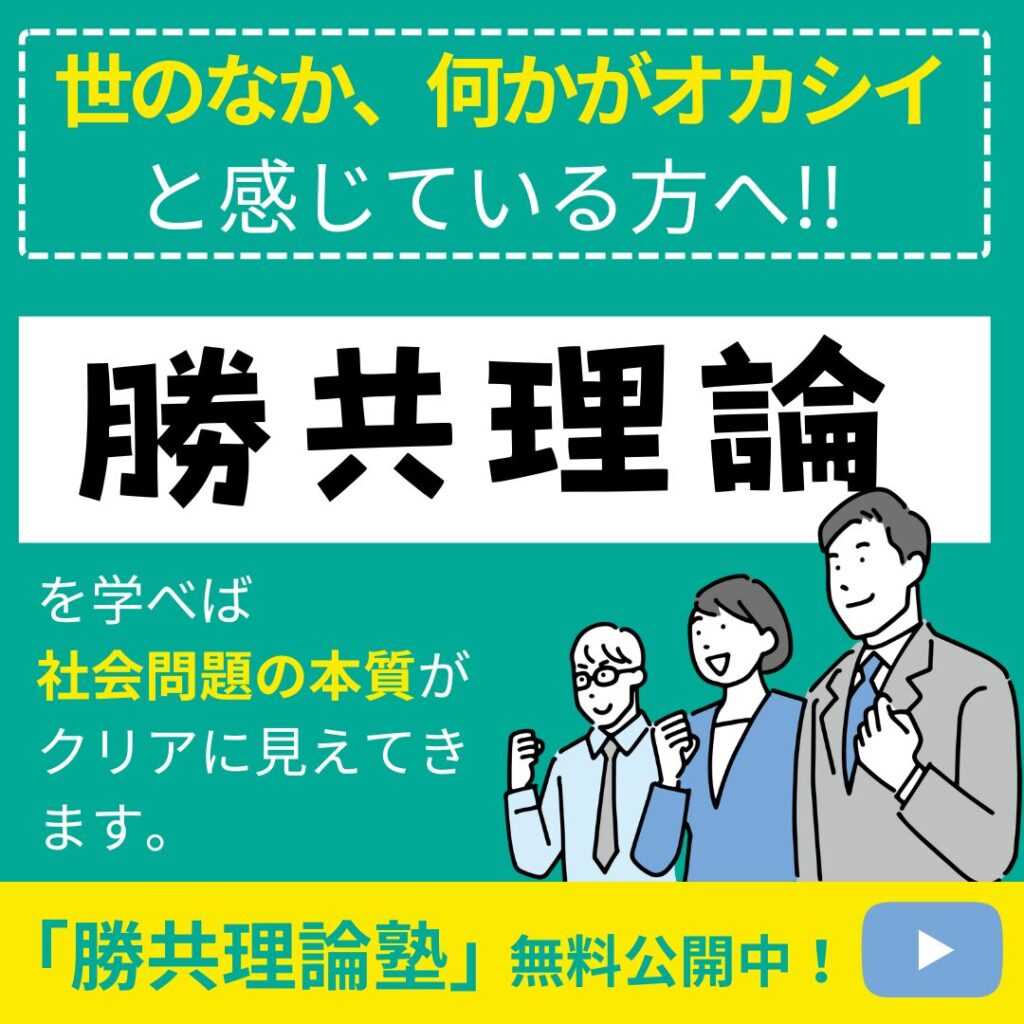テクスト論とオープンソースの衝撃
ロラン・バルト(下)
ロラン・バルトはエクリチュール(言葉遣い)と「作者の死」について、「テクストは様々な文化的出自をもつ多様なエクリチュールによって構成されている。そのエクリチュールたちは対話を交わし、模倣し合い、いがみ合う。しかし、この多様性が収斂する場がある。その場とは、これまで信じられてきたように作者ではない。読者である。(略)テクストの統一性はその起源にではなく、その宛先のうちにある。(略)読者の誕生は作者の死によって購われなければならない」(「作者の死」)と述べました。
このバルトの「テクストの生成」と「作者の死」の考え方は、書物や芸術作品など「作者により生まれたもの」が、「読み手や鑑賞者によって編み上げられるテクスチャ(織り物)」と見なす考え方で、一種の「存在=生成論」と見なせますが、これを、内田樹氏が「オープンソース」としてのリナックス登場の背景について説明しており、一部紹介しました(『寝ながら学べる構造主義』)。
冒頭のバルトの記述は、ほとんどそのままインターネット・テクストに当てはめられるとし、リナックスという「オープンソース」の登場の衝撃について「音楽や図像についてコピーライト(著作権)の死守を主張している人たちがいますが、その人たちもむしろ自分の作品が繰り返しコピーされ、享受されること(前回述べたようにベリオの作品がマーラーの交響曲をそのまま引用した例など)を『誇り』に思うべきであり、それ以上の金銭的なリターンを望むべきではない、という新しい発想に私たちはしだいになじみつつある」とバルトの思想と内田樹氏は重ね合わせます(『寝ながら学べる構造主義』)。
ところが、バルトのテクスト論は確かにそうかもしれませんが、あえて言うならばむしろマルクス主義の労働価値説と最もかけ離れているものこそ、「オープンソース」の発想なのです。
このオープンソースのオペレーティング・システム(OS)のうち、特にリナックス(Linux)は元々、フィンランドのリーナス・トーバルズ氏が「誰でも参加でき自由に改造できるOS」を提唱し、世界中のコンピュータオタクが参加し驚くべき進化を遂げました。アップルのパソコンMac搭載のMacOSと同じUNIX(ユニックス)系と言われるOSです。特に最近では、グーグルの開発したChromeOSを搭載した「クロームブック」はCMでも知られ、ウィンドウズ搭載のパソコンより低スペックですが手頃な値段で手に入る機種としてかなり浸透してきました。このクロームOSもリナックスベースのOSです。また、スマートフォン業界では、アップルiPhoneと2分するのが「アンドロイドOS」機種で、このアンドロイドもリナックスの一種です。つまりスマートフォン界ではUNIX系がデファクトスタンダードなのです。
水道哲学と対極にあるウィンドウズ
ウィンドウズというOSブランドをパソコンの「デファクトスタンダード」(事実上の世界標準)に仕立て上げたマイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏は世界一の大富豪となりましたが、リナックスの創始者リーナス・トーヴァルズ氏は、そのような道を拒絶し、「オープンソースのカリスマ」として「尊敬される名誉」を選んだとするのが内田氏の見立てです。
ただし、これをもって「だから資本主義=悪なのだ」という単純な図式に陥ってはいけません。ウィンドウズが莫大なコスト(開発費や人件費)をかけているから「価値がある」のであり、リナックスは開発者が手弁当でやっているから「価値がない」という論理はあてはまりません。開発者に報酬という対価が与えられるか、「趣味」ないしは「奉仕」(ボランティア)として開発に携わるかは、労働価値説では説明できません。リナックスの開発者はプログラム開発を「強制」されているわけでも、「契約労働」しているわけでもありません。
むしろ松下幸之助の「水道哲学」のようなものに近いかもしれません。ITというインフラを水を飲むように当たり前のものにする、という使命感のほうが近いわけです。マイクロソフトのウィンドウズは確かにPCやインターネットを全世界の人々にとって身近なものにした、とは言えます。ところが、マイクロソフトは水のように安価にすることによって大量生産するという「水道哲学」の発想とは全く異なります。独占ないし寡占状態をまずつくり出し、大量生産して価格を抑えることもせず、一貫して自らが価格の生殺与奪を握りました。
古いバージョンについて無料にするといった戦略もなく、ただ新しいハード(PC)には新しいOSを搭載させるべくPCベンダー(製造メーカー)各社に、日本ではリナックス搭載PCを発売しないよう「囲い込み」を図ったのです。それは企業として当然のことなのかもしれませんが、まさに「水道哲学」とは対極にある企業思想と呼んでかまわないでしょう。
確かに、リナックスは当初、コマンドが複雑でウィンドウズやマックOSのようにマウスで視覚的直感的に操作できるGUI(グラフィカル・ユーザ・インターフェイス)環境ではありませんでしたが、その後、恐るべき進化を遂げGUI環境ではウィンドウズを凌ぐほどになりました。
共産主義体制下では生まれない理由
重要な点は、こうしたリナックスなどの「オープンソース」のソフトウェアは、社会主義体制下では、決して生まれない、ということです。なぜでしょうか。それは、まったくのフリーウェア(無料ソフト)にするのも、マイクロソフトに対抗しウィンドウズと拮抗した有料OSとするのも、まったく作者の「自由意思」に基づいているからです。資本主義という経済活動が自由な発想と意志が保障され尊重されて初めて効力を発揮するものであり、「ボランティア」とはもともと「自発的な」の意味を持っているように、自発性のない社会は、カール・ポパーも指摘するように、「全体主義への道」であり、「開かれた社会の敵」と断じてもかまわないでしょう。だからこそ、キリスト教などの宗教的な社会規範をバックボーンに持つ文化では、資産家などによる慈善活動のボランティアや寄付行為が珍しくないのです。
バルトは確かに、従来のマルクス主義が階級闘争を措定し、打倒すべきだとした資本主義の後に到来すると見た「終局形態」としての「オープンソース」のような考え方を予見していたのかもしれません(「作者の死」と「テクスト論」)。
しかし実際には、マルクスの時代には思いもよらなかった事態が展開しているのが現代なのです。
ではリナックスなどのオープンソースは、まったくのボランティア事業なのでしょうか。ビジネスモデルとしては成立しえないものなのでしょうか。確かに、オープンソースそのものは「無償公開」が原則であり、「コピーライト(著作権)」に対抗して「コピーレフト」と称したりもします。
ですが、その答えは「否」です。つまり「オープンソース」から派生し、別の付加価値が加えられたものは、実際、商業ベースに乗っていたりするのです(前述のクロームブックやアンドロイドのスマホなど)。
例えば、日本語ワープロソフトのシェアは、かつてはジャストシステムの「一太郎」の独壇場でした。NECのパソコンがまだ「PC│98」と呼ばれていた時代のことです。もともとMac向けのビジネスソフトとして登場した「ワード」(表計算では「エクセル」)はウィンドウズ95以降、次第に形勢が逆転し、今や世界標準となりました。
自発性を重んじる開かれた世界観
このように「自発的」か「自発的でない」かは、ある意味で社会の「自由度」をはかる重要な「目安」ないし「指標」(メルクマール)となっています。しかも、レヴィ=ストロース的な「贈与」という文化人類学的な考え方からすれば、自らの「仕事」に対して「労働としての対価」を求めない「オープンソース」の発想は、まさに「下部構造としての経済活動」という「マルクス主義の常識」の埒外にある「贈与」に当たると言えるでしょう。というのも、別掲カコミに示したように、バルトは「秩序」という語に「警察的」「権威」「弾圧」といった極めて政治的な価値観を援用して記述しています。それはフランクフルト学派の立場とも重なっています。
その意味で、バルトはやはり「マルクス主義というイデオロギー」「階級闘争というドグマ(教義)」の呪縛から逃れられなかったのではないでしょうか。
今日的な「著作権の全能性」に対し明確に「否」を唱えたのがバルトというなら、「自分の作品が繰り返しコピーされ、享受されることを『誇り』に思うべきであり、それ以上の金銭的なリターンを望むべきではない、という新しい発想」(『寝ながら学べる構造主義』)は、既にマルクスの呪縛から解き放たれていると言えるかもしれません。
これがマルクス主義の立場なら、こう考えるでしょう。本来なら自分が汗を流した「労働」の結果、音楽や図像、プログラムやソフトウェアなどの作品が生まれたとすれば、当然その「労働」に見合った対価を獲得せねばならない。そうでなければ、それらはそれを利用する人々により「搾取されている」と捉えることになるでしょう。
しかし、「コピーライトの全能性」を持つ作者とその作品を享受する利用者との関係というのは、「搾取と被搾取の関係」「階級闘争」に還元できません。ルカーチ流に「階級意識」から生まれ出るものは、法で縛ろうと自由意思に委ねようと結果は変わりません。これが「宿命論的世界観」の限界で、それを超克するのが「開かれた自由な世界観」と言えるでしょう。
ト学派のスタンスとも重なっているように思われます。
【権力・体制の「エクリチュール」】
本来的にマルクス主義的なエクリチュール(マルクスやレーニンのエクリチュール)と勝利を収めたスターリン主義のエクリチュール(人民民主主義のエクリチュール)とを列挙することができるし、また、確かに、トロツキー主義的なエクリチュールとか、たとえばフランス共産主義のものである戦術的なエクリチュール(《人民》ついで《健全な民衆》の《労働者階級》に代えての使用、《民主主義》とか《自由》とか《平和》などという辞項の故意の両義性)とかが存在する。
それぞれの体制が自分のエクリチュールを所有しているということに疑いはないが、そのようなエクリチュールの歴史は、まだこれから作成されるべきものである。エクリチュールは、語り(パロール)の顕著にアンガジェした形式であって、貴重な両義性によって、権力の存在と外見とを、すなわち権力がそれであるものと権力がそれであると思われたいと望んでいるものとを、同時に含んでいる。そんあわけで、政治的なエクリチュールの歴史は、社会的な現象学の最良のものとなるであろう。例えば、〈王政復古時代〉は、階級的なエクリチュールを練り上げたのであり、そのおかげで、弾圧は、古典主義的な《自然》からひとりでに出現する断罪として、即座に持ち出されていたのだ。すなわち、要求を掲げる労働者は、つねに《個人》とかストライキ破りとか《穏健な労働者》とかであって、裁判官たちの奴隷根性は、そこでは、《司法官の温情あるいは心遣い》となっていた(今日、類似の手法によって、ド・ゴール主義は共産主義者たちを《分離主義者》と呼んでいる)わけである。了解されるとおり、ここでは、エクリチュールは良心として機能しているのであって、行為の弁明にその現実の保証を持ち出すことによって、事象の始源とその最も遠く離れた転変とを詐欺的に合致させることを使命としているのだ。しかも、エクリチュールに関するこのような事象は、すべての権威的な体制に固有のものであって、警察的なエクリチュールと呼ぶこともできるようなものである。例えば、《秩序》という語の永久に弾圧的な内容は周知の通りなのだ。(『零度のエクリチュール』)
(「思想新聞」2025年11月1日号より)