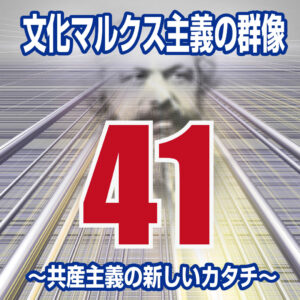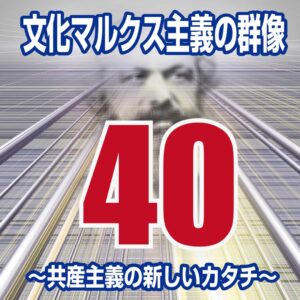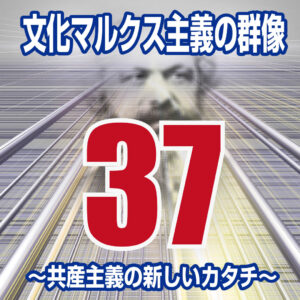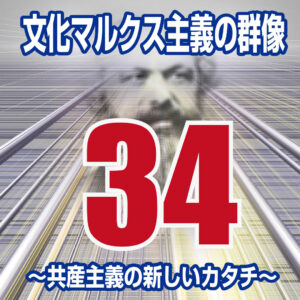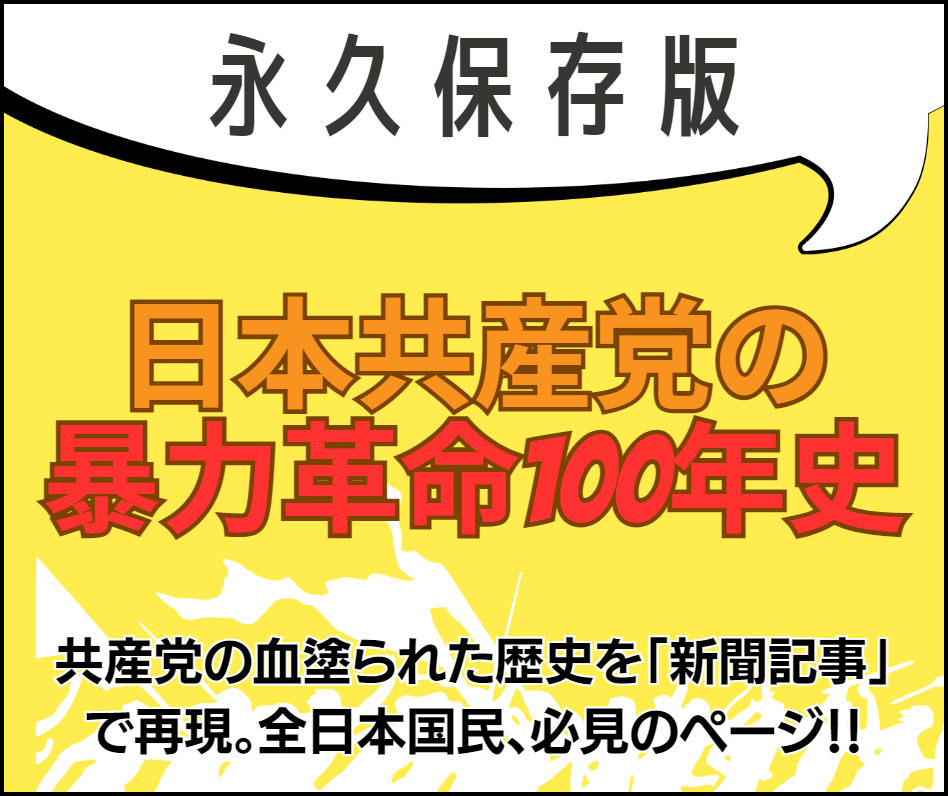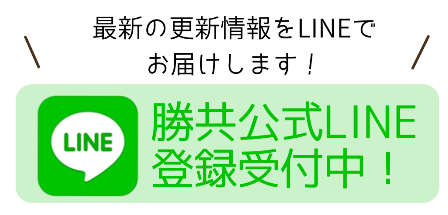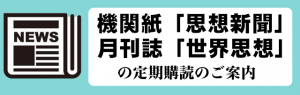善悪の彼岸とは何か
インテルメッツォ
ロラン・バルトの記号論は、「テクストの生成」と「作者の死」の考え方から、著作権というものは何かを考えさせ、「オープンソース」の発想につながることを述べました。
無神論者=リベルタンとしてのサド
しかしながら、バルトは「革命のエクリチュール」を唱え、その著書『サド、フーリエ、ロヨラ』は特にポストモダン思想に強い影響力を残したサドとフーリエを採り上げた点で侮れません。「無神論者=リベルタン」としてのサドの、道徳価値の転倒を説くニーチェすら超える「悪徳」賛美は、「革命的エクリチュール」展開の上で格好のテクストでした。
このうちサド、つまりサド侯爵については、「リベルタン(〝リベルタン〟は16〜17世紀の無神論的自由思想家の意味から転じて、18世紀には性的放蕩者の意味)=無神論」が実は、サドの思想の中核と考えられています。
ここで想起されるのが、いわゆる「ユーロコミュニズム」としての地位を確立したフランクフルト学派の創始者であるホルクハイマーとアドルノの共著『啓蒙の弁証法』です。
実は、この『啓蒙の弁証法』で比較対照する思想としてイマヌエル・カントにおける「啓蒙」の考え方と、サド侯爵の「道徳の彼岸」、言い換えると「悪徳の栄え」です。
この「道徳の彼岸」という意味では、『善悪の彼岸』を書いたニーチェの思想が想起されますが、ニーチェよりも遙かに善悪観を解体し、悪に積極的な意味づけをしているのです。この点が、さらにバルトの後に哲学者としてはより高名であり、21世紀の現代への影響が大きいのがミシェル・フーコーです。フーコーに至ってはサドをより思想的「革命家」として評価しているのです(ジェンダー論、LGBT思想のの理論的支柱と言えます)。
善悪の彼岸説くニーチェ思想
サドの思想は、自らの快楽のためなら殺人すら正当化できるもので、ある意味で「究極の自己中心思想」と言えます。このサドほどではないにせよ、ニーチェはキリスト教会を「奴隷道徳」だと断じ、可能な限り「自己肯定」の世界観を説くのです。
例えば、キリスト教が「隣人愛」を説くのに対し、ニーチェは「遠くにある者」にはその「愛」は届かないとして、叙事詩の主人公ツァラトゥストラに「遠人愛」を説かせます。
しかし、「あらゆる価値の転倒」や「善悪の彼岸」を唱えたニーチェですら、サドのような露骨な「悪の正当化」は主張しませんでした。サドは「悪徳の栄え」をも書いたように、「悪徳=犯罪」こそが社会を変革する、と考えました。
バルトは、作中で拷問の末に人々が虐殺されるという場面は、現実のサドの姿ではない、とわざわざ「弁護」しています。確かにサドが獄中生活を送った咎は「淫蕩」であって、殺人ではなかったかもしれません。
悪徳こそ社会変革するとのサド思想
しかしながら今日、現実世界の「快楽殺人」はほぼ、その犯罪者自身の「性的サディズム」との相関関係が指摘されます。法の理念とは「社会正義の実現」にあるはずですが、サドはこれに全く反しているのです。
つまり、このように見ると、ニーチェにおいても自己肯定が肥大することによって「他者への配慮」は疎んじられることになります。つまり「偽悪趣味」とは言い過ぎかもしれませんが、やはり「自己中心的」と言わざるを得ません。
キリスト教をはじめ、多くの宗教は「利他性」や「奉仕」を強調しています。しかしニーチェやサドはこれらを否定する思想です。
やはりリンゼイが宗教を基点として民主主義を二つの方向性に持つ思想の系譜を説いたことがここでも当てはまりそうです。
(「思想新聞」2025年11月15日号より)