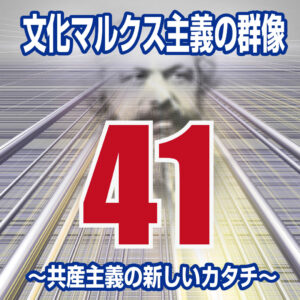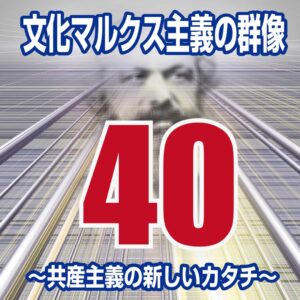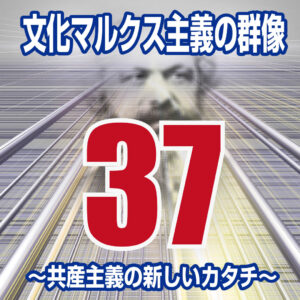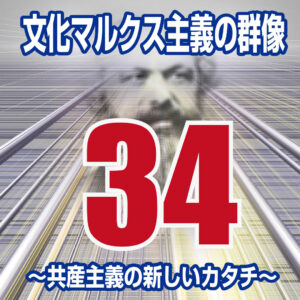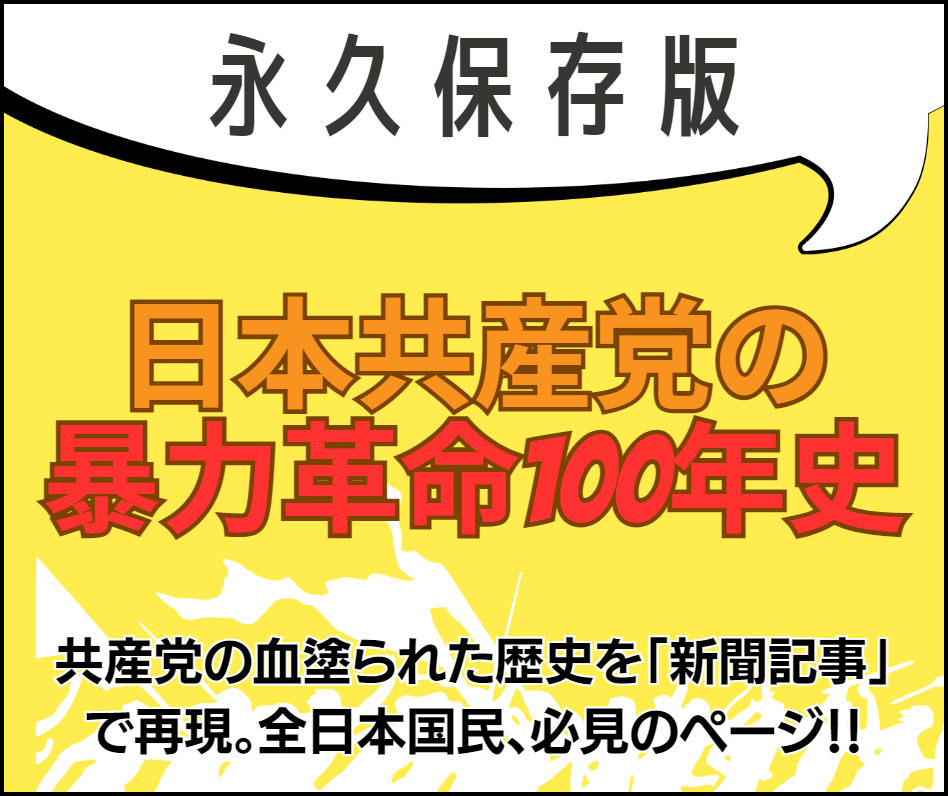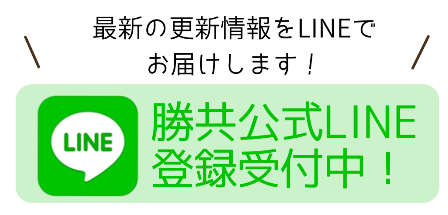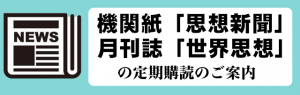「問いの体系」と「認識論的切断」
ルイ・アルチュセール(中)
アルチュセールはマルクス主義哲学を「認識論的切断」という概念で捉え直すことで「構造主義的マルクス主義」という「ポストモダンなマルクス」の可能性を引き出しました。
プロブレマティックとは「思考の図式」
マルクス史家のマクレランは「『認識論的切断』という概念は、フランスの科学哲学者、ガストン・バシュラールから借りたものであるが、それは、時を同じくしてトーマス・クーンが詳しく展開していた科学的パラダイムという観念にほぼ相当するものである。アルチュセールによれば、マルクスの初期の著作と後期の著作は、二つの別個の問題設定を含んでいる。問題設定とは、『それに固有の主題の客観的な内的参照体系、与えられる答えを支配している問いの体系』である」(『アフター・マルクス』)と述べます。
確かに科学哲学者バシュラールの「認識論的切断」は、クーンが主張した概念「科学的パラダイム」「パラダイム転換」に相当します。ここでいう「問題設定」=「問いの構造」(プロブレマティック)とは、「それに固有の主題の客観的な内的参照体系、与えられる答えを支配している問いの体系」とアルチュセールは定義づけています。
このアルチュセール自身の記述を踏まえ、今村仁司は「ひらたく言えば、どのような思想もその内部に自覚されざる『思考の図式』を抱えており、その図式は思想家の思考に対して深いところから(つまり知らぬ間に)方向を与えるばかりでなく、用語ないし言葉の意味までを徹底的に方向づけ規定する。このような思考の図式を『問いの構造』と呼ぶのである」(『アルチュセール全哲学』)と解説しています。
こうしてアルチュセールは、「マルクスは、歴史理論(史的唯物論)を築くことによって、ただ一つの同じ動きの中で、それ以前に彼が持っていたイデオロギー的な哲学的意識と断絶し、同時に新しい哲学(弁証法的唯物論)を築いた」(『マルクスのために』)と見立てることで、「(若い)ヒューマニズム」というイデオロギーを克服したマルクスが、「マルクス主義者」となりえた境地を『資本論』に見たのです。
イデオロギーからの解放のプロセス
その「マルクスのイデオロギー克服」について、マルクス主義全体の中で占める「哲学」の地位の低下は、特にロシア革命以後に顕著に見られた中で、アルチュセールはマルクス主義思潮におけるいわば「哲学の復権」を企てたと言えます。
社会主義体制下で「ルイセンコ主義」や「大躍進」など「イデオロギーの下僕となった疑似科学」の横行に代表されるように、マルクス主義・共産主義思潮を哲学的次元から立て直そうと試みたのが、アルチュセールでした。そのための「イデオロギーからの解放」というプロセスを、今村は次のように述べています。
◇
マルクスの言説から、いくつかの要素を取り出して、それらを観念論と唯物論に振り分ける操作がある。そうした操作は、マルクスの思想の「源泉」や「先駆者」を語ったり、あるいは反対に、観念論的でありながら「既に唯物論を先取りしていた」といった、「後に発芽し開花するであろう萌芽」論を語ったりする。……アルチュセールはこうした歴史の書き方を「前未来形で書く歴史」と呼んでいる。このような読み方にはいくつかの前提が隠されている。
1・要素還元的前提。あらゆる理論体系や思想は要素に還元できると主張する。それは分離された要素を、先駆者と後継者、観念論と唯物論に割り振り、相互の比較が可能と考える。
2・目的論的前提。目的=終わりから遡及して理論や思想を裁く。歴史の中で複雑な条件を受け止めながら進行する思考の過程を無視して最初から「ゴール」を設定している。
3・観念の自律性の想定。これは思想が自分自身の内部だけで自己了解を遂げうると前提している。
これらの前提を持つ読み方は、一言で言えば、目的論的読み方と言える。それは、諸要素が全体の構造の中で持つ意味を無視して、単独に取り出したり、割り振ったりできると信じている。決してゴールなど予定されえないのに、独断的なゴールを設定するところから、こうした無理がまかり通る。決して自己の外部に出ることなく、観念の内部で自己了解を遂げて、思想の自己内発展のモデルを作り上げる操作、それがイデオロギーの特徴である。これを退ける時、新しい読み方が可能になる。(『アルチュセール全哲学』)
◇
マルクス自身が独断的ゴールを設定する
さて、以上の今村の記述は、「もっともだ」と思うかもしれません。確かに「読み方=解釈」の違いが、マルクス主義における「哲学の悲劇(あるいは苛酷な運命)」を招いてきたのではないかと。ところが、私たちの知る限り、今村=アルチュセールのいう「目的論的読み方」に立っているものこそ、実は「マルクス主義」自身である、と言えるのではないでしょうか。
今村は「マルクス主義の哲学は、他の諸々の思想類型をブルジョワ的だと批判し告発する批判主義的思想ではない」と弁明しますが、これはプルードンの『貧困の哲学』を揶揄したマルクスが『哲学の貧困』を著したように、プルードン批判のためなら何でもありという「戦闘的アジテーター」というのが、残念ながらマルクスの本質と言わねばなりません。
さらに、「目的論的読み方」の前提の二番目にある「最初から独断的なゴールを設定している」のは、マルクス自身と言えるのです。すなわち、プロレタリアートによる暴力革命によって社会主義社会、共産主義社会が実現するというのは、ある種の「終末的ユートピア論」であると言え、まごうことなく「予定調和的な目的論」のはずです。「いや違う、この点はヘーゲル哲学からの受け売りにすぎない」と弁明されるかもしれませんが、この点こそが、いわば若者たちを「革命幻想」へと駆り立てていった左翼の「イデオロギー」であったことを指摘せねばならないでしょう。
(「思想新聞」2026年1月15日号より)