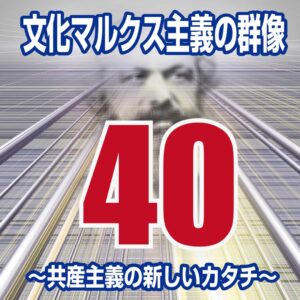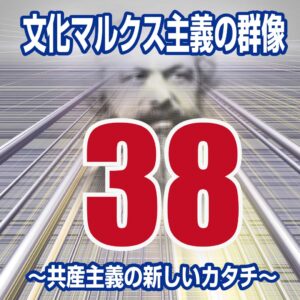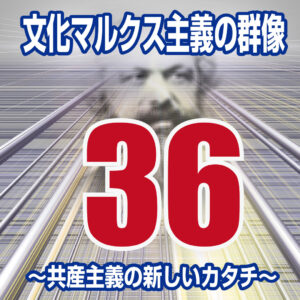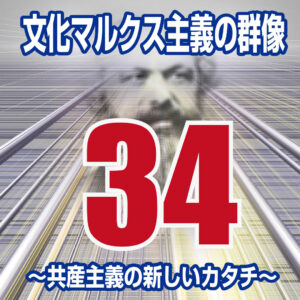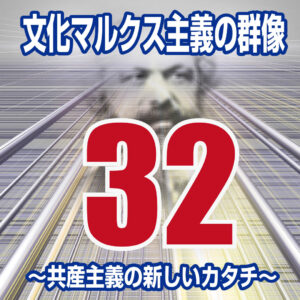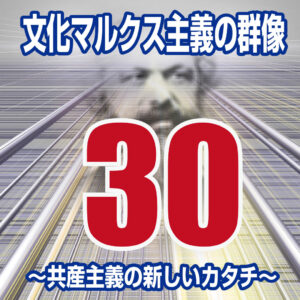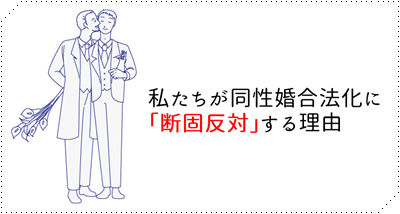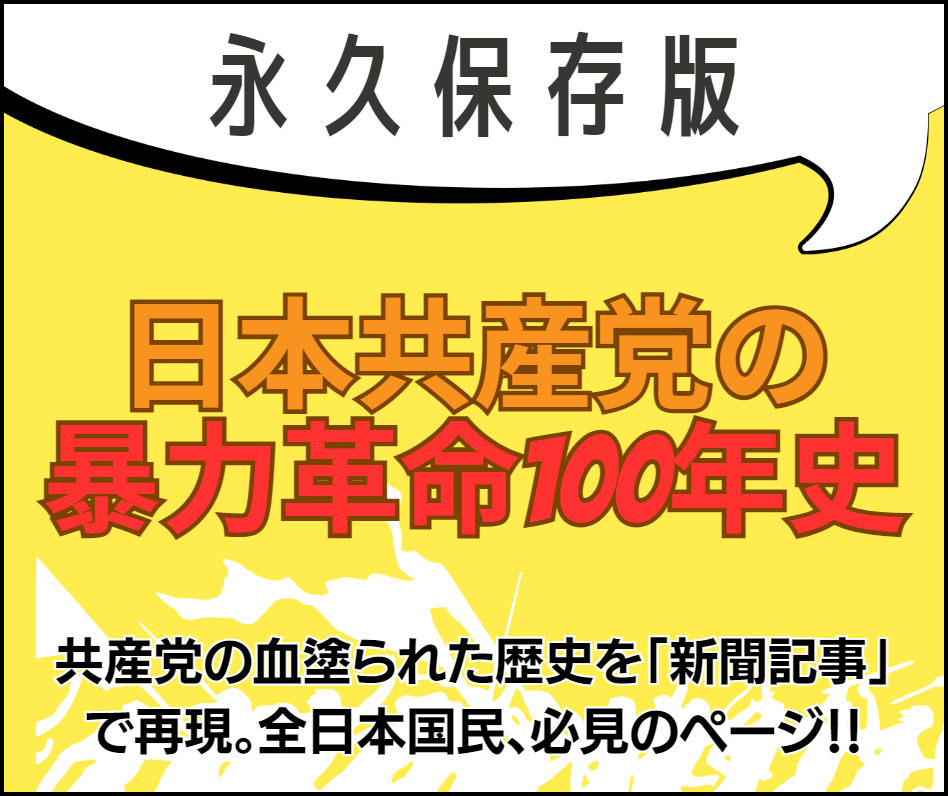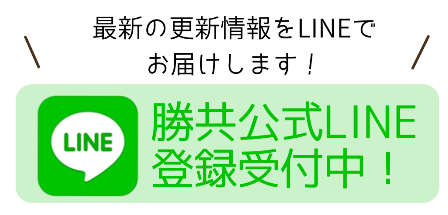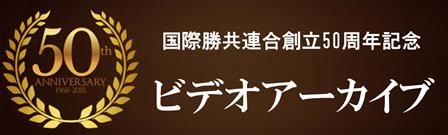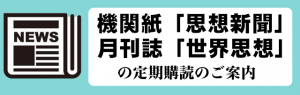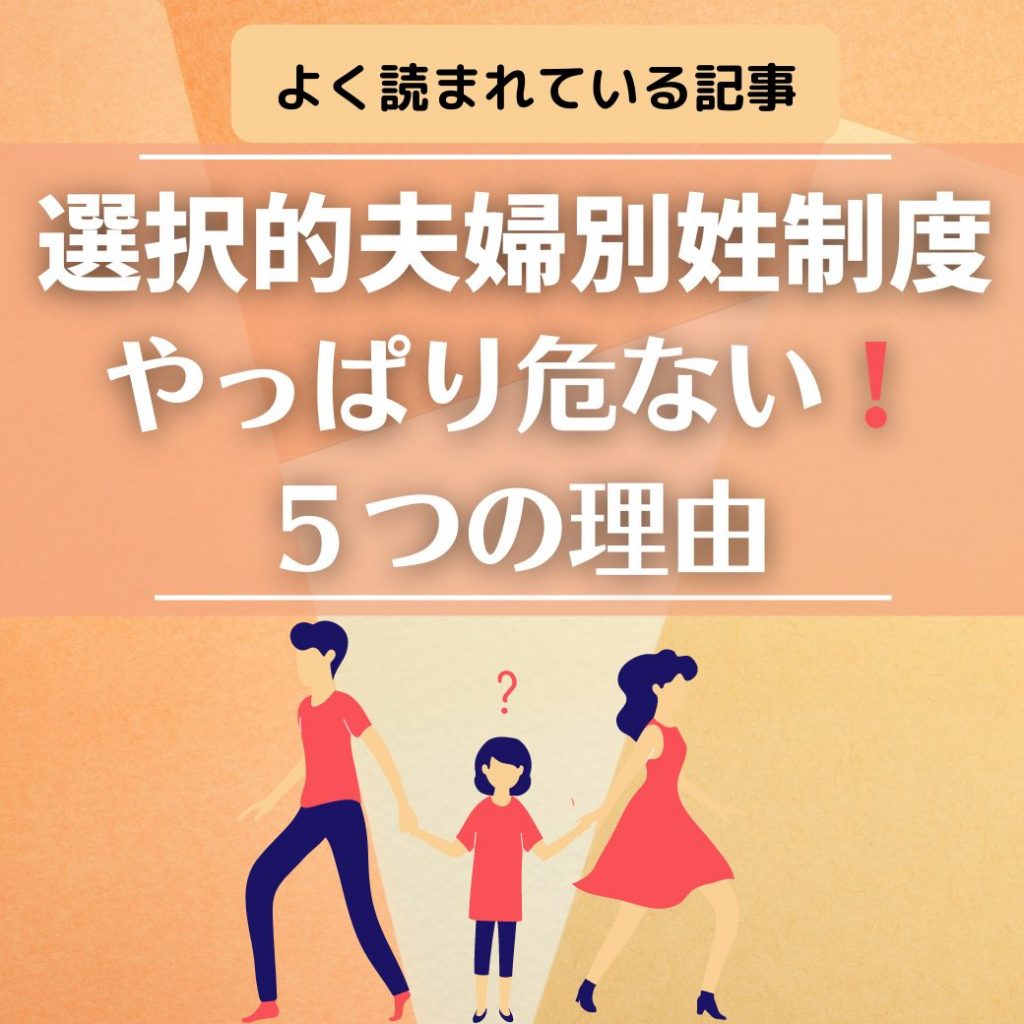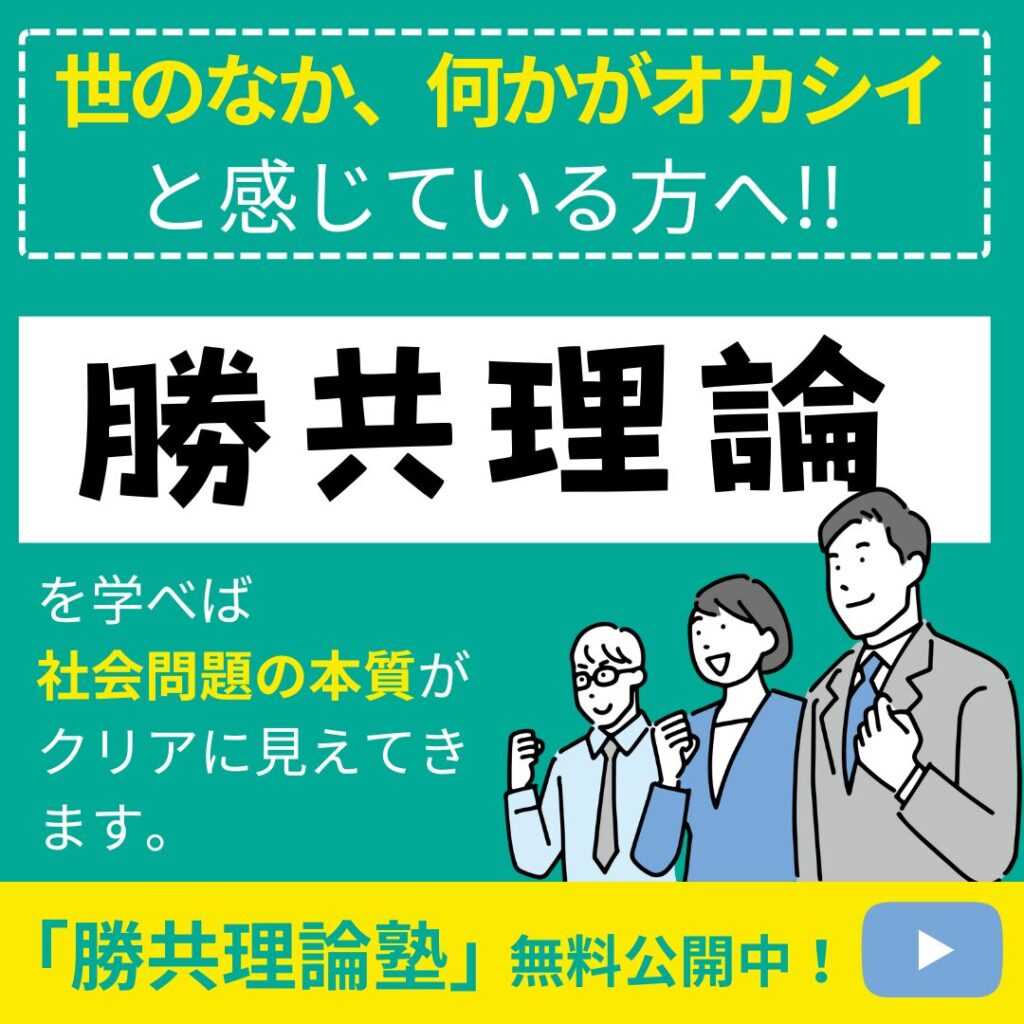唯物弁証法で説明できない《クラ》の環
続・ブロニスワフ・マリノフスキー
マリノフスキー(1884〜1942)
社会的構造のみならず個人の意識をも機能主義のうちに採り入れ「文化=装置」として捉えるマリノフスキー。彼は学派を形成しなかったものの、ニューギニア東部で展開される「クラ」の呪術的伝統に、安直な唯物史観や進歩史観には収まらない人間精神の文化的営みを見た点は評価に値するでしょう。
前回マリノフスキーの思想的特徴と「文化の3次元説」についてふれました。そのマリノフスキーに関わる思想的系譜を図表としてまとめることができます(『世界の名著・59』泉靖一氏解説参照)。晩年のマリノフスキーは英米の大学で多くの弟子を育てたにもかかわらず、彼らの多くはマリノフスキーの許を去りラドクリフ=ブラウンの社会人類学の研究者となりました。泉靖一氏によれば、社会という抽象的・集合的なカテゴリーを超え、個人および無意識の世界をも重視したマリノフスキーは、あくまで「閉じた体系」で社会調査を含め理論的に一般化することが難しかったため、「学派」として独自に発展することを困難にしたようです。
宗教・呪術は支配正当化の方便か
ところで、マリノフスキーは必ずしも「文化」を否定的に捉えてはいませんが、生物学的な人間観を出発点としており、文化を即物的な「装置」に還元しています。マリノフスキーの文化概念が、文化の縦深的構造と、文化装置論であるという特徴を述べました。「文化=装置」という考え方は、確かに即物的ではありますが、「ポストモダン」の思潮では、こうした専門用語の語句ばかりが先走りして、浅薄で皮相的な用いられ方をするきらいがあります。「国家は暴力装置である」(レーニン『国家と革命』)といった使われ方など。ですが、むしろこの場合、「装置」(Apparatus)ではなくて、「体系」(システム)というふうに考えるべきではないでしょうか。機械や装置などと言えば、何者かによって作為的に造られた「人工物」であると想起してしまうからです。
そこには「権力者によって支配を目的に造られた恣意的な人工物」という捉え方が横たわっているようにも見受けられます。民族や部族に伝わる禁忌(タブー)や規範(ルール)、その他の慣習など。
それに加えて、マルクス主義的唯物弁証法に通底する基本的通念としてあるのが「下部構造が上部構造を決定する」というものですが、下部構造とは即ち、経済など基本的生活の欲求と言える部分です。つまり、人間は利己的存在であり、自分の経済の目的のために活動する。それが個人・社会・国家を形成するという考え方で、社会規範や慣習、文化などは(国家や教会などの)権力者が民衆を支配・教化するための「方便」と見なす考えです。
しかしながら、マリノフスキーの著書を読んでみると、逆に、マルクス主義唯物弁証法的な「進化概念」とは、異なっていることを、いみじくも傍証していることがわかります。文明化されていない、いわゆる「未開文化」において、唯物弁証法的な考えに立つならば、すべてが経済活動を中心として、未開の社会は営まれるはずですが、トロブリアンド島をはじめとしたニューギニアで行われている特異な「クラ」と呼ばれる交易の制度の研究を通して、得られた結論は主著『西太平洋の遠洋航海者』で述べられています。この「クラ」の概念についてマリノフスキーは同書で以下のように記述します。
経済観念超えた宗教的呪術的伝統「クラ」
![]()
「クラとは、部族間に広範に行われる交換の一形式である。それは、閉じた環をなす島々の大きな圏内に住む、多くの共同体の間で行われる。この環は図(別掲左上の地図)に見られるように、ニュー・ギニアの東端の北及び東にある多数の島を結ぶ線によって表わされる」……
そして、経済観念を超えた宗教的・呪術的伝統としての「クラ」がいかに階級史観を反証するものとなっているかということです。
◇
クラは、ある程度まで珍しい型の民族学的事実であるように思われる。その珍しい点とは、一つには、クラの社会学的、地理的な範囲の広さにある。諸部族間の大きな関係があって、広大な地域と多くの人々を、はっきりとした社会的絆で結び合わせ、義理のやりとりでしっかりとつなぎ止めて、細々した規則やしきたりを、調和の取れたやり方で守らせる──クラは、それを行う人たちの文化的水準の程度を考えれば、驚くほどの規模と複雑さを持った社会の機構だと言える。
また、この大きな社会的相互関係と文化的影響の網の目のような構造は、いやしくも新しく一時的で、あやふやなものなどと考えてはならない。なぜなら、その高度に発達した神話と呪術の儀礼を見てみれば、それがどんなに深くあの原住民たちの伝統に根ざしたものであるかがわかり、またそれが非常に古くから育ってきたものに違いないことが理解されるからである」(マリノフスキー『西太平洋の遠洋航海者』第13章)
◇
いみじくも同書に序文を寄せた師であり、『金枝篇』の著者フレーザーも次のように指摘しています。
経済勘定に収まらぬ人間精神の営為
「マリノフスキー博士は、トロブリアンド島人の注目すべき交換の仕組みを特に選んで研究の対象とし、原始経済の大きな意味を見事に力説されている。……トロブリアンド諸島と他の島々との間に行われる特異な貴重品の流通は……効用・利益・損失などの単純な計算に基づいているのではなく、単なる動物的な欲求より高い次元の情緒的、美的欲求を満足させるものであることを示している。
このことからマリノフスキー博士は、いまだに経済学の教科書に終始頭をのぞかせ、ある人類学者たちの考え方を枯らせるような影響を与えているように思われるあの『未開社会の経済人』という概念が、一種の幽霊に過ぎないとし、それに厳しい非難を浴びせておられる。……ひたすらあさましい利得の動機によって突き動かされ、最も抵抗の少ない場面場面を選んで、スペンサー流の原理に基づき、利得を仮借なく追求するものらしい。もしそのようなおぞましい架空の存在が、決して単なる便利な抽象概念としてばかりでなく、実際に未開人の社会にそっくりそのままの形で生きていると考える学者がまだいるとしたら、……博士の〈クラ〉についての記述は、そのような化け物を徹底的にぶちのめす一助となるだろう。つまり博士は、クラ組織の一部をなす実用品の交易が、実は原住民たちの考え方によると、全く何の実用にもならない他の品々の交易に比べれば、さして重要ではない……。
マリノフスキー博士…によれば、クラの制度においては、呪術が極めて重要な役割を演ずると判断される。これは、非常に興味深く示唆的な特徴である。博士の説明によれば、どうやら原住民の心の中では、呪術の儀礼を執り行い、呪術的な文句を唱えることが、この仕事全体の成功のために、必要欠くべからざるもののようである」
◇
こうした記述が何を意味しているかと言えば、実は宗教的・呪術的・儀礼的なものの重視にほかなりません。多くの人類学者は社会進化論的な考え方で、呪術→宗教・哲学→科学と時代で移り変わると見ます。
ところが、さはいえど、どんなに文明が進展し科学技術が進歩しても、宗教的呪術的なものは、社会的影響力が小さくなったとはいえ文明社会から消滅しません。日本や欧米社会においても加持祈祷やエクソシズム(悪魔払い)など、呪術的な側面を残しています。
マリノフスキーの《クラ》探究は、文化や精神的な営みが、「支配者による教化」という唯物進化論的な観念で説明できません。マリノフスキーのこうした姿勢は、彼の師の一人ウェスターマークの「近親婚の禁忌」研究と共に、「伝統文化の守護」という観点で見れば、唯物弁証法的なイデオロギーでは括れない人間精神の奥深さを示唆しているとも言えるのです。
![]()
(「思想新聞」2025年4月1日号より)