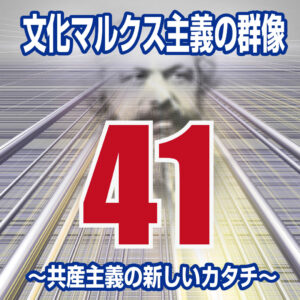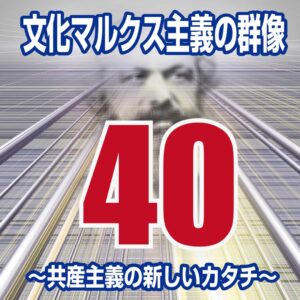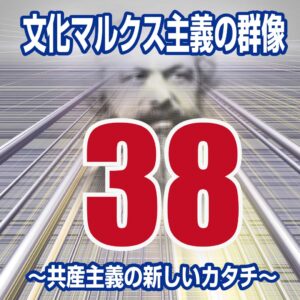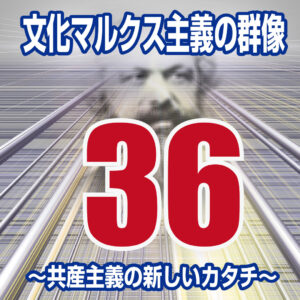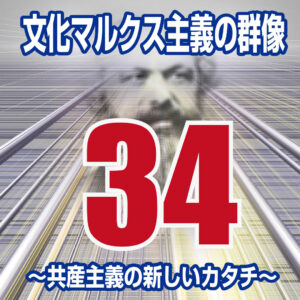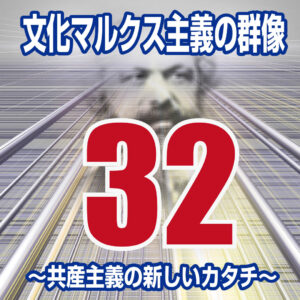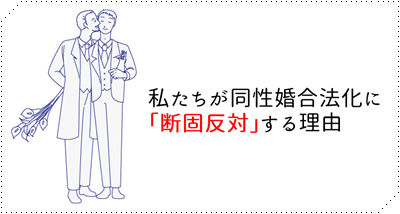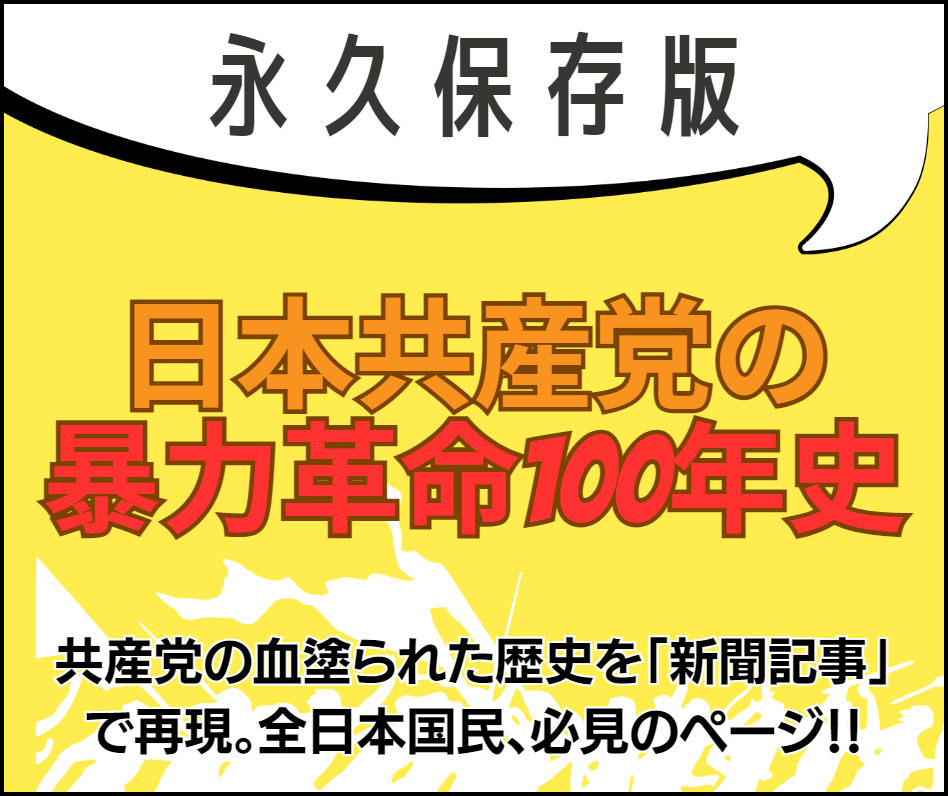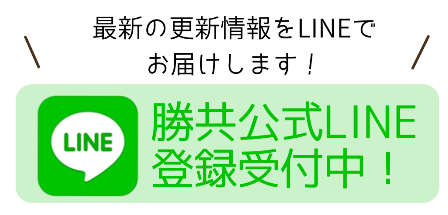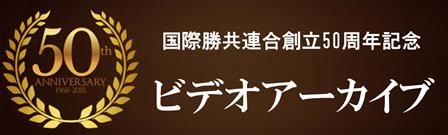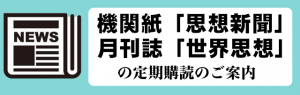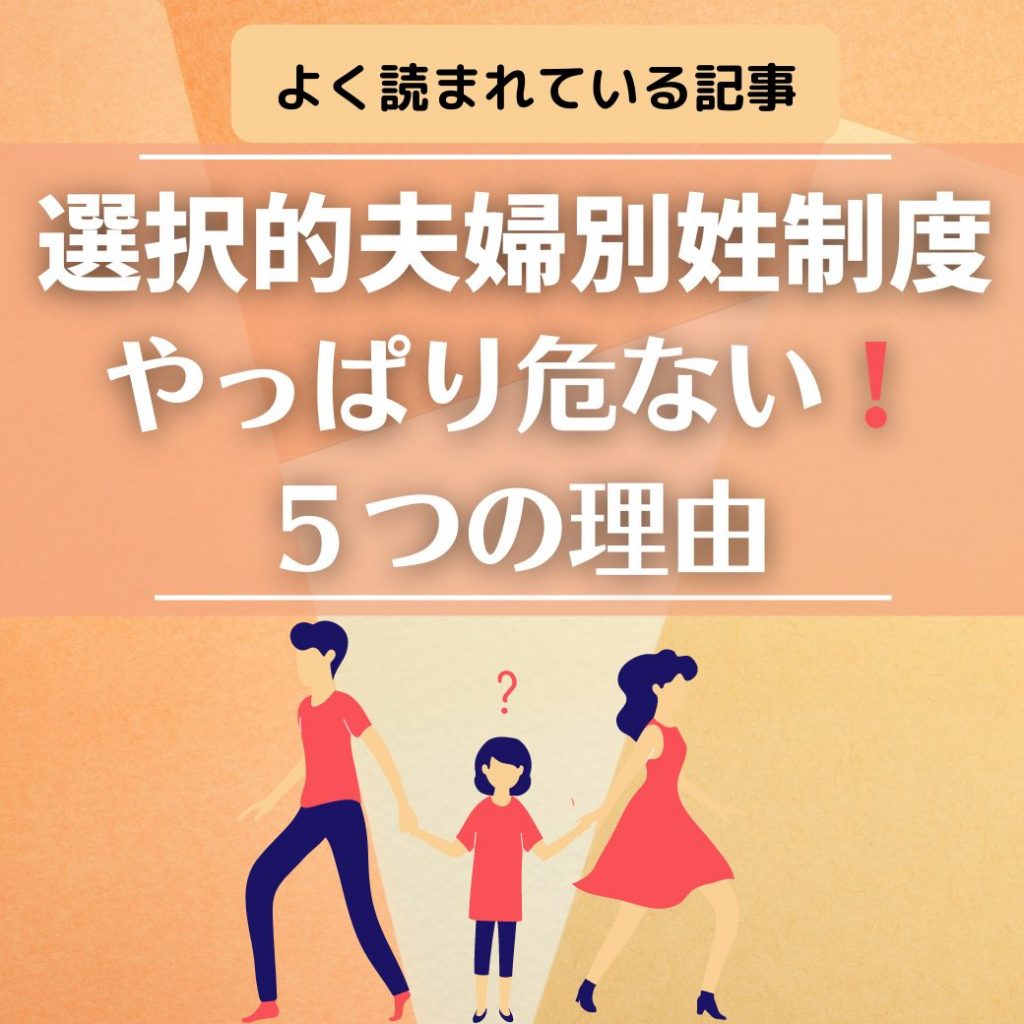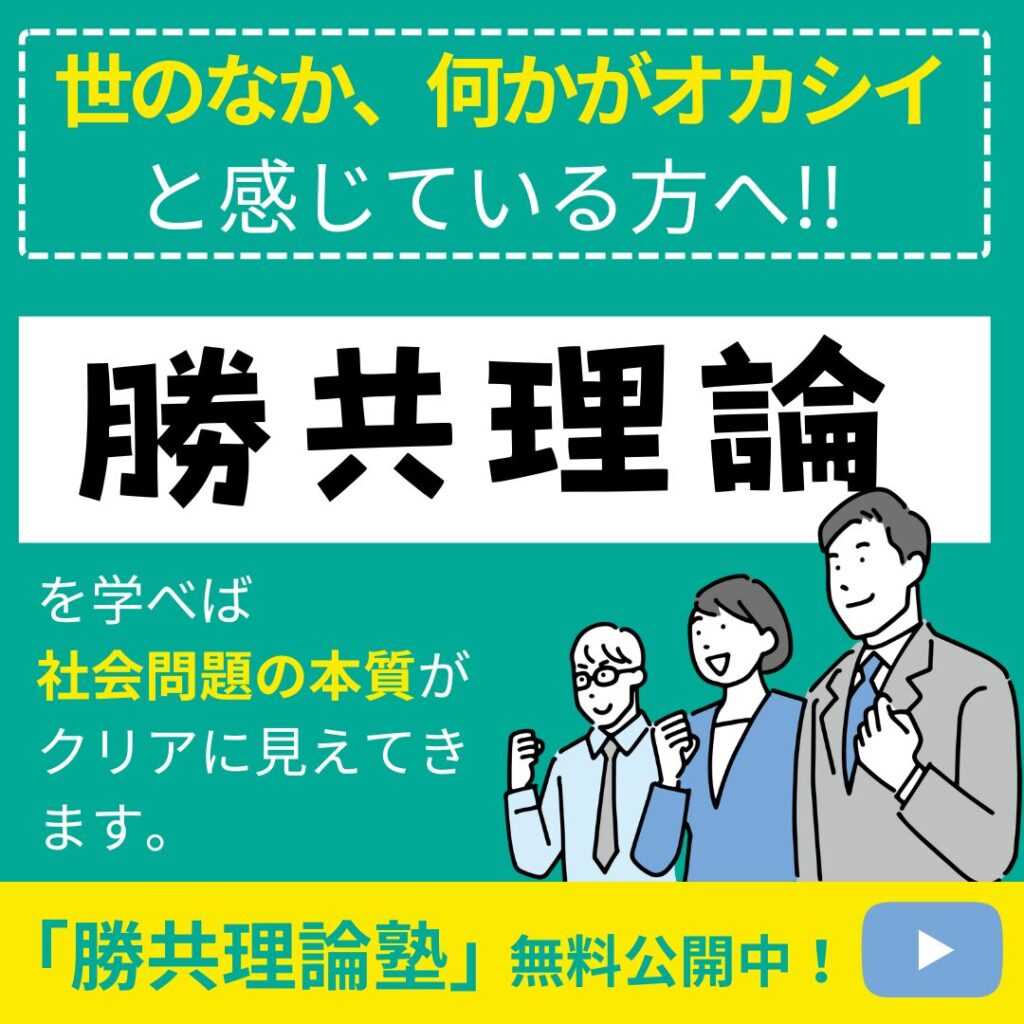構造主義とマルクス主義の微妙な関係
クロード・レヴィ=ストロース (上)
デュルケーム以来の「フランス社会学」の学問的伝統の中にあるレヴィ=ストロースが創始した「構造主義」という考え方がフランスの思想史、ひいては世界の思想シーンにおいてどのように位置づけられるかを考えてみます。
まずはじめに内田・難波江共著『現代思想のパフォーマンス』における、レヴィ=ストロースの章の記述から、少々長いですが紹介してみます。
◇
二十世紀の最大の知的転換点の一つは間違いなくクロード・レヴィ=ストロースと彼の構造人類学によって記された。
新しい方法は、先行する知的威信を砕くことによってその正統性を承認される。レヴィ=ストロースと構造主義は、一九四〇〜五〇年代ヨーロッパの知的なパラダイムであったジャン=ポール・サルトルの実存主義を退場させた。『野生の思考』でレヴィ=ストロースがサルトルの思考を人類学者の冷静な観察眼をもって解剖して見せたとき、傷ついたサルトルは、構造主義は「ブルジョワジーがマルクスに対抗して築いた最後のイデオロギー的障壁」という定型的な反論を試みた。……「何が正しくて、何が間違っていたかは、歴史が事後的に証明する」という考え方、これがサルトルの、そして一九六〇年代までの人文科学の信仰箇条であった。一九五二年、アルベール・カミュとの論争において、サルトルはカミュを「歴史の法廷」に召喚し「歴史的使命への対応」を怠った罪で告発した。 ……「もし君が君自身であり続けたかったら変化しなければならない。だが、君は変化することを恐れた」。サルトルがそう書いてカミュの思想家としての死を宣告した十年後に、あるフランスの知識人はサルトルと構造主義の関係について……こう記している。
「十五年前には意気揚々としていた哲学が、今日では人文科学の前に影が薄くなり……人々はもはや実存主義者ではなく、構造主義者なのだ」
……レヴィ=ストロースはまさしくそのような歴史観そのものの終焉を告知するためにやってきた。「歴史」を思想家たちがそれぞれの歴史的使命を競い合う闘技場と見なし、そこに勝ち残ることが、その当の思想の真理性を証明するという発想そのものをレヴィ=ストロースは根源的に問い直したのである。
クロード・レヴィ=ストロースは……十七歳でマルクスを読み始め、学生時代には社会主義学生連合の書記長に選出され、社会党代議士の秘書を務めるなど、大戦間期のマルクス主義運動の実践に深くコミットした……五〇年代から一貫してフランスの代表的知性として、アカデミズムの頂点に……おり、その方法論が私達の世界観に及ぼした影響はマルクス、フッサール、フロイトに比肩するといっても過言ではない。
◇
マルクスやフロイトらの影響に比肩
以上の引用は、大きく三つのポイントにまとめられます。①マルクス主義的実存哲学者サルトルを批判し思潮的主流から退場させた②若い頃マルクス主義に傾倒し大戦間期のマルクス主義運動に深くコミットした③レヴィ=ストロースの構造主義が現代世界に及ぼした影響は、マルクス・フッサール・フロイトに比肩する││という点です。
③については、別掲の十九世紀末から二十世紀末までの思想潮流を表した図からも確認できるでしょう。
そもそもサルトルのカミュ批判の発端は、カミュによる共産主義批判でした。だから「歴史法廷」の審判を問うたサルトル自身が、スターリン死後、急速に「思想力」を失ったのです。
レヴィ=ストロースのサルトル批判は、人間個人の主体的決断と社会への「企投」を(半ば強制的に)説くサルトルの思想は、人間個人の次元であるはずの「コギト」(考える私)が、いつのまにか社会的に普遍化されてしまっている、だからそれは個人の枠をはみ出した「僭越なる思想」にほかならないとレヴィ=ストロースは断じています。さらに、サルトルの思想的視野の狭さを露呈している、と厳しく指摘します。サルトル哲学の拠って立つ現象学と実存主義は、人間主体の意識と決断と行動に責任を持たせることを強調した極めて主観主義的思想でした。これに対してレヴィ=ストロースの構造主義は一言で言えば「客観主義の復権」になります。
近親婚の禁忌を普遍的な習俗と認知
ところで、レヴィ=ストロースの結論はいわば、エンゲルス及びモーガンによる結論、「原始共産主義=原始乱婚社会」が、キリスト教的な「一夫一婦制による階級社会」の登場によって廃れてしまったとする、『家族・私有財産・国家の起源』の主張を、真っ向から否定するものでした。未開社会において「乱婚社会」が見出されないばかりか、近親婚の禁忌(インセスト・タブー)についてある特定の部族集団についてのみならず、どのような部族集団についても説明を可能にする「構造的解釈」によって、鮮やかに説明されてしまったからです。
確かに、「社会における女性の交換」という場合、何か女性が「モノ」であるかのような扱いを受けている、としてフェミニストらが猛烈な抗議を行ったとも伝えられます。フェミニストが、文化人類学を引っさげてジェンダー論を展開するのにミードを援用するが、レヴィ=ストロースに関しては全く触れることがないのは、こうした事情でしょう。恐らく、多くのフェミニストは本音では、レヴィ=ストロースを「反動主義者」とかサルトル流に「ブルジョワジーの秘境的学知」と見なしているでしょう。ラディカル・フェミニズムの考え方を突き詰めれば、「インセスト・タブー」自体が、「ジェンダー・バイアス」の産物として、認められないからです。
とはいえレヴィ=ストロースは、やはり「ポスト・マルクスの群像」に加える必要があります。レヴィ=ストロースのスタンスは、「反西欧」「反形而上学」という点にあり、彼のサルトル批判も、まさしくこの観点に立っています。その意味で、フランクフルト学派の派生である「カルチュラル・スタディーズ」と軌を一にしていると言えます。
(「思想新聞」2025年7月1日号より)