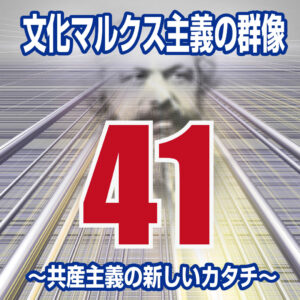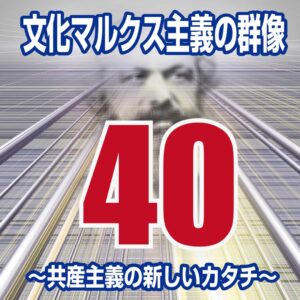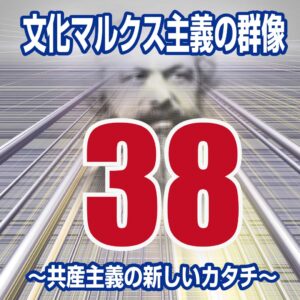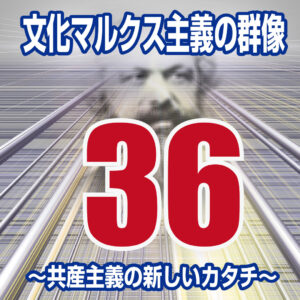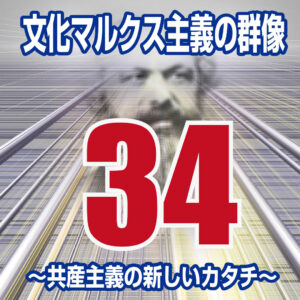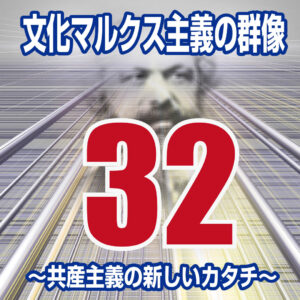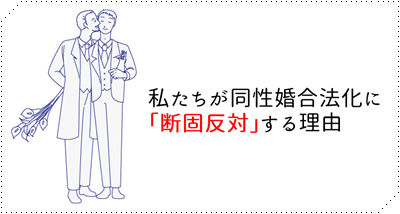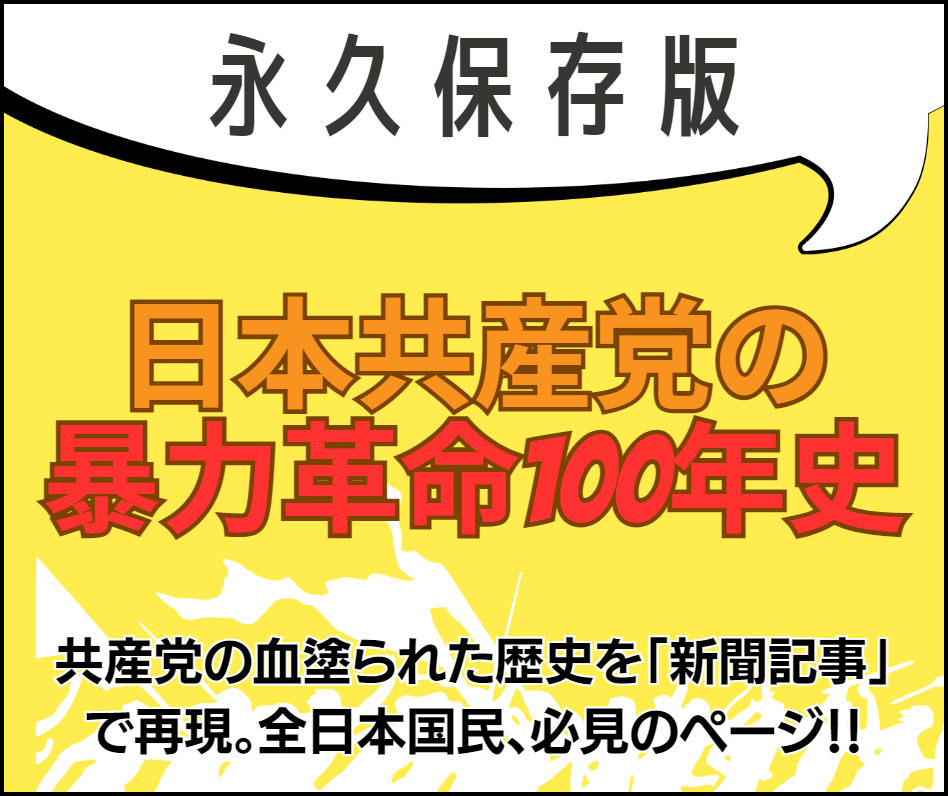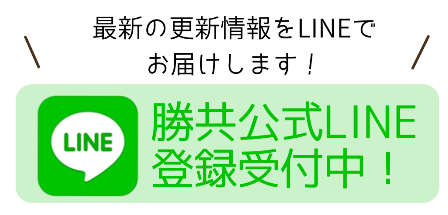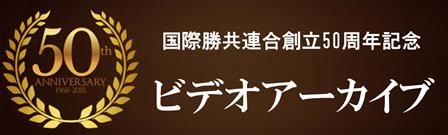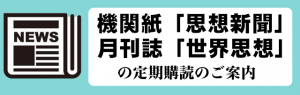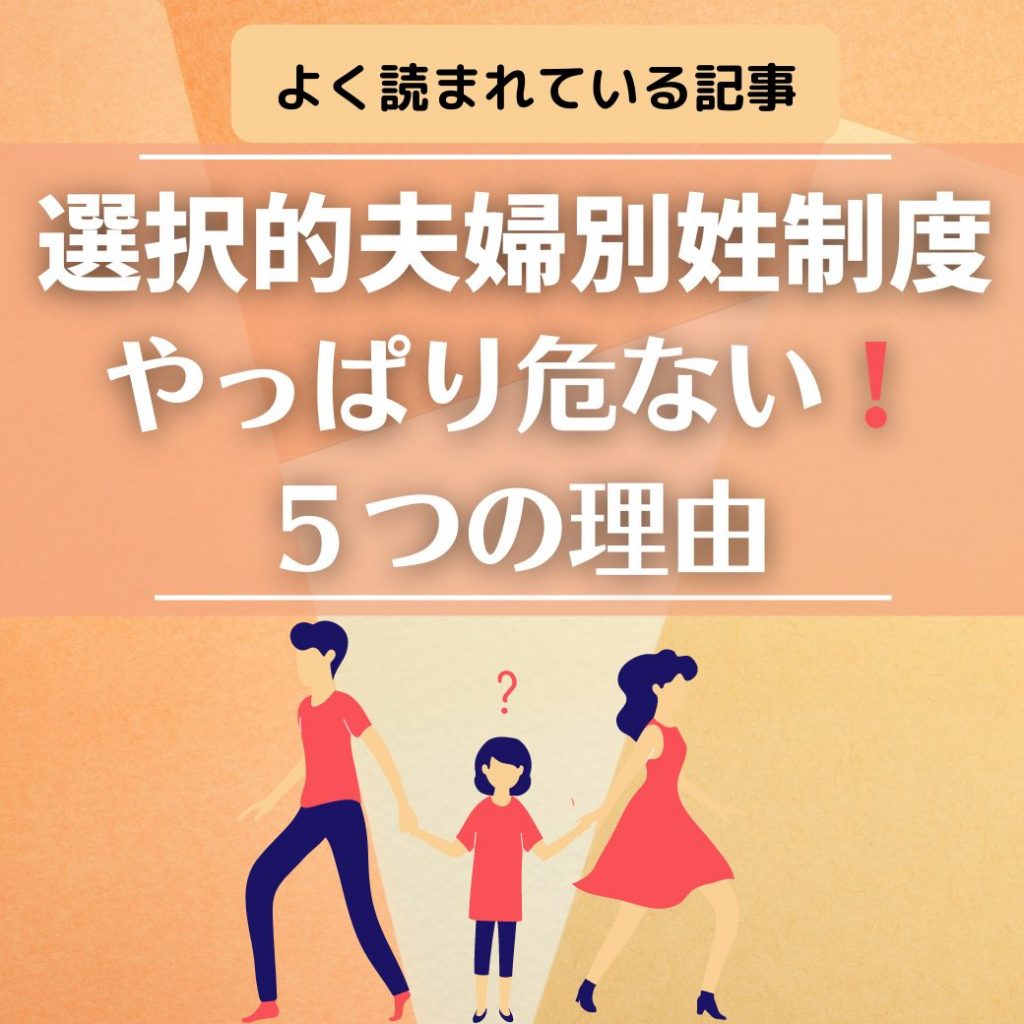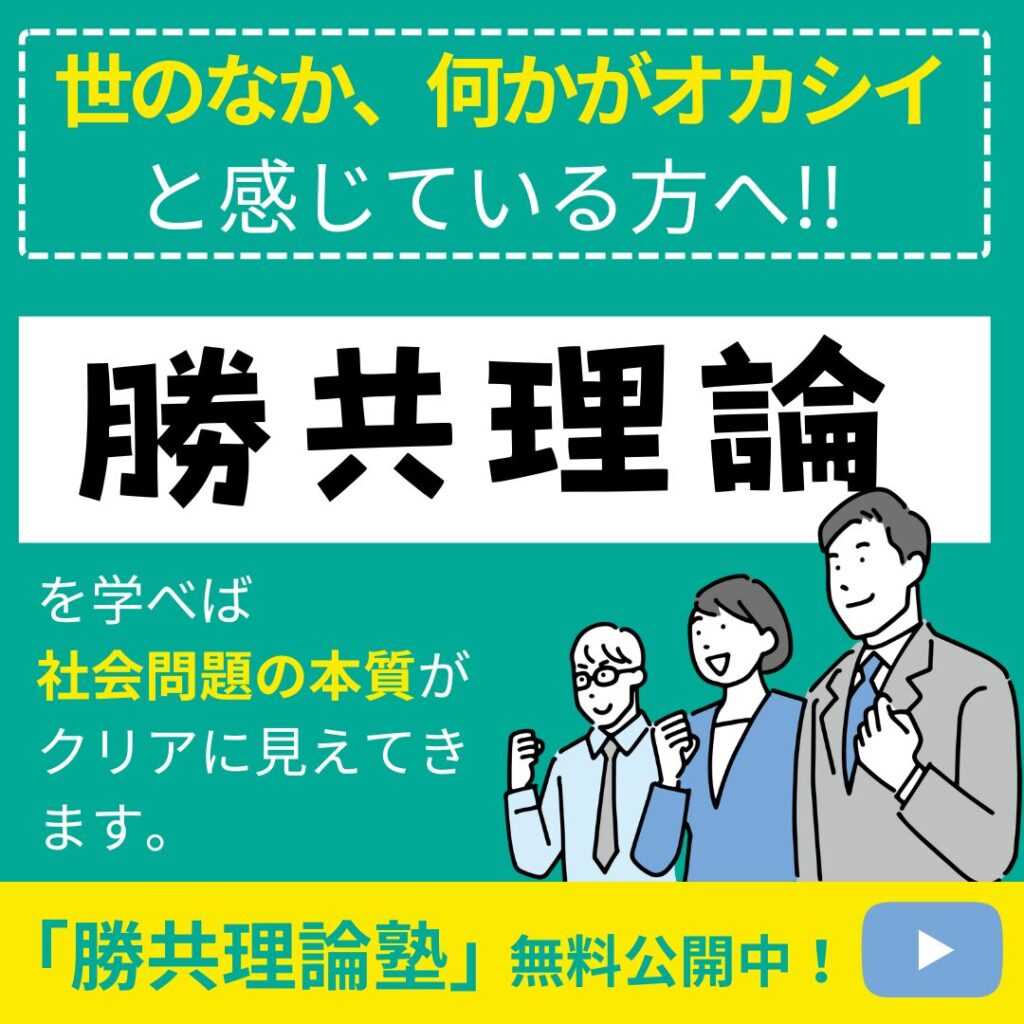オイディプス物語と倫理規範の極限
クロード・レヴィ=ストロース (中)
レヴィ=ストロースはサルトルに対し「コギトの僭越なる社会学化」だと批判しました(『野生の思考』)。人間主体、個人主体の「決断」の素晴らしさ、重要さを称揚しながら、実際には「サルトル自身のコギト(考える自我)」にしかすぎないものを、あたかも「みんなが各自で考え、決断した(コギトを超えた)共同主観性」だと錯覚した「共同幻想」にすぎなかったことを、レヴィ=ストロースは冷徹に見抜いたのです。
その意味で、サルトル同様の轍を踏む科学者の一群がいます。「インテリジェント・デザイン」(ID=知的設計者)理論を、「新しい創造説」として進化論に対する大変な脅威と見なすリチャード・ドーキンスを筆頭とする無神論的科学者です。「利己的遺伝子」説で知られるドーキンスがいくら論文や書物で何万語を費やしても、「神の不在」は証明できません。そもそも証明ができないからポパーは「疑似科学」としたのです。ドーキンスら無神論的科学者たちは、まさにサルトルの「神はいない、だからすべてが許される」を新しい「真理」だと持ち上げますが、「神は存在しない」と宣言するほど科学者の立場を狭めます。「コギトの僭越なる社会学化」はまさにそういうことです。
さて、レヴィ=ストロースによる「交換と贈与」のシステムをもう少し踏み込んで紹介しましょう。
「資料①」は社会集団内での「女の循環(交換)」について記したものです。そこでレヴィ=ストロースは、「血縁関係という生物学的起源システムを姻戚関係という社会学的システムに置き換えるための方法」だと論じています。
そして親族の基本構造を二項対立から説明しようとします。そのカギを握るのが、「母方の伯(叔)父」の態度だというのです(下図)。その親疎関係は、個人的なものではなく、社会構造的な恣意的なものだとの結論です。そこからレヴィ=ストロースは「贈与・交換」の法則性を導き出しました。「女性の交換」というと、人権侵害に聞こえますが、フェミニストの間では非常に悪名高い日本の「イエ制度」を見ると、これが実は「男女平等」なのです。というのも、「女性の交換」のみならず「男性の交換」も行われるからです。女性は「イエ」に嫁として入り、男性もまた婿として「イエ」に入る。
韓国や中国では女性は結婚しても苗字が変わりませんが、これは「イエ」よりも「血」を中心とした文化習俗だからです。しかしこの「イエ制度」こそ、男性も女性も親族間において「交換されうる」可能性を持つシステムだと言えます。しかも日本において顕著に見られるのは武家社会においては頻繁に行われた「婿養子」の制度です。これは婚姻に直接結びつかなかったとしても、「養子」に家督を継がせるというものでした。この江戸時代の幕藩体制こそ、日本の「イエ制度」の極致と呼べるでしょう。こうした制度・習俗は、明らかにある集団から別の集団への「女性の交換」ならぬ「男性の交換」と言えるものです。
フェミニストが根拠づけられぬ禁忌
それについて、本欄では、文化によっては日本のように「男性の交換」すら行われる場合があるという実例を紹介しました。ところが、フェミニストがいくら非難したとしても、フェミニズムからは「インセスト・タブー」すなわち、「近親婚(近親相姦)の禁忌」の根拠は説明できません。この難問を説明するのに、レヴィ=ストロースは「オイディプス神話」を手がかりにします。以下、粗筋です。
◇
最高神ゼウスは雄牛に化け美女エウロペを誘拐する。彼女を捜索に出かけた兄カドモスは、デルポイでアポロンの神託を受け、荒野に都(テーバイ)をつくる。都の外の洞窟に住む竜を退治したカドモスは、その牙を畑に撒く。するとその牙から甲冑をまとった竜の戦士らが生まれ、互いに殺し合いを始める。
カドモスの曾孫ライオスは「自分の子供の手にかかって殺される」という神託を受け、妻イオカステとの間に生まれた王子を山中に捨てるように密かに臣下に命じる。拾われた王子は金の留め金で足を刺し貫かれていたため「腫れ足(オイディプス)」と名づけられ、隣国の王宮で育つ。育ての親を本当の両親と信じ成人したオイディプスは、「父を殺し、母と通じる」というアポロンの神託を恐れ王宮を離れ旅に出る。そして山中で出会った暴虐な老人を実父ライオスと知らずに怒りにまかせて打ち殺す。
オイディプスがたどり着いたテーバイでは怪物スフィンクスが謎をかけ答えられない旅人を食い殺していた。オイディプスは謎を解き王位と王妃イオカステを獲得。だが、テーバイに再び悪疫が訪れる。ライオスの殺害者を発見してこの凶運を鎮めようと焦ったオイディプスは、全ての真実を知る。イオカステは自殺し、オイディプスは自らの目を潰して放浪の旅に出る。
◇
さてレヴィ=ストロースがオイディプス物語を四つの説話群に分けたチャートで(下図)説明します。
「左端の説話群に取りまとめられた出来事の全ての関係は-ー誇張されたーー血族関係に関わっている。ここで、親族たちは、社会的な規範が許す限度を超えて親密な関わりを結んでいる。それゆえ、第一の説話群の共通点は、『過大評価された親族関係』とする。第二の説話群は同一の関係に正逆反対の記号をつけたものであることがすぐにわかる。これは過小評価された(価値を切り下げられた)親族関係ということになる」と、レヴィ=ストロースが『構造人類学』で記述したように、このチャートの四つに分けられたカテゴリー(説話群)のうち、重要なのは、第一と第二のカテゴリーです。「誇張された血族関係」、この極端さが、いわば「倫理・道徳の一線」だと、レヴィ=ストロースは主張するのです。
この点を「第一説話群の『過剰評価された親族関係』とは具体的には『近親相姦』のことであり、第二説話群『過小評価された親族関係』とは、具体的には『近親間の殺し合い』のことである。これは親族集団を崩壊させる二つの極限として示されている」と『現代思想のパフォーマンス』が解説。
前者が「オイディプスの母イオカステとの結婚」に象徴されるものであり、後者が「オイディプスによる父ライオスの殺害」に象徴されるもので、まさにこの両者は、「親族集団を崩壊させる二つの極限」であると言えるでしょう。それは、あえてレヴィ=ストロースの考え方を敷衍すれば、かつての毎日新聞「変態記事事件」や、身内親族殺しという凶悪事件が突発することは、こうした「二つの極限」が「倫理的歯止め」とならなくなっています。![]()
極限示し外側から道徳を根拠づける
さらに重要なのは、次の「このような危機的な親族関係においては、家族を成立させている差異が失われ、成員たちは安定的な親族役割(父、母、兄弟姉妹、子)に自己同定できなくなっている」という指摘です。
これは昨今の夫婦別姓問題や民法「改悪」による「多様なる家族」観のめざすものが何であるかを示唆しているとも言えます。
そして「近親相姦する集団では、あまりに血族内での親密さが濃密なため『集団を外部へ押し広げる力』が失われている。一方、近親間で殺し合う集団では、あまりに親族的な親密さが希薄なため、『集団を求心的に取りまとめる力』が失われている。自閉して外部を持たない共同体と、求心力を失って離散する共同体という二つの極限形態の間に人間たちはその社会モデルを設定しなければならない。つまり、『父を殺し、母と通じた』オイディプスとは、人間が決して超えてはいけない二つの極限を身をもって示しているのである」という同書の表現は、「資料」に掲げた箇所と相まって、人間の倫理道徳というものを、「倫理の埒外」を示すことにより、外側から根拠づけている(哲学的に「超越論的」と言います)と言えるのです。
(「思想新聞」2025年7月15日号より)