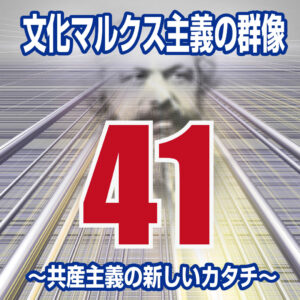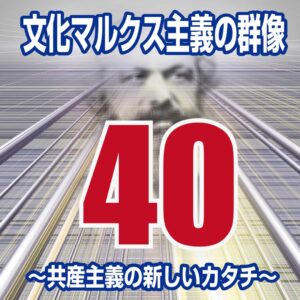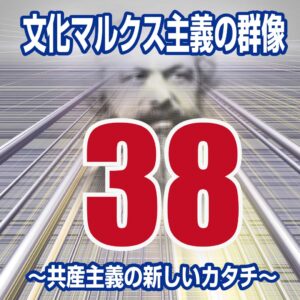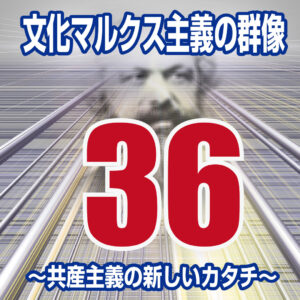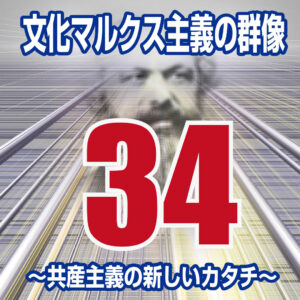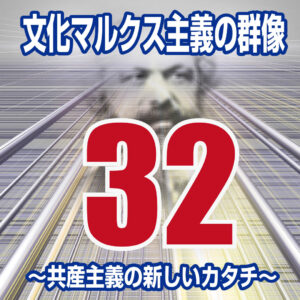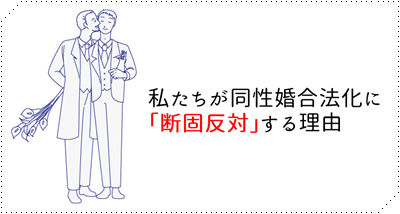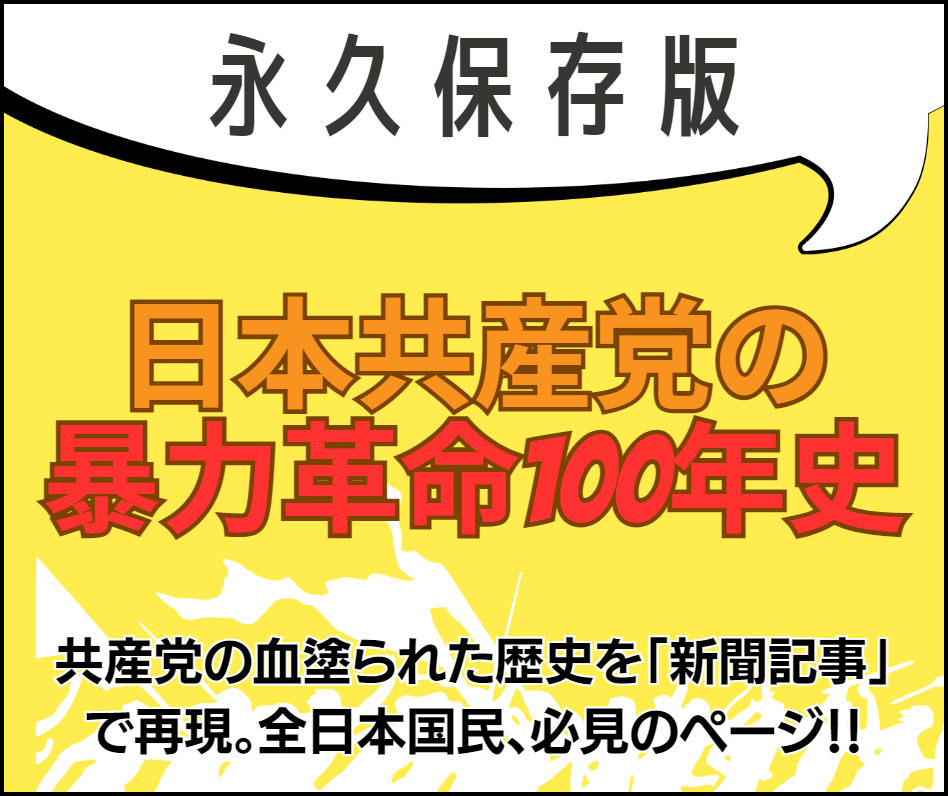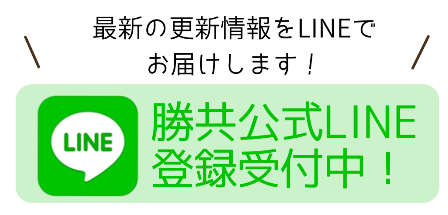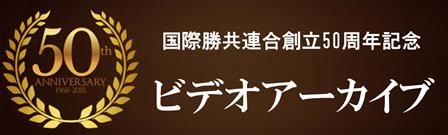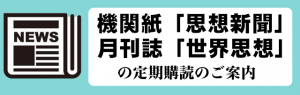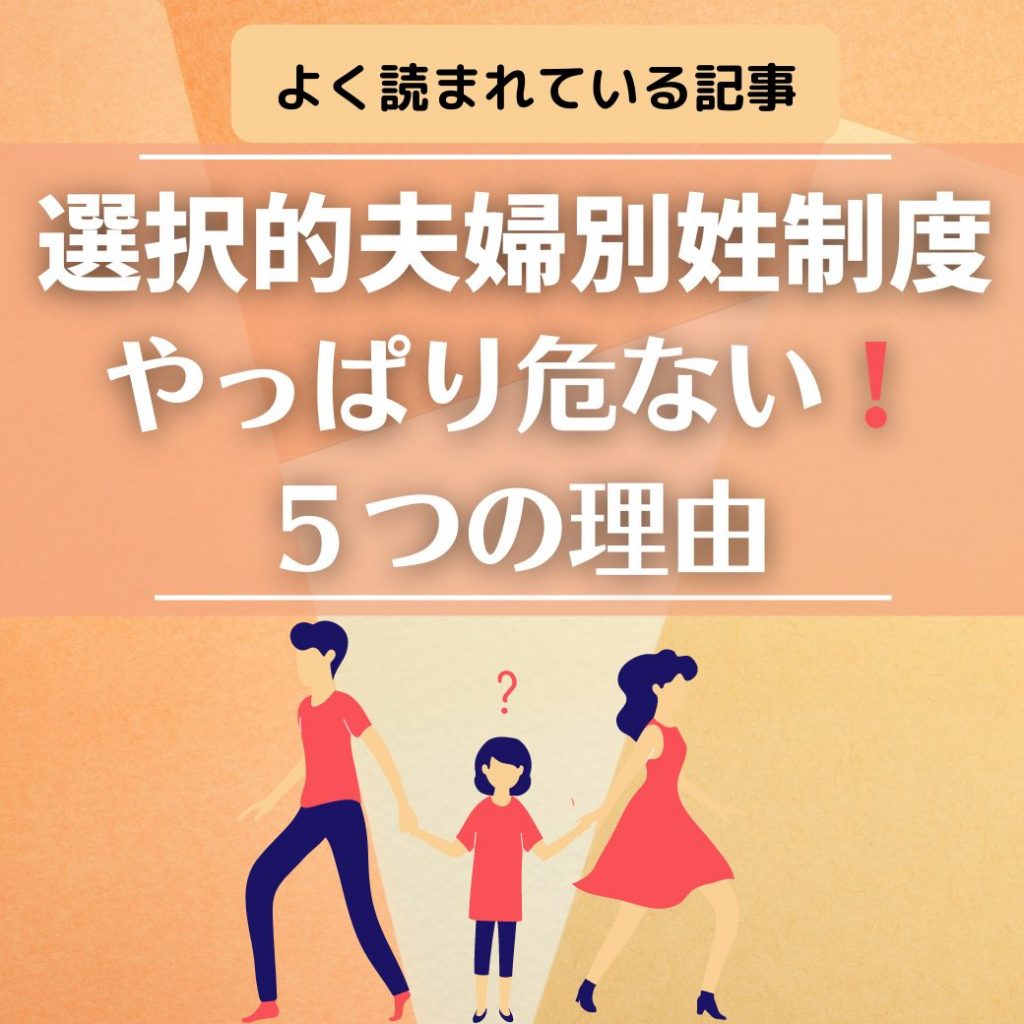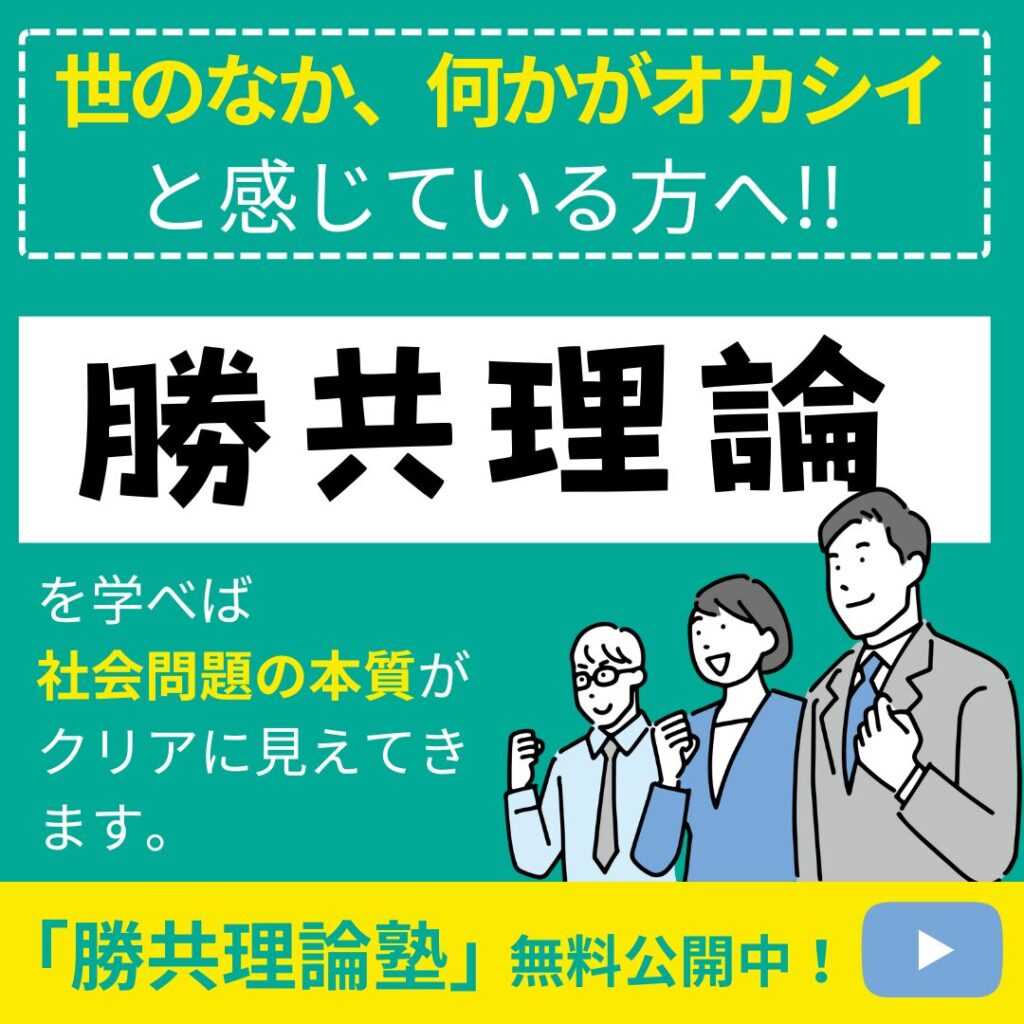贈与による利他性こそが人間の本質
クロード・レヴィ=ストロース (下)
レヴィ=ストロースは、親族間の「親疎」の度合いから人としての「倫理道徳の限界点」を示すことで外側から倫理を根拠づけようとしました。これをレヴィ=ストロースはソシュールに倣い一種の「記号」と見なし「構造」という言葉で説明しようとしました。
しかしこの点こそ、ロラン・バルトやミシェル・フーコー、ジル・ドゥルーズといった後続の構造主義思想家たちが、「レヴィ=ストロースの構造主義」に飽きたらず、やがて「ポスト構造主義」と呼ばれたゆえんだと言えるかもしれません。なぜなら、彼ら「ポスト構造主義」者たちは、倫理規範や道徳規準という垣根を取り払うことで、「新しい倫理」の構築を企てたからです(ドゥルーズ=ガタリ『アンチ・エディプス』フーコーによる序文)。
無神論的実存主義と有神論的実存主義
レヴィ=ストロースの打ち立てた構造主義とは、徹底した「アンチ実存主義」だと、先にも紹介しました。「主体の決断と企投(参加)」を促し、政治的活動に駆り立てるサルトル実存主義を、「コギト(考える自己)の僭越」と呼び否定することで、レヴィ=ストロースは本来的な学問、客観的で普遍的な学を樹立しようとしたのです。マルクスが「哲学の政治的党派性」を説いたように、サルトルの哲学もきわめて政治的にマルクス主義的党派性が色濃く反映されたものでした。
ただし、実存主義思潮がすべて政治的左翼運動に転化していったわけではなく、カール・ヤスパースやガブリエル・マルセルら「有神論的実存主義」は、もっと冷静であり、より個人の内面世界に踏み込んだ思想だと言えます。
ニーチェ主義の左翼化という袋小路
もっとも、西欧哲学が伝統的に担ってきたところの「形而上学」を解体しようとする意志、すなわち「西欧中心主義」に対する明確な否認(及び西欧思想の徹底的な相対化)は、レヴィ=ストロースにおける「思想的核心(コア)」と呼んでもいいでしょう。こうした「反形而上学」「反西欧中心主義」を打ち出したのは、サルトル以前、「実存主義」と目されたニーチェです。アラン・ブルームは「ニーチェ主義の左翼化」と言いましたが、やはり文化共産主義に影を落としているのです。
加えて、画家である父の影響と幼い頃から広重や北斎などの浮世絵=ジャポニスムに親しんだことが、知日家レヴィ=ストロースを生み出したのです。反西欧のベクトルを持つとは言え、文化伝統の否定という文化共産主義的範疇で捉えきれないのが、レヴィ=ストロースと言えるのです。
源流としてのマルクス・フロイト・ニーチェ
もっとも、西欧哲 レヴィ=ストロースの打ち立てた構造主義は、やがて彼自身の思惑と離れ、構造主義からポスト構造主義へと向かうことになります。アラン・ブルームが米アカデミズムに吹き荒れた性解放運動を告発した『アメリカン・マインドの終焉』で強調したのは、マルクス主義、フロイト主義、左翼化したニーチェ主義です。ブルームに加え、内田樹・神戸女学院大名誉教授は「構造主義というのは、…私たちは自分では判断や行動の『自律的な主体』であると信じているけれども、実は、その自由や自律性はかなり限定的なものである、という事実を徹底的に掘り下げたことが構造主義という方法の功績なのです。……これが前│構造主義期において、マルクスとフロイトが告知したことです」(『寝ながら学べる構造主義』)と述べ、さらに「人間の思考が自由ではない」と主張したニーチェを加え、構造主義に連なる3つの源流と指摘します。
この内田氏の構造主義解釈は、マルクス主義への評価と共に非常に肯定的です。しかしレヴィ=ストロースに限れば、内田氏の評価は極めて正当なものです。「近親相姦の禁忌」など人類共通に見られる規範習俗、伝統文化の独自性についてレヴィ=ストロースは尊重しているからです。
親族システムの存在理由示す3つの資料
内田氏は、さらに進んでレヴィ=ストロースを解釈し、彼の意図した「人間の本性」について迫ります。
レヴィ=ストロースは人間が社会構造を作り出すのではなく、社会構造が人間を作り出し、社会構造は、人間的感情や人間的論理に先立つと考えました。
しかし、社会制度の起源は全て闇に消えているわけではなく、ある社会集団が今ある親族システムを「なぜ」選択したのか、その個別的理由は分からないが、親族システム「というもの」が存在する理由は分かっており、「資料①」に見られるように、親族構造は端的に「近親相姦を禁止するため」に存在するのだ、と内田氏は指摘します。
次に、なぜ人間は近親相姦を禁止するのかという問いにレヴィ=ストロースは「資料②」のように、「女のコミュニケーション」を推進するためと答えます。さらに親族が存在するのは親族が存在し続けるためであり、「資料③」のように「反対給付」、つまり「贈り物」を受け取った者は、心理的な負債感を持ち、「お返し」をしないと気が済まない、という人間固有の「気分」に動機づけられた行為は、知られる限りのすべての人間集団に観察される、と内田氏は指摘します。
こうした贈与論から見えてくるものは何か。意外にもそれは「ポストモダン」とは毛色の異なる見解であることがわかります。
内田氏は「贈与と返礼による社会的効果の本質」として「人間は自分が欲しいものは他人から与えられるという仕方でしか手に入れることができない」という真理を人間に繰り返し刷りこむことであり、この贈与と返礼の運動は、まず自分がそれと同じものを他人に与えることから始めなければならない、それが贈与についての基本ルールだと看破しています。
「利己的遺伝子」のように、人間は生来利己的であるというのは、ドーキンス博士ばかりではありません。しかし、「人間社会はそういう静止的、利己的な生き方を許容しません。仲間たちと共同的に生きてゆきたいと望むなら、このルールを守らなければなりません。それがこれまで存在してきた全ての社会集団に共通する暗黙のルール」と内田氏は述べます。
中でも白眉は、「もし人間の定義があるとしたら、それはこのルールを受け容れたものという他ないでしょう。人間は生まれたときから人間であるのではなく、ある社会的規範を受け容れることで人間になる」というレヴィ=ストロースの考え方は、たしかに人間の尊厳や人間性の美しさ、隣人愛や自己犠牲といった行動が、人間性の「余剰」ではなく、人間性の「起源」あるいは「本質」であると呼べるでしょう。これが実は、ニヒリズムとは対極にあり、宗教的精神と結びついていると言えるのです。
贈与と返礼という利他性の円環が人類史
内田樹氏の『寝ながら学べる構造主義』の記述はきわめて平明でありながら、レヴィ=ストロースの思想史的立ち位置を、正確に捉えている論考であると指摘したは、一言で言えば「人間本性の利他性」ということになるでしょう。
そうに考えれば、「他者(他の共同体)への贈与」という円環こそ、人類社会と歴史をつくってきたという「人類史の物語」を、レヴィ=ストロースが総論として持っていること、それはつまり、明らかにマルクス主義の「人類歴史は階級闘争史である」とする唯物史観とは真っ向から対立すると言わざるを得ません。
英政治学者A・D・リンゼイは『民主主義の本質』において近代民主主義を、全体主義の起源となる「似非民主主義」と宗教的自由に根ざした「正統民主主義」の二つの系譜で示しました(上図)。これに倣って言えばマルクスの弁証法的唯物論の帰結は、トマス・ホッブズの「万人の万人に対する闘争」以来の、「利己主義の系譜」によってもたらされたものと言えるでしょう。これまで王侯貴族たちが民衆の上に立ち、資本家階級が労働者の上に立ち、搾取し支配することによって社会が成り立ってきた。それを打破し、階級を転倒させるためには暴力革命が必要で、それを経ることで国家は消滅し、共産主義社会という「労働者の天国」が到来するーーというのがマルクスによる「唯物史観の物語」です。
このマルクス主義の物語が、既に実現不可能な「神話」と化していたことは、本論稿の「社会民主党編」で述べました。社会主義革命とは本来、資本主義の最先端の国や地域から資本主義自体の矛盾により恐慌が起こる結果、必然的に起こるものと考えられましたが、実際には産業革命の発祥地・英国でも、いち早く大衆消費社会を招来した米国でもなく、国家基盤の不安定なロシアにおいて最初に起こったことは、マルクスやエンゲルスの「見当違い」だったからです。
しかもそのロシアを70有余年も支配したソビエト共産党(ボリシェヴィキ)の一党独裁体制は、「労働者の天国」どころか、政治犯の「収容所群島」と化し、「ノーメンクラツーラ」という「新しい支配階級」を生み出しただけでした。
社会規範を受け容れてこそ「人間」になる
この意味において、思想・信条・信教の自由を認めない一党独裁体制は、人間の自由意志や自発性に由来するところの利他性、自己犠牲、隣人愛という「人間の美徳」を拒絶するものであることがわかります。そこには社会に連綿と受け継がれてきた伝統や習俗、価値観などは、たちまち切り捨てられるのです。
サルトルのマルクス主義的実存主義に対する明白な「否」にもかかわら拘わらずず、レヴィ=ストロースの唱えた構造主義は、マルクス主義そのものと対峙したわけではありませんでした。「構造主義四天王」と呼ばれる思想家たち、中でもルイ・アルチュセールは終始マルクス主義の立場を離れず、「構造主義的マルクス主義」を唱えました。
ドイツのフランクフルト学派は、ユダヤ系学者を中心に展開され、マルクスとフロイトの「融合」を試みました。ポストモダンと言われるフランス現代思想に一貫して共通するものは、「反西欧」になります。西欧近代の歴史を否定しようと思えば、容易に援用されがちなのは、マルクス主義ということになります。そして「神は死んだ」を叫び、超人思想を説いたニーチェもそうです。
しかし徒らに超人を追うよりも、大多数の人はむしろ「人間は生まれたときから『人間である』のではなく、祖先が暗黙のうちに親族制度や言語や神話を構築したところのあるルール、社会的規範を受け容れることによって『人間になる』」というレヴィ=ストロースの主張に無意識のうちに従っていると言えるのではないでしょうか。
(「思想新聞」2025年8月1日号より)