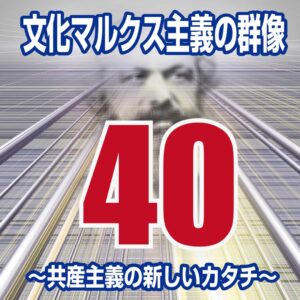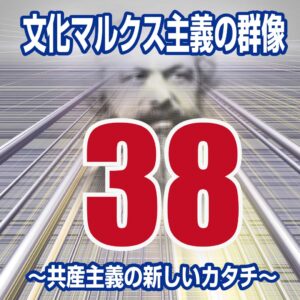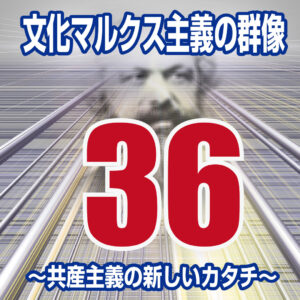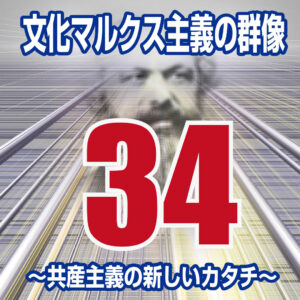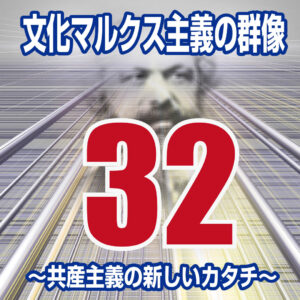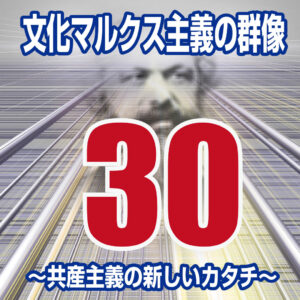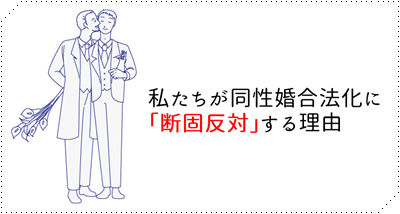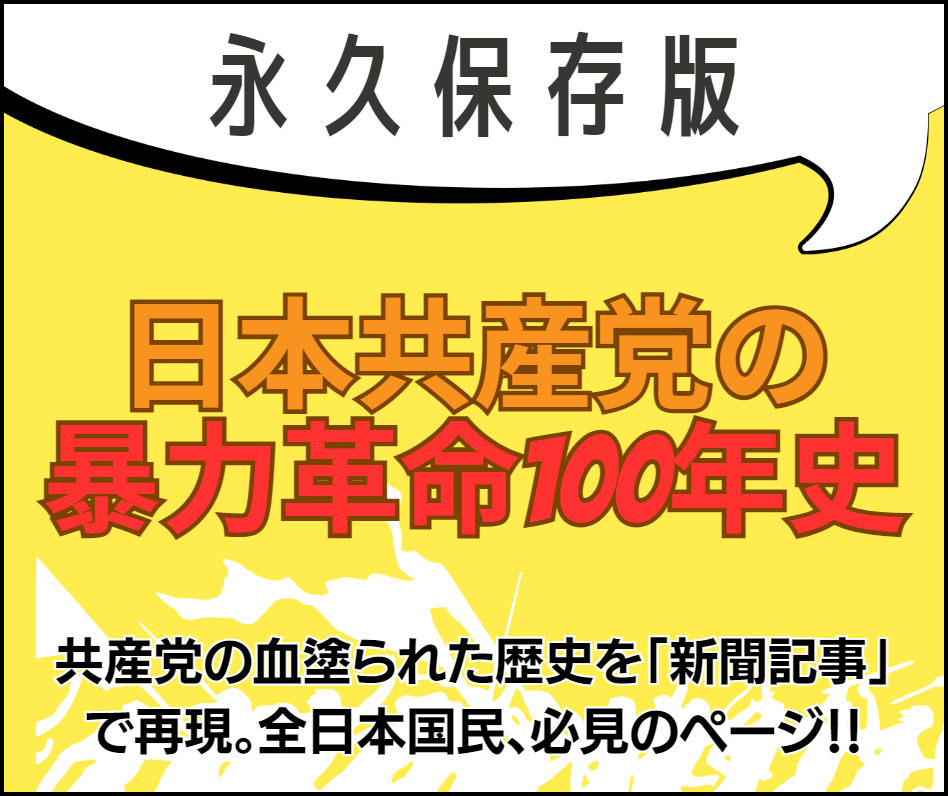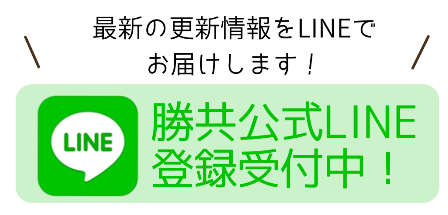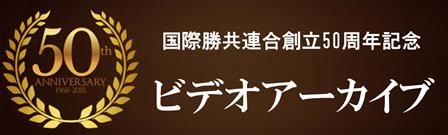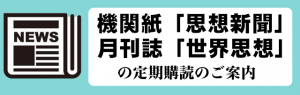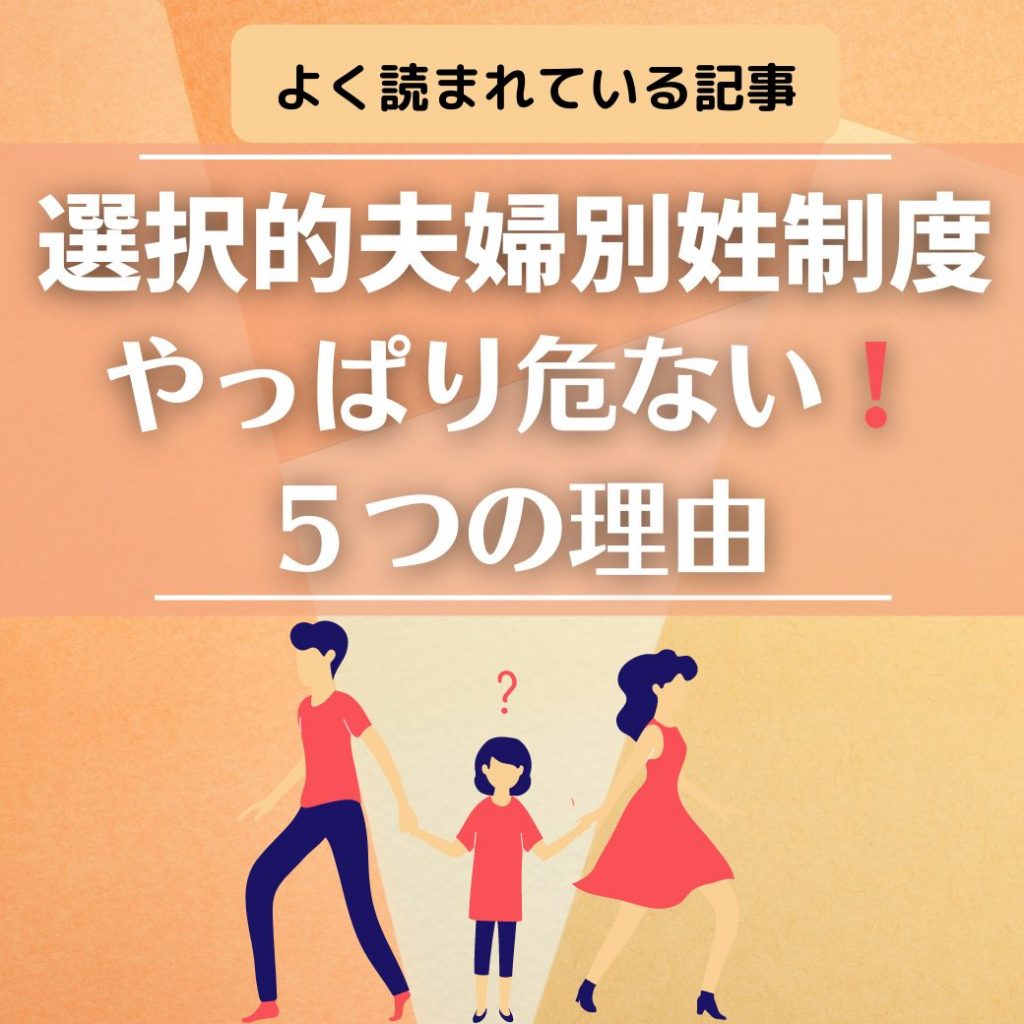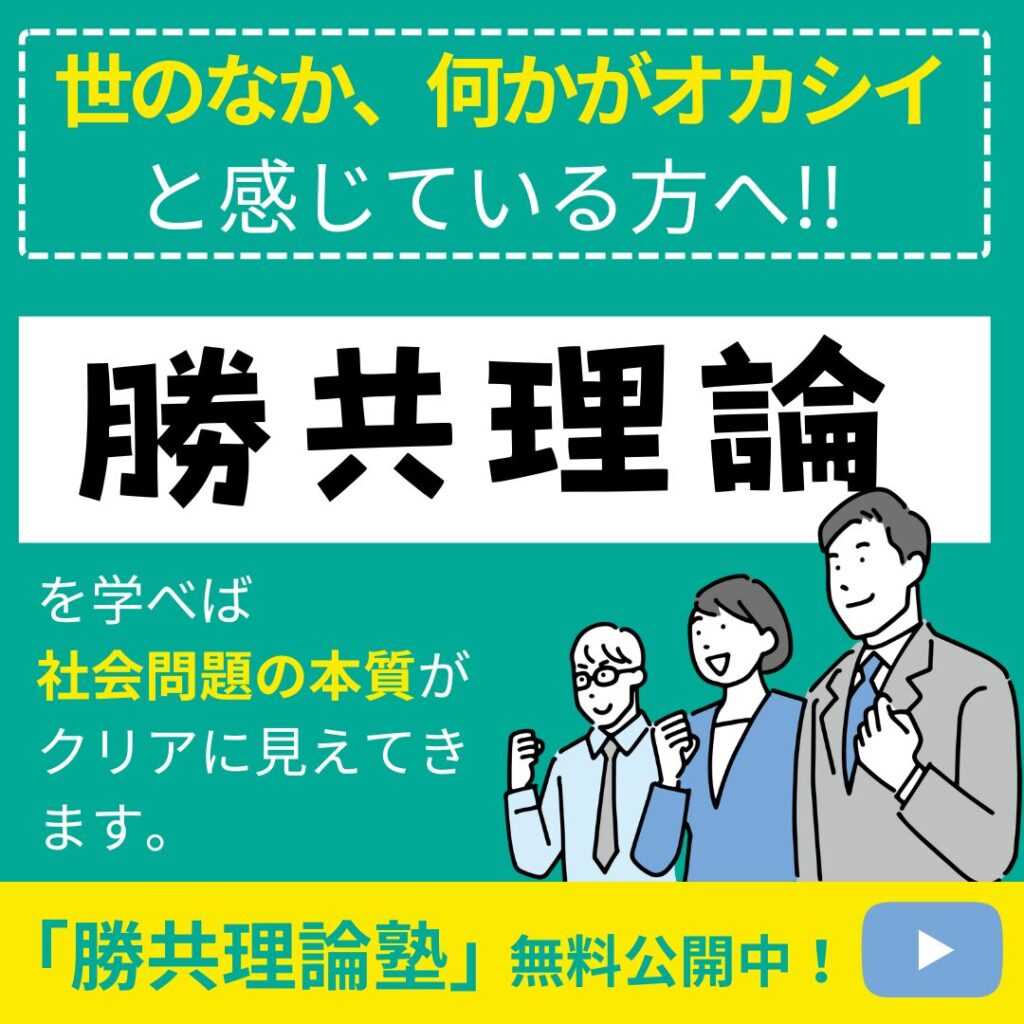「構造主義」に道拓く「記号学」を創始
フェルディナン・ド・ソシュール(上)
現代思想の源流の一つとなった「記号学」
フェルディナン・ド・ソシュール(1857〜1913)
フランス現代思想の代名詞「構造主義・ポスト構造主義」。その「思想的源流」の一つと言えるのがスイスの言語学者フェルディナン・ド・ソシュールの「記号学」という考え方です。ポストモダン思想がなぜ「差異」というものに拘るのか──。それを「記号学の父」、ソシュール思想に遡って求められます。
「ポストモダン」という言葉が、当然のように現代思想に導入されるようになった背景には、「構造主義」ないし「ポスト構造主義」が「現代思想の旗手」として登場した点が指摘できます。その「構造主義」を最初に展開したのがクロード・レヴィ=ストロースで、そのレヴィ=ストロースの思想も、実は言語学において決定的な影響を与えたフェルディナン・ド・ソシュールの「記号学」(または「記号論」)にその多くを負っており、ソシュールはマルクスやニーチェ、フロイト、フッサールなどと共に現代思想の一潮流を成しています(下図の「主要現代思想系統図」を参照。フロイトの上にソシュールがきています)。
直近ではあまり声高に言われなくなった思想的潮流、「構造主義・ポスト構造主義」。しかし、1960〜70年代に世界同時多発的な学生紛争などによる「革命・政治の季節」を醸成したのが、「マルクス主義&実存主義」であったとすれば、その「挫折」による「ノンポリの時代」的背景から、1980年代に一世を風靡したのが、構造主義思潮でした。
特に日本では「ニュー・アカデミズム」と呼ばれ、栗本慎一郎『パンツをはいたサル』、浅田彰『構造と力』、中沢新一『チベットのモーツァルト』などが社会現象となり、構造主義思潮「ブーム」の一翼を担ったのが、「記号学」でした。
![]()
弟子が没後まとめた『一般言語学講義』
ソシュールは、フランスのユグノー貴族の系統を受け継ぐ旧家の長男として、宗教改革者カルヴァンの「お膝元」、スイスのジュネーヴに生まれました。ソシュール家の父祖モンジャンはフランスのソシュールを領地とする貴族でしたが、息子の代に新教徒(ユグノー)側に立ちスイスに亡命し、その子孫はジュネーヴに定着。名だたる学者の家系として知られ、フェルディナンの父アンリも昆虫学の権威と呼ばれた生物学者でした。
ソシュールが天才言語学者として注目されるようになったのは、彼が21歳の若さで浩瀚な論文『インド・ヨーロッパ諸語における母音の原初体系についての覚した。この論文は、印欧語族のもとになる祖語の時代に、現代では表記されなくなった音が含まれていたのではないかと推論したもので、「比較言語学史上の金字塔」とも評価されています。
彼はパリ時代にフランスの最高学府「コレージュ・ド・フランス」の言語学正教授のオファーがありましたが、フランス国籍取得が就任の条件だったため、亡命貴族の末裔らしい筋の通し方でジュネーヴ大学教授となったのです。
ソシュールは意外にも生前、専門的論文の他はまとまった著作は出版しませんでした。しかし、ジュネーヴ大学での3期にわたる言語学の講義録(弟子が編集)により、言語学という専門分野を超え後世への決定的な影響を与えることになります。
コトバこそが人間の現実を作り出す
ではこのソシュールの思想とはいったい、どのようなものなのでしょうか。ここでは、内田樹・難波江和英共著『現代思想のパフォーマンス』(光文社)の記述がわかりやすくコンパクトにまとめているので、こちらを参照してみます。
◇
ソシュールは、十九世紀から二十世紀にかけて、すべての思想のもとになる言えることによって、言語と人間の関係について現代ならではのヴィジョンを開いた……ソシュール以前の言語学では、どうしても、コトバは人間が現実を理解するための道具と見なされやすくなる。そこでソシュールは、コトバの見方をコペルニクス的に転回して、この考え方をひっくり返してしまった。つまり、このコトバは人間が現実を理解するための道具ではなく、コトバこそが人間の現実をつくっていると考えたのである。……もう少し説明してみよう。私たちは自由にものを見ているようでいて、実は本人が思っているほど自由にものを見ているわけではない。その一つの理由は、私たちのものの見え方(現実)が、自分の頭に刷り込まれた日本語(語彙・文法・修辞)によって、かなりコントロールされているからである。
例えば、何を見ても「メッチャかわいい」としか表現できない若者には、その表現のかたちが自分の感情のかたちそのものに見えてしまう。そこにあるものが「メッチャかわいい」と感じられたのは、それが「メッチャかわいい」からではなく、それを「メッチャかわいい」と表現したからではないか。その意味で、コトバはその人のものの見え方(現実)に輪郭を与えて、それをコントロールしているといえる。
このようにソシュールは、私たちが「現実」と思っているものが、実は私たちの言語の働きからつくり出されたものであることをとの関係を問い直す。
◇
同書はさらにソシュールの思想の特徴を次の四点にまとめています。
①「コトバはモノの名前である」という伝統的言語観(言語名称目録観)を否定したこと
②従来の言語学における歴史的な方法(通時言語学)に対し、同時代の言語現象を対象にする非歴史的な方法(共時言語学)を導入しそれを優先させたこと
③言語とは何かを考える上で、人間に特有の言語能力(シンボル化能力)を「ランガージュ」、それぞれの共同体で使われている国語体を「ラング」、それぞれの話者が発話するときの音声の連続を「パロール」と呼んで、三つのレベルを区分したこと
④言語を単一の構築物としてではなく、相互に関係した要素から構成される価値の体系と考えたこと
実体概念から関係概念へのパラダイムシフト
このうち最も重要なのが④だとし、「言語を一つのまとまりをもつ実体としてではなく、いくつもの要素が働きかけ合うシステムとして捉える視点が認められる。このように対象となるもの(例えば言語)を捉えるにあたって、実体の概念から関係の概念へと視点を移し換えること、それはまた現代思想と呼ばれる思考の方法の特徴の一つである」と、「実体」から「関係」へのいわば「パラダイム・シフト」だというのです。
「コトバはモノの名前である」と考える「言語名称目録観」とは、左上の「図1」のように、絵の表現する表象をそれぞれ「木」(arbor)「馬」(equos)と一対一にて対応している、と考えるものですが、ソシュールはそうではないと考え、「シーニュ(記号)」=表象という場合の「シーニュ(記号)が結びつけているのは、概念と音響イメージである」と主張しました。この「概念」と「音響イメージ」のことを、ソシュールはそれぞれ「シニフィエ」(意味されるもの)と「シニフィアン」(意味するもの)と呼び、コトバと呼ばれるものは、これらから構成される複合的な単位のことで、この複合的単位のことを「シーニュ」(記号)であるとしました(図2)。ソシュールのいう「シニフィアン」、つまり「音響イメージ」とは、「物質的な音、つまり純粋に物理的なものではなく、音の心的な刻印、つまり私たちの感覚に訴えかけてくる音の印象」で、「私たちは、唇や舌を動かさないでも、自分自身に話しかけたり、ある詩を頭の中で朗読したりできる」とソシュールは解説しています。
私たちが「イヌ」と言うときの「イ」と「ヌ」の音のつながりを声に出さないで、頭の中で唱えた時に浮かぶのが「音響イメージ」で、このイメージが連想されると同時に、「イヌ」という概念が、例えば「イエ」でも「イカ」でも「イス」でも、「イケ」でも「イモ」でもない別のものとして区分されながら立ち現れてくるのだというわけです。そして「イヌ」の音響イメージが「シニフィアン」であり、それによって区分される「イヌ」の概念が「シニフィエ」、そしてこの二つの要素から構成される複合的な単位が「シーニュ」ということになります。
![]()
(「思想新聞」2025年4月15日号より)