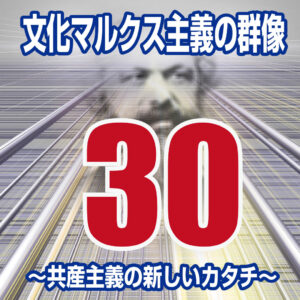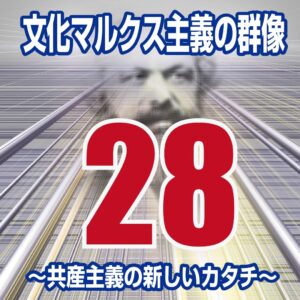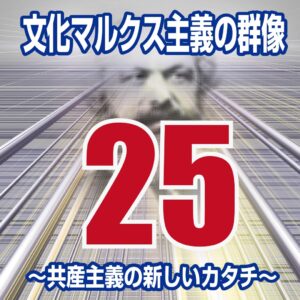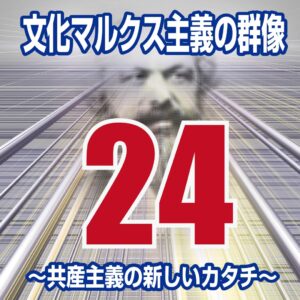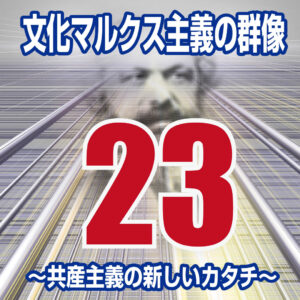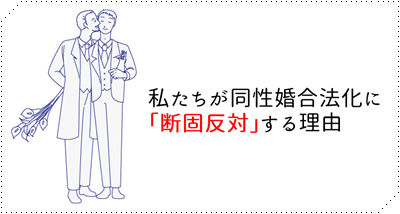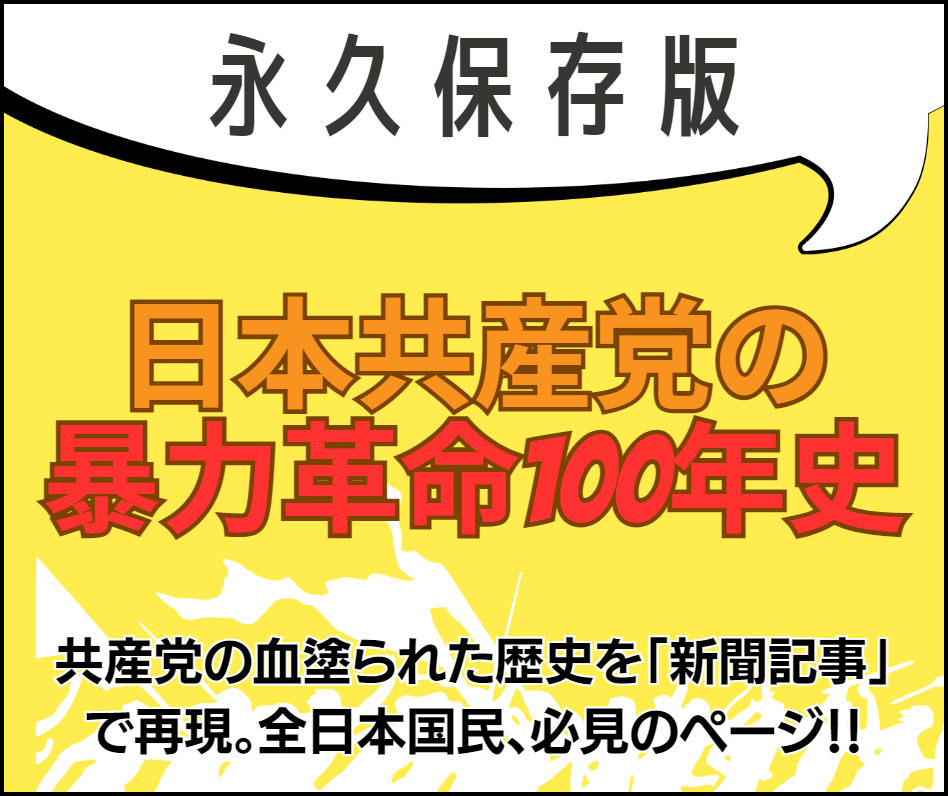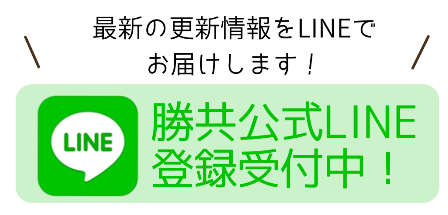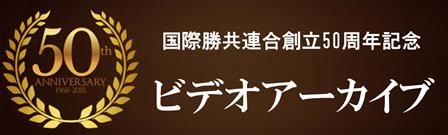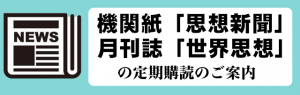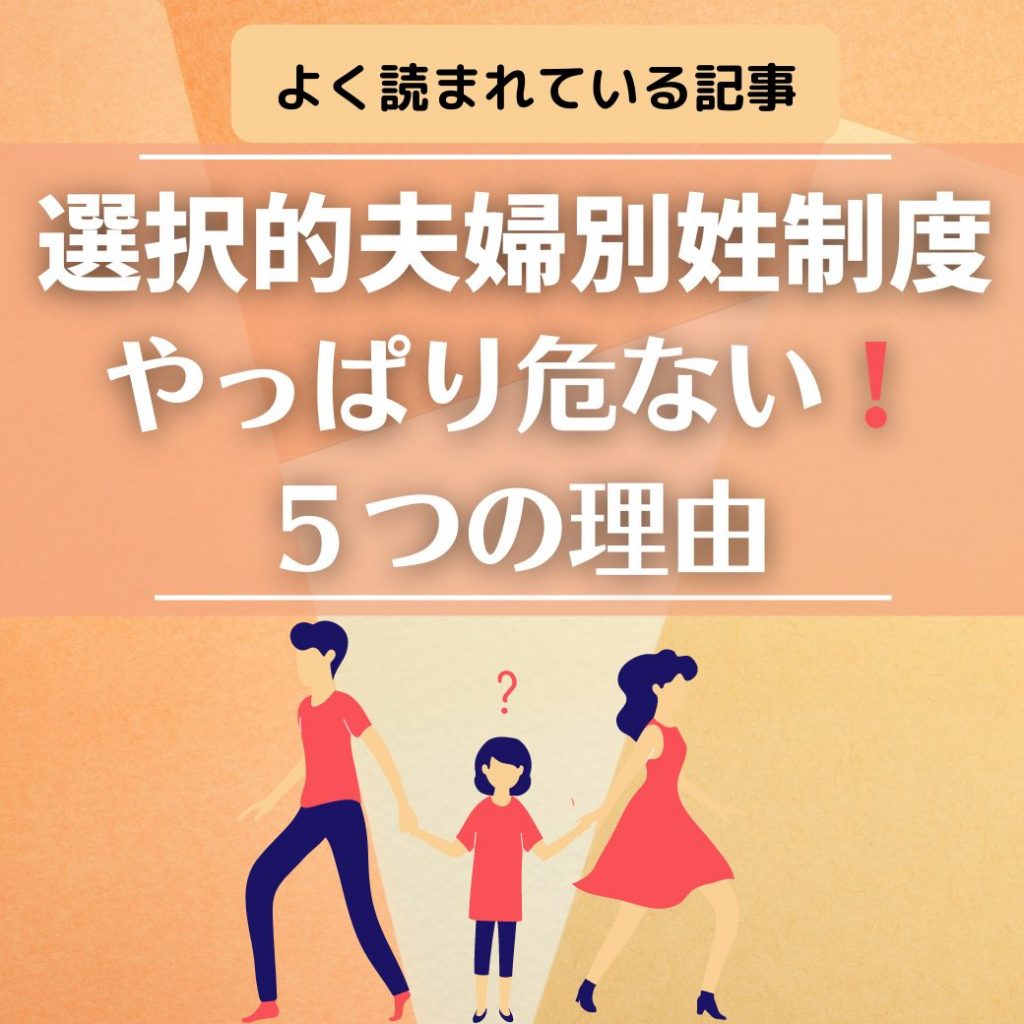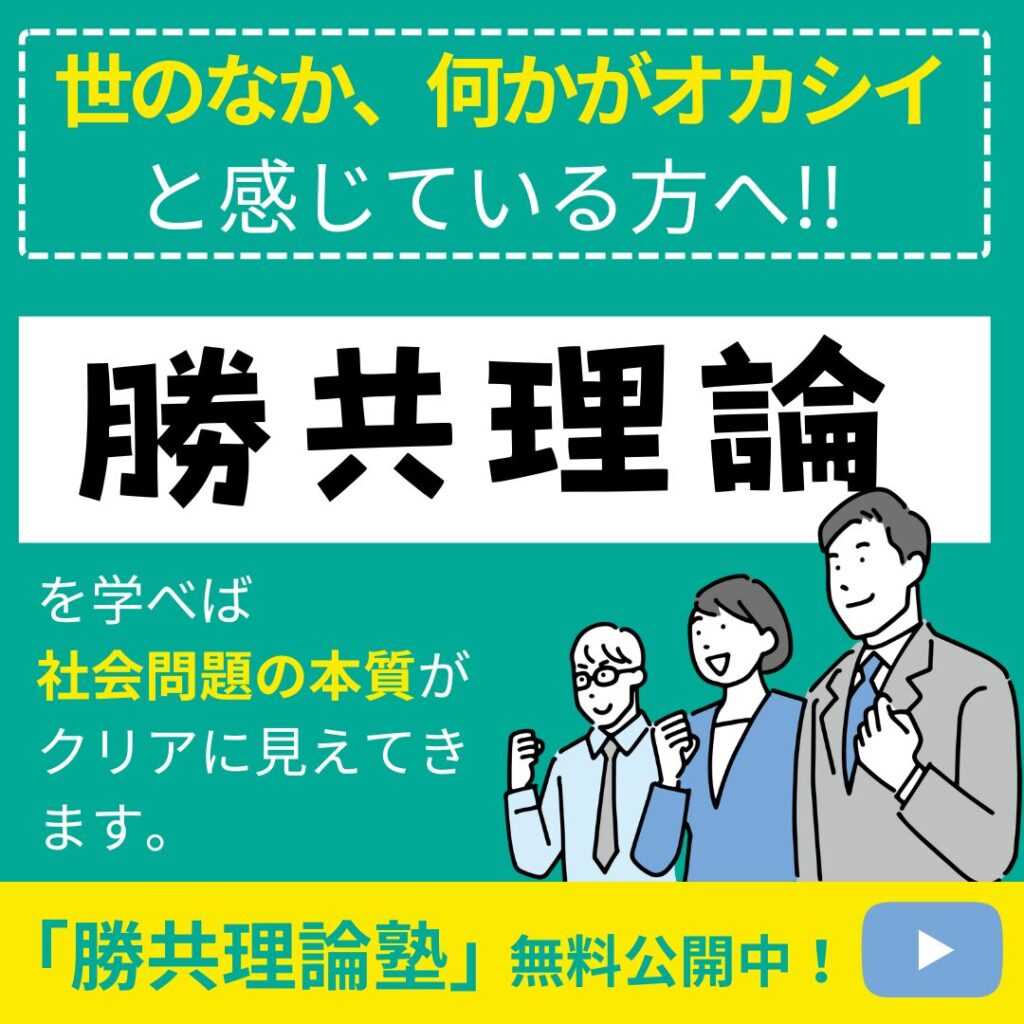文化決定論 vs 遺伝決定論
マーガレット・ミード
マーガレット・ミード
ホルクハイマーとアドルノらが提唱した「フランクフルト学派」は、「マルクスとフロイトの融合」によって「マルクス主義の学際的システム」を標榜し「ユーロ・コミュニズム」の地平を切り拓き、そしてフロイトの「汎性欲論」をさらに過激化させたライヒが「性と文化の革命」として「性解放」を位置づけます。
この「性解放」と、「文化的性差」(ジェンダー)の問題を、文化人類学という若い学問領域で展開したのが、米国の文化人類学者マーガレット・ミード(1901〜78)です。コロンビア大学大学院生だったミードは、南ポリネシアのサモア島でのフィールドワークに野心的に取り組み、その「成果」を『サモアの思春期』(Coming of Age in Samoa)に結実させ、賛否両論を巻き起こすも「文化人類学史上画期的な研究」との評価を受けました。
本連載20回目のラマルクの稿でも触れましたが、20世紀初頭の人類学・生物学界では「遺伝」(氏=生まれ)か「後天性」(育ち=環境)かでどちらが重要かという論争が行われ、主に前者がダーウィニズムから優生学への流れ、後者が文化人類学という対立軸がありました。後者の中心的論客が、ミードが師事したコロンビア大学のフランツ・ボアズ教授でした。
これまで述べたように、遺伝的要因を強調すれば、人種差別を正当化するような優生学が学問として興隆し、後天的要因を強調すれば、環境や文化が変われば人格や人間性が全く変わるという、ある種のイデオロギー的なものを持っていました。ボアズに連なる学派は、ミードのデビュー以前から自然淘汰としてのダーウィニズムを擁する遺伝決定論と熾烈な《氏│育ち論争》を繰り広げて、ミードはその「刺客」として登場したと言えます。
どのような問題意識でミードは南洋サモアの若者たちの文化風習についてのフィールドワークに取り組んだのか。ミードの文化人類学に対する批判的研究を打ち立てたニュージーランドの文化人類学者で、足かけ40年もの歳月をかけてサモアの文化習俗の「真実」に取り組んだデレク・フリーマンによる『マーガレット・ミードとサモア』(邦訳=木村洋二、みすず書房)の記述で見てみましょう。
◇
「ボアズの命で思春期問題を調査するためにサモアに赴いた二十三歳のミードは、驚くべき結論を持ち帰った。欧米では、思春期は情緒的なストレスと葛藤の時期というのが常識である。もしもこの問題が成熟という生理的プロセスによって起こるものならば、どの人間社会をとっても同じような問題が見出されるはずだ、と彼女は論じる。ところが、彼女の報告によれば、サモア人の生活はのどかそのもので、思春期も一生のうちで一番気楽で楽しい時期なのであった。つまり、ミードによれば、サモアは人類学でいう「否定的事例」(negative instance)なのであり、このような反対例の存在は、アメリカおよび各国の思春期につきものの混乱が、生物学的原因ではなく、文化的原因によるものであることを明らかにしている。一九二〇年代に頂点を迎える生物学的決定論と文化決定論の論争において、文化の主権を信じる者の目には、このミードの反対例は決定的な切り札と映った。
一九二八年に出版されるやいなや『サモアの思春期』は大いに注目され、決定的と見えた調査結果はただちに掌中の玉といった趣きで人類学の教説に組み込まれた。以来、ミードの調査結果は繰り返し多くの教科書の中で紹介され、人類学関係のベストセラーとなった『サモアの思春期』の人気の高さも相まって、世界中の何百万の人々の考え方に影響を与えた」
◇
倫理規範や通過儀礼を社会的抑圧と見る
![]()
さて、ミードの『サモアの思春期』には、「サモアの青少年の間には、倫理規範や通過儀礼などの社会的制約(ミードにとっては「社会的抑圧」)などが存在せず、気楽かつ開放的で、おおらかでストレスもなく、絵に描いた楽園のような青春を謳歌している」、という趣旨が記されています。しかも、ミードの見たサモア人の「性倫理観」について、「サモア人たちは、罪というものを自覚していないだけでなく、性交を『すぐれた娯楽』と見なし、『すばらしい技巧』をあみ出しており、彼女が研究してきた中で最も『性に対して陽気で気楽な態度』を持つ人々であった。サモアの社会では、『性は異性愛も同性愛も許され、技巧上の付加などのあらゆる種類のバリエーションを持った遊戯である、という一般的考え方の下で、非常に円滑して機能している』と報告されている」(フリーマン『マーガレット・ミードとサモア』)というのです。
ところが、フリーマンの同書では、ミードは重要な事実を歪曲して伝えている、と極めて重大な点を指摘をしています。それはサモアにおける宗教(キリスト教)の占める役割の大きさです。すなわち、ミードは知ってか知らずしてか、キリスト教的倫理・道徳の観念がサモアに存在し、少なからぬ影響を与えているにもかかわらず、その事実を、極度に矮小化して述べているのです。
ミードの記述と全く乖離した社会的実態
その部分を、フリーマンの著書から、ミードの驚くべき反宗教的態度について引用してみます。
◇
一九二五年末、ミードがサモア調査を始めた頃までには、すでにマヌアの人々は一八四〇年代に始まったキリスト教への改宗を終えており、幾世代にもわたってプロテスタント系ロンドン伝道協会の厳格な儀式を固守してきたことを誇りとしていた。だが彼女は、『サモアの思春期』の本文において、「ソフトで素朴な賛美歌の歌声」と「簡素で優雅な夕べの祈り」への心をかき立てるほのめかし以上に、マヌア人の日常生活におけるキリスト教会の根本的意義に関して実質的に何も言及していない。それどころか、一九二〇年代半ばのサモアにおけるキリスト教の位置は、付録の中のたった一段落に追いやられているのである。また未開地サモアにおいては、宗教は「微々たる役割しか果たして」来なかったというのが彼女の見解であった。超自然的存在との接触はすべて「偶発的で些細なこととされ、また制度化されてもおらず」、社会が宗教に与えた特権は微々たるものでしかなかった。神々は、「その聖性を首長たちに委譲して、自分たちのことにかまけていると考えられており」、人々が規則におとなしく従い続ける限り、人間界を慈悲深く治めるものとされたのである。
さらに、ミードが一九二五年から二六年にかけて研究したサモア人たちは、ほとんど百年の間キリスト教徒であったにも拘らず、彼女によれば、「自分たちの生活や文化をより快適かつ柔軟にするものとして」西洋文化を部分的に取り入れただけであり、そこには「原罪の教義はなかった」。実際、宣教師はサモア人に、いかなる「罪の自覚」を植えつけることはできなかったし、特に「多くの現地人の牧師がキリスト教教義の特異な解釈を行なう」ので、「性行為と罪の意識が個人の中で分かちがたく結びつけられる西洋プロテスタンティズムの厳格さ」をサモアで確立することは不可能であった。さらに、キリスト教会は教会員の資格として純潔を求めたのだが、ミードによれば、現実には誰一人として結婚するまで教会員になるものはいなかった。というのは、教会側は青少年に断念を強制して、若い未婚の教会員を集める努力をほとんどしなかったからである。「結婚前の違反行為は、教会当局によってしぶしぶ認められ」、若者たちは宗教的な葛藤によるストレスから解放されていたのである。彼女によれば、いかなる強い宗教的関心も、サモア社会の微妙なバランスを乱さないために、社会の外へと追いやられていたのである。そういうわけでマヌアの人々は、プロテスタントのキリスト教を受け入れたにも拘らず、それをサモア社会の「入念に作られ大事にされている」伝統様式の中へ、「単なる楽しみと満足を与える社会的な形式として」取り入れることができるように、「厳格な教義のいくつかを穏やかなものに作り変えた」のであった。
◇
以上は、ミードの記述に沿ってフリーマンがまとめたサモアの宗教と性道徳になりますが、ミードの記述は実情と全くかけ離れ、キリスト教道徳が根づき、婚前交渉は容認されない厳格な社会であることを検証しているのです。
しかしながら、ミードがサモアのキリスト教的な宗教観念を排除したところで、ではサモアの土着の宗教から、ミードの記したサモアの習俗、サモアの若者の行動様式が得られるのかと言えば、それは全く事実に反する、とD・フリーマンは断言しています。
すなわち、サモア社会では思春期・結婚適齢期の若い女性の「処女性と純潔」が、むしろ西欧キリスト教社会以上に強調され徹底しているというわけです。
このように見ると、「非文明社会=未開社会≒原始共産社会」と単純に見たエンゲルスの『家族・私有財産・国家の起源』(及びルイス・ヘンリー・モーガンの『古代社会』)に見られるような、「原始乱婚社会」の雛型というものを、ミードはサモア文化に見た、というよりは完全に決めつけていたと言えるでしょう。
もっとも、18世紀フランス初の世界周航者ブーゲンヴィルによる南洋タヒチに関する記述では、エンゲルスやモーガンの記述を彷彿とさせ、「文明社会が失った楽園」のようなノスタルジー(郷愁)に浮かれたように思われます。フリーマンはブーゲンヴィルの記述は誤りとはしていませんが、明らかに同じような「幻想」を抱いてミードがサモアを訪れたことは間違いない、としています。
![]()
人類学研究王道とかけ離れたミード
ところが実際のサモア社会では、性が極めて厳格に、そして神聖なものとして扱われ、それを乱す人間は容赦ない社会的制裁を受ける、という事実がすっぽりと抜け落ちているのです。
しかしながら、フリーマンはミードが恣意的あるいは確信的に、サモアの若者の聞き取り調査(フィールドワーク)を行っていたのではない、とかばう姿勢すら見せています。
とはいうものの、フリーマンは、ミードがもしカール・ポパーの唱えるような「科学の反証可能性」について認識し、それを自戒していたならば、そしてたかだか十週間ほど学んだにすぎないサモアの現地語でフィールドワークを強行しようとすることがなかったら、このような偏見と誤りに満ちた『サモアの思春期』という「事故」は起こらなかった、と分析しています。
このことは逆に「(人文)科学としての文化人類学」そのものに対する疑念を招かざるを得ないということになります。だからこそ、フリーマンはカール・ポパーの科学哲学の方法を援用しているのです。
フリーマンは、レオ・フォーチュンの『ドブ族の魔術師』に寄せたブロニスラフ・マリノフスキーの序文で、マリノフスキーは、フォーチュンが「現地人と生活を共にすることを決断し」、宣教師館も政府官舎も「断固として避けた」ことに、大いに満足を表明しているとし、「価値観や行動を理解しようとしている当の相手と一緒に暮らすことから、民族学者がどんなに大きな恩恵を得るかは、疑問の余地もない」と「研究の王道」を述べ、ミードのフィールドワークの手法が、こうした「王道」とはあまりにもかけ離れているかを強調するのです。
(「思想新聞」2025年2月1日号より)