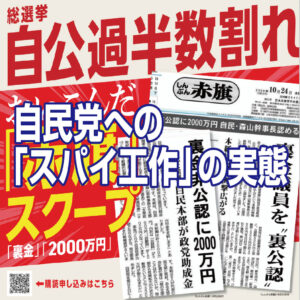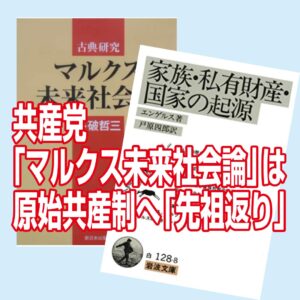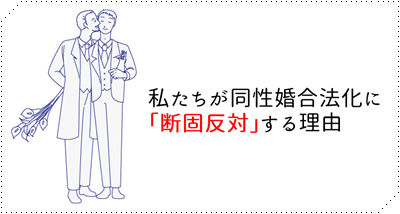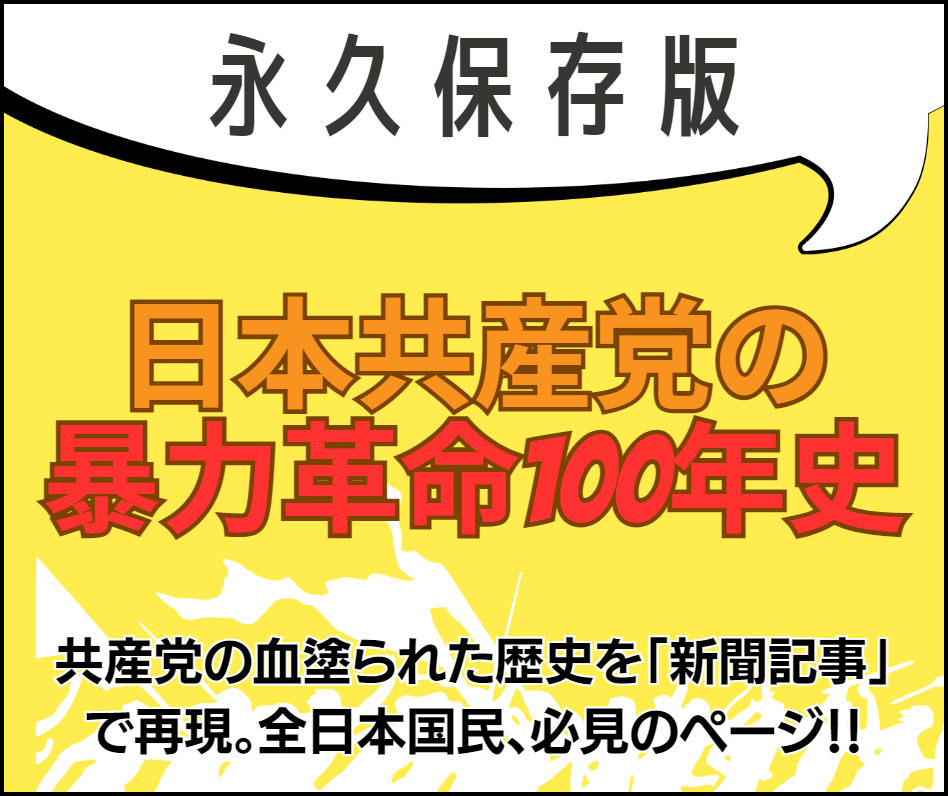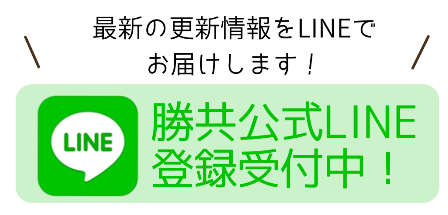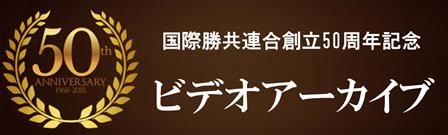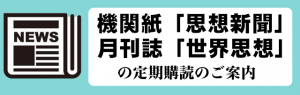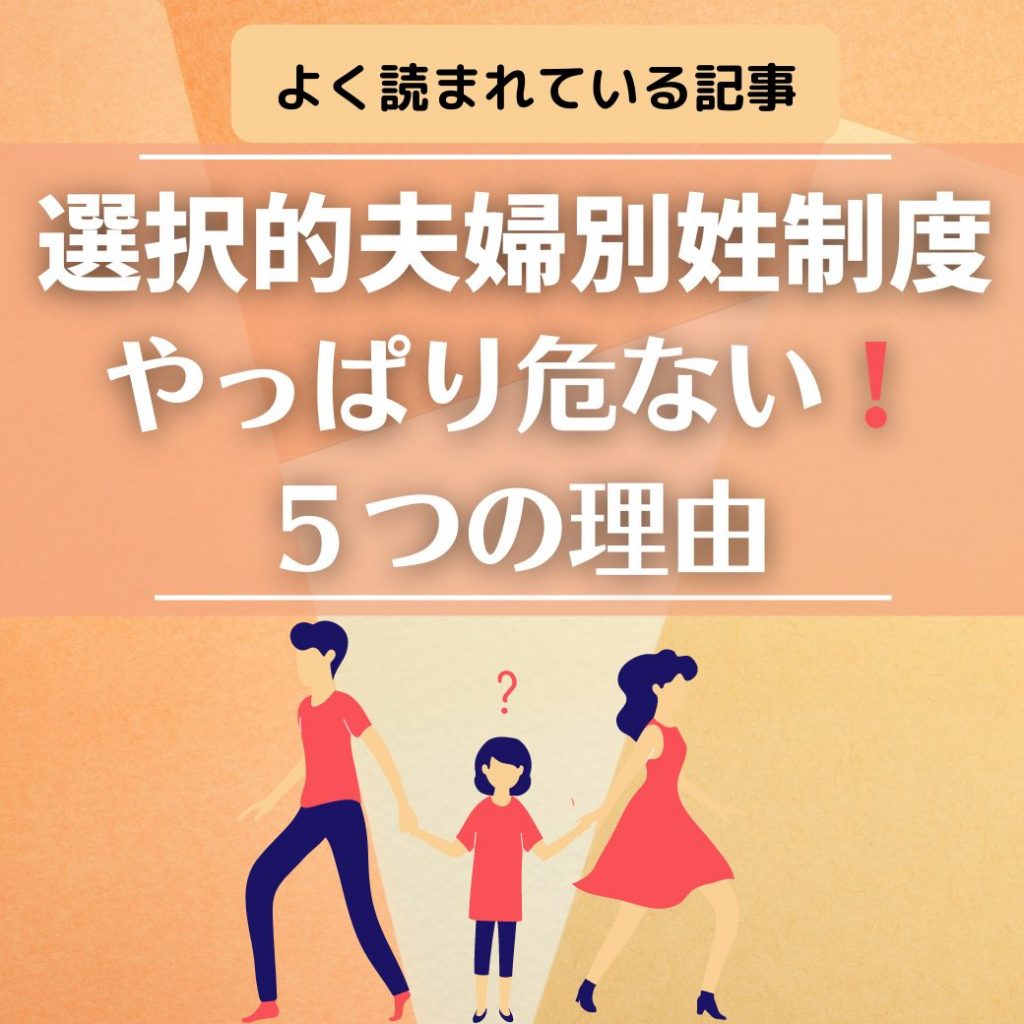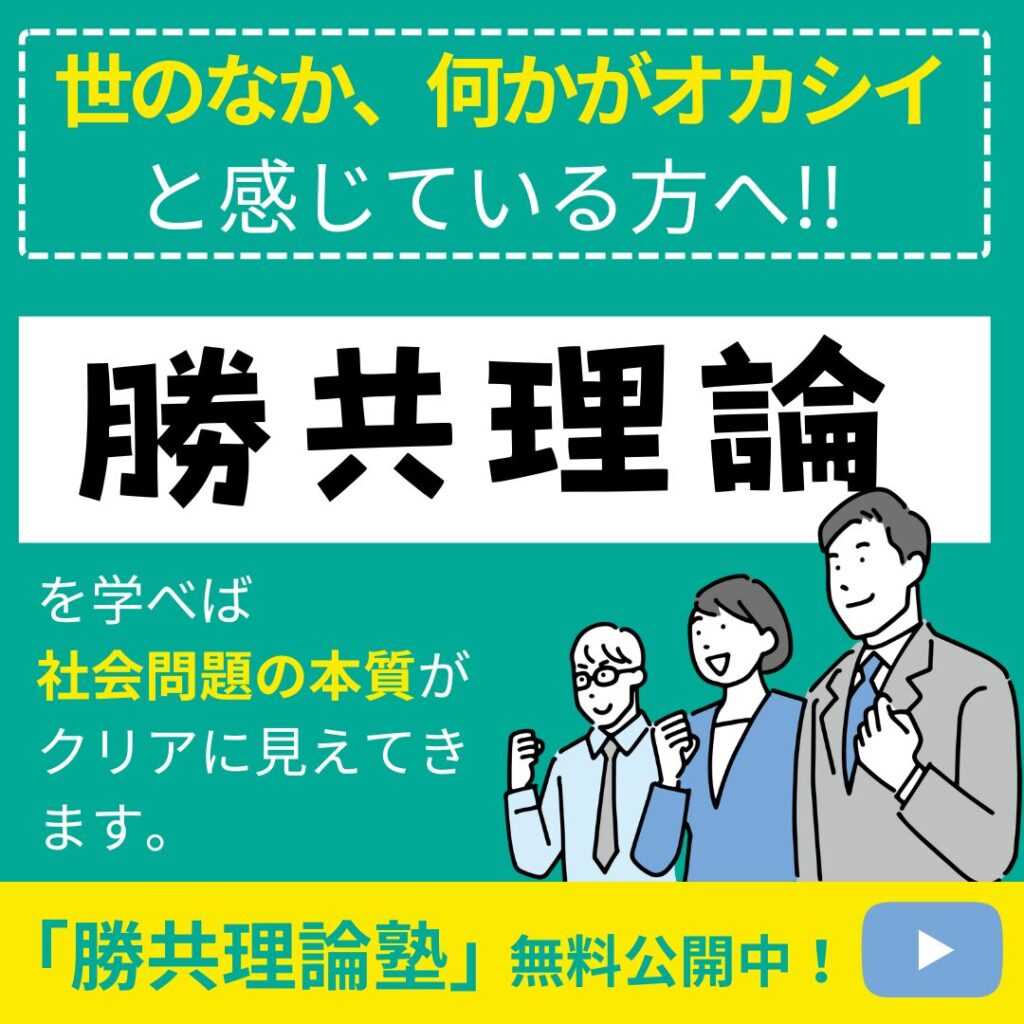世界人を体現した「現代の三蔵法師」
![]()
仏教について知識のある人なら、「ダイセツ」の名を知らぬ者はないほど、世界で最も著名な仏教学者の一人。だが、鈴木大拙(貞太郎)という人間の真髄は、学者としてよりも、それを超え、禅に依って「世界人」として生きたスケールの大きな人格にある。
1959年、晩年の大拙は、ユニークな神学を説き鮮烈な生涯を駆け抜けた、ユダヤ系フランス人の女流思想家シモーヌ・ヴェイユの著書を繙き、数十年も前に書いた自著が引用されていることに驚く。工場での劣悪な労働環境の中でヴェイユが直観した「労働者にとって必要なのはパンよりも詩情である」という断片に、自らの説く「妙」の世界があることを発見した。大拙にとって、この「日常に詩を見ること」こそ宗教にほかならず、そこには洋の東西もありえなかった。
現在は石川近代文学館となっている旧制四高跡(金沢市内)。大拙や西田幾多郎らがここで学んだ
加賀藩家老の本多家に仕える侍医の家系に5人兄弟の末子として生まれた貞太郎は、小学1年にして父を亡くし、翌年には兄を失い、生活に困窮し学校を辞した。
しかし、仏教の信仰篤い母に励まされ、独学で旧制第四高等中学校に入学。英語と文章力に非凡な才能を示した。その母も、貞太郎20歳にして急逝、四高も中退せざるを得ず、小学校の英語教師などを務めた。
不幸のどん底で、貞太郎の心の支えとなったのが、四高時代の恩師、北条時敬が熱っぽく語った鎌倉円覚寺での参禅修行だった。母の死後、東京に遊学しながら円覚寺に赴き、北条が教えを受けた今北洪川老師、続いて同寺を引き継いだ釈宗演について修行の日々を送った。この間、東京帝大文科大学哲学科選科を修了し、「大拙」という号が師の宗演から与えられている。
語学に長けた大拙が世界へと飛翔するのは1893年、宗演がシカゴでの万国宗教会議に出席した際、師の講演する原稿の英訳を任されて以来のこと。師の薦めで1897年に渡米。イリノイ州オープン・コート社に入り、道教など東洋学関係の出版に携わり、一躍学界にその名が知れ渡ることになる。
1909年帰国し、東大、学習院大などで教鞭を執り、21年からは大谷大教授を務めた。その間米国人女性ビアトリスと結婚。39年夫人の没後鎌倉に移り、松ヶ岡文庫を建て、96年の生涯を閉じるまで、大拙は終生「現役」として精力的な執筆・講演活動を行った。
大拙の残した業績は、欧米に禅仏教思想をわかりやすく広めたということにとどまらない。彼は、神秘思想家スウェーデンボルグの邦訳を手掛けた草分けでもあり、東西の宗教の違いを越えて、霊的世界への関心を示した。「日本人と霊性」をテーマとした『日本的霊性』は、「日本崩潰の重大原因は日本的霊性自覚の欠如」とした、いわば終戦間近の日本で書かれた恐るべき警世の書であり、今日の日本社会にも十分通じる内容を持っている。
四高時代の学友、藤岡作太郎・西田幾多郎と併せ「加賀の三太郎」と称される鈴木大拙。その没後「現代の玄奘三蔵」と時の円覚寺管長・朝比奈宗源が呼んだのは、言い得て妙である。