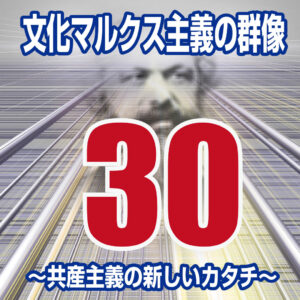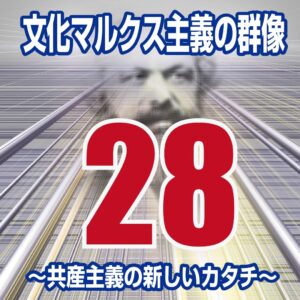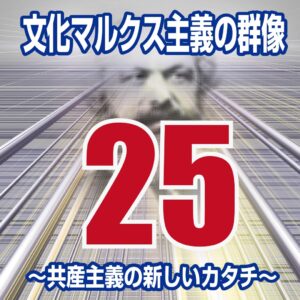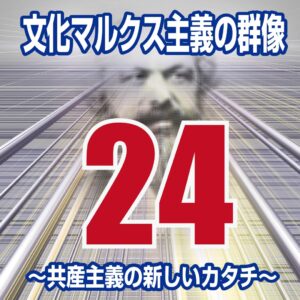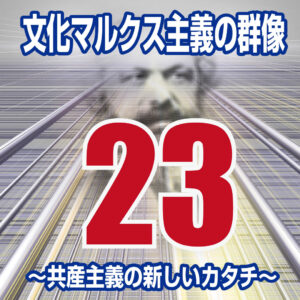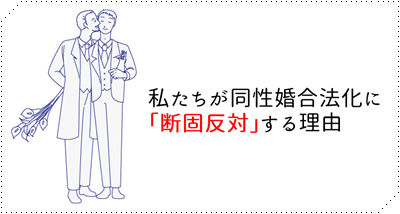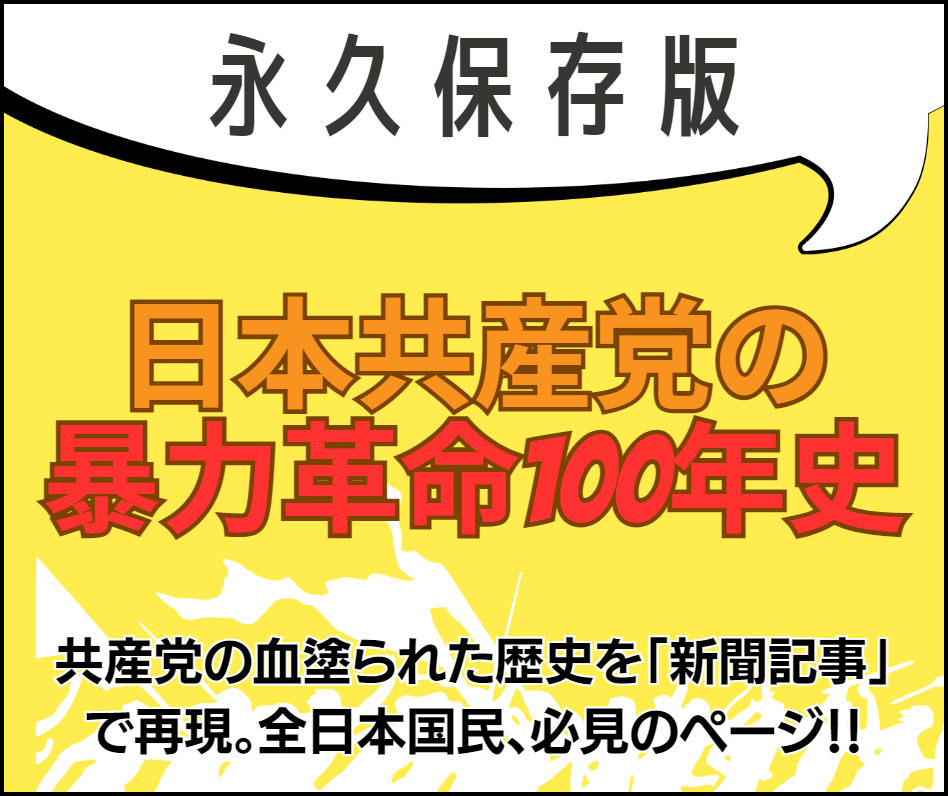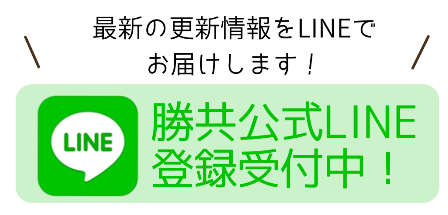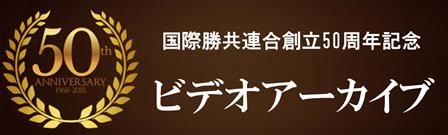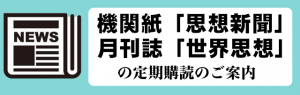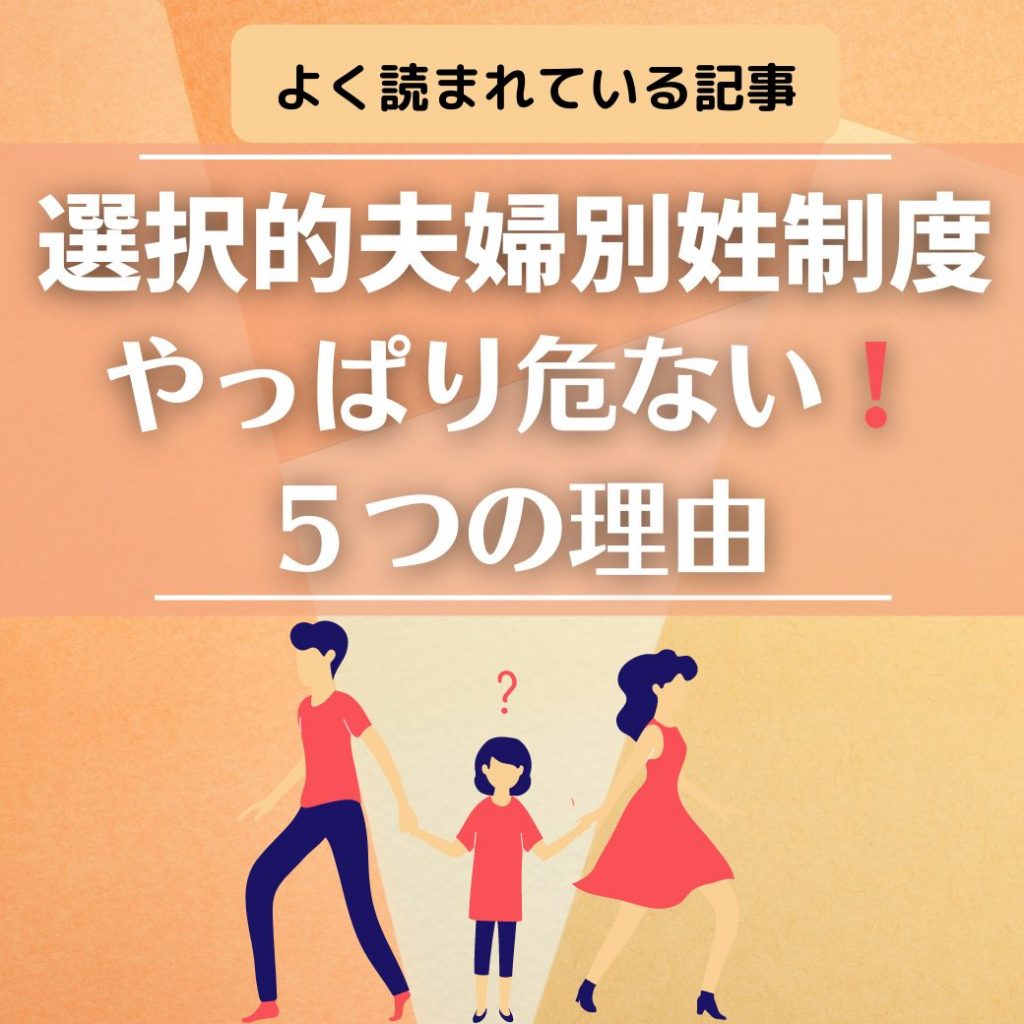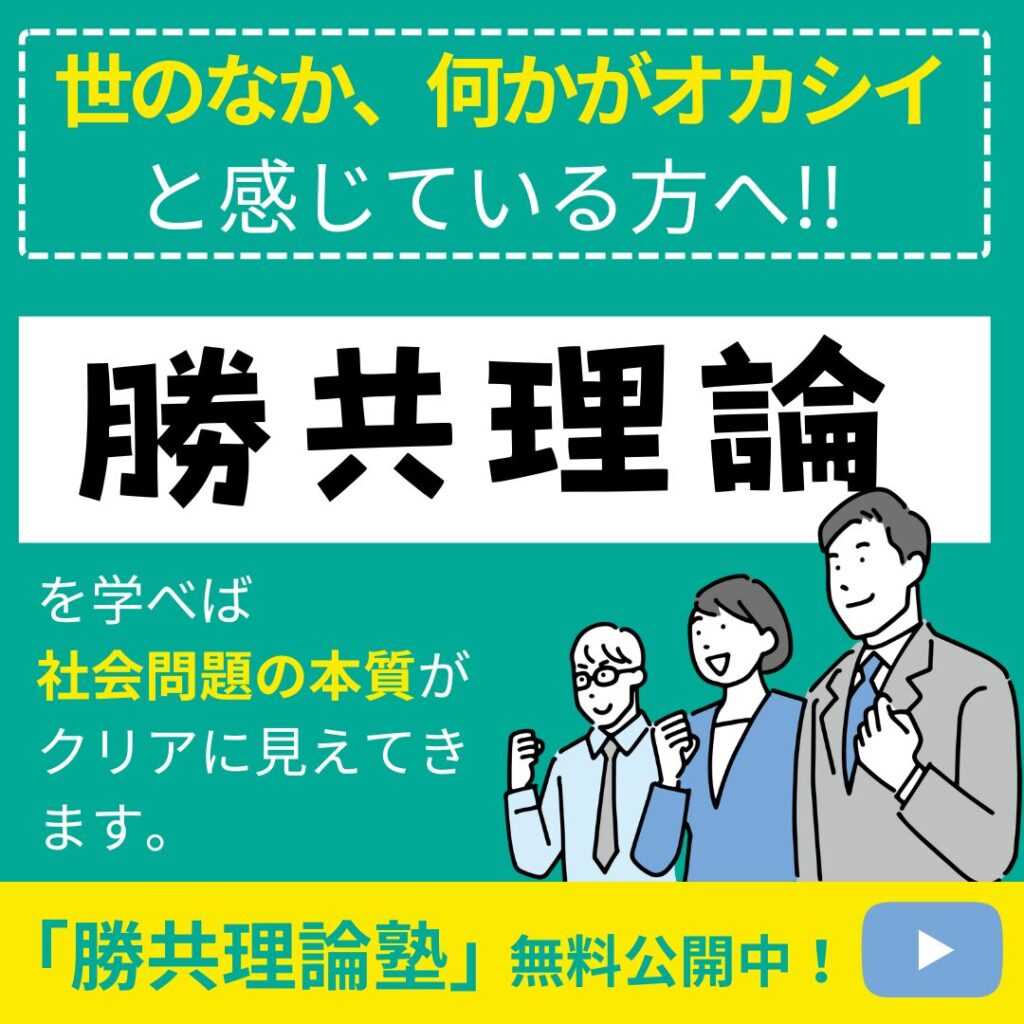霊的世界探る思想vs文化共産主義
唯物論と対峙した科学と哲学
イマヌエル・スウェーデンボルグ
フランクフルト学派の『啓蒙の弁証法』で評価したのが、キリスト教道徳を破壊するサド侯爵の「獣性」の価値観であり、ダーウィンとヘッケルの行き着いた、人間精神も動物から盲目的に進化したという価値観は、「反宗教的」「反道徳的」価値観として共通する部分があると言えます。
そうした価値観と一線を画すのが、ウォレスらの人間の肉体とは別なところに、人間精神の深遠さや神秘性、霊魂不滅性があるのではないかと考え、科学者やジェームズなどの哲学者が目に見えない「人間の魂」「心霊主義」に実証的に迫ろうとした点について、前回触れました。
ダーウィンの進化論や科学では未解明のものについて言及することは、学者として大変勇気のいる決断でしたが、それを回避せず正面から取り組もうとしたのが、ウォレスやジェームズだったと言えます。
このような「科学と宗教の対決」はこの19世紀後半だけのことではありません。例えば鉱山学などで17〜18世紀の一流の科学者と見なされていたのが、スウェーデンのイマヌエル・スウェーデンボルグです。彼はキリスト教神秘主義の巨頭と目され、様々な予知能力で知られ、いわゆる彼岸、つまり霊的世界に行き来して自分の死の期日を正確に記録していた霊能者でした。前回の心霊主義に関し降霊術が社会的に流行したことに言及しましたが、19世紀のこの「流行」では「インチキ」もあったとデボラ・ブラム著『幽霊を捕まえようとした科学者たち』では述べています。
しかし、前回も若干ふれましたが「宗教は集団ヒステリー」と断言したフロイトとは袂を分かった弟子にあたるカール・グスタフ・ユングも、ジェームズやウォレスと同様に、「霊的能力」「超自然的力」を肯定する学者でした。
母方の家系が霊能力を持ったユング
![]()
カール・グスタフ・ユングは、祖父のカールがバーゼル大学医学部教授で後に総長まで務め、父のパウルも旧約聖書のアラビア語訳の研究で博士の学位を得たアカデミックな家系に生まれました。しかしパウルは家庭の事情から研究職を諦め、牧師の道に進み、牧師の娘と結婚し、ユングが生まれました。精神的に病弱だった母エミーリエの代わりに父に育てられたユングは、家庭に母の不在とその代わりを務める父という構図で、夫婦仲も悪く、「頼れる父」がいないことを嘆くようになります。
牧師だった父のパウルは、好奇心に満ちた少年ユングから「神はどんな存在か」「どのような神体験をしたか」と聞かれ、ユングにとり「誰もが知っている、ひからびた公式的な神学上の答え」しかしなかったそうです。内的体験を期待したユングは何度も失望し、神学と教会が「神との直接的な関係」を築くことを塞いだと感じ、父に対して「信仰への懐疑」を感じ取ることになります。
これでは、マルクスのように、いかにも無神論に傾きそうですが、ユング自身がそうならなかったのは、エミーリエもその母(つまり祖母)アウグステもいわゆる霊能者で、交霊会を催したりしていたためのようです。実はユングの妹ゲルトルードも霊能力があったようで、身近に霊的世界にふれていたこともあって、ユング自身も心霊現象や超心理現象に強い関心を抱いていたようです。
この霊的世界、精神世界について西欧で探求してきたのがキリスト教的神秘主義の一つである「神智学」と言われる分野です。カントからフィヒテ・シェリング・へーゲルというドイツ観念論の哲学では、ドイツ神秘主義とも言われる神智学(ヤーコプ・ベーメ、マイスター・エックハルト、ゾイゼ、タウラーら)についてかなり肯定的な態度を取り、絶対者・最高存在としての神について語ろうとしました。
カントは、現代では総じて、宗教的独断から哲学を分離した理性批判の哲学者として評価されますが、ユングはむしろ「霊魂不死」の擁護者カントとして、スウェーデンボルグとの関わりから捉えました(林道義『ユング思想の真髄』参照)。
ユングはアンセルムスの「神の存在論的証明」へのカントの厳しい批判に同意しつつも、カントが霊界や超自然的なものを無闇に否定しなかった「科学的探求心」に敬意を表しているのです。カントも『視霊者の夢』で一目置いた稀代の霊能者スウェーデンボルグも実は、ベーメら神智学の系譜に連なっています。
カントとプラトンの「二つの世界」
カントは物理的に目に見え、人間の「五感」で認識できる世界を「現象界」、我々の五感では認識できない世界を「物自体の世界」すなわち「叡智界」と呼びこれを区別しました。これはある意味で「二元論」的世界観と言えます。
一方、古代ギリシアの哲人プラトンも、我々の住んでいる世界と、純粋な概念(イデア)の存在しているところの世界である「イデア界」とを区別しました。
仏教的な此岸と彼岸という考え方もいうなれば二元論的ですが、スウェーデンボルグの説く「現世」と「霊界」は、仏教的な「輪廻転生」とはいささか様子が異なります。スウェーデンボルグと同じく「霊媒」でありかつ「神智学」と並ぶ「人智学」(アントロポロゾフィー)を唱えたルドルフ・シュタイナーは、キリスト教的な世界観やメシアとしてのイエスの価値を認めつつ輪廻転生をも説き、それを「霊的進化」システムに集大成し、それは少なからぬ新興宗教にも影響を与えました。
プラトンは『国家』において、イデア界と物質世界を、「洞窟の比喩」を用いて説明しています。
プラトンによれば、洞窟で深い奥底を見るのに、そのものを直接見る場所へいけないとすると、明かりを照らした時に洞窟に映る影しか見えないわけです。
このように、我々が見たり聞いたり触ったりする実在の世界(物質界、現象界)に存在する「実在」「存在者」というものは、実はこの洞窟に映る影のようなものにすぎない、というわけです。イデア界にある存在するものが真理だというなら、私たちの現実世界にある実在というものは、「不完全な存在」だということになります。
プラトンのイデア論は、「数理性」を万物のアルケー(根源)としたピュタゴラスの「オルペウス教」の影響を多分に受けているためか、イデアについて説明する場合に「正三角形」を具体例として引き合いに出します。
すなわち、純粋な三角形のイデア(概念)というものは理解でき、頭には想起できるものの、実際に地面や黒板、ノートに書いたりすると、たちまちそこに存在するのは、辺が直線ではなく微妙に曲がって歪んだり、その太さも一定ではなく、精確な三角形を描けない「不完全」なものでしかないというわけです。
つまり「完全な三角形」のイデア(観念)とはイデア界にのみ存在するのだということになるわけです。
![]()
ポパーやウィトゲンシュタインも
近代ヨーロッパ哲学を決定づけたイマヌエル・カントは、プラトンのイデア論に近い考え方をしました。そのことによって「物自体」と呼んだところの「真の実在」とは、本当は私たちの手の届かないところにあるものだ、と考えました。
物自体の世界にあるものが真の実在であって、私たちの知覚の及ぶ世界、すなわち現象世界では、その「影のようなもの」、つまり存在の一部分を表象しているにすぎない、というわけです。数学的真理に重きを置く思想家や科学者というのは、実はプラトン的な「イデア界」、すなわち超自然的世界の実在を認めています。そもそも「形而上学」とは自然科学的な認識を超えたという意味でアリストテレスが著書を著しましたが、その師プラトンこそが形而上学について言及していたのです。形而上学的命題は、カントにおいて理論理性では不可知論として明確に区別されました。ただし、前回も述べたように、実践理性の要請によって認識できるとした、神・魂の不死・自由の問題のうち、死後の世界、霊魂の不滅についてスウェーデンボルグと接触しようとするなど、尋常ならざる関心を持ちました。何度も述べますが、カントは形而上学的命題を、「外側から確保しようとした」のです。それをカントは「信仰のための場所を空けた」と表現しました。
また逆に、プラトンのイデア論では共存していると見なされた数学的真理と倫理的な(形而上学的)命題について、これをはっきりと区別しようとしたのが、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』でした。こうした考え方を踏まえた上で、科学哲学者のカール・ポパーは「三つの世界論」を主張しました。これらはいわばプラトンのイデア論を敷衍するものと考えられます。キリスト教世界がプロティノスら新プラトン主義を受容したように、スウェーデンボルグのいう「霊界」を含む超自然的世界を認める世界観こそ、宗教的価値を認め「死ねば終わり」の唯物的世界観への有効な「反証」となりうるのです。
宗教的価値を敵視する文化共産主義
哲学の世界では「形而上学の解体」こそが「現代哲学の常識」のように映っています。しかし、形而上学に引導を渡したはずの唯物論に対して、哲学者はもとより、少なからぬ科学者が否定的な見解をもつプラトン主義的態度を取っているのです。
その一方、「利己的遺伝子」で有名なリチャード・ドーキンス博士(『神は妄想である』を著し「戦闘的唯物論」表明)のような確信的唯物論者は、人間精神に何らかの超自然的な「知的設計者」による作用の表れと見る「インテリジェント・デザイン(ID)理論」派に対し、執拗な攻撃を加えているのです。
(「思想新聞」2025年1月15日号より、加筆)