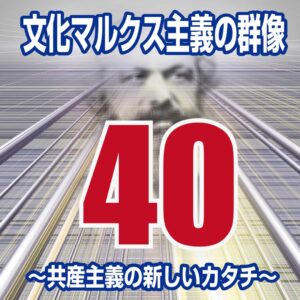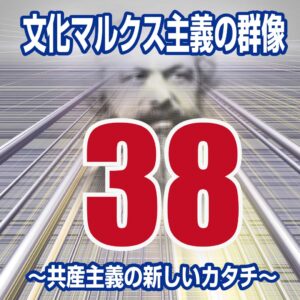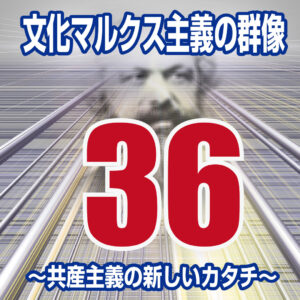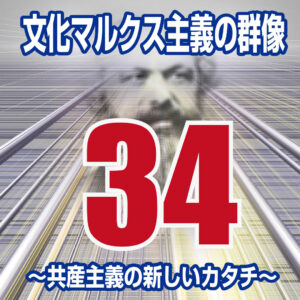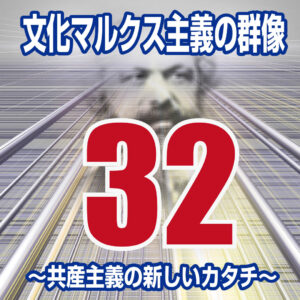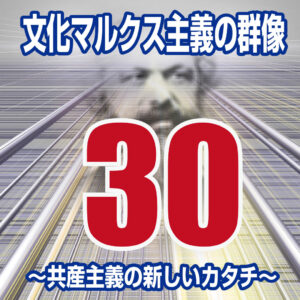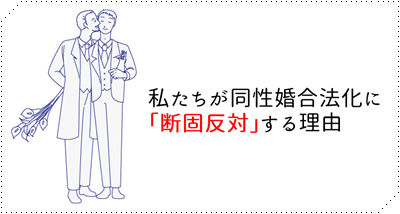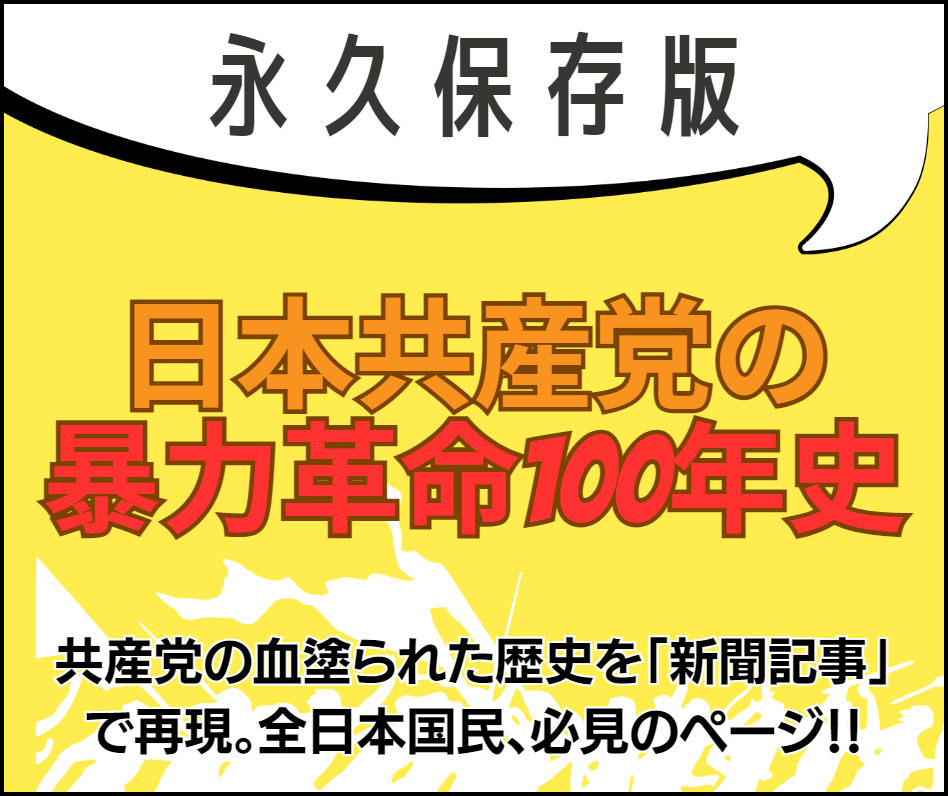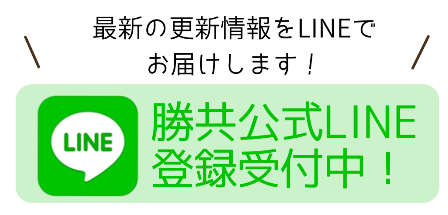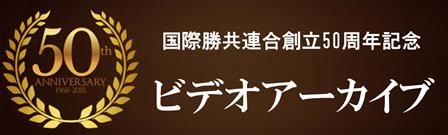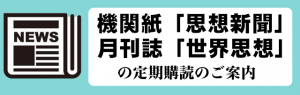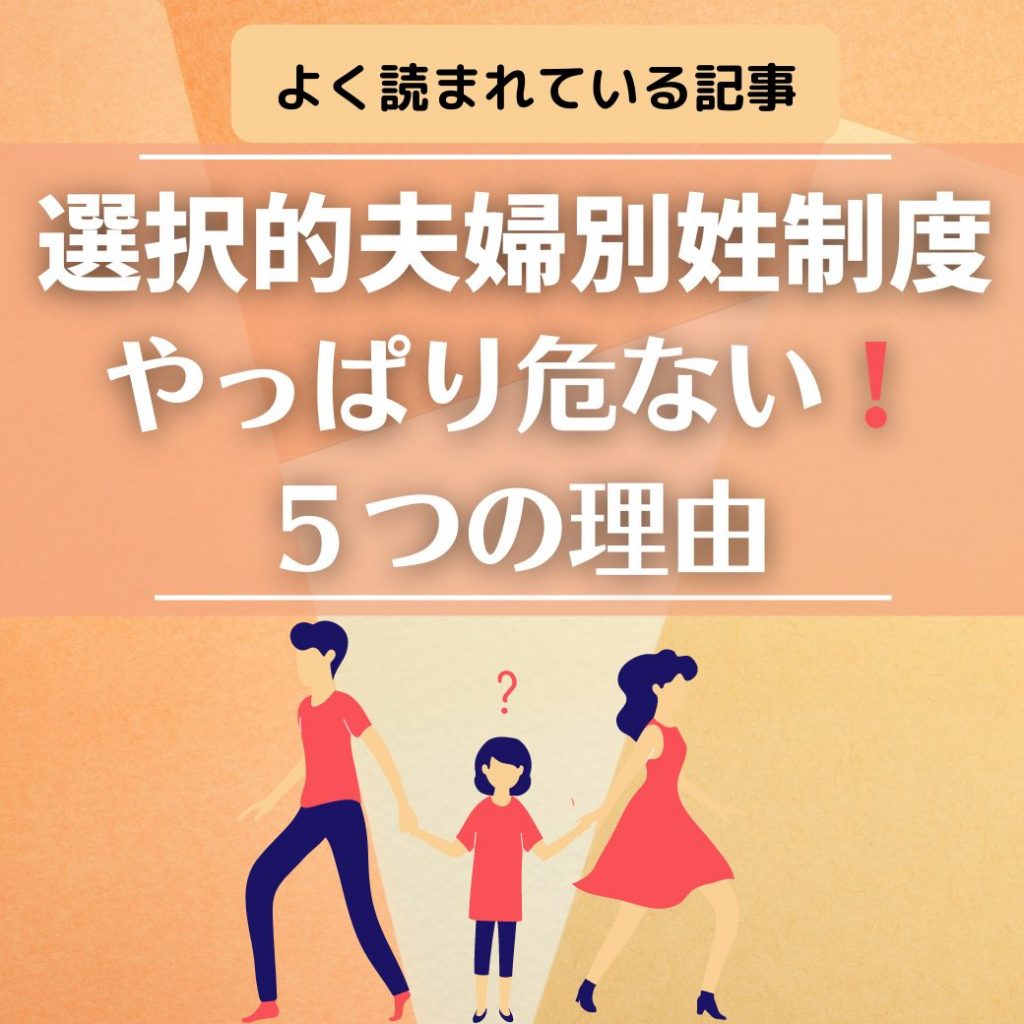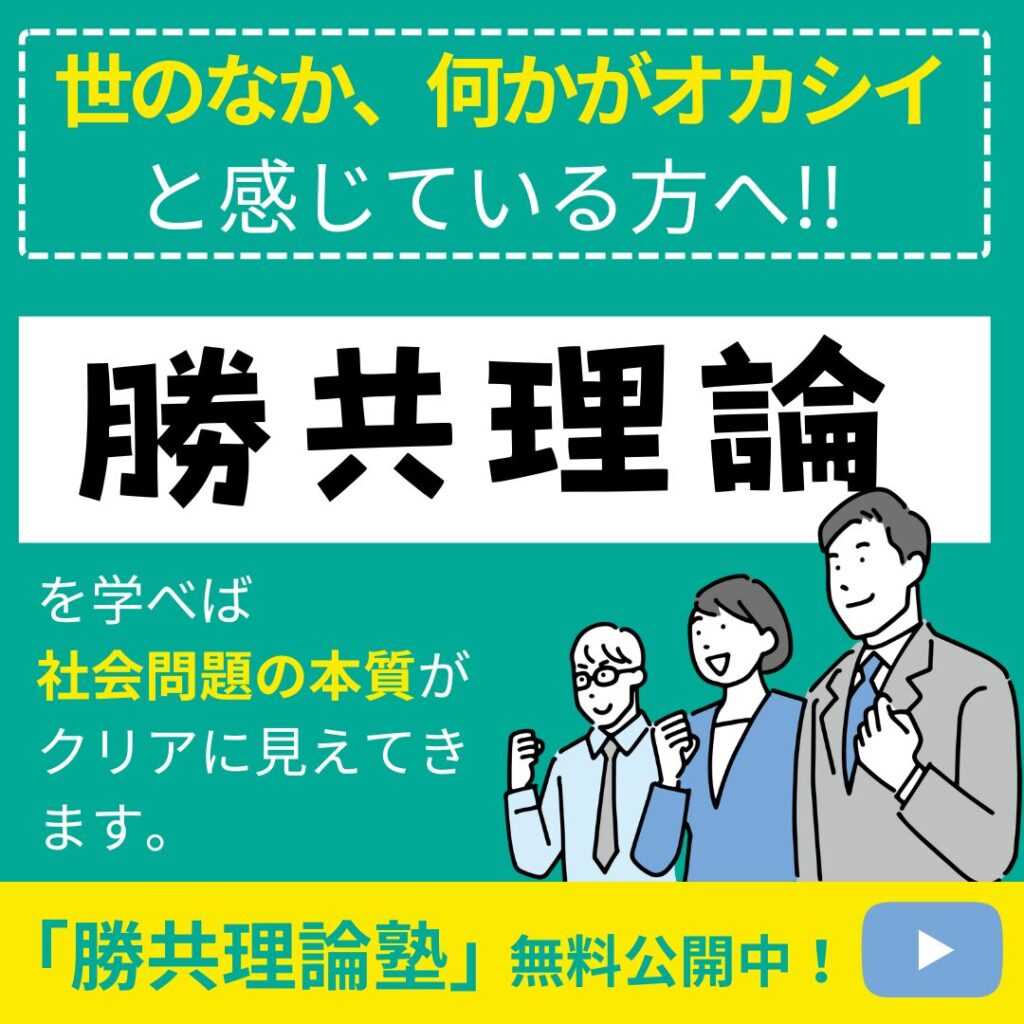性別役割逆転の「神話」築く
続 マーガレット・ミード
1951年頃のマーガレット・ミード
ミードがボアズ学派の新進文化人類学者、つまり「遺伝決定論(氏)」よりも「文化決定論(環境・育ち)」の重要性を代弁する実践的研究書として『サモアの思春期』がもてはやされたと先に述べました。
しかし、その研究姿勢には問題があり、文化人類学のフィールドワーク(聞き取り調査)としては実際の社会に入り込む「参与観察」がいわば「王道」であったのに、たまたま冗談のような証言をする少女へのインタビューを「採用」してしまったこと、後に豪州の研究者デレク・フリーマンが長期間かけて研究することでミードの記述が誤りであることを突き止め『マーガレット・ミードとサモア』にまとめました。
その際にフリーマンが援用したのが、科学哲学者カール・ポパーの唱えた「科学の反証可能性」です。これは「科学的知識は、科学上の命題や仮説は、それを反証しようとする種々の試みによって体系的に検証され、これらの反証の試みに持ちこたえられる限りにおいて、妥当な学説として受容される」ものが科学と言えるとする理論で、フリーマンが自著においてミードの報告が己れの理論とは誤っているデータを提示して、学問(科学)的に反証しようとするものでした。
そこで示したのがサモアの宗教・習俗でした。ところが、フリーマンはサモアでミードが聞き取りを行ったという女性に取材し、「自分と友達はふざけてミードに自由奔放な乱交の話を聞かせ彼女をだました」と「狂言」だったという証言を得たのです。つまり、ミードのサモアでのフィールドワークが、サモア社会に直接触れたというよりは、人種的偏見の入り交じった白人の「印象及び伝聞」による要素が色濃く出ているということになります。
すなわち、ミードは「自分の信念のために苦しんだり、特別の目的のために死を賭けて闘う者など誰もいない」と断言しましたが、実際のサモア人の男社会では「子供を含むあらゆる男性に求められる第一の美徳は、個人としての勇気、特にあらゆる種類の肉体的な戦闘における勇気」であり、サモア人は愛情に動かされるが、脅しには動じないのが、サモア人にとって誇り高き倫理規範と歴史であることを、様々な証言からフリーマンは浮かび上がらせたのです。
ロック《白紙説》援用したボアズ派
![]()
英国の科学ジャーナリスト、マット・リドレーの『徳の起源 他人を思いやる遺伝子』(翔泳社)によれば、ミードの師ボアズは「人間の行動は、自然と教育の両方の産物であると考える代わりに、彼は対極に位置する文化決定論に走った。文化以外の何かが行動に影響を与えるという考え方を否定したのである。自説を証明するために、彼は人間性の全能性(分離された体細胞から全組織を再生する能力)、つまりジョン・ロックの《白紙説》を証明する必要があった。正しい文化を与えられれば、人間は嫉妬や愛情、結婚や階層のない社会を作り上げることができる」と説いたといい、「限りなく人間性を鍛え上げることが可能であり、ユートピアも存在しうるのである。そうでないと信じる人は救いようのない運命論者」という信念でした。この信念をリドレーは「逆自然主義的誤信」と名づけ、ミードもこれを持っていたというのです。
ここでいう「ロックの《白紙説》」とは、17世紀英国の政治哲学者ジョン・ロックが「人間の心はタブラ・ラサ(白紙)である」と説いたことで知られます。明らかに「氏(生まれ)より育ち(教育・環境)だ」とする考え方です。
これは確かに、遺伝など生物学的要因が決定する「ダーウィン進化論」や「優生学」に対する一つの「反証」を提示でき、実際に学問的にもそうした批判が行われてきました。
しかし、だからといってこの《ロックの白紙説》ですべてを説明することはできません。むしろそれがまさにジェンダー論のイデオロギーとなってきた、あるいは利用されてきたことに気づかされるのです。
例えば今日、人口に膾炙しているLGBT(性的少数者)の問題や、あるいは「ジェンダー平等」と言われている問題です。一般的には男性と女性という「生物学的性差」(セックス)と「男らしさ・女らしさ」という「社会的性差」(ジェンダー)があると言われてきました。このうち後者のジェンダーは、「後天的に環境によって作られるもの」であるから、できる限りこれを決めつけるような文化・社会は「悪」である、そのためそれを「逆手に捉えることが称賛される」という風潮が「政治的校正」(ポリティカル・コレクトネス)として形成されるようになりました。
マネー医師の「実験」の犠牲となった少年
このことを実際に行った極致が、ジョン・マネーという医師による「実験」で、生まれた時に男児を逆に女児として育てようとし失敗した記録が『ブレンダと呼ばれた少年』という書籍として残されています。
それは今日のまさに「トランスジェンダー」のはしりと言えるものでした。この「実験」が罪深いのは、本人の「意思」とは無関係に、性差を無理やり逆転させようとした、いわば完全なる「児童虐待」と言えるおぞましいものでした。
しかし今では、トランスジェンダー特例法は「差別」だといって性別適合手術など不要で、生物学的性とは関係なく「性自認」によって自分がなりたいと思う性を宣言することが認められてしまうという社会になりつつあります。
これはまさに、ミードらのイデオロギーの実現した社会といえ、先天的なものとは関係なく、後天的に何にでもなれるという今日の風潮を生んでいます。
![]()
チャンブリ族の特異性を「発見」
さて、ミードの不幸な「研究成果」は、恐るべきことに、サモアだけにとどまりませんでした。その極めて残念な研究とは、今日のジェンダー論者が有力な「エビデンス(証拠)」として引用する、いわゆる「チャンブリ族の研究」です。
「チャンブリ(Chambri)族」とは、インドネシアの東に位置するパプア・ニューギニアのセピック川に近い湖に浮かぶ島に住む部族です。1935年、ミードは新しい論文『三つの未開社会における性と気質』(以下『性と気質』)の中で、「男女の性別役割が逆転した社会」の実例としてチャンブリ族を規定しました。
これは後に、「性別役割というものがそれぞれの性別に固定的なものだとの主張を否定する事例」として、フェミニストやジェンダーフリー論者が好んで取り上げるようになりました。
1931〜33年にかけニューギニアでモンドグモール族、アラベシュ族、チャンブリ族という、三つの未開部族を調査した内容を、ミードは『性と気質』に書きました。
このうち、セピック河畔で半農半猟で生計を立て、男女ともに攻撃的積極的な性格で、子供の養育態度は、男女とも子供に無関心なモングドモール族。山岳地域に住み焼畑農業で生活し、男女とも穏やかな性格で子供の養育に強い関心があるアラペシュ族。そして、チャンブリ湖内の小島に住むチャンブリ族は、女性が主に漁撈を営んで生計を立てるため、女性は支配的な性格で男性は依存的な性格、子の養育では女性は授乳以外での子供への接触が少ないとしています。つまり、「男らしさ/女らしさ、および性別による役割分担は文化によって大きく異なる」という「結論」を、ミードは三つの未開社会の事例から導き出した、と確信したのです。
ところが、ドナルド・E・ブラウンは『ヒューマン・ユニヴァーサルズ』(新曜社)の中で、「チャンブリの男性と女性」として、ミードの事実誤認を検証・指摘。このうちデボラ・ゲワーツの反証した試みの記述を挙げてみます。
◇
ゲワーツは、実際のチャンブリ族とミードの見た彼らを次のように再構成した。チャンブリの伝統的概念では、男性は攻撃的で、女性は服従的である。男性と女性の相互作用においては、彼らは普通はこの概念にしたがい、証拠の示す限りでは(一八五〇年頃までさかのぼれる)明らかにそうだった。確かに、チャンブリの女性は、一家の稼ぎ手ではあったが、女性は「生産をコントロールすることは一度もなかった。というのは、より重要な取引きの決定がなされる政治的な駆け引きの舞台に出ることはほとんどなかったからである」。チャンブリの社会では女性が生産的な役割を担っていたけれども、その労働の産物をコントロールするのは夫や父親であり、彼らはそれを自分の(男たちの)地位を強めるために用いていた。ゲワーツは、ミードがチャンブリ族を調査したときと状況が変わったと考えるだけの理由を見出すことができなかった。ミードは、自らの労働の収益を渡すかどうかは女性に選択権があるとはっきり述べているが、女性が自分の権利を主張してものを渡さなかった例や自分の好きなようにそれらを分配したという例を挙げているわけではない。ゲワーツは、チャンブリ族の女性には「自分の生産物を誰に、どのような時に与えるかを決める自由はなかった」と断言している。むしろ女性は、生活の中で様々な男たち──夫と父親──の対立する要求の圧力の下にあり、男たちは、妻や娘に暴力をふるうこともあった。チャンブリ族の女性が優位だとしても、それはチャンブリ族の男性に対してではなかった。女たちは男たちと敵対することもあったが、それは「政治的な意思決定に何ら直接の権利を持たない危険分子の挑戦」であった。
◇
また歴史性を顧慮しなかったミード
ミードは「われわれの文化の男性と女性の態度が完全に逆転しており、女性が優位であって、感情的ではなく、仕切る側であり、一方、男性のほうは責任を欠き、情緒的に不安定であった」、「チャンブリ族では社会の実験を握っているのは女性であり」、「女性の実際の優位は男性の構造的地位よりもはるかに現実のものであった」 と同論文で断定していますが、ブラウンは、ゲワーツの調査に依拠しながら、「チャンブリ族は近隣の部族との戦いに負けて長い間流浪の身となり、ほんの最近自分たちの島に戻ってきたばかり」という「時間的文脈」を、考慮に入れなかったと指摘しています。ここでまた出てきたのが「歴史的問題」です。それはミード自身が『性と気質』で記述しながらも、特殊な状況を顧慮せず、文化として一般化してしまったと分析しているのです。
(「思想新聞」2025年2月15日号より)