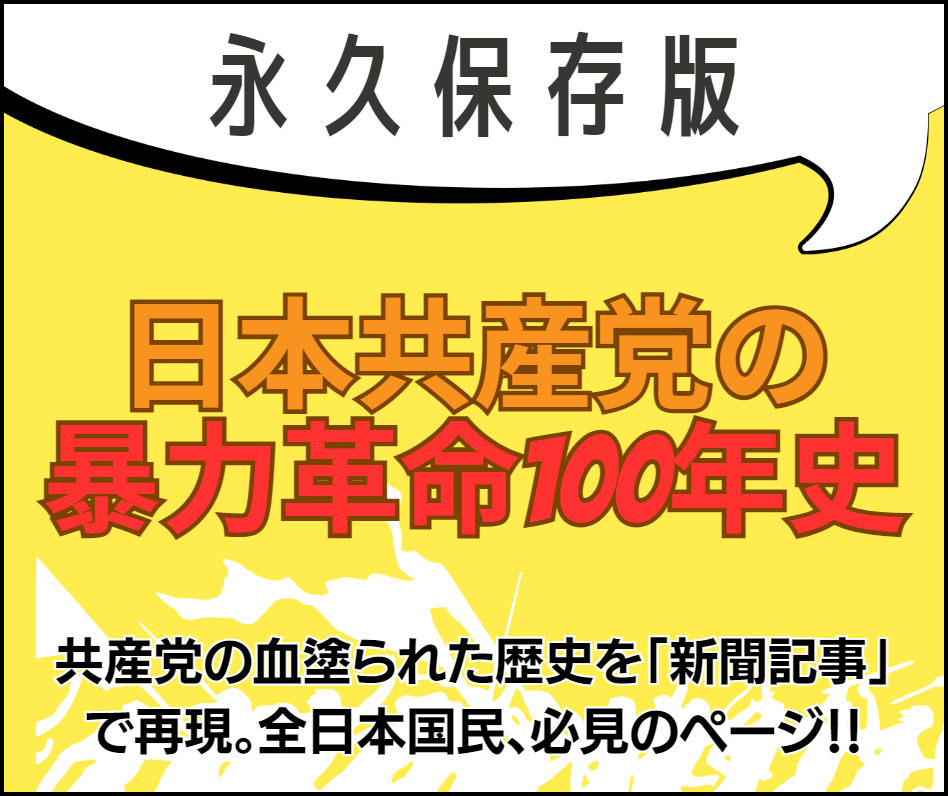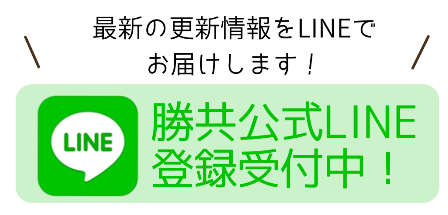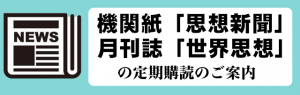「愛と性」切り離す「動物的還元主義」
ジークムント・フロイト
「文化共産主義」が「男女平等」どころか、「ジェンダーフリー」「過激性教育」など「文化破壊」の道をひた走る大きな要因が、ジークムント・フロイトの影響と言えるでしょう。
マルクスと結びついたフロイト思想
ジークムント・フロイト(1856〜1939)
フロイトは人間の「無意識」に目を向け「心の深層」に迫り、心理臨床において巨大な足跡を残しました。しかしフロイトの「精神分析学」は「エディプス・コンプレックス」論などにより、家族関係に「闘争」概念を刷り込んだのです。そればかりか、人間のあらゆる営みは「リビドー」(性的エネルギー)の顕れと見たフロイトの思想は、ヴィルヘルム・ライヒや、フランクフルト学派のヘルベルト・マルクーゼら「フロイト左派」によって「性解放」の思想へと奇怪に「変貌」を遂げることになります。
ベトナム戦争以降に米国の大学やインテリに蔓延した「価値相対主義」「フリーセックス」の風潮を鋭く告発したのが、シカゴ大学教授アラン・ブルームの『アメリカン・マインドの終焉』でした。ブルームは、フロイトとマルクスとの結びつきについて、次のように述べています。
「フロイトはマルクスのどこを探しても見あたらない興味深い事柄について語った。無意識の内的な動因である性本能(エロス)はマルクスには縁遠いものだったが、ひいては無意識に関する心理学全体が、マルクスにとっては完全に無縁だったのである。……フロイトは人間の本性と社会との永遠の矛盾について語ったが、このフロイトの主張には弁証法的運動を行わせることが可能なのであって、社会主義社会では神経症の原因となる抑圧の必要がなくなるであろう。かくしてフロイトは、マルクス主義者の軍隊に手際よく登録され、経済学の魅力には性本能(エロス)の魅力が添えられる」
さらに、マルクス主義以上に、世を惑わしミスリードしたのがフロイトだと見るドイツの科学ジャーナリスト、ロルフ・デーゲン氏は、「心理学のウソが危険なのは、時と共にそれが知らず知らずわれわれの自己認知の一部となってしまうからだ。『内へ向けたまなざし』も、外へ向けたまなざし=視覚と同じように錯覚を起こす。見た目には、地球は平らで太陽が地球の周りを回っているように見えるのと同じような錯覚を心も起こす。自分の行動の理由を考えるとき人は自分の心の中を真に覗いてはいない。実際には、外から他人を見るように自分自身を観察し、他人についての間に合わせのもっともらしい理論を作り上げる。…『肛門期への固着』や『フロイト的失言』が自分に当てはまると『認識』している人は、実は機械文明時代初期の古ぼけたメタファーを自分にかぶせているだけだということにまるで気づいていない。こうした意味で、フロイトはマルクスよりさらに大きく持続的な損害を引き起こした」(『フロイト先生のウソ』)と厳しく批判しているのです。
ダーウィニズムの影響で還元主義に
ショーペンハウアー
フロイトは、精神科・神経科医として出発しながら、マルクス同様にダーウィン進化論の影響を受けます。そしてダーウィニズムの機械的唯物的自然観の影響下にあったE・ブリュッケの生理学研究室に入り、ヤツメウナギやザリガニの神経細胞の比較からダーウィニズムを実証しようとする研究を行ったのです。そこから、当時神経病学の大家とされたパリのシャルコー教授の下でヒステリー研究に開眼、精神分析学への道を築くことになります。
英国の分析家A・ストー『フロイト』(講談社)によれば、フロイトは「人類全体に良いものはなく、ほとんどはクズ」と見なすほどの極端な人間嫌いでした。
フロイトは解剖学的研究からダーウィニズムの徒となり、「無意識世界におけるダーウィニズム」の樹立を企てました。つまり、「ダーウィンの描く人間像は《還元的》だった。というのも彼は、人間は、神の姿を写した特別な生物であるという考えを追い散らしただけでなく、極めて複雑な行動を単純な生物学的起源に還元する傾向があった。フロイトはそれと全く同じことをしようとしたのである」(同書)からです。
人間を「最悪の存在」としてペシミズムを説いたショーペンハウアーに倣い「人間はクズ」と見なしたフロイトはまさにダーウィン以上の唯物的還元主義者であったと言えるでしょう。しかもフロイトは「精神分析の開祖」として学者仲間に絶対的権力を振るい、自らの結論に対する反論を一切許さず、ブロイアーやフリース、アドラー、ユングといった同僚や弟子たちが次々に離反しました。フロイト自身はそうした訣別を「裏切り」「背信」と見なしました。ですからフロイトの理論を「ドグマ」(教義)とする一種の宗教である、と精神分析を見る考え方もあります。
死への本能から世界のニヒリズム化
わが国のフロイト研究の第一人者の故・小此木啓吾博士は、フロイト思想の本質を「①生物としてのヒトの無力さ②タナトゥス(死の本能)に対抗するエロス(生の本能)の営み」を挙げ、「死に対する生の営みとしてとらえる根源的認識こそ、フロイト思想のエッセンス」と指摘します(『フロイト思想のキーワード』講談社現代新書)。
実はこのタナトゥスを認めれば、大変なことになります。動植物の世界では、本能的に「自殺」「自滅」する個体はほとんどありません。「人間が自殺を考える唯一の動物」とする見方も一般的です。暴力や犯罪・戦争が、「タナトゥス」の現れだとする見方もあります。しかし、「本能」となれば、暴力の当事者、加害者にとっては正当化するための根拠になってしまいます。この思想では、無法状態としてのアナーキズム社会を招来させてしまいかねません。
生物学的に「死ねば全てが終わり」の認識から、自暴自棄的に「生=エロスを享受しよう」という「刹那的な人生観」を大量生産します。フロイトにとり「歯止め」「タガ」となっているのが宗教的道徳観念で、それを取り払えば、刹那的人生しか残りません。
これがフロイト思想の「科学的還元主義」と言われるゆえんであり、人間は様々な背景や人生観を持った存在ではなく、「生物学的な種」にすぎず、芸術や哲学における人間の高尚な営為も原始的本能の昇華物にすぎぬという価値認識は、恐るべきことに「世界のニヒリズム化」に寄与しているのです。
功罪相半ばするフロイトの思想
エディプスに謎掛けするスフィンクス(ドレ画
またフロイト思想に今日的意味で重要な業績があることも否定できません。
第一に、人間の無意識の領域を考える上で、「精神分析のキモ」たる「エディプス・コンプレックス」など、「親子関係」を重要視したこと。例えば犯罪心理分析や矯正施設の現場で、必ずと言っていいほど「社会環境」よりも「家庭環境」を重要視します。それまでは、家柄とか、階級や社会階層が問題となっても、個々の家庭環境にメスが入ることはありませんでした。
第二に「汎性欲論」。「汎性欲」とまでいかずとも、「愛と性」が、人生において最も重要なものと明らかにしたことです。これはカトリック聖職者に代表されるように、多くの宗教家にとってはまさに「タブーの領域」でした。これを扱ってきたのも、文学の領域でした。単に恋愛を綴ったものではなく、人間の究極的な欲望の象徴として描いた初めての作品は、恐らくゲーテの『ファウスト』でした。それを手に入れるためならば、悪魔に魂を売り渡してもかまわない、というファウスト博士の野望を描いたこの作品は、きわめて現代的なテーマであることがわかります。
とはいえ「愛と性が重要」と言いながら、フロイトはあくまで分析を主眼に置き、明確にその治療法・解決法を示しません。なぜなら、それは彼自身が破壊しようとした「宗教・道徳の領域」にほかならなかったからです。ここから逆に、フロイト以降、特に左派の弟子たちは性を愛と完全に切り離し、「性の解放」思想に変貌していくのです。
第三に、「夢」に関し「無意識の世界」を垣間見るカギとして重要視したことです。同じ心理療法でも、パブロフ、スキナー、ワトソンらの行動科学的アプローチからすればナンセンスなのが、「夢」という世界です。心情的に科学的唯物主義者だったフロイトは、この「夢」と霊的(精神)世界との結びつきを否定するも、ユングは逆にしっかり結びつけました。
このためユングは「オカルト主義者」と見なされやすいのですが、「臨死体験」の報告にもあるように、死後生や霊魂不滅、精神世界を認める人々にとって、夢はそうした「彼岸に通じる道」と解されます。
愛の規範性の尊重と性と生命の神秘
フロイトは晩年、ユダヤ教とモーセについて研究し、モーセの強烈な家父長的権威と、権威主義的だった自分の父親にオーバーラップさせました。ユダヤ教ラビ(祭司)の家系に生まれたフロイトでしたが、ユダヤ人が迫害される境遇に置かれたのはつまり、「モーセがユダヤ教をつくったから」とその責任をモーセ一人に帰してしまいます。
『旧約聖書』によれば、モーセは神からいわゆる「十戒」を授かります。この「盗むなかれ、姦淫するなかれ…」という「タブー」はキリスト教徒やユダヤ教徒でなくともよく知られています。「姦淫」「姦通」とは何でしょうか。「一切の性的接触・関係を絶て」ということを意味するのではありません。妻あるいは夫以外に性関係を持つことです。逆に言えば「まっとうな家庭を築け」という意味にほかなりません。
しかし、「性の解放」からすれば、むしろこのモーセの「十戒」に反抗し、「破戒」することに意義を見出します。ここに健全な「結婚」「家庭」という概念は、「死語」に追いやられ、今や「事実婚」「多様な家族」へと相対化されてしまうことになりました。
さて、洋の東西を問わず、結婚式というものが神の前で誓いを立てるセレモニーであり続けてきたように、宗教的観点と切り離せないものでした。また過ちを犯す存在だった人間を、良心や善の方向に導く杖として「規範」は働いてきました。
世の中に秩序があるように、「愛の世界」にも秩序があって初めて幸福な生活を享受できると考えるべきではないでしょうか。「性の解放」を批判・克服するには、宗教的基盤に根ざした「愛の規範」思想によるべきなのではないかと。
フロイト思想の超克を考える上で、渡辺久義・京大名誉教授が『意識の再編』で「性の神秘」を論じたように、生命がなぜ尊いのか——この答えは「性と生の神秘」を解さずしては絶対に出ないでしょう。
(「思想新聞」2024年7月15日号より)