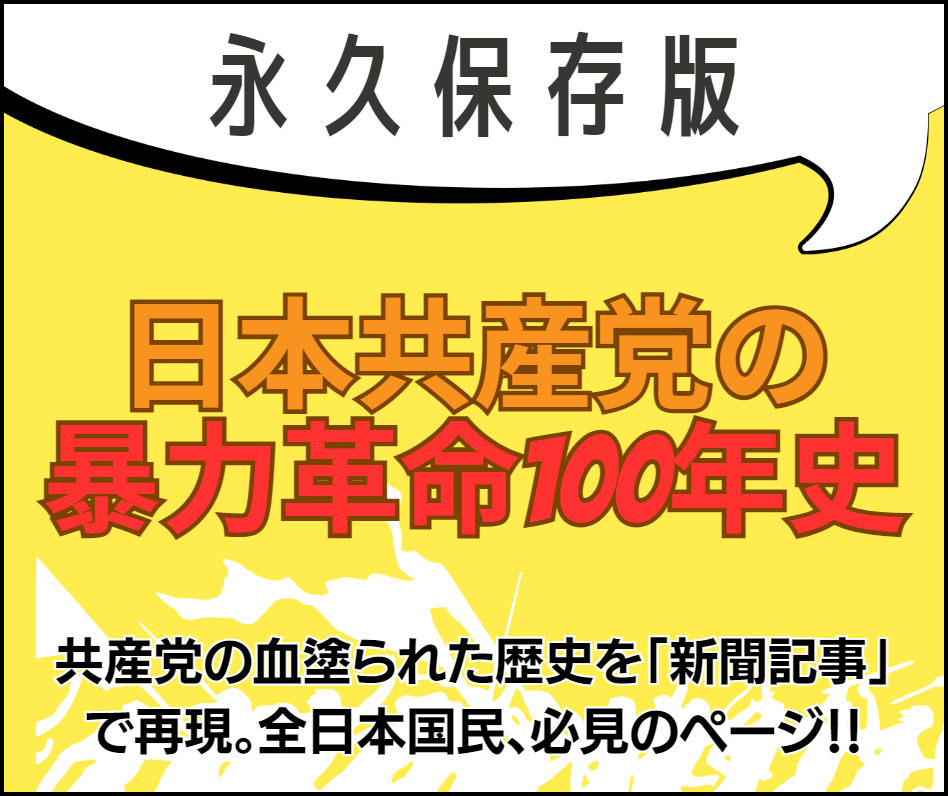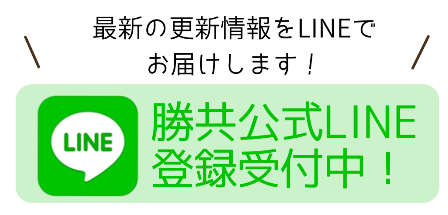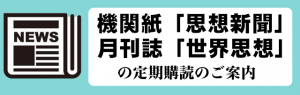「マルクスとフロイトの融合」企てる学際的唯物論
マックス・ホルクハイマー
マックス・ホルクハイマー(1895〜1973)
田中英道・東北大名誉教授は、GHQ(連合国軍総司令部)による戦後日本の占領政策で最も大きな影を落としたのが、「米戦略諜報局」(OSS)で、その中核となったものこそ、ドイツから亡命した「フランクフルト学派」の思想だと指摘します(『戦後日本を狂わせたOSS「日本計画」: 二段階革命理論と憲法』展転社)。そのフランクフルト学派のリーダー的人物こそ、後に米国で亡命生活3を送ったマックス・ホルクハイマーでした。
フランクフルトは、ユダヤ人に寛容で自由な気風を保ったドイツ屈指の商業都市。文豪ゲーテの生誕地で、フランクフルト大学は、正式名を「ゲーテ大学」と文豪の名を冠し1914年、民間資金で設立されました。この大学に附置された「社会研究所」こそ、フランクフルト学派の舞台でした。
織物製造業を営むユダヤ人実業家の家系に生まれたホルクハイマーは、同じユダヤ系の親友フリードリヒ・ポロックと共に、第1次大戦従軍後、設立間もないフランクフルト大学に入学。ホルクハイマーは助手時代、ポロックと「自由なマルクス主義の研究機関」の設立を提案しそれを財政的に支えたのが、世界的実業家の息子フェリックス・ヴァイルでした。発端となったのは、フランクフルトでの「第1回マルクス主義研究週間」の開催で、ルカーチ、コルシュ、リヒャルト・ゾルゲ、K・ウィットフォーゲル、福本和夫らが参加。ゾルゲはもちろんソ連のスパイ、福本は構造改革路線を最初に日本に持ち込んだ理論家(本紙連載「シン・日本共産党実録」でも「福本イズム」の提唱者として登場します)で、後にマッカーサー憲法案に大きな影響を与えたと言われる「憲法研究会」の鈴木安蔵の師にあたる人物なのです。
マルクス主義の理論家が結集し、相互に徹底討論することで「純粋マルクス主義」に到達する││なる企てでしたが、常駐の研究所設立に話が。しかし、契機となったこの時の「収穫」は、ルカーチの主著『歴史と階級意識』の色濃い影響だったと言えます。
学際的唯物論からマルクスとフロイトの融合
ホルクハイマーは卓越したプロデュース能力で「社会研究所」を1923年に発足させます。既存のマルクス主義解釈には飽きたらず、マルクス主義の新しい可能性を模索し、「学際的唯物論」構想に至ります。さらに彼は1930年に所長になり、研究所として「青写真」を具体的に展開し、マルクス主義イデオロギーによりあらゆる学問領域を統合する壮大な構想で、極めて野心的な企てでした。その過程で出てきたのが、「マルクスとフロイトの融合」ということになります。
ホルクハイマーは新カント学派のコルネリウスが指導教授でしたが、むしろカントの「意志と表象」概念を敷衍展開したショーペンハウアーの思想こそ、フロイトとの共通基盤だったと言えるのです。
「批判理論」の構築と『啓蒙の弁証法』
![]()
ホルクハイマーの企図したマルクスとフロイトの融合は、具体的には盟友アドルノとの共著により米国時代に出版された『啓蒙の弁証法』という主著に結実します。
そもそもフロイトの精神分析学のフランクフルト学派への受容は、フロイトの弟子で、ナチズムの権威主義についての著作で知られるエーリッヒ・フロムがフランクフルト学派の紀要に寄稿してからだと言われています。
フロイトとホルクハイマーとを介する「共通項」としてのショーペンハウアー哲学の中心概念である「生への盲目的意志」をホルクハイマーは「盲目的欲望」と解釈しフロイトの「リビドー」概念を先取りするものとして評価し、このショーペンハウアー仕込みの「この世は最悪」と見なす「ペシミズム」によって、フランクフルト学派の「痕跡」と言える「批判(的)理論」を構築していきます。
1933年、ヒトラー政権の樹立でホルクハイマーは教授資格を剥奪され、ドイツを追放、社会研究所は閉鎖に。翌年、米国に亡命したホルクハイマーは、コロンビア大学で「社会研究所」を再設立します。米国でフランクフルト学派の牙城となったのが、実はコロンビア大学でした。
フランクフルト学派の理論体系は「批判理論」と呼ばれ、もともと文芸評論的な性格を持っているのですが、この『啓蒙の弁証法』でも古代ギリシャのホメロスの叙事詩『オデュッセイア』とサド侯爵の『ジュリエット』を中心とした文芸評論という趣を保ちつつ、カントが提起した「啓蒙」の概念についての哲学を展開するアンソロジーというのが、この書の趣旨だと言えるでしょう。
カントは楽天的な倫理道徳主義を説きますが、ホルクハイマーはこれを家父長的全体主義に導くとして退けます。
これに代わり称揚されるのが、フロイトの精神分析以上に、「サド作品」で、キリスト教社会では衝撃と言えるものでした。『啓蒙の弁証法』ではホルクハイマーとアドルノが章ごとに分担して書かれたとされますが、『ジュリエット』の章はホルクハイマーが書いたと言われます。
ショーペンハウアーのペシミズムから踏み込んでニヒリズムの哲学を打ち立てたニーチェもそうでしたが、西欧文明の限界と社会的価値観の転倒を企てたニーチェ以上に、「革命的」と評価を与えるのが、マルキ・ド・サドです。
サド侯爵は「性道徳の廃棄」を企て実践した「狂人」として、大半を獄中で過ごしました。このサドを聖人視するのは、フランクフルト学派の他に、記号論のロラン・バルト、そしてポスト構造主義のミシェル・フーコーらがそうです。実を言えば、彼らは同性愛者でした。キリスト教道徳では伝統的に生殖と関わりのない性愛(婚姻外の性関係)は認めてきませんでした。こうしたキリスト教道徳を家父長制社会、つまりファシズムを生む権威主義社会を形成してきた元凶と見るホルクハイマーは、機械的快楽主義を説くサドを、それと戦い殉じた英雄に祭り上げたのです。
![]()
「家父長文化」破壊が文化共産主義の本質
かくして精神分析の影響下、ホルクハイマーは「権威主義的人間」を生む「家父長制社会」の担い手たる「家族の解体」、そして「体制順応的」人間が形成する「国家(権力)」への「反抗」こそが「正義」であるかのように暗い「破壊の哲学」を展開しました。
これぞ「家族解体」「文化伝統の破壊」を目論む「文化共産主義」イデオロギーです。文化共産主義者にとり、このイデオロギーの浸透を阻むのは、「家族や文化伝統の守護」を国・民族の礎と見なす「保守思想」「宗教思想」という天敵なのです。
ホルクハイマーは「体制順応的(=権威主義的)人間」の「生産装置」として、否定的に「家族」を見たのです。
マルクスの階級闘争史観、そして文化・社会現象も「階級意識」で捉えるルカーチの方法論に呪縛された恣意的「決定論」ないし還元論と言えます。結果的に家族解体・文化破壊を促進させることがホルクハイマーをはじめとする文化共産主義者の目論見なのです。
中世最大の教父アウグスティヌスの「家族の平和は、社会の平和と深いつながりを持つ」という言葉にホルクハイマーは反対し、アウグスティヌスの規範意識は、「体制順応」を産む「生産装置」だと断定します。「肉体愛」「機械的快楽」を説くサドを「良心の呵責からの解放」の旗手として称揚するゆえんがここにあります。
しかし、アウグスティヌスの規範意識は、欧米社会に限らず、いかなる伝統的文化においても該当する普遍的なものと呼べます。「家族の平和」に無理矢理「階級意識」を持ち込むのは、「家族解体」を「普遍化」「一般化」してしまう危険があります。
個の「自由」を過度に尊重すれば「公正」が立たず、公の正義(公正)を求めれば個の自由は制限され、まさにカントの「二律背反」状態に陥るわけです。共産主義やナチズムなど全体主義では「自由」は極度に制限され、個人の国家・社会への奉仕が義務づけられます。一方、極端な「自由」への無制限の崇拝は結局、暴力やテロ、私刑の横行するアナーキズム社会を招来させます。「自由と公正の弁証法」なる机上の観念論に陥ったホルクハイマーの「批判理論」とは厳密なものでなく、気分ないしは独断的かつ恣意的なものです。それがはっきりするのは、「絶対的真理」と「相対主義」(としての懐疑論)とに関わるスタンスです。
結局、「現存する文化の相対性を暴露し、その絶対的真理性を否定する。否定こそは、哲学において決定的な役割を演ずる」という「批判的否定」こそホルクハイマーの本質にほかなりません。すなわち「絶対的真理」という場合の「絶対」の拒否です。
「絶対の拒否」は、裏返せば「相対主義」です。ところが、「絶対」を拒否することで「真理」も結局「相対的」なものにとどまり、「絶対的真理」に至ることはありません。それがホルクハイマー思想の難点なのです。
![]()
(「思想新聞」2024年8月15日号より)