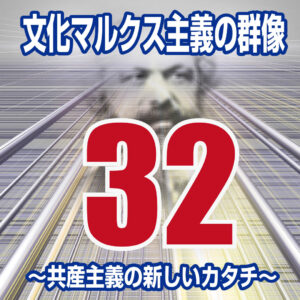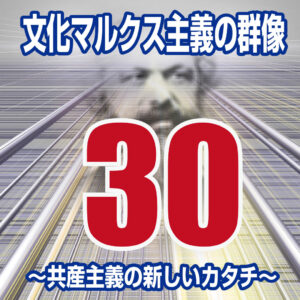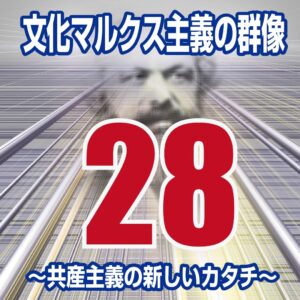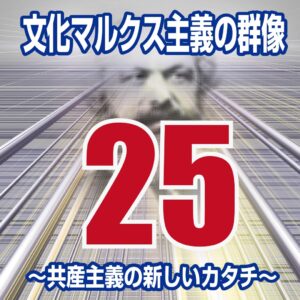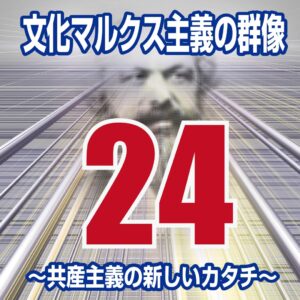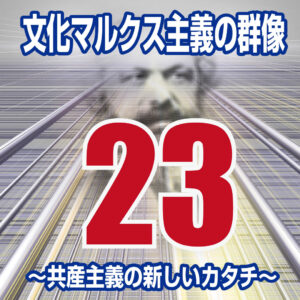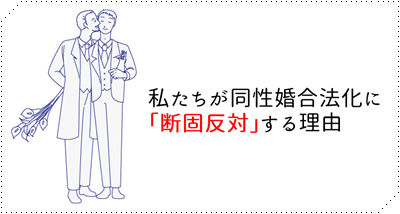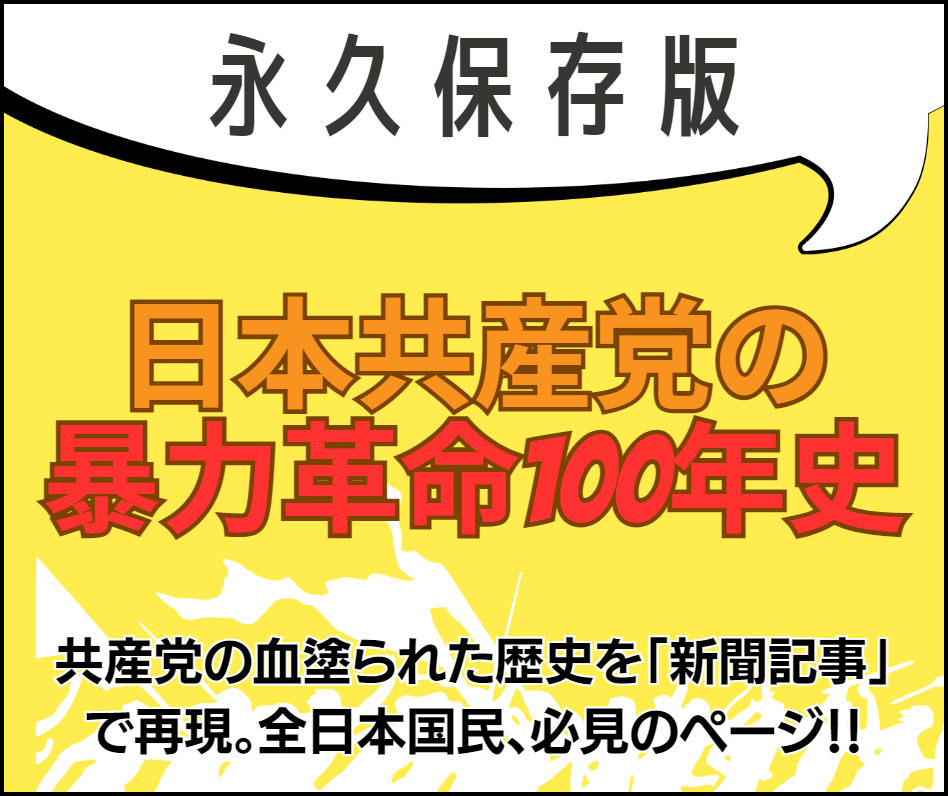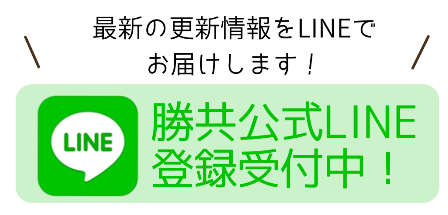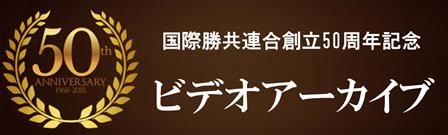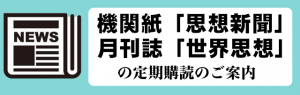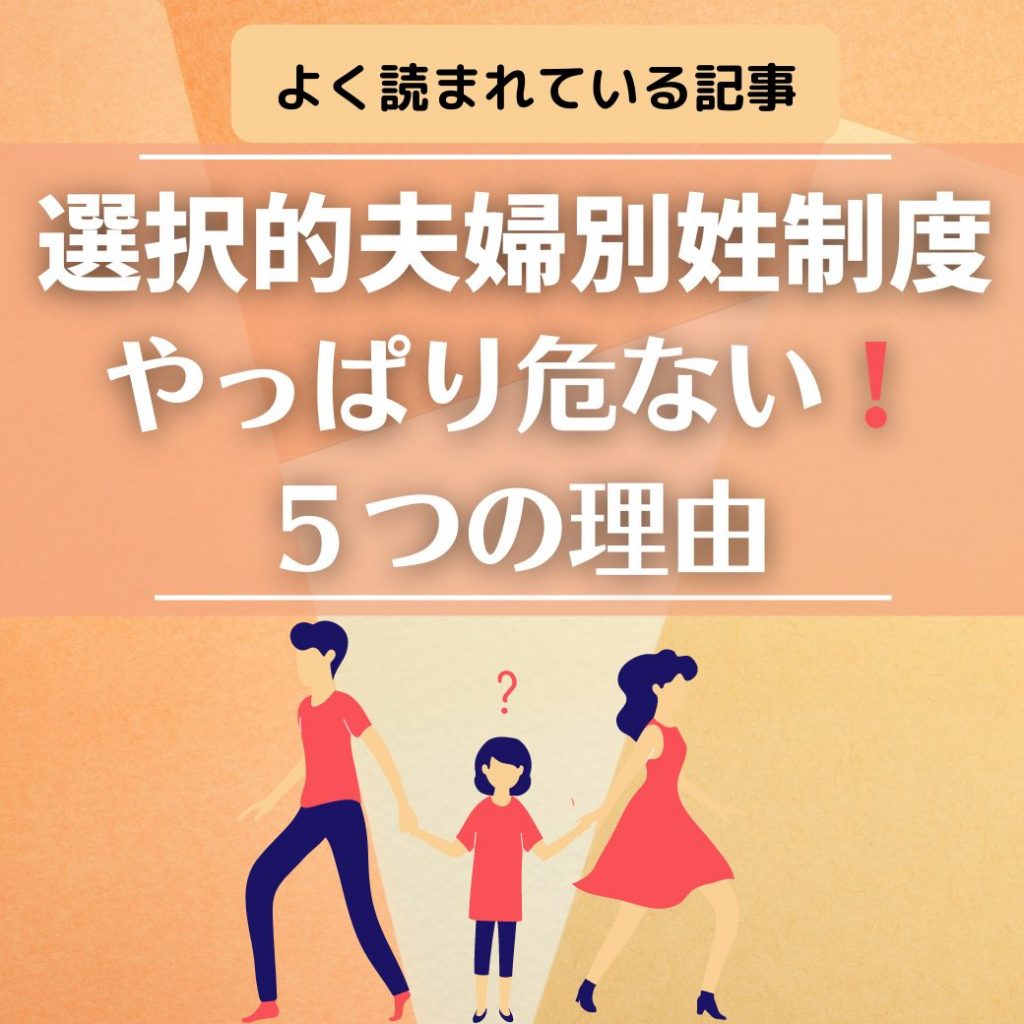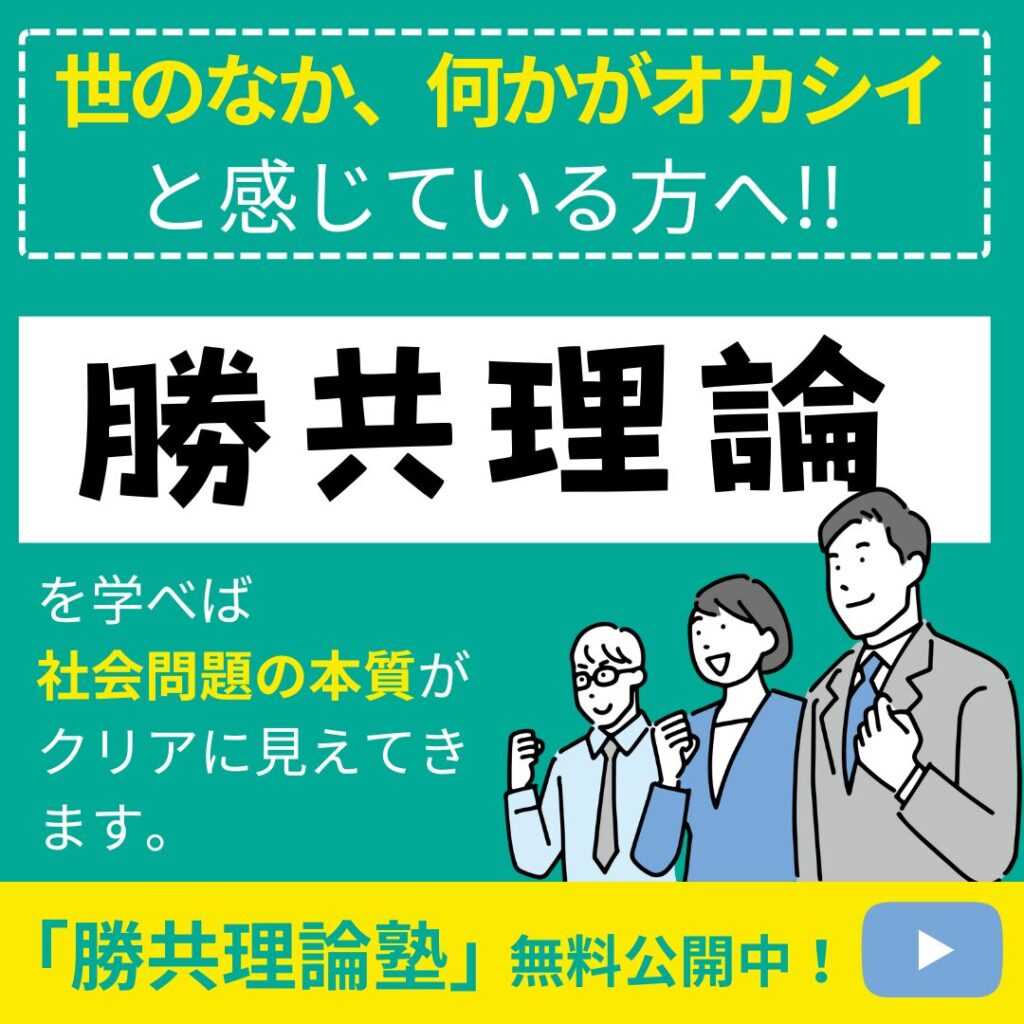ソ連社会に「家族解体策」もたらす
アレクサンドラ・コロンタイ
前回のライヒは1929年、社会主義政権を樹立したソヴィエト・ロシアを視察旅行し、ソ連共産主義(ボリシェヴィズム)による家族・性政策に「性解放先進社会」を見て嬉々として分析。『性と文化の革命(セックス・レボリューション)』後半部分として結実させたのです。
事実婚・堕胎合法化の実験先進社会と見なす
アレクサンドラ・コロンタイ(1872~1952)
ロシア10月革命でソビエト連邦成立時(レーニンは人民委員会議議長=首相)、「保健人民委員(厚生大臣)」として辣腕をふるったのが、アレクサンドラ・コロンタイです。コロンタイは世界初の女性政策担当部局「ジェノーデル(女性部)」を創設、事実婚を認めた結婚制度、堕胎の合法化、労働制度などに「革命的な変革」をもたらした一連の施策は、「社会主義フェミニズムの実験」として歴史的に理解されています。
コロンタイはまた、小説『紅い恋』を書き政治的信念を体現した、「世界で最も著名な〝自由恋愛〟(フリーセックス)と子供の国有化の提唱者」と米上院文書に報告されています。
また、英国の歴史家E・H・カーの『ソヴェト・ロシア史1924~26 経済』によると、コロンタイは、「家族というものは必要でなくなる。それは、家庭経済がもはや国家にとって有利ではなくなるがゆえに、国家にとっては必要ではなくなる。家庭経済は婦人労働者をより有用な生産的労働から不必要にも分離しているのである。他方それは、家族の別の任務─育児─がしだいに社会によって引き継がれるがゆえに、家族の成員自身にとっても必要ではなくなる」と言ったと述べています。
社会における「性革命」が実現された世界で最も「先進的」な社会こそ、ソヴィエト連邦にほかならないとライヒは真顔で考えました。それが如実に窺えるのが、『性と文化の革命』(中尾ハジメ訳)「第2部:ソ連における『新しい生活』への闘い」の記述で、ソ連での「家族解体」政策を激賞したもの。以下その冒頭部分を引用します。
◇
第8章 「家族の廃止」
ソ連での性革命は、家族の崩壊と共に始まった。全住民のあらゆる階層で、家族は根底から崩壊した。この成り行きは、苦しみの多い混沌としたものだった。それは、恐怖と混乱を巻き起こした。それは、家族の持つ性質と役割についての性経済の理論が正しいということの客観的な証拠となった。つまり、家父長制の家庭は、権威主義の原理に基づくあらゆる社会秩序を、心の構造とイデオロギーの上で再生産する場なのだ。社会秩序を廃棄することは自動的に、家族制度を根底から崩すことなのだ。
社会の革命の中で家族が崩壊したのは、性欲求が、経済や権威主義による家族の鎖を断ち切ったことによるのだ。それは、経済と性の分離を意味した。家父長制では、性欲求は、少数者の経済的な利害に奉仕し、またそういう具合に、その圧力のもとに置かれていた。未開の仕事民主主義的な母系制では、経済が、社会全体の欲求──性欲求を含む──を満足させることに奉仕していた。
社会革命の持つ自明な傾向は、経済を再び、生産的な仕事をする者全員の欲求を満足させることに、奉仕させることだった。欲求と経済の間の関係をこういう具合にひっくり返すのが、社会革命の本質的な部分だ。この全般的な成り行きという点から見て初めて、家庭の崩壊が理解できる。もしこの成り行きが、家庭の経済による束縛の重荷とか、それによって押さえつけられている性欲求の強さだけに、関わる問題だったら、それは迅速に起こっただろう。問題なのは、なぜ家族は崩壊したのか? ではないのだ。これなら、その理由は明らかだ。
答えるのがもっと難しい質問は、こういう成り行きが、革命のもたらしたほかの結果のどれよりも、遙かに苦しみが大きいのはなぜか? だ。社会的な生産手段を奪い去るのは、それを所有していた者を傷つけるだけで、革命の担い手である大衆を傷つけるものではない。しかし、家族の崩壊は、まさにその経済革命を実践しようとする者たち、労働者たち、雇われた人たち、農民たちに、打撃を与えるのだ。家族への固着がもつ保守の役割が、革命の担い手の中に禁止という形を取って、最もはっきりと露わになるのは、まさにこの点でだ。妻と子供への固着。もし家庭があるなら、それがどんなに貧乏であろうと、それへの固着。毎日の決まったやり方とかその他のことへ執着する傾向。彼が肝心の行動、つまり、自律する、仕事民主主義社会の確立を、始めようとするとき、こういうもの全部が彼を引き戻すのだ。
◇
いかがでしょうか。「性革命は、家族の崩壊とともに始まった」という冒頭の一文が、いみじくも「文化共産主義」の狙いと本質を吐露しています。
労働者に家族愛を断たせる文化共産主義
そして重要なのは、「家父長制の家庭は、権威主義の原理に基づくあらゆる社会秩序とイデオロギーの上で再生産する場」と見なした上で、「社会秩序を廃棄することは、自動的に、家族制度を根底から崩すこと」にほかならないとしているのです。
さらに、「革命の中で家族が崩壊したのは、性欲求が、経済や権威主義による家族の鎖を断ち切ったことによる」という文脈の中で読み取れるのは、「文化共産主義の悪魔性」とも呼べるホンネの部分です。
すなわち家族の崩壊を最も妨げて来た部分は、「保守の役割」を担った「家族への固着(つまり愛情)」にほかならず、「愛と性」「性と経済」の分離というものが達成されるためには、革命の担い手であるはずの、労働者や農民などプロレタリアート自身の「家族の解体」という苦しみを受けなければならなかった、ということを述べています。
こうした「家族への固着・愛情」を引きはがし、分離してめざすものこそ、「仕事民主主義社会」(ライヒのいう共産主義社会)だということになります。
「事実婚=乱婚」主義者のコロンタイ
ソ連社会主義体制下で女性革命家コロンタイが中心となり実行された「家族解体政策」は、ライヒの賞賛するように、女性の「権利が拡大」し、「性の解放」「戸籍の解放」をもたらしたはずでした。
しかしレーニン亡き後の「赤いツァーリ」として君臨したスターリンは、これが「国を滅ぼす」ものであると見抜き、一斉に政策転換を図ります。それを象徴しているのがいわゆる「スターリン憲法」だったとも言えるでしょう。ではなぜ、スターリンはそれに気がついたのでしょうか。
ボリシェヴィキ革命後の旧ソ連時代の「家族解体」政策に関しイニシアチブを取ったのがコロンタイでした。確かに、コロンタイは紛れもなく帝政時代からロシアにおけるフェミニズム(女権拡張)運動の草分け的存在とは言えます。
平凡社『哲学事典』では「コロンタイ」の項では「『同志関係としての愛』という形で社会主義社会における恋愛のモラルを確立しようとしたが、本質的には一夫多妻主義的な謬論であった」としていますが、コロンタイは「一夫多妻論者」どころか、「事実婚による自由恋愛(フリーセックス)」を唱えたのであり、「事実婚=乱婚」主義者ということになるでしょう。
そしてアンドレ・ミシェル著『フェミニズムの社会史』では、コロンタイとソ連の女性・家族政策について言及し、女性労働者の権利を要求した運動や、革命後には赤軍として男性兵士同様、女性も白軍(帝政支持派)とのゲリラ闘争に身を捧げたとしています。
家族が解体すれば必然的に育児、すなわち子供の面倒は社会が見る、ということになるわけです。
「普通の結婚」が空虚という独断
![]()
社会主義計画経済体制という「コミューン」の中に、かつてシャルル・フーリエが企てた「情念交換所」という「実験的装置」を、20世紀に再現しようとしたと言ってもよいものです(エンゲルスの『家族・私有財産・国家の起源』は、「空想的社会主義者」と呼んだはずのフーリエ思想の影響が多分に見られることがわかります)。
家族を解体し、育児を社会に「アウトソーシング」(つまり「丸投げ」)することで必然的に人間関係は希薄なものとなり、家族構成員に対し生ずる「責任」も放擲されてしまうわけです。そう考えると、社会や国家の根幹を揺るがす事態を招く方向に突き進んでいる、とさすがの「鋼鉄の独裁者」スターリンも悟ったのではないでしょうか。
なお上図は、「性肯定」による「文化の発展」という模式図で、『性と文化の革命』に所収・掲載されたライヒ自身の図を基にしたものです。これに倣えば、まさに「生きるのはいいこと」という文化は、「性を肯定する文化」と定義します。他方、キリスト教などは「性否定の文化」であり(語弊がありますが)これに基づく「普通の結婚による性は空虚」と決めつけます。
巷間、教育現場などに顕著に見られる皮相的な「宗教抜きの生命礼賛」の主張は、フロイトすら忌避した「性(快感)肯定至上主義(=性解放)」そのものだ、と指摘せねばなりません。
(「思想新聞」2024年10月1日号より)