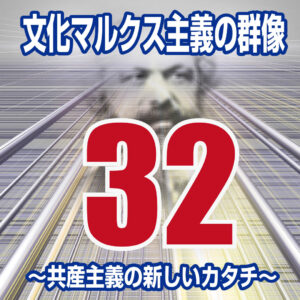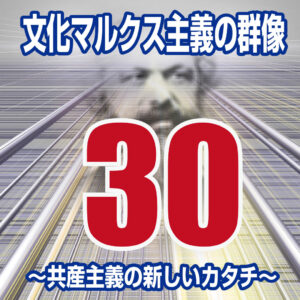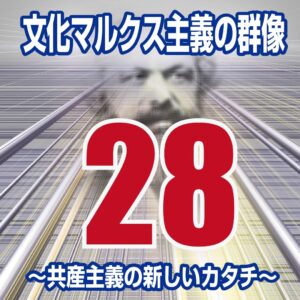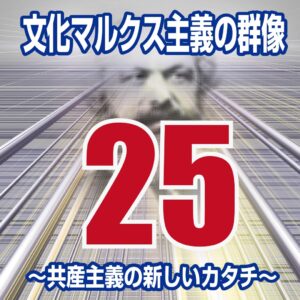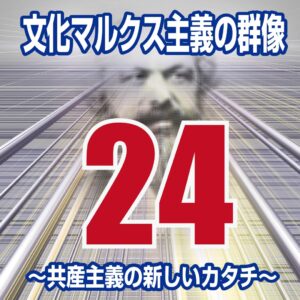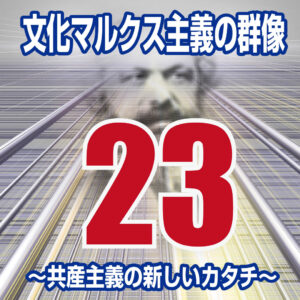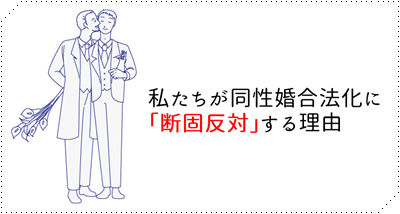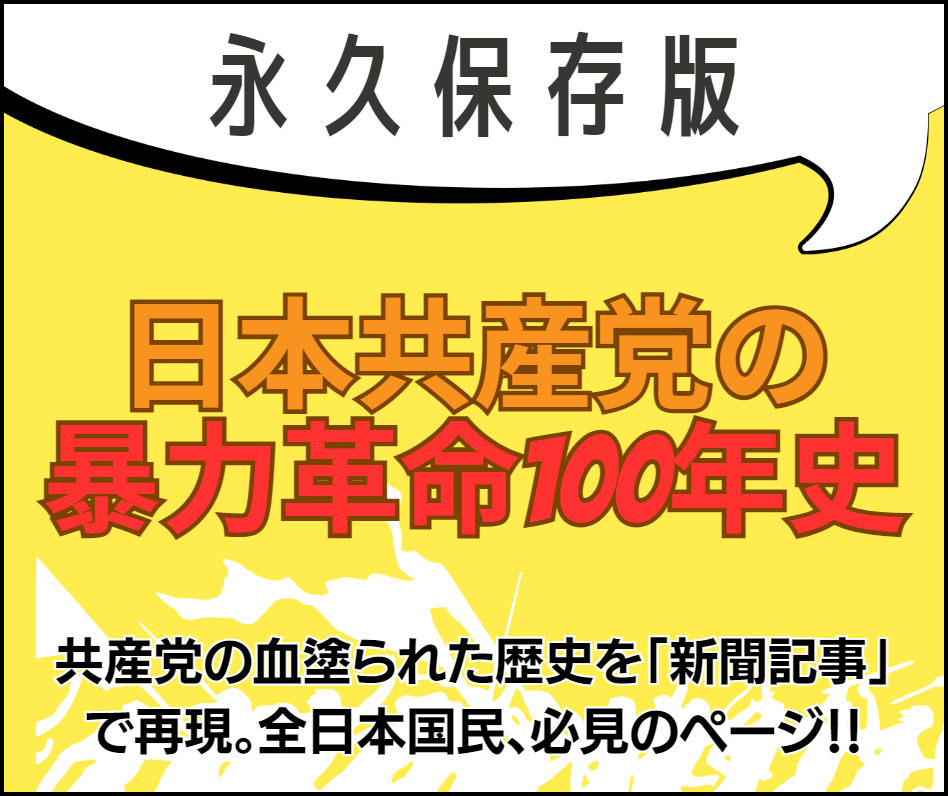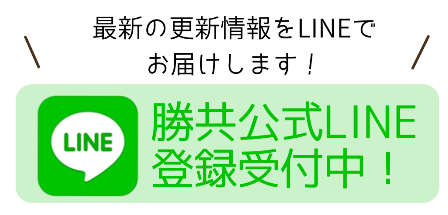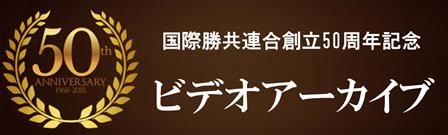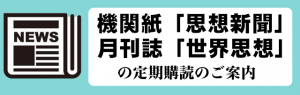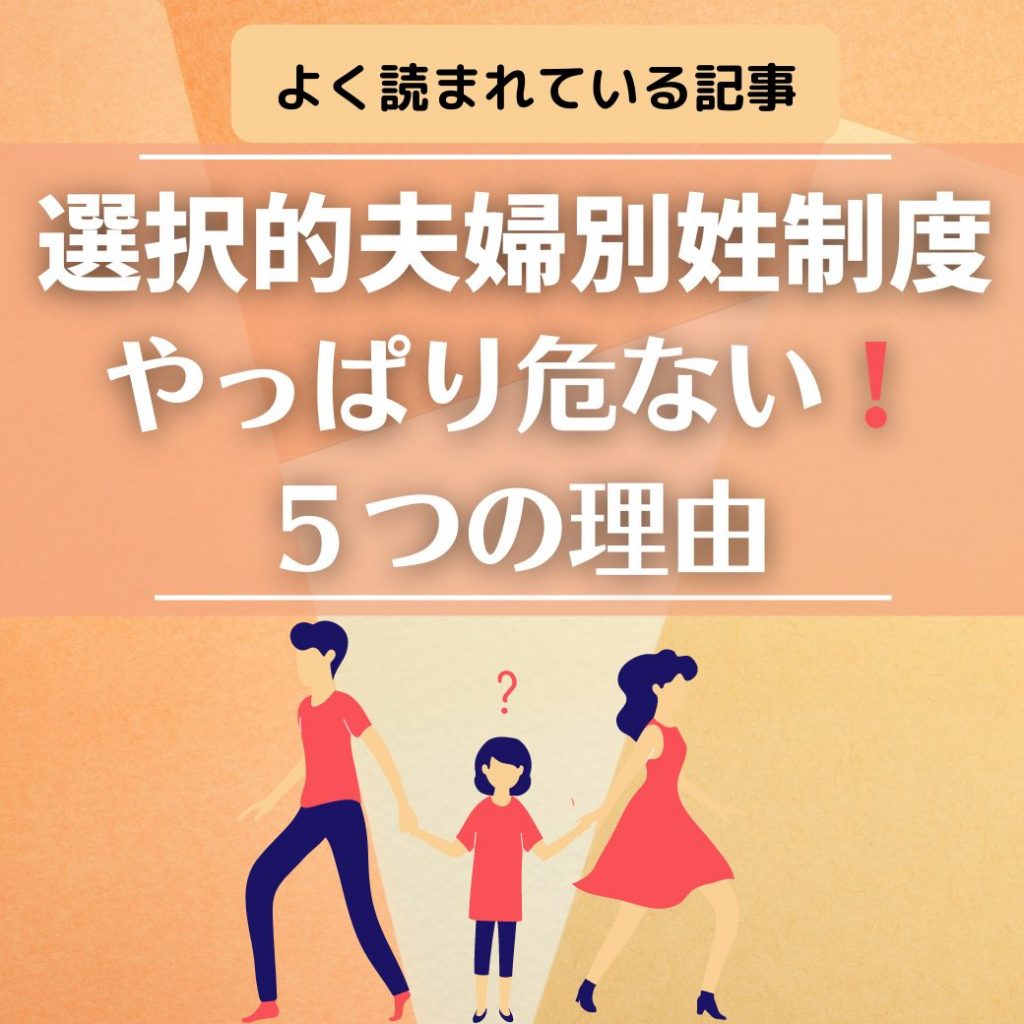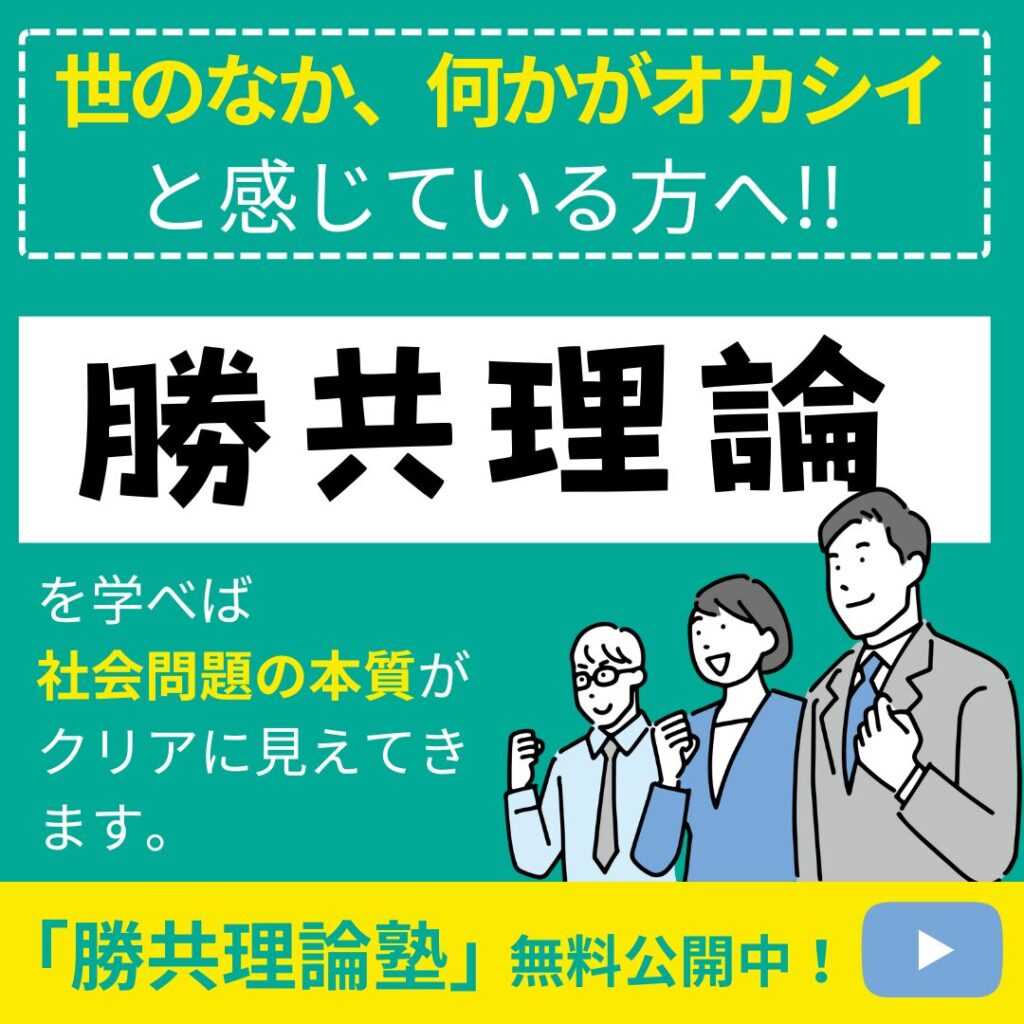「女性の味方」の実態は稀代のエゴイスト
続 ウイルヘルム・ライヒ
「性は神聖なもの」という宗教的発想
ウィルヘルム・ライヒ(1897〜1957)
コロンタイらのソヴィエト社会主義による「家族解体」政策を視察し、「性肯定による文化発展」の図式(『性と文化の革命』)の必然的運命とライヒは見なしましたが、「生きることはいいこと」という「宗教抜きの生命礼賛主義」であり「性(快感)肯定至上主義」に通じると指摘しました。
ただ、宗教が歴史的に「性」を絶対的に否定してきたわけではありません。
確かに、カトリックでは聖職者の妻帯を禁じ、また仏教も天台宗は僧職者の妻帯を禁じます。しかし、それは罪を犯すことなく「性を神聖視するため」のもので、結婚は神によって祝福される「唯一の性的関係」としているからです。古今東西、神仏の前で保障され、契約されるのが「結婚」という儀式であり続けてきたゆえんでしょう。
エンゲルスは『家族・私有財産・国家の起源』で、「原始乱婚社会では嫉妬が克服された」と独断的見解を唱えますが、「感情と知性を持った人間が、そんなことを克服できるわけがない」とマルクス主義思想家の吉本隆明ですら、エンゲルスの暴論に異を唱えています。
「性的自己決定権」こそ生命軽視する
「命を大切に」「生きるってすばらしい」という「生命礼賛の観念」は、本来は極めて宗教的なものでしょう。そう考えれば、「性」とは生命の誕生に直結する神秘的なシステムとして、「神聖視」するのは当然で、「避妊」や「堕胎」といったいわゆる産む/産まないを決める「性的自己決定権」(リプロダクティヴ・ヘルス・ライツ)の主張は、生命軽視にほかならず、ライヒの「集団での、生きることはいいことだと肯定させるような性関係」の主張は、極めて独善的で、自ら「性的コミューン」を実現させる詭弁にすぎません。
ライヒは「普通の結婚が持つ性の空虚さ」と表現しますが、「家庭を築く」という営為のうちにこそ、真の意味での「生命礼賛」が存在する、と言えないでしょうか。
男女の性的関係から想定されるのは、子供が生まれ、育てるということです。ライヒの考え方によるならば、生まれた子供は「副次的な産物」であるか、それどころか「邪魔な存在」のように忌避されます。
また、ライヒの主張を敷衍していけば、容易に「生きるが勝ち」(強者が生き残る淘汰論)ということになるでしょう。つまりダーウィニズム(自然淘汰)の社会的展開で、いかなる手段を講じても最終的には「勝ち組」になりさえすればいい││。これはまさしく「宗教抜きの(唯物的な)生命礼賛」の皮相的側面と指摘せねばなりません。
この考えこそ実は「エセ生命礼賛主義」であり、「性と結婚」を神聖視する宗教的価値観を否定するための詭弁と言えるのです。唯物的な価値観に根ざすものは、死者を哀悼したり、思いを致したりはしません。その傾向が色濃く反映されているのが、法の考え方です。例えば、殺害された被害者の生命よりも、むしろ現在生きている加害者の更生を期待する、という傾向の体系と言えます。
「家族を守る」思想説くヘーゲル
フロイトは生命の本能たる「リビドー」と、「タナトゥス」と呼ばれる「死への本能」を対置させ、ある種の人間存在の非合理性を説きました。まだ「死」に対する意味を考える余地を残し、少なくとも「死生観」があったと言えます。対してライヒは、フロイトの「死」に対する執着を、無意味なものと考えました。それどころか、「性=生」という観念を抑圧するものだとして糾弾しさえしました。つまりライヒにとっては、「性を抑圧するものすべては悪」という価値観だったのです。
これに対してヘーゲルは、結婚について「自然的で個別的な人格性を前述の一体性において放棄して一人格を成そうとすることの同意である。この一体性は……彼らの解放である。人間の客観的なつとめ、したがって倫理的義務は、婚姻状態に入ることである」(『法の哲学』)と述べます。「結婚は人間の倫理的義務」とまで断言し、キリスト教的倫理観に基づく家族重視の社会というものを哲学的に基礎づけようとしたのが、実はヘーゲルの思想と言えます。
ヘーゲルによれば、やはり個人で努力するよりも、家族を築くことによって人格完成される、と捉えていたと言わざるを得ません。そうでなければ「人間としての義務」とまでは言えないでしょう。そしてまた、共同体において、個々人としての意見の違いや矛盾などははらんでいたとしても、共同体全体で考えた場合の「人倫」の実現こそが弁証法における、矛盾を止揚した「ジンテーゼ」(総合)という完成段階に至ると考えていました。
家族守護のヘーゲルと対極にあるライヒ
![]()
しかし、ライヒは『性と文化の革命』で次のように述べます。
「義務としての結婚には、まだなっていない性関係の場合にも、難しさを生み出しているいくつかの事実に触れなければならない。何のことかというと、特に女性によって受け入れられ、そして代弁されている、一夫一婦制のイデオロギーのことだ。……性道徳は、実のところ所有の利害で充満しているので、男が女を『所有』し、女が『自分を与える』ということが当たり前のことに思われるような事態をもたらした。……女性は性行為に対して否定的な態度を持つようになる。この態度は、権威主義の教育によって養われている。……女の子は赤ん坊の時から、女はたった一人の男とだけ性交するべきだという要求を、吸収してきたのだ。そういう教育の影響は――無意識のうちにある罪悪感がこれにとりついて――たいへん深く、強力なのだ。……『私の母親は一生ひどい結婚に耐えてきた。だから私もそれに耐えなければならない。』たいていの場合、忠実な一夫一婦制を守った母親との、こういう同一視が、最も有力な抑制因子だ」
ヘーゲルの「人倫」など、キリスト教的家父長制社会を正当化するドグマとして真っ向から対立している、と言わざるを得ません。
ライヒの主張する理論と、実際の人生を探ると、一見、男女平等と性の解放、婚姻制度の廃止と事実婚主義を賛美したライヒという一人の人間が、果たして「真っ当」な「空虚ではない性のあり方」を歩んだのか。実際そこには男女平等という観点どころか、自分に都合のよい、自分を正当化するための道具と見なさざるを得ない、身勝手極まりない状況が浮上するのです。
伝統的な結婚を「生涯にわたる強制的な一夫一婦制」と決めつけ、「持続的愛情関係による事実婚」を提唱したライヒは、持続する限りで「永続的で排他的なものとはならない」とライヒはハッキリと認め、「愛の永続性」を否定しました。
その言葉通り、彼の異性関係の実態を示しているのが上の相関図です。しかも、ライヒという人物は「女性と子供の味方」では決してありませんでした。
それどころか、女性の権利の擁護者に見えて実は堕胎まで強要するエゴイストだったのです。
(「思想新聞」2024年10月15日号より)