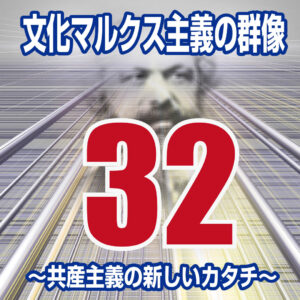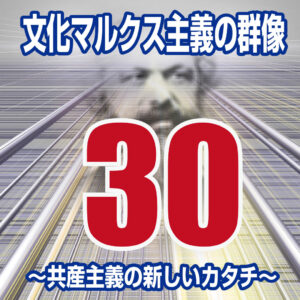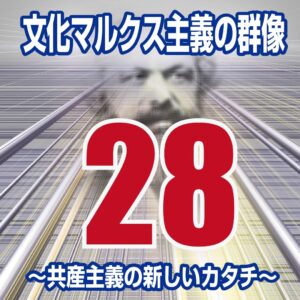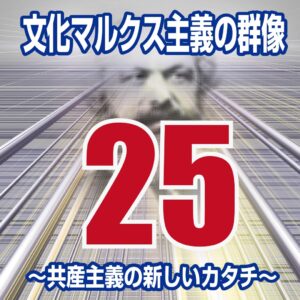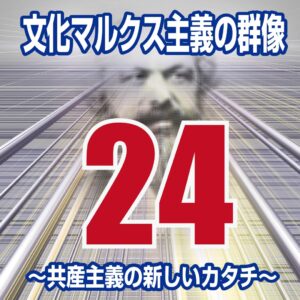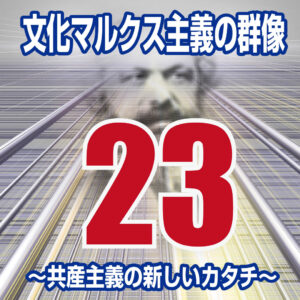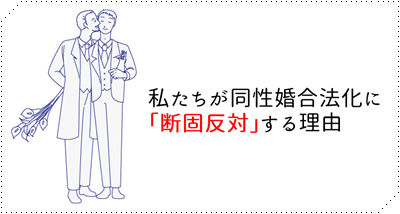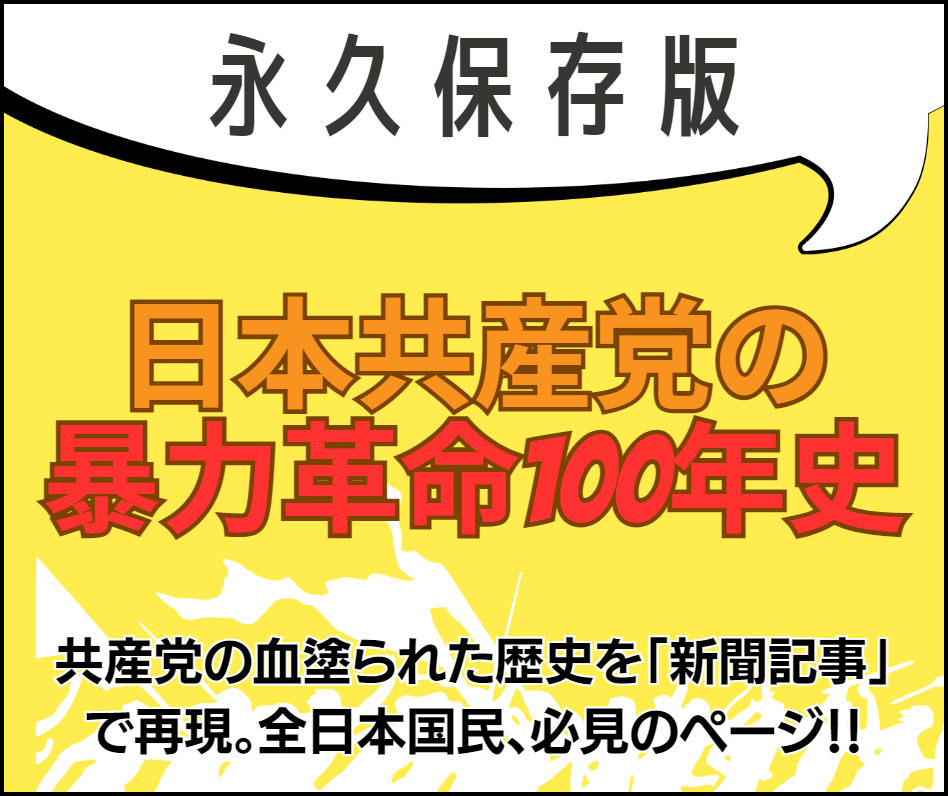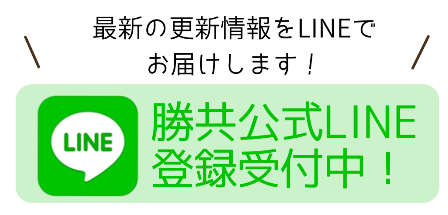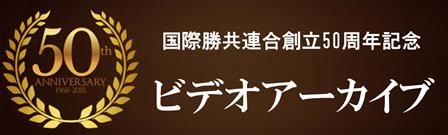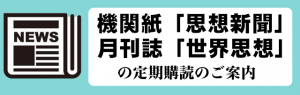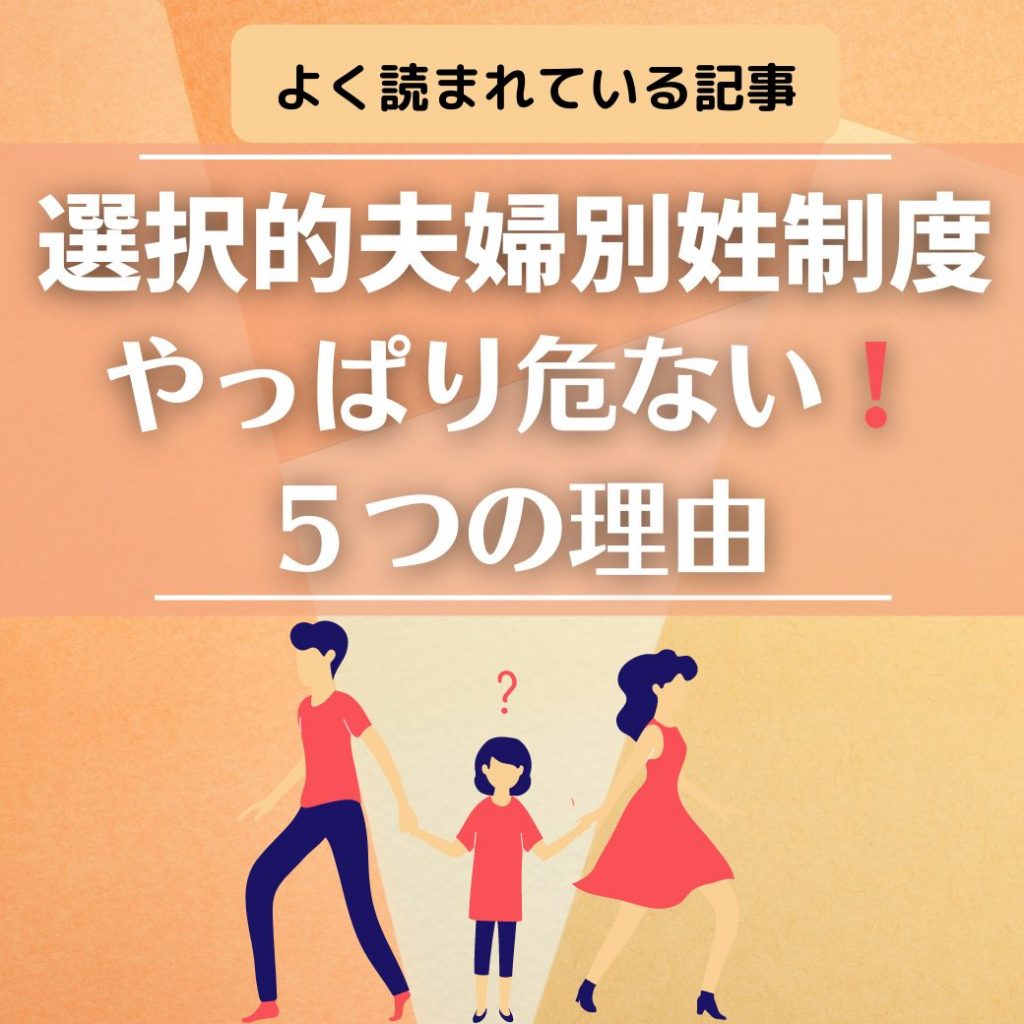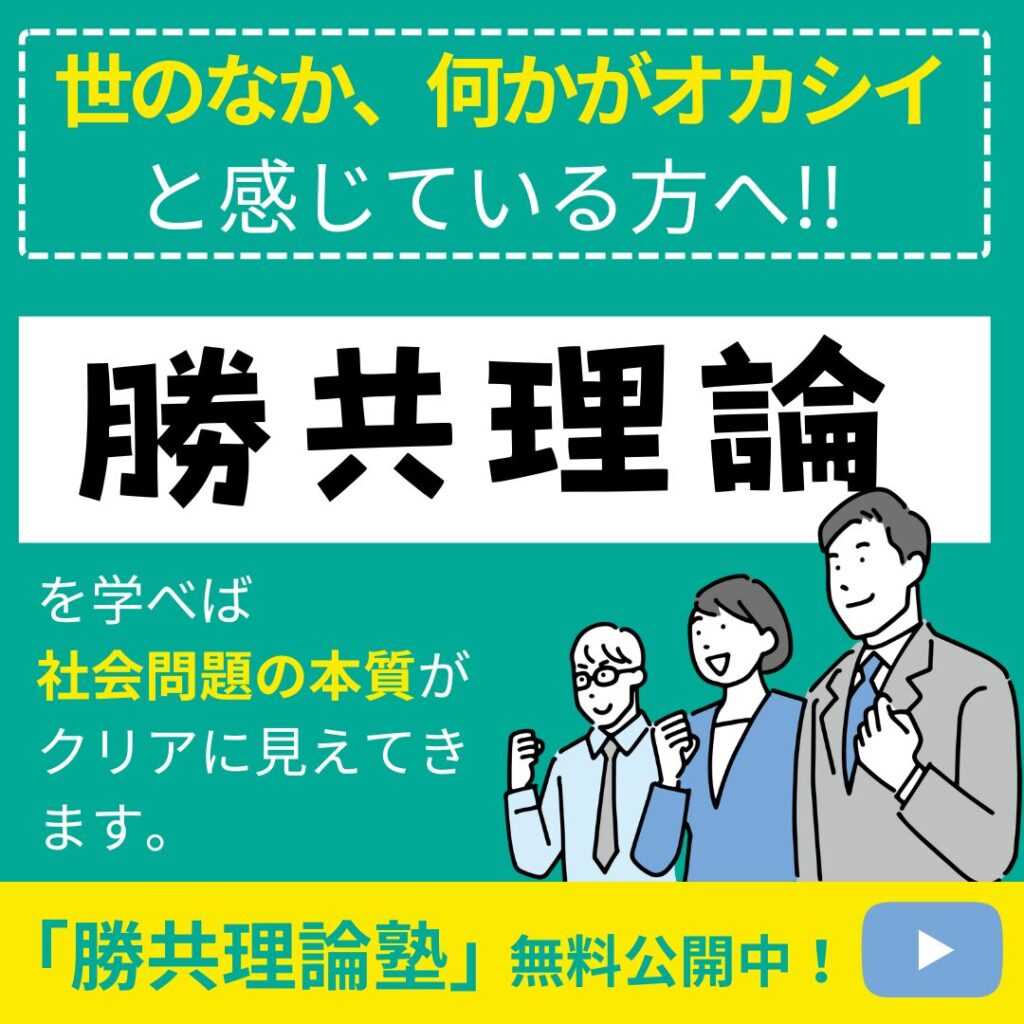コギト中心主義超克するパラダイム
ライヒ結婚観への思想的反駁
欲望のため子供を犠牲にしたライヒ
マルティン・ブーバー
伝統的な結婚を「生涯にわたる強制的な一夫一婦制」と決めつけ、「持続的愛情関係による事実婚」を提唱したライヒは、「愛の永続性」を否定し、女性の権利の擁護者に見えて実は堕胎を強要するエゴイストだったのです。
前回の「相関図」で示したようにライヒは、伝統的な結婚形態を「強制的なもの」と決めつけて糾弾し、「永続しない持続的な愛情関係としての事実婚」を奨励。さらには「産む/産まぬ」を自ら決定できる、つまり「性的自己決定権」と「堕胎」を合法化する運動を展開しました。
しかし、真正なる意味で「生命尊重」を訴えようとすれば、「生命の誕生」を人為的に妨げる「堕胎」という行為は決して認められないでしょう。なぜなら、胎児は「モノ」ではなく、誕生してなくとも生への意志を持った立派な生命体だからです。だから宗教的には「殺人」と見るのです。
ところがライヒは胎児どころか、生まれた子供すら「性行為の派生物」にすぎないと考えたでしょう。「伝統的な結婚は地獄」と喧伝し、離婚を扇動しながら両親の離別によって犠牲となる子供たちの「セーフティネット」は考えなかったからです。
それはライヒ自身の「家庭」においても如実に言えました。つまり、最初の妻アニーとの間に生まれた子供たちが犠牲となったからです。また米国時代の「第三の妻」イルゼ・オレンドルフも、ライヒとの間に男児をもうけました。ところが、北欧時代に苦楽を共にし、最もライヒが愛情を注いだと言う「第二の妻」エルザ・リンデンベルクには、子供を持つことを許さず、妊娠しても堕胎させたのです。
かくして、ライヒが決して「男女同権論者」でも「子供の人権主義者」でもないことは、子供の養育について、ルソーやフーリエのように「社会的分業」論者から明らかです。
西欧思想が共有するコギト中心主義
こうしたライヒのような結婚観・人間観は、エゴイズムと唯物無神論の極致と言えます。そこで、こうした考え方を批判・克服する思想としてどのようなものが挙げられるか、考えてみましょう。
さてそもそも、マルクスとエンゲルスが依拠したのはヘーゲル左派哲学でしたが、西洋近代哲学の一方の雄・「合理論の祖」と言われるのがフランスのルネ・デカルトです。デカルトは「コギト・エルゴ・スム」(我思う、ゆえに我在り)と主張し、「考える自分(自己意識)以外の一切を疑う」という「方法的懐疑」を唱えました。
この「コギト」(考える私)が西欧哲学の「骨組み」となってきた、ということは多くの哲学者が捉えている点ですが、これは言うなれば「独我論」にほかなりません。つまりこうした独我論的姿勢は、「シングルの思想」(シングル・パラダイム)とも言い換えることができます。ところが、「人は結婚して家庭を築くことが義務であり、人格の完成、すなわち人倫の実現が成し遂げられる」という「家庭守護」の思想は、いうなれば「カップルの思想」(デュアル・パラダイム)ということができるでしょう。
主著『全体性と無限』で、ハイデガー哲学を「存在論の帝国」と手厳しく批判したエマニュエル・レヴィナスが企図していたものも、実は「コギト中心主義の克服」にあったと言えます。具体的に言えば「他者への気づき」ということです。この「他者への気づき」とは何でしょうか。この点について、わかりやすく、かつうまく表現しているのは、ユダヤの宗教哲学者マルティン・ブーバーの『我と汝』です。
ブーバーの「我ー汝」の世界観
ブーバーの表現によれば、二つの根源語「我—汝」「我—それ」を用いた二種類の世界観があるというのです。本稿の文脈で言えば、後者「我—それ」で表現される世界観こそ「コギト中心主義」の独我論的世界観(シングルの世界観)であり、前者の「我—汝」で表現される世界観が、「私と他者との関係性から築かれる世界観」ということになります。
日本語で「他者」「他人」という場合、むしろ「我—それ」でいう「それ」に近いニュアンスがありますが、キリスト教的な、つまりは新約聖書的な表現で言えば、それは「隣人」と言い換えられるべきものです。つまり、自分とは遠くの方にある抽象的な存在ではなく、「我」にとって身近でしかも「呼べば答えが返る」ような存在とも言えるでしょう(ブーバーの原著のタイトルは『Ich und Du』であり、Du〔きみ〕はDich〔あなた〕より近しい関係を表現しています)。
前回言及したレヴィナスでもこのブーバーに関し触れている箇所もありますが、この「他者」あるいは「汝」という箇所は、「神」という言葉で言い換えられることがわかるのです。
![]()
「隣人を愛する」ということの意味
それはイエス・キリストが「汝の主を愛するように、汝の隣人を愛せよ」と説いたことに呼応しています(ニーチェは『ツァラトゥストラはかく語りき』の中でこれを逆手にとり「〝遠人〟こそ愛せ」と主張しています)。しかし、イエスのいう「隣人」とは「己れと身近に接する人」という意味ですが、身近な存在ほど実は「愛すること」が難しいということを、ドストエフスキーは『カラマーゾフの兄弟』の無神論者イワンに語らせています。
そしてその「隣人」とは家族や同胞だったら比較的愛するのは容易かもしれません。ところが、「異邦人」つまりユダヤ民族にとっての異教徒ですら「隣人」たりうるわけです。異教徒であっても「善きサマリア人」になりうるということです。もっと言えば異教徒にさえ「神は働く」ということも意味しているのです。
そのような「他者」を「隣人」と認めることがすなわち、「我—汝」の世界観(あるいは有機的自然観)と言えるのではないでしょうか。これは別の言い方をすれば「私には(配偶者や神などの)同伴者が存在する」との認識(カップル・パラダイム)になります。
その反対に、「隣人」ではなく単なる「異邦人」それどころか「敵」と見なしてしまうこと、それが「我—それ」という独我論的世界観(あるいは無機的自然観)ということになるのではないでしょうか(シングル・パラダイム)。
そこで、「コギト中心主義」(独我論ないしはエゴイズムとも読み替えられます)を超克する思想への糸口として、「我—汝」と「我—それ」の人生観について深掘りしてみましょう。
いわゆる「シングルライフ」は決して後ろめたいネガティブな生き方ではない、というプロパガンダがその趣旨に合ったと述べました。
この「シングル」の人生観には多分に「自己決定論」のイデオロギーが胚胎しています。(子供を)産む/産まないを自分で決める権利、すなわち「リプロダクティブ・ライツ」はその典型例ですが、自ら命を絶つ、つまり自殺することも、「権利」として認められるべきものなのでしょうか。実を言えば、このことが究極的には「シングル」なのか「カップル」の人生観なのかが如実に問われてくる問題と言えます。
私の意識と独立し機能する身体
独我論的人生観か非独我論的世界観のという差異というのは、「私という存在」」私という生命」をどう見るか、という問題にゆきつくと言えるでしょう。「私という存在」は、100%「私」の意志で自存できるのでしょうか。例えば、私は自らの意志で息を止めたり、食事をしたりします。ところが、手足を動かしたり、言葉を話したりするようには、自分の心臓を動かしたり、血液の流れを意識的に「自分の意志で」動かすということはしません。
このことは何を意味しているのでしょうか。私の身体は、私という意識、あるいは意志とは独立して無関係に働いていることは明らかです。この点については、既にデカルトの時代から心身二元論として指摘されてきました。デカルトは身体を「機械」のようなものと考えて、解決を図ろうとしました。
所与への認識と「我ー汝」の世界観
しかしそうではなく、この意識とは独立しているように見える身体現象を通して、ある認識に至ることもありうるでしょう。その認識とは何かと言えば、「私という存在は《所与》なのだ」という認識です。この場合の《所与》とは何でしょうか。つまり「与えられたるところのもの」ということです。言い換えるなら、「私という存在は自らの意志をもって自分の人生を開始したのではない」という「事実」にほかならないのです。
それは直裁的に言えば、両親の性交渉が原因なのであり、情緒的に言うと、両親が愛し合った結果、この世に生を受けたのが、私という存在なのです。
しかも私と結びついているのは、何も父母ばかりではなく、祖父母・曾祖父母、…と先祖から連綿と受け継がれているのが「血統」、言い換えれば遺伝子、ということになります。使い古された表現ですが、私という存在は、先祖から代々遺伝子という「襷」(ないしはバトン)を受け継いで現在に至っているわけです。
(「思想新聞」2024年11月1日号より)