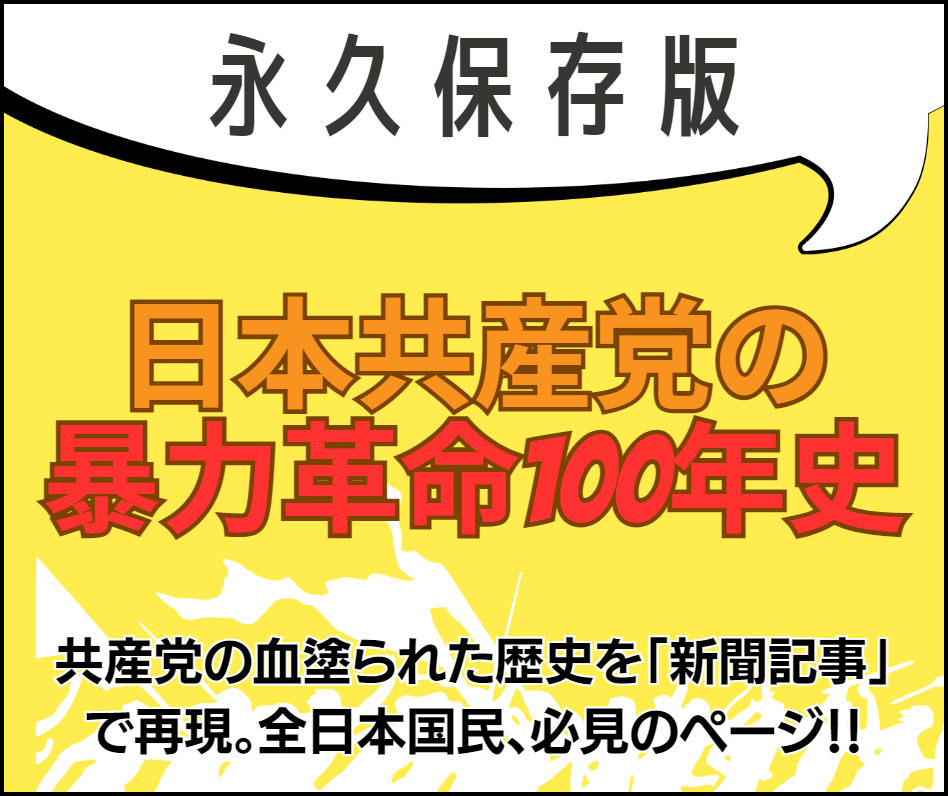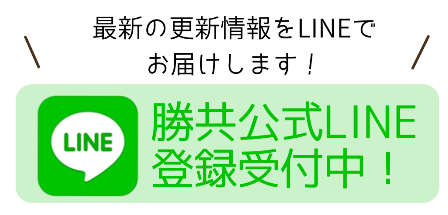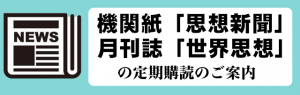現代社会をミスリードする3哲学
プロローグ・後編
まず、前回提起した「21世紀の共産主義」ともいうべき「共産主義の新しいカタチ」は、そのターゲット(攻撃目標)を、国家・基幹部分ではなく、それよりもっと根源的な文化・宗教全般に絞っていること、それがまさに「文化共産主義」と呼ばれるゆえんです。
つまり、いわば「ハードの革命」から「ソフトの革命」へと路線転換したのです。逆説的に言うと、国民の文化や宗教さえ解体・転倒させてしまえば、国家体制は自ずから変わらざるを得なくなるわけです。いくら国家体制の下で法律や制度を変えたとしても、それを構成している人々の考え方や感じ方受け止め方が変わらなければ、「真の革命」は達成できない——と「文化マルキスト」(ブキャナン『病むアメリカ 滅びゆく西洋』成甲書房)らは喝破していたのです。
この「文化マルキスト」についてその特徴を、八木秀次氏は、『世界思想』2003年9月号インタビューで「(「文化マルキスト」が)今日本にはびこっている。シロアリのように、二千年以上の年輪を持つ日本という大木を、中から食い荒らす。彼らはもう体制派で、審議会を使って次々に政府や自治体の見解を出している」と述べています。
![]()
社会を誤らせてきた3つの思想
チャールズ・ダーウィン
ところで、このような「新しい共産主義のカタチ」というものは、全体の思想的流れからすると、どのように位置づけられるのでしょうか。この点について今回は概観してみましょう。
李相軒・著『頭翼思想時代の到来』によれば、現代社会を蝕む「戦犯」として三つの思想を挙げています。それは、マルクス主義・ダーウィニズム・フロイト主義の三潮流で、渡辺久義・京大名誉教授も『意識の再編』(勁草書房)でまったく同じ指摘をしています(図Ⅱ参照)。
そしてさらに、この三つの流れというものが、現代思想においてどれほど大きな影響力を持っているか、I図から一目にして瞭然でしょう。I図の元になっているのは、講談社『現代思想の冒険者たち』シリーズ添付の図です。
![]()
ジークムント・フロイト
このうち、ダーウィニズムなどの「科学理論」については、同シリーズは触れていませんが、あえてI図との関連で言いますと、ダーウィニズムを哲学・思想的に補強したものは、ニーチェの思想と言うことができます。ニーチェはショーペンハウアーのペシミスティック(悲観主義)な意志の哲学を継承して「神の死」を宣告し、弱者がすがる奴隷然としたキリスト教的価値観を棄てて超人を目指し強く生きよ、とニヒリズム説きました。そしてそれを弱肉強食の論理で人種差別を国策としたのがほかならぬナチス・ドイツでした。
確かに、思想的影響というものは、マルクスと結びついたダーウィン進化論、マルクス主義とフロイト思想の融合というように単純なものとは言えないでしょう。そこにはヘーゲル弁証法の再解釈があったり、ニーチェのニヒリズム思想、そして実存主義の「企投」(アンガージュマン)思想が加わったりして、複雑な様相を呈しています。
もちろん、一部に「何でも《共産主義》にしてしまっていいのか。レッテル貼りではないのか」と訝る向きもあるかもしれません。しかし、私たちにはことの本質を見極める必要があるのです。ですから、これまで機関紙で展開した勝共思想講座でもマルクスの弁証法的唯物論の成立する契機、すなわち「動機と経路」を克明に分析した「疎外論」で子細に論じてきました。
フリードリヒ・ニーチェ
古来、「思想」と呼ばれるものはおよそ、人間が生み出す以上、多かれ少なかれその人間の人生が投影されてきました。にもかかわらず、思想家というものは一様に、自らの思想・哲学の独自性・斬新さ・ラディカルさというものを喧伝しがちです。
もちろん、「真理」というものは、新奇さやラディカルさにあるはずだ、とは到底言えるものではありません。それはいわば単なる一つの「蓋然性」にすぎないのであって、むしろそれと同様に、古さや伝統的な価値観の中にこそ真理は存在する、という可能性は否定できないのではないでしょうか。
かえって、歴史的に永らえてきたものにこそ、「真理」の片鱗が顕現しているとは言えないでしょうか。具体的に言えば、それは「伝統や文化」に現れていると見なされます。そして、ものごとの考え方や世界観・自然観もその一つと言えるかもしれません。
実際に、マルクスがシナリオを書き、レーニンが演出した「正統マルクス主義」というタイトルの共産主義の「舞台」は、「上演」から七十年にして、突如として「打ち切り」となりメジャーの舞台から姿を消しました。現在は閑古鳥の鳴く状況ながら細々と延命は続いていますが…。このように、「歴史の審判」というのは残酷と言えます。
マルクス主義は疑似科学だと喝破したポパー
カール・ポパー
I図にも科学哲学者として名を連ねるトマス・クーンは有名な「パラダイム」という概念を用いて、科学史における「真理と見なされる枠組み」の転換と変遷を説明しました。ここでも、科学的真理と言えるものすら、「歴史の審判」を受けるということなのです。
「画期的な発明」「革命的な理論」とうたわれるものは、確かに新奇さやラディカルさにおいて瞠目されはするでしょう。そしてそれは、思想としての「生命線」なのかもしれませんが、それを「自(僭)称」したがるものほど、実はあてにならなかったりします。
この点を厳しく追及したのが、「マルクス主義は疑似科学にすぎない」と唱えた科学哲学者カール・ポパーの「反証可能性」と言えるでしょう。
かように考えると、表面的には、あまりにも複雑で錯綜した「思想的回路」を解きほぐし、動機的本質にまで迫りながら、問題部分を摘出する作業が要るわけです。このような作業を通じ、何がわかるのかというと、まさに「図Ⅱ」のような、驚くべき「共通性」と言えるのです。
嫉妬の情念を掻き立てて正当化する
その唯物論、闘争理論、支配—被支配の人間観、抑圧的な社会・歴史観、それを解き放つ解放理論という、思想的骨格です。
先の八木教授はまた「ジェンダーフリー(注:男らしさ女らしさを否定し専業主婦を侮蔑する考え方)は思想的にはマルクス主義に原型があり……ポストモダン思想や新左翼の過激思想が入り込んでいる。そのためありとあらゆる左翼団体がかかわっている。旗を振っているのは七〇年安保の全共闘世代……ジェンダーフリーはいわばルサンチマン(怨恨)の思想で、源流にあるマルクス主義が憎悪の思想なのと同じだ。人間の妬みや嫉妬の思いを掻き立て、それを正当化する理屈を与える思想」と看破しています。
この怨みの情念は、まさにテロリズムにも通じているのです。
(「思想新聞」2024年2月1日号より)