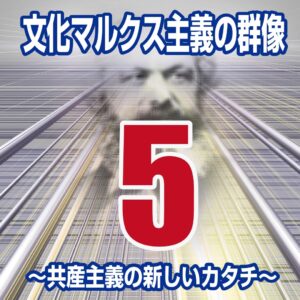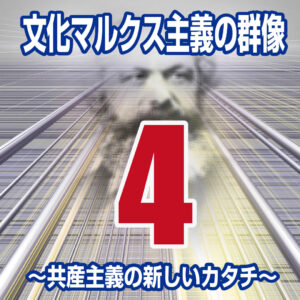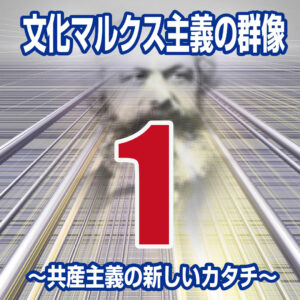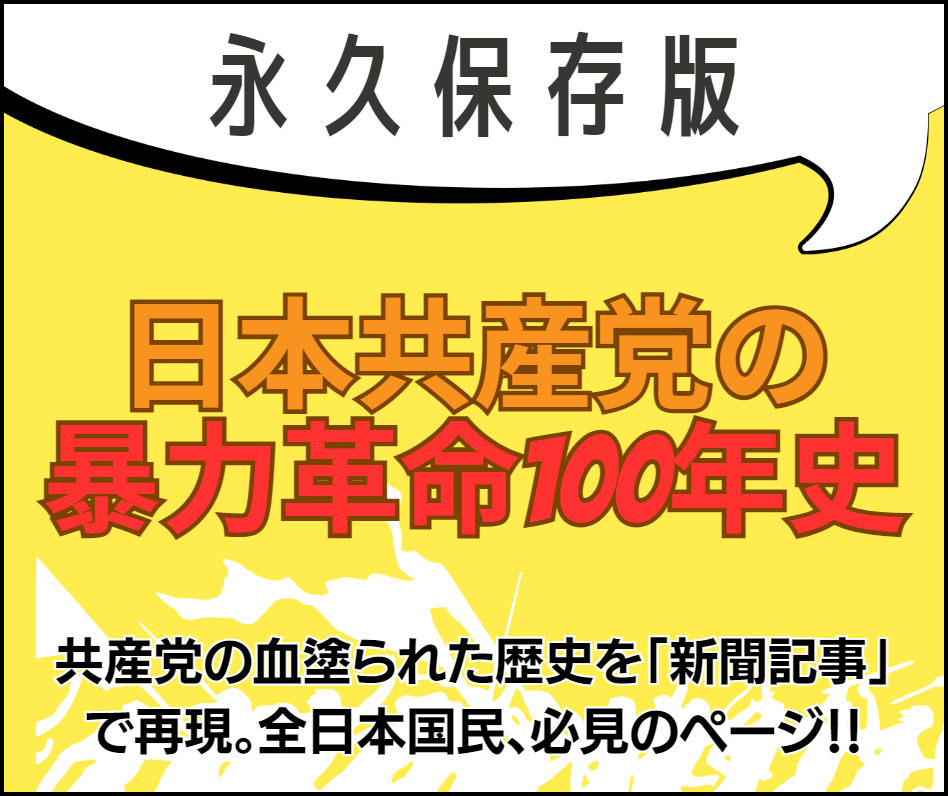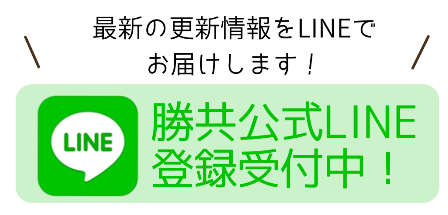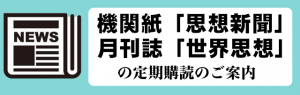「人間の獣化」と「反文明」
J・J・ルソー
「マルクス後」に入る前に、マルクス以前の文化共産主義者として欠かせない3人の思想家を取り上げます。まずレヴィ=ストロースが「人類学の父」と呼んだルソーです。
上智大名誉教授の渡部昇一氏は生前の講演で、1970年代の米国で「家庭の価値」が危機に瀕した理由の一つはジャン・ジャック・ルソーの影響だとし「戦後日本の左翼はマルクス・レーニン主義を背景に家庭の価値を破壊しようとした。このイデオロギーを仰ぎ見なくなった今、日本の家庭破壊論者が徹底するのがルソーの思想で……家庭が崩壊した人は自分が置かれる状況を正当化したいが為に、ルソー主義を振り回す」と警告しました。
また渡部氏は『教育を救う保守の哲学』の中で「家族の廃止!……両者(ブルジョワと家族)は資本の消滅とともに消滅する」と述べたマルクス/エンゲルスの『共産党宣言』だが、その原型となった世界最初の家族解体論はルソーの『人間不平等起源論』だと喝破しました。
渡部昇一氏㊧はルソー㊨の『人間不平等起源論』こそ、『共産党宣言』の家族解体論の原型だと指摘した
「孤児院送り」こそが育児の社会化の本質
「子育て支援=育児の社会化」政策が、「少子化対策」と位置づけられますが、育児を社会に「丸投げ」することは、子育てを通し「親」となり子を持つ「喜び」を放擲し絆を破壊し、子供を「孤児院」に送るのと変わらないのです。
しかしキリスト教倫理が支配的だった18世紀に、公然と「実践」したのがルソーその人です。カントが愛読し教育論や教育心理学で「聖典」視される彼の教育小説『エミール』も、実はトンデモない代物です。
渡部氏は「少年エミールは《親と別れて孤児になります》と先生に誓っていますから、親子切断を煽動していて、これも家族解体の書」と述べます(前掲書)。
元来、ルソー自身が「孤児」という境遇にあり、「家庭的愛情」とは無縁の人生を過ごしました。一見、説得的に見える『エミール』も、自分の境涯を正当化する論理が根底にあり、同時代の哲学者ヴォルテールは、「女に産ませた子供3人を棄ててしまった。エミール殿の教育に専念するため、またエミールを立派な指物師にするために」とルソーの「言行不一致」ぶりを痛烈に皮肉ったのです。
ところがルソーは、3人どころか女中あがりのテレーズとの間に生まれた5人をすべて孤児院に送りました。彼の弁解では、経済的余裕がなく、「子供が家にいると騒がしく文筆活動ができない」「子供は国家で教育され自分の父親を知らず全部が国家の子供になるのがよい」と、女性の社会進出を妨げるのが家事・育児と見なすフェミニズムと軌を一にするのです。
自分の出生で死別した母の影を追い求めたルソーの生涯は、破廉恥な醜聞に満ちていました。
若い女性の前で下半身を露出したり、知的障害女性をレイプし妊娠させる事件を起こしたり、書生を務めた家で窃盗するなど、揶揄では済まない奇行・犯罪を繰り返します。またルソーが献呈した『人間不平等起源論』を読んだヴォルテールは「あなたの書を読むと、四つ足で歩きそうだ」と書き送りました。つまり、同書は「獣化した人間」を「自然人」と美化し表現していると言えます。
「反文明教」がポル・ポトや反原発の狂気に
ポル・ポト
ルソーは『エミール』冒頭で、「万物をつくる者の手をはなれるときすべてはよいものであるが、人間の手にうつるとすべてが悪くなる」と述べます。同書のテーマは、罪なき無垢の存在として生まれた嬰児が、「悪に染まった社会」の影響を脱し教育することは可能かということです。
ルソーはアカデミーの懸賞論文に当選した「学問芸術論」で「学と芸術の進歩が人間を堕落させる」とし、次の『人間不平等起源論』は、人間の「自然人」としての立場を理想とし、文明が生じて貧富格差や階級、社会悪が生じたとします。堕落した社会から「自然人」としての本来性を回復するため神・自然などを排除し「人間の自由意志のみによって社会を築くべし」と説いたのが『社会契約論』で、人民主権の聖典としてフランス革命の理論的支柱となりました。
ルソーは「自然に帰れ」と唱えるも、その自然とはヴォルテールが「人間の獣化」と揶揄するほど知識人には受け入れ難いものです。実際、ルソーの『エミール』を読むと、首を傾げざるを得ない箇所が散見されます。例えば、子供が怪我や病気でも、医者にかかるなというのです。
この医療不信、というより「医師は人民の敵」と見なす恐るべき社会が現実に到来したのがポル=ポト率いるクメール・ルージュ支配下のカンボジアでした。
ポル=ポトは毛沢東主義に加えさらにルソー思想が大きな影響を及ぼし、インテリ階級を徹底殲滅したのです。だからインテリ層の人々が、「プロレタリアの敵」として粛清されました。
中川八洋氏は『脱原発のウソと犯罪』(日新報道)で、「脱原発」の論客・小出章氏の「種としての人間が生き延びることに価値があるかどうか…わかりません」との発言を、「小出は、『人間の死滅』すら是としている…レーニン/スターリンの《自国民六千六百万人殺し》につながる、最凶最悪の反人間イデオロギー」と断じ、ルソーとポル=ポトに結びつけます。
「自国民の人口をたった四年間で四分の一(二百万人)も殺した、カンボジアのポル=ポト共産政権の反・文明教を継承している。小出は史上もっとも恐ろしい、悪魔のドグマの狂信者である。……この文明社会を非とし、野蛮で原始時代こそ人間の理想郷だと、世界史上初めての奇説狂論を提唱したのがルソーである。実際にも、毛沢東もポル=ポトも、ルソーの『人間不平等起源論』の狂気的な信奉者であった。…(ポル=ポトら)狂気の共産主義団体は、国家権力を握ると直ぐカンボジア全土から郵便ポストも病院もことごとく破壊し一掃した。
全国の医者や大学教授は全員、すぐに殺された。病院や大学は、人間の幸福を害する文明という病原菌の発生源だとするルソーの教義に忠実に従ったのである。電気を含めて都市の文明的な社会そのものが、人間の幸福を奪う最大の悪鬼であり、この鬼退治こそ理想のユートピア社会を出現させる第一歩だとするルソーの狂気を、ポル=ポトは宗教的に狂信していた」
小出氏は、放射線被曝の福島県の「キケン」なイメージを、過剰なまでに増大・拡散させた点で、科学的見地からのものではない虚偽だと中川八洋氏は激しく糺弾するのです。
「反人間原理」としての文化共産主義思想
![]()
宇宙の始まりを考える際に援用されるのが「人間原理」という考え方です。
人間原理とは、有り体に言えばこの宇宙は「人間が住みやすいようにできている」という認識です。これは時に人間中心主義との誤解を招きます。宇宙そして地球には人間以外の生物ないし自然があることを軽視している、と見るからです。
さらに、人間原理のうちでも、「宇宙や地球の成り立ちは或る知的な存在により創造された、目的論的なプログラムが働いているとしか考えられない。確率的に限りなくゼロに近い《奇跡》のような宇宙、地球、そして世界が単なる偶然の産物と考えるにはあまりに精巧だから」とする考え方が、いわゆる「インテリジェント・デザイン」理論と呼ばれる説です。
日本では宗教的な「キワモノ」に扱われがちですが、ダーウィン以来の進化論が数多くのアポリアを抱える「仮説」ということを考えると、「アンチ進化論」の性格を持つことを認識する必要があります。「利己的遺伝子」で有名なリチャード・ドーキンス博士は「デザイン理論」より宗教文化そのものへの敵意を剥き出しにします。デザイン論者は必ずしも宗教的立場からの言明ではなく、文字通り「進化論帝国」に対する異論として唱える学者の方が多いのです。こうした「人間原理」的な考え方に、真っ向から反対する考えもあります。
ルソーに端を発する「エコ・テロリズム」で、「反人間原理」思想です。「人間の存在自体が罪」とする究極の自虐思想で、一種の文化革命です。脱原発で電力不足になろうが人間の業だから滅んでも構わない、という無責任なニヒリズムです。
反原発運動とは、まさにエコ・テロリズムです。ルソーは、子供を「自然のまま」に教育することを唱えました。これは現代のカール・ロジャーズらの非指示教育プログラムとして1960年代の米国に吹き荒れ、米国の教育を根底から揺るがし、英国でもラッセルやニイルによる実験学校にルソー主義が適用されたのです。
ルソーの問題点は、親身に子供のことを考え、子供の能力を発揮できるような教育を考えたのではなく、あくまで自分本位に「厄介払い」という自分の動機を正当化し、子供に「勝手気ままに」過ごさせる教育理論をぶち上げたことです。
だから理屈上では『エミール』は立派な人格を持った存在に成長するが、その通りに行った学校は、ラッセルの学校のように惨めな失敗に終わり、その事実は強調されねばなりません。
「エコ・テロリズム」の核心は「人間など罪深いから滅んでもかまわない」という信念。「滅んでもかまわぬ」という発想は明らかに信念を逸脱して狂信的です。イルカ・クジラ漁船や、食肉解体業者などへ時折見られる「テロ行為」は、人間への憎悪に基づくといえます。さて「人間原理」とは、人間の築いた文明を受け容れた上で世界や宇宙を認識していくと考えられます。だから自ら多くを享受しているはずの「文明を真っ向から否定する」ルソー主義は、「反人間原理」の思想だというわけです。
(「思想新聞」2024年2月15日号より)