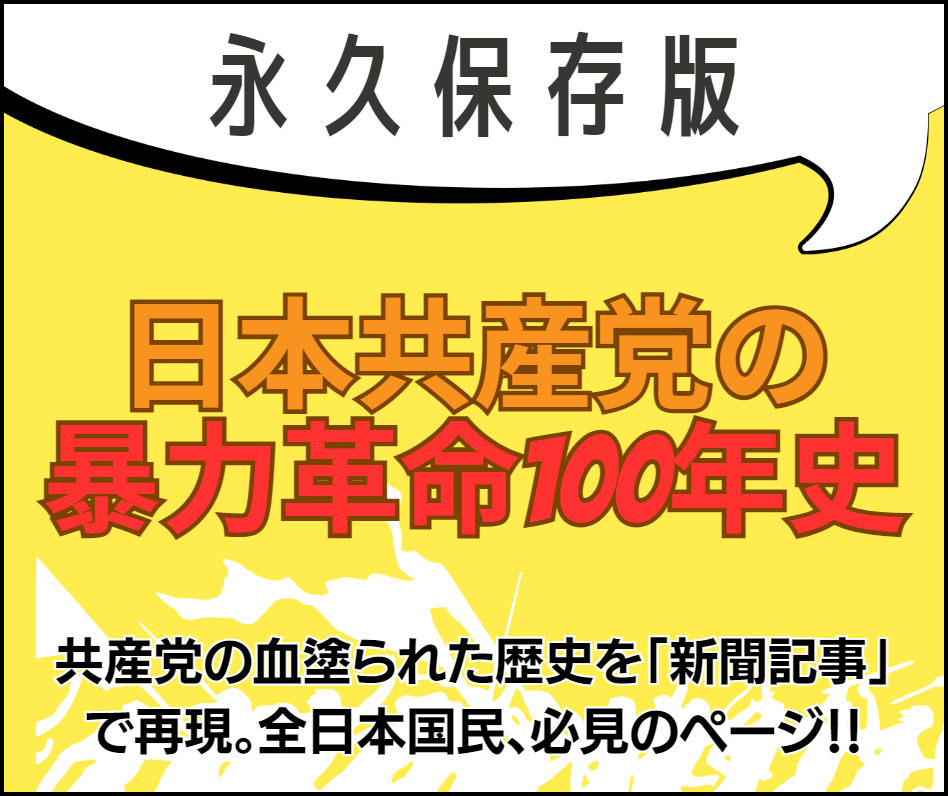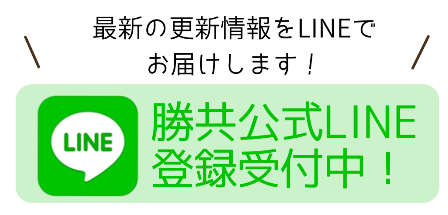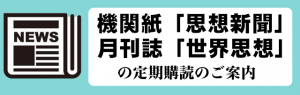「愛の思想」欠落で家庭に階級闘争を煽る
フリードリヒ・エンゲルス
米フェミニストのJ・フラックスは、「現代を特徴づける代表的思潮」として精神分析学・ポストモダン哲学・フェミニズム理論——の三つを挙げています(有賀美和子『現代フェミニズム論の地平』)。
この「フェミニズム理論」とは、「婦人参政権」を要求した「第1波」ではなく、1960年代以降のS・ボーヴォワールの『第二の性』に代表される「第2波」を指します。
つまり、近代における産業化の進展で「公・私の領域」の乖離をもたらし、男性を市場労働に従事させ、女性を無報酬の家事労働に従事させる近代的性別役割分業を生じ、それが固定化された、と見ています。ですから「専業主婦」として家庭という私的領域に囲われ、社会的役割を低下させた、という認識に立つため、今日の「フェミニズム」は、女性抑圧の廃止を、〈家族〉や〈産む性〉という基点に立脚し、近代社会構造や資本主義を問い直す女性解放論である、としています。
こう見ると、女権拡張の議論が「外」に向かうのではなく、なぜ「家庭」という「内なる領域」に対し仕掛けられるのかが、フェミニスト側からわかります。しかし、こうした第2派フェミニズムの主張する論理とほぼ重なるのが、実は別掲資料に掲げたエンゲルスの記述です。
これを見てわかるように、「最初の階級闘争」は「一夫一婦制としての家族」であった、というのです。エンゲルスはこの家族の問題から説き起こして、「国家」とはいかなるものか、に言及します。
![]()
母権制から父権制への「革命」
フリードリヒ・エンゲルス
さて、マルクス主義の手になる国家論を強いて言えば、先のエンゲルスの『家族・私有財産・国家の起源』です。そこでは次のように述べています。
「富が増加するのに比例して、この富は、一方では、家族内で男性に女性よりも重要な地位を与え、他方では、この強化された地位を利用して、伝来の相続順位を子に有利なように覆そうとする衝動を生みだした。しかしこれは、母権制による血統が行われている限り、だめであった。したがって、この血統が覆されなければならなかった。
そしてそれは覆された。これは決して今日我々が考えるほど困難ではなかった。なぜなら、この革命——人類が体験した最も深刻な革命の一つ——は、氏族の生きている成員のただの一人にも手を触れる必要がなかったからである。氏族の全ての所属者は、依然としてもとのままでいることができた。今後、男の氏族員の子孫は排除されて父の氏族に移ることにする、という簡単な決議だけで十分であった。これによって、女系による血統の算定と母方の相続権とは覆され、男系による血統と父方の相続権とが樹立された」
しかしエンゲルスはこの「母権制から父権制への移行」が「革命」と言いますが、その根拠とは実にお粗末で「我々は何も知らない。それは全く先史時代のこと」とうそぶきます。
さらに「母権制の転覆は、女性の世界史的な敗北であった。男性は家の中でも舵を握り、女性は品位を汚され、隷属させられて、男性の情欲の奴隷、子供を産む単なる道具となった」と文明社会=悪という思想に連なります。
エンゲルスが依拠したのはモーガンの記述やバッハオーフェンの「母権制に関する豊富な資料」、さらには、M・コヴァレフスキー『家族と財産の起源と進化の概論』などに限られ、その証明というと甚だ怪しいシロモノです。
エンゲルスの嫉妬克服論を批判した吉本隆明
一夫一婦制度とは無論、一人の男性と一人の女性というカップルが夫婦となり家族を営むシステムです。それが健全な社会通念・倫理観として存することは、そこに三角関係のような事態が生じれば、「不倫」(古い言葉で「姦通」)ということになるため明白です。この時、「不倫」された立場では当然「嫉妬」の情念にかられるでしょう。しかしエンゲルスは、「資料」(別掲)にあるように原始社会では「嫉妬は克服され」て「集団婚」が成立したというのです。
エンゲルスがいかに人間の愛や情念を軽視し、男女の関係を「性愛」「性交」といった即物的次元に還元してしまっているかが窺えます。その稚拙さを批判・指摘しているのが、吉本隆明『共同幻想論』のうち「母制論」の記述です。
同書は、安保世代や全共闘世代に多大な影響を与えた「国家解体論」としての性格を持っています。簡単に言えば、夫婦や家族、そして国家という観念は幻想だという考え方で、マルクス主義的に言えば「上部構造」にあたるもの。それらは「幻想」つまり、脆弱で不安定で曖昧なものだ、というニュアンスを伴うわけです。ここで注目すべきは、マルクスやフロイトの思想を日本的な文脈で敷衍することを企図した吉本氏ですら、辛辣な批判を加えているという点にあります。「人間は歴史のどの時期も嫉妬の感情から解放されたことはなかった」というその記述には、生物科学的視点と異なる文学歴史的なアプローチだという点はあるにせよ、どう見てもエンゲルスの人間理解には疑問を抱かざるをえません。
しかもマクレラン著『アフター・マルクス』(新評論)の以下の記述も、いわば内側からの非常に示唆的で重要な批判です。
原始的な諸社会における無規律性交や集団婚についてのモルガンの見解、並びに、母系の結縁集団の方が、父系のそれよりも年代的に先に成立していたという彼の見解が、極めて疑わしいものであるとするならば、家族に関する部分が、エンゲルスの書物のとりわけ一番弱い部分となっているのも、何ら不思議なことではない。それより奇妙なのは、彼が、種〔人間そのもの〕の生産と生活資料の生産とを徹底的に二分する、といったやり方をしていることである。例えば彼は、一夫一婦婚に関して、それは自然的な諸条件にではなく、経済的な諸条件に基づく家族形態の、最初のものであった、という見方をしており、また例えば、〔家族形態の進化の推進力に関しては〕、野蛮社会と未開社会とにおいては自然淘汰が働いていたのに対し、その後においては自然淘汰に代わって新しい社会的推進諸力が働き始めるようになった、として前者と後者とを対照的に処理する手法を採っている——こういったやり方は全て、経済的なものと社会的なものとの実に脱マルクス主義的な分断を措定するものであるように思われる。
![]()
「愛の思想」に欠けるマルクス・フロイト主義
階級社会で成立した一夫一婦制の「ブルジョア的結婚」は、社会主義革命でどうなるのか。エンゲルスは「[一夫一婦制は]消滅するどころか、かえって初めて完全に実現され」、それは「相互の愛以外にどんな動機も残らない」婚姻、つまり愛のみに基づく婚姻としました。また日本共産党も1946年の「日本人民共和国憲法草案」で「婚姻は両性の合意によってのみ成立し、かつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦制を基本とし、純潔な家族生活の建設を目的とする」とします。共産主義の提示する本来の結婚観は、真に夫婦の愛に基づいた家庭、純潔なる家庭の建設をめざすものというのです。
しかし、果たしてそんな理想がマルクス主義では実現しません。「富が溢れ自由な階級なき社会」をめざした社会主義革命が「富の枯渇し、自由が抑圧された新しい階級社会」を生みだしたのが現実でした。結婚と家族観においても、その理想と逆の結果をもたらし、ソ連社会が米社会と同様フリーセックスの蔓延と家庭崩壊が社会現象になりました。かつて70年代の「連合赤軍事件」で、「出産・育児は反革命」と烙印を押され、女性兵士が処刑されたのが現実なのです。
エンゲルスの主張も日本共産党「草案」も、根のない木であり、画餅にすぎません。原始共産主義社会は無規律性交のフリーセックス社会だったとの立場、そして一夫一婦制が経済的な搾取体制として成立したという立場からは、真実の愛による一夫一婦制度が成立するはずがありません。
エンゲルスは、フォイエルバッハが唯物論の立場から人間愛を説いたことに対し、「彼は下半身は唯物論者で上半身は観念論者であった」と批判しましたが、同じことがエンゲルスにも言えるのです。すなわち「エンゲルスは下半身ではフリーセックス論者であるが、上半身では一夫一婦制論者である」と。
故李相軒・統一思想研究院院長は「人間の始元が無規律性交の社会であるとするならば、原始共産主義社会の高次な形態であるという共産主義社会はより洗練されたフリーセックス社会になるというのが、必然的な結論ではないか。唯物弁証法の『否定の否定の法則』によれば、古い最初の段階(原始共産主義社会)が否定されて、新しい第二の段階(階級社会)になり、それがさらに否定されて第三の段階(共産主義社会)になるが、その時、第三の段階は、高次元的に、最初の段階に復帰するからである。性解放論者たちが、モーガン=エンゲルスの主張を受け容れながら性の解放を叫んでいるが、その結論はともあれ、彼らは理論的に首尾一貫しているのである。真の夫婦愛に基づいた一夫一婦制の家庭をめざすのであれば、それにふさわしい愛の思想が提示されなくてはならない」と『頭翼思想時代の到来』で述べるように、マルクス主義はもとよりフロイト主義・ダーウィニズムも同じく決定的に欠落しているのが、「愛の思想」にほかなりません。
(「思想新聞」2024年4月1日号より)