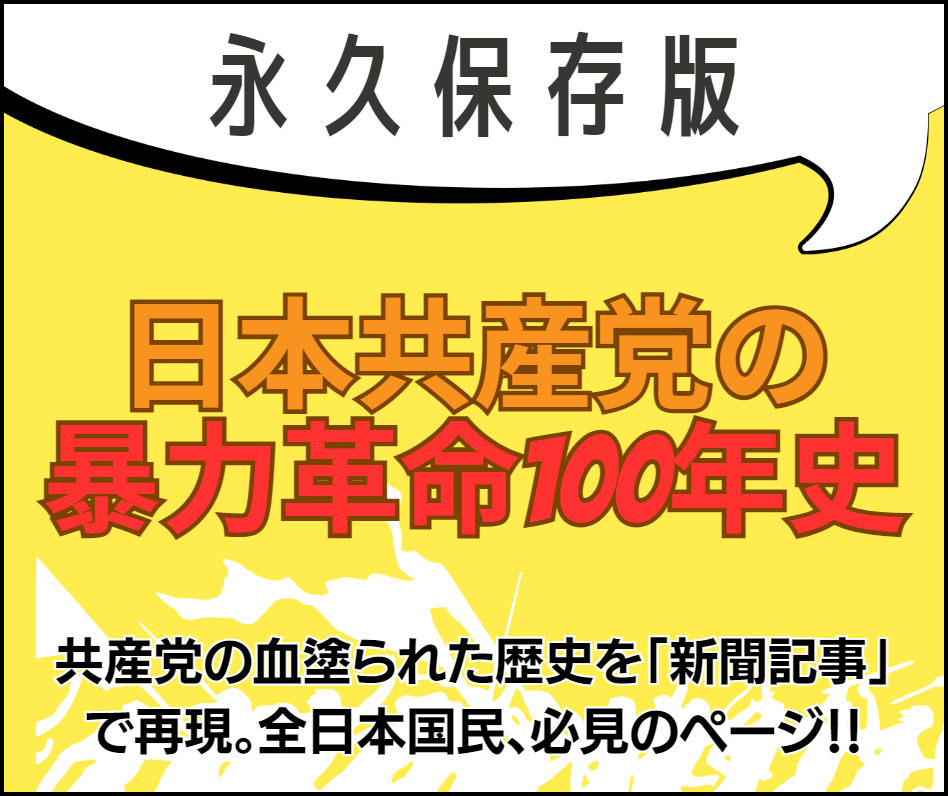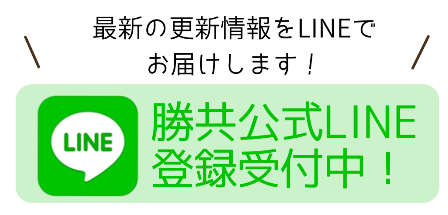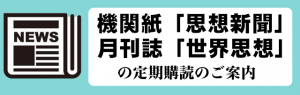「一夫一婦制」を破壊するフェミニズムの先駆
シャルル・フーリエ
「フェミニズム」という用語を初めて用いたのは、前回のマルキ・ド・サドと同時代のシャルル・フーリエ(1772〜1837)であると言われます。「科学的社会主義」を標榜したマルクスとエンゲルスは、フーリエの社会主義と実験的なコミューン(共同体)を、サン=シモンと同じ「空想的社会主義」と呼び、これを批判しました。
「情念引力」が人間行動を支配と考える
ところが実際には、エンゲルスの『家族・私有財産・国家の起源』が、米国の人類学者L・H・モーガンの『古代社会』に多くを負っているのと同等に、フーリエからも多大な影響を受けています。
例えば、『家族・私有財産・国家の起源』でエンゲルスは、フーリエの「一夫一婦制と土地所有は文明の主要特徴であり、文明は富者の貧者に仕掛ける戦争」という見立てを絶賛しています。空想的社会主義者のうちで最も過激でラディカルと言えるのが、フーリエの思想なのです。
商人出身のフーリエは、万有引力が自然界を支配するように、「情念引力(法則)」が人間行動を支配していると考えました。12種類ある情念は文明社会では抑圧されており、その抑圧から解放され情念が満たされることが幸福と見なしました。そして情念が満たされ、最大の幸福を得られた時に、生産力が飛躍的に上昇すると説きました。
フーリエは、それを実現する「理想の社会」として「ファランジュ」と呼ばれる「生活共同体」(アソシアシオン)を提唱しました。400〜2000人(1620人が理想とされた)の住民で構成されるこのファランジュは、一人1ヘクタールの農地を持ち、「ファランステール」なる共同宿舎で生活するという「生産と消費の自給自足の共同体」だと言えます。
またこのファランジュには、「情念の解放」のために「情念取引所」なるものを設けることで、労働や教育のみならず、「結婚」という性的制約を取り払い、「女性解放」「快楽充足」を保証すべきだとする事実上の「性解放社会」を主張しました。いわばエンゲルス以上に「文化共産主義の先駆」と言えるのです。
子供=騒音を発する厄介な存在と見なす
![]()
さて、図はフランスの構造主義哲学者ロラン・バルトの『サド、フーリエ、ロヨラ』において紹介した共同宿舎「ファランステール」の模式図です。図の左の部分、庭と耕作地にはさまれた「騒音:工房・鍛冶場・子供」という記載がありますが、これは唯物論的世界観を表明した証左、と呼べるでしょう。なぜなら、「情念引力理論による快楽至上主義の生活」からすれば、子供は「親や社会が愛情を傾けて育てるべき存在」ではなく、「堪え難い騒音を発する厄介な存在」と捉えられているからです。
フーリエは、育児の仕事を、「親から社会へ」と「アウトソーシング」(外注)するものと考えました。前々回のジャン=ジャック・ルソーも、5人の子供たちを「騒がしく執筆活動ができない」と次々と孤児院に送るなど「育児の社会化」を自ら「実践」して恥じなかった人物なのです。
構造主義者ロラン・バルトは、フーリエとマルクスに関しこう述べます。
「〈政治的なもの〉と〈家庭的なもの〉(これはフーリエの体系の名である)、科学とユートピア、マルクス主義とフーリエ主義、これは目の合わない二枚の網のようなものである。一方の側ではフーリエは全科学をするりと通り抜けさせ、マルクスがこれを採り上げ、発展させる。政治的観点からすれば(そしてとりわけ、マルクス主義がもはや消しえない一個の名を、彼に欠落したものに与えるすべを知ってからは)、フーリエは全くわき道にそれた、つまり非現実的で非道徳的な存在になった。しかしこれと向き合って、もう一つの網が快楽をするりと通り抜けさせ、フーリエがこれを採り上げるのである」(『サド、フーリエ、ロヨラ』)
こう見ると、バルトはマルクス主義の限界を「補完」する思想としてフーリエ思想を見立てたと言えます。
フランス・ギーズの「ファミリステール」
フーリエ思想が共同組合社会として具現
そしてフーリエの弟子たちを中心とする実践的共同体からは、名だたるフェミニストが現れました。出産をしても結婚をしない女性の生き方というものが、既に19世紀に「実践」されていたのです。
A・ミシェル『フェミニズムの世界史』では「ファランステール」について次のように説明しています。
「(フーリエの先駆とされ「空想的社会主義者」でマルクス=エンゲルスも言及する)サン=シモン主義は、改良主義の伝統につながるものであるが、女たちの間に新しい希望をかき立てる。……同棲の要求は、女たちにとって、愛と婚姻に関する伝統的な考え方に比べ、新しいものであった。女たちはそれを、ファランステール〔協同組合社会〕やコミューニティーの設立に参加して実践しようとする。たいていの場合、女たちがそこで自分の性に割り当てられた伝統的な役割を果たすとしても、例外はあった。例えば、1830年に創られたギーズの〈ファミリステール〉は、共同体の管理運営に女も平等に受け入れていた。
こうした試みは、ヨーロッパでは稀で一時的なものであったが、アメリカではもっと頻繁に行われた。例えば19世紀のアメリカで記録されたものとしては、72の宗教的な性格の、ないし人間主義的な視点に立つコミューニティーの他に、空想的社会主義の理論を体現する14のコミューニティーと、フーリエの理論に着想を得た約40のファランステールがある。なお、ファランステールは、すべて1840年に設立されている」
ここでもやはり、フーリエのコミューンが具現化し、特に米国において盛んになったのです。補足しますと、「ピアノの詩人」ショパンの「パトロン兼恋人」として知られる女流作家のジョルジュ・サンドは後にフーリエ的社会主義に傾倒するようになります。2月革命期の女性労働運動を組織した(後期印象派の画家ポール・ゴーギャンの祖母)フローラ・トリスタンもフーリエの影響を受けています。
かくして「子供=邪魔者」と見たフーリエは、具体的には何を重視したのか。それは「ファランステール」で繰り広げられる「パーティ」だというわけです。性解放の「性の自由」どころか、フーリエ理論では「(文明に毒された)一夫一婦制」が忌み嫌われ、半強制的に「パーティ」参加が義務づけられる「地獄」なのです。そこにフーリエの「怨恨感情」が窺えます。
こうしたフーリエの思想は、なぜこれほどまでに「実践的な成果」を得たのでしょうか。マルクスほどの「国家」や「権力」に対するスタンスはほとんどありませんが、社会や共同体については驚くほど細かな構想を持っていたのです。
そして、人間の「欲望」や「情念」に対する考え方は、むしろ「上部構造(精神的文化的営為)に対する下部構造(経済構造)の優位」にこだわったマルクス=エンゲルスよりも遙かに「フロイトの先駆」と呼べる点があるのです。
エンゲルスの『家族・私有財産・国家の起源』では、フェミニズムの基本原理とも言える、「家族における闘争」として、妻(被抑圧者)の家父長(権力者)たる「夫からの解放」を掲げていますが、フーリエはそもそも一夫一婦制を認めていません。
現代日本で、こうしたフーリエ的な考え方を表明したのが、フェミニズム界を牽引してきた上野千鶴子東大名誉教授です。彼女は「結婚とは相手に自分の性的自由(性器の使用)を独占的に売り渡すこと」と結婚を侮蔑しました。しかし近年、歴史学者の色川大吉氏と入籍していたことが週刊誌で報じられました。
左からシャルル・フーリエ、ジョルジュ・サンド、フローラ・トリスタン
一夫一婦は狭量だとし愛を性に還元
フーリエにおいては「愛」の概念が「性愛」「快楽」といったものに矮小化されてしまうのです。ですから「特定のカップル」の考え方は「狭量な利己的な愛情」のように還元されてしまうのです。
しかし世の多くは、一夫一婦制が多いのです。それは何もキリスト教に限りません。イスラム教も元々は、戦争で夫を失った寡婦が路頭に迷わないためにムハンマドが一夫多妻を認めたという経緯があります。
フーリエの思想は、なぜ男女の愛が排他的でなければならぬのか、「博愛」のように愛してみよ、という「悪魔の挑発」のようにも思われます。
そもそも一夫一婦制の根拠は、男女の愛を起点として築かれた家族が、子や孫という生命のつながりを目撃し、確認し育む場と社会が認めてきた伝統的倫理観にあると言えましょう。
しかしそうした発想が、フーリエの共同体には全くありません。生まれた子供は確かに「共同体の子」として育てられるでしょう。ところが家族概念もなくなれば、「責任」もなくなります。親が親となる機会を失うことにもなるのです。
確かに今日、育児ノイローゼの母親や、知識の乏しい父親の無理解で、夜泣きなど「騒音」を理由に、わが子を手にかける傷ましい事件が起きたりします。しかしそうした苦労以上の「喜び」が子を持つことで得られるからこそ、世には多くの家族が営まれているはずなのです。上野氏らの説くラディカル・フェミニズムもまたこれらを「厄介」としか考えないのです。
(「思想新聞」2024年3月15日号より)