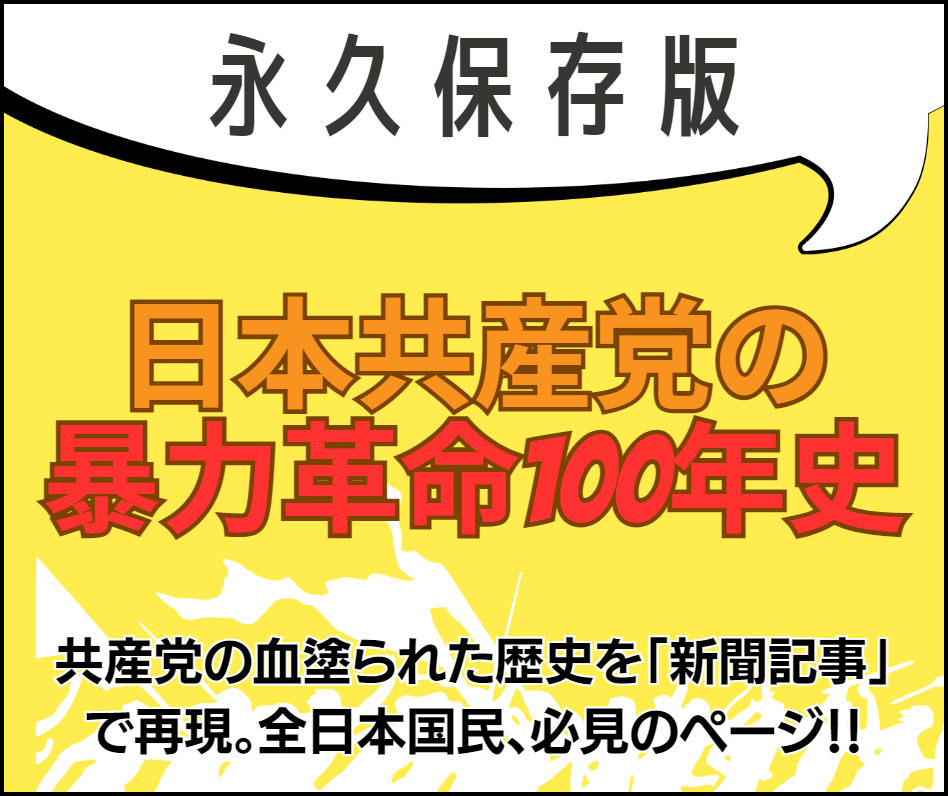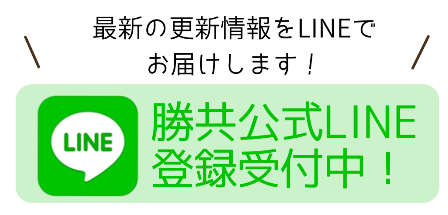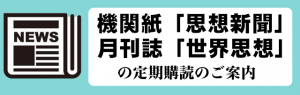「良心の呵責」棄てる「獣性」
マルキ・ド・サド
政治体制の転覆を目指すマルクス=レーニン主義に対し、「文化」など「上部構造」と呼ばれる精神的営為を破壊することでより簡単に「革命」が可能となるとするのが、「文化マルクス(共産)主義」「ユーロコミュニズム」です。その中核を担ったのが、フランクフルト学派です。その中心人物こそ、ホルクハイマーとアドルノという2人のユダヤ人哲学者でした。
ルカーチの『歴史と階級意識』を範としホルクハイマーとアドルノが構築した「批判理論」を2人の主著として展開したのが『啓蒙の弁証法』です。
ホルクハイマー(左)とアドルノ(右)
情を排した道徳法則を説いたカント
ホルクハイマーとアドルノが同書で問題提起するのは、19世紀から20世紀にかけ、西欧の哲学界ではヘーゲルと共に絶大な影響力を与えたドイツの哲学者カントの提起した「啓蒙」という概念と定義を批判し、そこから倫理道徳観を生み出す文化そのものを否定することを企てるのです。
カントは『啓蒙とは何か』で「啓蒙」の本質を「他人の指導を必要としない悟性」と定義しますが、これはいわば「自己決定」できる能力、「自律性」です。
ところがこのカントを批判するために、ホルクハイマー=アドルノは同時代人のサド侯爵(マルキ・ド・サド)を「ポスト近代西欧合理主義」の「先駆者」にまつりあげます。カントの批判哲学は「理性の限界を示し、信仰に場所を空ける」というキリスト教道徳と親和性のある哲学でした。
ホルクハイマー=アドルノは『啓蒙の弁証法』で、サドの小説『ジュリエットの物語、あるいは悪徳の栄え』を援用し、その宗教擁護的な倫理道徳観を徹底批判するのです。
サドはサディズム(加虐性愛)の語源として知られますが、貴族でありながら不品行の罪でバスティーユ牢獄など長らく獄中生活を送りました。その獄中で書かれた作品は、当時、カトリックによる宗教的支配体制下にあった大革命前のフランスで唯物無神論を唱え、あらゆる性道徳・倫理観を踏み超えるものです。「性愛の機械的快楽」を追求しあらゆるタブーが無効にされる「放蕩の規則」が示されます。
ルカーチの『歴史と階級意識』の影響下から「フランクフルト学派」として独自の路線に踏み込んだのが、ホルクハイマーとアドルノの共著『啓蒙の弁証法』です。これはカントの啓蒙概念・倫理思想と対比する形でサドの「悪徳の哲学」の「意義」を蘇らせ、フロイト精神分析学をも援用し学術横断的に体系化に向かおうとするものでした。
カントは「ここに二つのものがある。それは││我々がそのものを思念すること長くかつしばしばになるにつれて、常にいや増す新たな感嘆と畏敬の念とをもって我々の心を余すところなく充足する、すなわち私の上なる星をちりばめた空と私の内なる道徳法則である」と『実践理性批判』で述べるように、「内なる道徳法則」こそがカント倫理学の中心概念でした。
ところがその「内なる道徳法則」には、実は重大な「弱点」とでもいうべきものがありました。それは、内なる道徳法則により行われるべき「実践行為」というものは、感情・愛情などの情念で左右されてはならない、と厳密に規定したことです。このことは何を意味するのでしょうか。
カント倫理学の問題は、端的に言うと、東洋の儒教で性善説を説いた『孟子』の「惻隠の情」を否認していることにあります。この惻隠の情とは、ズバリ「同情」と言えますが、「人間は誰でも、他人の悲しむ姿を見すごすことのできない同情心がある」ということで、「思い遣りの心」とも言い換えられます。『孟子』にも出てくる喩えですが、子供が井戸に落ちた、といって人間は誰でも救おうとする、無意識の「善なる心」があるというわけです。
ところが、カントの説く倫理学ではこうした「情にほだされた行為」は、結果として良かろうと悪かろうと、認めません。確かに、子供を助けようとすることによって、自分の名誉を得たいという動機があった場合、カントにとっては極めて不純な動機による行為でしかありません。
このように、自己の意思決定において「感情」「情念」を持ち込むことを徹底的に排除したのがカントの「道徳法則」でした。
さて逆に、このカントの「非情さ」を逆手に取ったのが、実はサドにほかなりませんでした。恐らくサドこそ、フロイトの精神分析で正面から取り組むようになった「快楽犯罪」について、動機や心理的メカニズムから初めて記述した人物なのではないでしょうか。
「非情さ」逆手に良心の呵責捨てる
『啓蒙の弁証法』では、サドの記述を次のように紹介しています。
◇
サドの作品は、ニーチェのそれと同じく実践理性に対する仮借のない批判を形づくっており、それに比べれば一切の破壊者[たるカント]自身の批判さえ、自己の思想を撤回するもののように見える。仮借ない批判は、科学的原理を破壊的な原理に高める。言うまでもなくカントは、『我が内なる道徳法則』を既に各種の他律的な信仰から純化してきたのだが、その勢いの赴く所、『尊敬』はカントの保証に反して、『我が内なる星空』が物理学的な自然事実となったと同様、単なる心理学的な自然事実になってしまった。カントはそれを自ら『理性の事実』と名付け、ライプニッツではそれは『社会の一般的本能』と呼ばれていた。しかし事実は、それが存在しないところでは妥当することもできない。
サドは事実の現前を否定しはしない。二人姉妹のうち善い方のジュスティーヌは、道徳法則の殉教者である。ジュリエットは、もちろん市民層が避けようとした帰結を引き出す。後女は最新の神話としてのカトリシズムを、そしてそれと共に文明一般をデーモン化する。かつて秘蹟のために捧げられていた諸々のエネルギーは、そのまま向きを変えて聖物冒涜のために費やされるようになる。しかしこういう転換は、そのまま社会の上に移される。こういった全てにおいてジュリエットは、決してカトリシズムがインカ人たちに示したような狂信的な態度を取りはしない。彼女は、カトリックにとって古代以来血のうちに潜んでいる聖物冒涜の作業を、啓蒙された態度で熱心に片づけるだけである。文明によってタブー化された先史時代の行動方式は、獣性の烙印の下に破壊的な方式へと姿を変えて地下の存在を導いてきた。ジュリエットはそういう行動方式を、もはや自然的なものとしてではなく、タブー化されたものとして実行する。彼女はその方式に対する価値判断を、それと反対の価値判断によって埋め合わせる。彼女がそういう仕方で原始的な反応を繰り返すとすれば、それ故にそれはもう原始的なものではなく獣的なものである。
(『啓蒙の弁証法』)
◇
ニーチェが「神は死んだ」と『ツァラトゥストラ』で唱えたのは有名ですが、サドはそれに先立ち、主人公ジュリエットに「死せる神ですって! カトリックの辞書に出てくるこういう自己撞着した言葉の組み合わせほど滑稽なものがまたとあるでしょうか。神とは即ち永遠の意味であり、死とは即ち永遠ならざるの意味ではありませんか。たわけたキリスト教徒たちよ。あなた方はいったいあなた方の死せる神をどうしようというのですか」と言わせたり、別の登場人物には「犯罪を犯すのに何か口実が必要だとでも言うのでしょうか」と言わせています。
「神の場所」に悪魔を座らせたサド
![]()
カントの「道徳法則」に感情を介在させない非情性が、結果的にナチズムをしてユダヤ人のホロコーストを招いた、と意義づけようとしたのがホルクハイマーとアドルノの「ルサンチマン(怨恨)」だったのではないでしょうか。
人間の行動を感情や性向よりも理性の支配に置こうとしたカントの「道徳観」を逆手に取り、サドは「神や死せる神の子への信仰、十戒の遵守、悪に対する善の優位、罪に対する救済の優位など、その合理性を証明できないものを崇拝することは、身の毛のよだつほど厭うべきこと」と捉えたのです(小牧治『ホルクハイマー・人と思想』)。
この態度が招来するものは、旧約聖書の「モーセの十戒」に「殺すな」「姦淫するな」「盗むな」とある戒めは、サドにとっては単なるイデオロギーに過ぎないと、『啓蒙の弁証法』で断じているのです。
先述した『孟子』の「惻隠の情」は、まさに「良心の呵責」であることがわかります。カントは「情」ではなく「(実践)理性」に信頼を置こうとしましたが、「内なる道徳法則」とは実は「良心の呵責」に他なりません。「同情」は、サドとニーチェが最も嫌ったもので、犯罪を重ねて行き着く「良心の呵責からの自由」は恐るべき「荒漠たる獣的世界」と言えます。
要するに、フランクフルト学派にとり「人間の倫理道徳観に影響を与える宗教」を打倒しようとしたサドを「ニーチェの先駆者」として祭り上げていることがわかるのです。
ミシェル・フーコー
この「サド賛美」は後に、フランスのミシェル・フーコーが『狂気の歴史』で「エピステーメー」(知の枠組み)における「近代の開拓者」と位置づけます。「サドは単純に神を否定する無神論者ではない。……彼は表象の空間の自律性の前提となった不在の神、正確にはそのような神の場所を確保する。だが、それはその場所に悪魔を座らせるためである」とフーコー解説書で指摘されるのです(内田隆三『ミシェル・フーコー│主体の系譜学』)。
(「思想新聞」2024年3月1日号より)