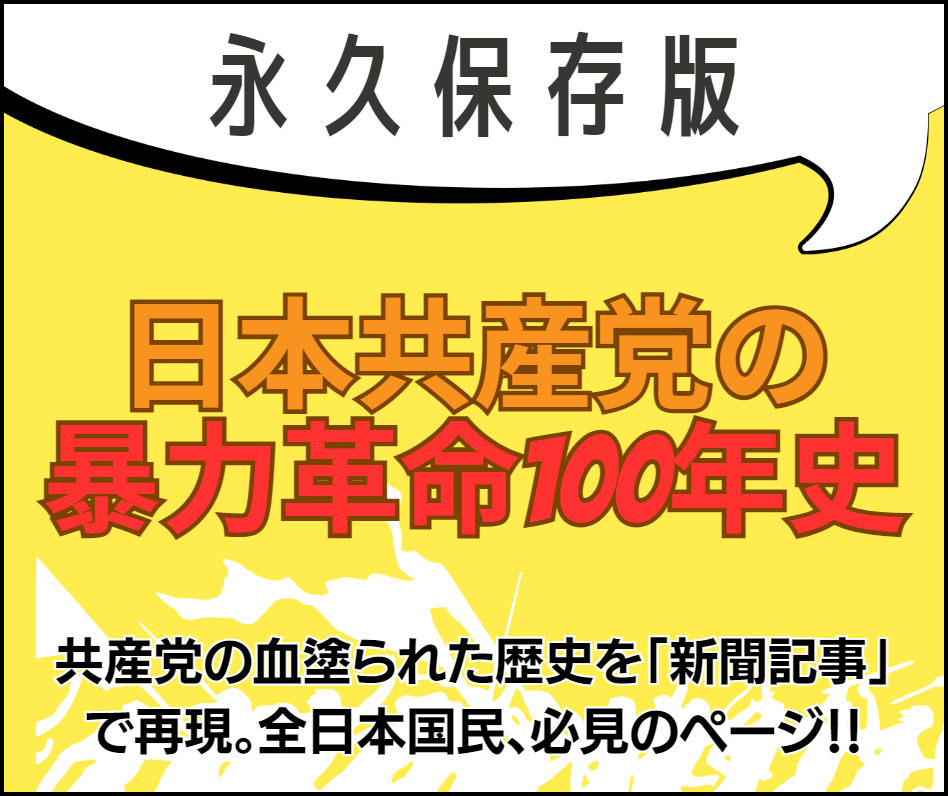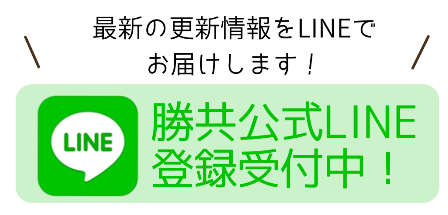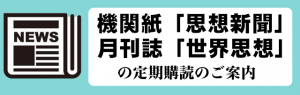宗教的倫理性に「心の自由の砦」を発見
独社民党と第2インター《下》
マックス・ウェーバー
マルクス没後、有力な後継者の1人だったはずのエドワルト・ベルンシュタインは、スイス、英国と亡命生活を送る中で「社会民主主義」、いわゆる「修正主義」に傾いていきます。『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』でマックス・ウェーバーが幾度もベルンシュタインの論文を引用したことが象徴的です。
そのベルンシュタインの論文とは、英国のピューリタン革命とフランスの2月革命とは全く性格が異なる点を指摘したことで、「宗教」や「信仰」のもつ「自由の深淵」に触れたためと結論づけることができます。これに関するA・リンゼイのピューリタニズム分析は後述します。
「修正主義」の烙印押されたベルンシュタイン
さて、英国からのベルンシュタインの報告を社民党急進派のローザ・ルクセンブルクは「英国の眼鏡をかけ世界を見ている」と批判、そうした見解が党の大勢を占め、1903年のドレスデンでの党大会でベーベル、カウツキー、ローザ・ルクセンブルクらの激しい非難により、ベルンシュタインの「修正主義」が公式的に「異端」の烙印を押されることになったのです。
ベルンシュタインら修正主義派の見解に対し、最も重要な反対論を展開したカール・カウツキーは、ベルンシュタインと並ぶマルクス・エンゲルスの「後継者」と見なされました。ウイーン大学に学び、1875年にオーストリア社会民主党に入党。ベルンシュタインと同様社会主義鎮圧法を避け85年にロンドンでエンゲルスに師事。91年に『エルフルト綱領』を起草、エンゲルス死後、第2インターナショナルの思想的代表者にして党理論誌『ノイエ・ツァイト』編集者として、30年間もマルクス主義に立つ全知識人の中心的・権威的な位置を担いました。
ロシア革命後、ボリシェヴィキを痛烈に批判、レーニンと対立し、今では共産主義の「傍系」とされます。しかし当時は、レーニンを遙かに上回る正統派マルクス主義の中心人物で「マルクス主義の法皇」とも称されたのです。
資本主義崩壊論と帝国主義分析
そこでベルンシュタインとカウツキーとの立場の相違に触れてみましょう。第一に、経済的観点からです。ベルンシュタインはマルクスの労働価値説に疑問を呈し、単に「思考上の公式・科学上の仮説としての妥当性」しか主張しえない机上の空論だと断じました。
労働価値説は、使用価値と交換価値のうち、真の価値は固有な使用価値ではなく普遍的に交換できる交換価値にあるとし、尺度を労働時間に据えます。価値は労働により生じ、そこから剰余価値(利潤)が生まれるも資本家が独占するのがマルクスの立場です。
しかしベルンシュタインはこれに異を唱え、効用性にも価値ありと批判。
ベルンシュタインは、急激な労働賃金上昇で「労働貴族」が形成され19世紀末に現れ出した経済的活況に、資本主義が「自己制御能力を高めつつある」と分析。マルクスの言う「資本所有の集中」はなく、所有権や資本家の数は増大するとし、「社会の発展は有産者数の相対的減少を、況や絶対的減少を示していると考えるのは全くの誤り」とマルクスを退ける結論を下します。
対してカウツキーは、カルテル・トラストなどの現象が資本主義の自己制御能力と見なすベルンシュタインとは対照的に、「資本主義の老衰」「崩壊の兆候」とし、これに「帝国主義的分析」を加味。この分析はレーニンにより批判的に継承されます(帝国主義論)。
第二に、社会階級の分析です。ベルンシュタインにとり階級は「生活状態の類似をもって主たる形成原理とする社会層」とし、しかも「中間階級の規模は拡大の傾向をもつ」ものです。むろん、ブルジョワ階級とプロレタリア階級との宿命的「権力闘争」を説く本来のマルクス主義にとり「新中間層」の出現は都合悪いものです。カウツキーはこの中間階級を認めつつ、最終的にプロレタリアート側で階級闘争に参加するとしました。
また、カウツキー思想の特徴として、私的所有の観点から農民層の利害とプロレタリアートの利害とは対立する点が挙げられます。プロレタリア革命の過程では当然、小土地所有という点で農民層は消滅する運命だと見なします。これはレーニンが称賛し、革命後に土地の国有化による「国営農場・集団農場」体制という名の新たな「農奴制」を生むことになります。
![]()
階級闘争というマルクスの教義
第三には、政治戦略についてです。カウツキーら正統派の立場は、「資本家階級の利益と労働者階級の利益とは両立し得ず、『国民的利益』というものは全く存在しえない」。ゆえに政治闘争でもプロレタリアートは独自路線を歩むべきだとします。しかしベルンシュタインはあくまで、①労働価値説を放棄すること②資本主義崩壊の信仰をやめること③中間階級の成長に注目すること——に拘り、「社会主義とは、十分な発展を遂げた資本主義の後を継ぐ多少なりとも平和的な制度」としました。
A・D・リンゼイ
一方、カウツキーは民主化や環境改善などの改良実践活動は重視するも、党活動を改良運動に終始することは誤りとし、生産手段の資本主義的私有所有の社会的所有への転化は革命でのみ可能——即ち、プロレタリアートが政治権力を奪取しての国家の根本的変革が最終目標でした。
こうした立場にも拘わらず、後にカウツキーがボリシェヴィキ暴力革命を批判したことは、ある意味正当なものですが、当事者からすれば、ジレンマに満ちた煮え切らないものと映ったでしょう。
彼がヒューマニズム的良心をもっていた証拠に、倫理と理念の問題について、「プロレタリア階級闘争組織としての社会民主党は、道徳的な理想や搾取や階級支配に対する義憤がなければやっていくことはできない。しかるにその理想は、科学的社会主義からは何らの援助も受けられない」と本音を吐露しています。
こうしたカウツキーとベルンシュタインの論争は、レーニンの前衛党論の共産党組織観からすると到底共存は許されません。ですが当時ドイツ社民党は緩やかな組織であり、1903年の党大会でベルンシュタインの修正主義は圧倒的多数で否認されたにも拘わらず党は分裂しなかったのです。カウツキーが改良活動を否定せず、「プロレタリア独裁」を議会民主主義的な支配と見た点も、さほどベルンシュタインと違わないとも言えます。
しかし、ダーウィニズムを援用し科学的社会主義を重視した彼らでも、ベルンシュタインは科学的決定論には断固として与せず、「真に自由主義を擁護するものこそ、(自らの唱える)真の社会民主主義である」と持論を貫いています。
英オックスフォード大副総長を務めた政治学者A・D・リンゼイは『民主主義の本質』の第二版序文で、「マルクス主義はホッブズの考え方そのものである」と述べました。このように、17世紀英国の哲学者トマス・ホッブズは、人間の自然状態における本性を「万人の万人に対する闘争」という性悪説を説き、機械的唯物論を唱えました。既にホッブズにおいて人間精神の営みというのは副次的なものにすぎないのであり、物質に還元できるとしていたのです。
ベンサム哲学に似る中国の体制
また、それは共産主義・社会主義という体制下のみに生じるものではなく、資本主義的自由主義においても十分に起こりうる、これを説いた点で、現代的な意義をもった「警鐘」としてあり続けています。
さてリンゼイは、「イギリス功利主義」の哲学者、ジェレミー・ベンサムもまた、「誤った民主主義」を説いたと看破しています。「最大多数の最大幸福」というテーマを掲げ、「幸福を数量的に計測することができる」としたベンサムの思想を、ある意味で「多数決の原理=民主主義」として理解する向きは少なくないでしょうが、まさに「逆立ちしたマルクス主義」そのものと言えるのです。
それはなぜでしょうか。中川八洋氏はベンサムを「極左で全体主義の理論家」と非難します(『保守主義の哲学』)。ベンサムは保守主義の政治思想家バークとは正反対に、フランス革命を諸手を挙げて支持しました。彼の思想の本質は、経済面での「自由放任主義」にも拘わらず、国民を監視し「幸福の強制」を行う全体主義なのです。ある意味、現在の中国の社会状態を予見しているとも言えます。儒教的倫理観を失った現代中国で、拝金主義が横行しているとよく指摘される点です。ですからリンゼイも、ベンサムやホッブズの思想を「精神的な祖先」としてマルクス主義と共有している、と説いているのです。
リンゼイの指摘する人間の自由を認める「真正民主主義」と「似非民主主義」という二つの流れをチャートに表したのが下図です。
人間の心には理屈で納得できる部分と非合理な部分があります。非合理面を極大に解釈したのがフロイトですが、それを制御しようと働くのが宗教的倫理性です。これを除けば秩序は崩壊するので、必然的にホッブズ・ベンサム・マルクスの監視社会になります。この意味で、宗教性とはまさに「心の自由の砦」であることがわかります。
![]()
(「思想新聞」2024年5月1日号より)