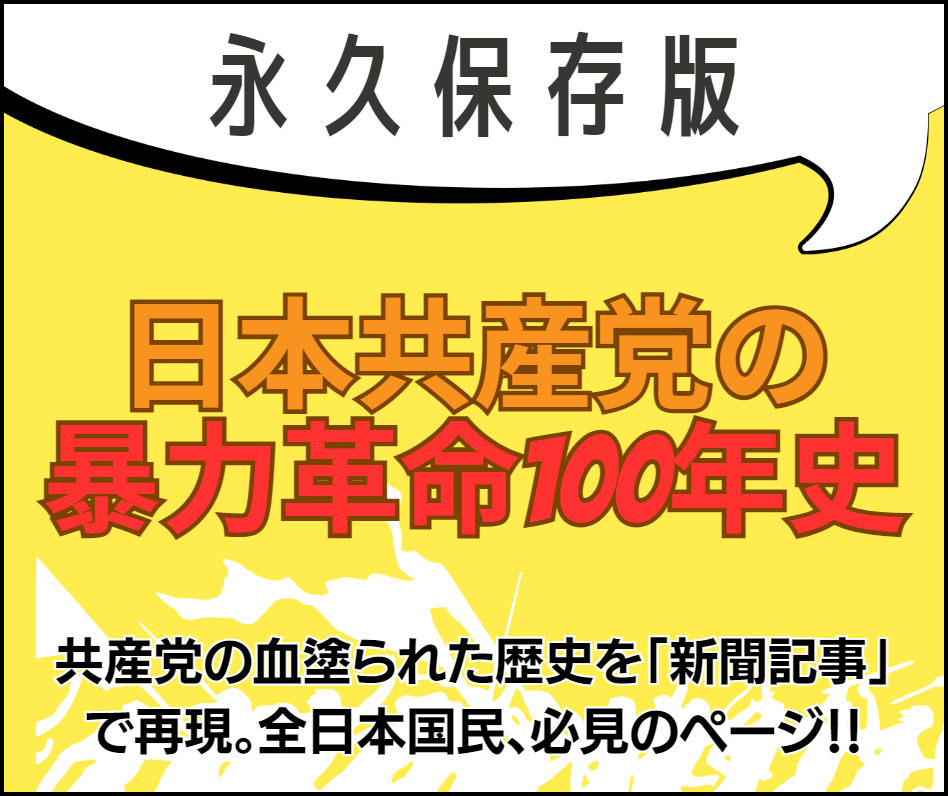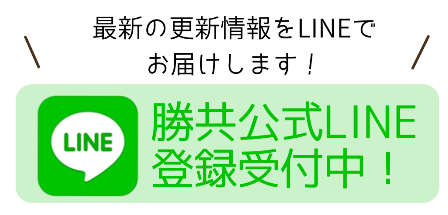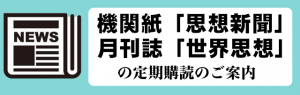「全権力をレーテに集めよ」と唱える
スパルタクス団
大衆路線をリードしたR・ルクセンブルク
ローザ・ルクセンブルク
マルクス没後からボリシェヴィキ革命後レーニンの圧倒的な影響下に1919年「コミンテルン」(第3インター)が結成されるまでの30年間、ドイツ社会民主党(SPD)を中核に国際共産主義・社会主義運動を担った「第2インター」はエンゲルスの庇護で1889年に結成。が1900年パリ大会で「社会主義者は(戦争反対のような)形而上学的な宣言にとどまるべきではない。具体的国際的抗議行動を」と演説、大衆的政治闘争路線をリードしたのが、ローザ・ルクセンブルクでした。
さてSPDの路線対立は、党創設以来、革命か改良か、という点にありました。ベルンシュタインの「修正主義」は1903年の党大会で否定され、論争は形を変え、ドイツに留まらず全欧で戦争と帝国主義をめぐり展開。07年シュトゥットガルト大会で、左派のフランス代表が「ゼネストで戦争勃発阻止」を主張、植民地絶対否定論を展開。対して右派は、国内の改良で戦争が防げるとし、また植民地自体の否定ではなく、植民地行政を改革することで文化的向上が可能と主張しました。
この大会では、ロシア代表レーニンの革命論が通った一方、右派の植民地改革論が採用され、矛盾をはらむ妥協に。SPDは穏健派が支配的で、当時のドイツは後発資本主義国として世界進出を目論むも包囲網に悩み、ロシアへの警戒感が強かったのです。
1907年の総選挙後、SPDでは、商工ブルジョアと連携し民主化を図れとする「改良派」に、「正統主義」を奉ずる「綱領派」は、それを妥協だと批判。連携は覇権的膨張主義のヴィルヘルム2世体制の片棒を担ぐ、と考えたのです。
この情勢に左の立場から提起したのが、ローザ・ルクセンブルクです。「自発的な大衆デモやストライキこそ革命の原動力」と捉える「大衆ストライキ論」を掲げた彼女は、労働者に「共和国」の目標を与えデモを政治闘争化する好機到来、と訴えました。
ところが綱領派の首領・カウツキーはこれを「急進主義」と批判。カウツキーによれば革命は、①支配体制に対し国民大衆が決定的に敵意を持つ②大衆組織を持つ非妥協的な一大反対政党が存在する③党が国民大多数の利害を代表し、信頼を得ること④支配体制の力と安定性に対する信頼を、その官僚制度と軍隊自体が崩している——この4条件が満ちると革命が成るとしたのです(『権力の道』)。
ドイツは帝国主義に走り「条件」が整いつつあるが、いまだ決定的時期は到来していない。条件が満ちるまで権力とは妥協せず、ローザらの説く急進的挑発に陥るなとの立場です。「柿は熟すれば落ちてくる」が正しいマルクス主義だ、というカウツキーの主張を支持する党員らは、「中央派」と呼ばれます。
こうしてSPDは、「改良派」と「急進派」、「中央派」の3派に分裂。ただし、3派とも党内に留まったものの、党執行部の実権は改良派が握っていました。というのも、12年のドイツの帝国議会選挙で社民党では改良派が議席数を伸ばし1人勝ちしたからです。
第1次世界大戦の背景とドイツ社民党
第2インターの最後の「クライマックス」とも言える第1次世界大戦は人類史上初めて「総力戦」という概念が登場した戦いでした。直接の引き金となったサラエボ事件(オーストリア皇太子夫妻暗殺事件)は、充満したガスに火を付けたにすぎなかったのです。
ところが大戦勃発時、SPDは「決議」通りに動きません。むしろレーニンのように「戦争を内乱へ、内乱を革命へ」と戦争勃発を歓迎したほどです。対してドイツ社民党は、逆に政府の戦争遂行に協力「速やかな終結」をめざしました。
ドイツの国論が二分するようになり、SPD「与党化」に反対する党内中央派や急進派は、新たなグループを結成します。
急進派幹部2人がスパルタクス団を結成
カール・リープクネヒト
ローザ・ルクセンブルクとカール・リープクネヒトは、党内に「インターナチオナーレ(国際)派」をつくり党執行部批判を強め、さらにローザは16年1月、非合法の「スパルタクス団(ブント)」を組織して過激な街頭闘争を展開。社民党に所属する国会議員の主張も分裂し、戦争予算に反対する党執行部反対派は、「社会民主主義共働団」という別個の会派をつくって対抗しました。
これに対し最高実力者エーベルトを中心とする党執行部は、あくまで政府による「上から」の改革を図ろうとし遂に、執行部反対派を党組織から「追放」してしまいます。
そこで追放された中央派と急進派は17年4月に「ゴータ会議」を開催、新たに「独立社会民主党」を結成。この党には、軍事予算に反対する平和主義的改良派のベルンシュタインも加わり、スパルタクス団も非合法組織を温存したままで参画。ここに至り戦時下の階級闘争が再開され、議会主義的な政府反対派が登場。が、労組をはじめ多数の国民は、あくまでも従来の社会民主党を支持、独立社民党は少数派として影響力は弱かったのです。
ドイツ革命の「殉教者」と見なされる
14年7月のドイツ議会におけるSPD代表としてフーゴ・ハーゼ(中央派)が対露戦争を支持する演説をし、「ブルジョア的ナショナリズム」に跪いたと映り、「国際派」を自任するスパルタクス団のローザ・ルクセンブルクとカール・リープクネヒトらは、独立社会民主党に属したものの、孤立を深めます。
カール・リープクネヒト(1871〜1919)は、社民党創設者の1人で国会議員を30年務めたヴィルヘルム・リープクネヒトの息子。社民党急進派に属し、第1次大戦下の帝国議会で軍事公債にただ1人反対、ローザ・ルクセンブルクと「スパルタクス団」を結成。そして第1次世界大戦後、ドイツ共産党を結成。19年にローザと共に、政府の意向を承けた右翼軍人によって殺害されました。
さて大戦が長期化する中、情勢は三つの方向から「ドイツ革命」へと動きます。第一は「外圧」で、連合国は終戦条件としてドイツ民主化を強く要求。第二は「上から」で、「妥協の平和」を模索していたSPD執行部や自由主義政党が民主化を要求。第三は、ルクセンブルクらスパルタクス団や独立社会民主党による「下から」の動きです。
ロシア革命に刺激を受けたスパルタクス団らによる「下から」の革命運動が激化していくと、軍部とユンカー(地主層)の保守派が硬化し、「祖国党」を結成して戦争継続を主張、再び指導権を握り、「勝利の平和」を目指します。ところが事態は劇的に変化。18年秋に英仏両軍がドイツの西部戦線を突破しいよいよ敗戦色が濃厚に。この事態を受け、ヴィルヘルム2世はウィルソンの14カ条を受け入れ、「上から」の民主化を決意。マックス公を首班に民主政権が樹立。その結果、社民党からも2人が入閣し遂に政権入りします。18年11月になると、ベルリンで労働者の武装ゼネストが勃発、警察や軍隊も放置し、マックス公は政権を放棄。そこに一時的にできるのが共産党政権で、これが「ドイツ革命」です。
だがドイツ革命はロシア革命とは異なり、SPDのエーベルトが首班となり、彼は社民党や独立社民党内の様々な主張(労兵評議会が政府を監督するなど)を押さえ込み、幅広い民主政党による連立政権を樹立。
全権力を「レーテ」に集めよと唱えたローザ
スパルタクス団による武装蜂起
このドイツ版「ソビエト(労兵評議会)」を「レーテ」と呼びます。ロシアのソビエトは1905年革命の際に自然発生し、17年の革命で再発生、これを政治権力と巧みに結びつけたのがレーニン自身です。マルクスやエンゲルスはソビエトの発生は想定してはおらず、レーニンはこれをボルシェヴィキ政権樹立のため「利用」した形です。その証拠に21年、蜂起したクロンシュタット水兵のソビエトの訴えを尊重するどころか、徹底弾圧したのです(クロンシュタットの反乱)。
スパルタクス団は「レーテ権力に全ての政治を移行」と主張し、武装蜂起による政権奪取を企図。レーテ(ソビエト=評議会)は通常、大工場と軍隊から千人毎に選んだ代議員が実際に行政権を握る考えです。ところがこの時レーテの過半数の代表は、多数派社会民主党を支持。
煽動的組織活動家のリープクネヒトと大衆的演説家・理論家のローザ・ルクセンブルクの戦略戦術の「温度差」が、ここで現れます。18年秋の蜂起で街頭で説しデモ隊のリーダーとなったのは一貫し武装蜂起を主張したリープクネヒトで、ルクセンブルクはむしろ自重を促し、あくまでボルシェヴィズムとは一線を画そうとしました。2人の指導者は実は、性格や戦略・戦術をかなり異にしていました。
エーベルト首相は、ロシア的ボルシェヴィキ革命を避ける一点でした。ロシア・ボルシェビキ革命が世界に与えた脅威と緊張——日本も参加した「シベリア出兵」——の教訓が生きました。ドイツでは、議会主義派が主流を握り、国民の愛国心の強さが、ロシアとは異なり革命派に正当性を与えなかったのです。エーベルトは革命派に武装解除を迫り、スパルタクス団の相次ぐ蜂起を封じ込めます。「ドイツ革命」はかくして終息したのです。
しかし議会制民主主義を破壊する「レーテ」は、後世に重要なファクターとなって現れるのです。
(「思想新聞」2024年5月15日号より)